交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
![CONTINUOUS]() 永続魔法
永続魔法
![EQUIP]() 装備魔法
装備魔法
![QUICK-PLAY]() 速攻魔法
速攻魔法
![FIELD]() フィールド魔法
フィールド魔法
![RITUAL]() 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
![CONTINUOUS]() 永続罠
永続罠
![counter]() カウンター罠
カウンター罠
 永続魔法
永続魔法
 装備魔法
装備魔法
 速攻魔法
速攻魔法
 フィールド魔法
フィールド魔法
 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
 永続罠
永続罠
 カウンター罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
 レベル1最強モンスター
レベル1最強モンスター
 レベル2最強モンスター
レベル2最強モンスター
 レベル3最強モンスター
レベル3最強モンスター
 レベル4最強モンスター
レベル4最強モンスター
 レベル5最強モンスター
レベル5最強モンスター
 レベル6最強モンスター
レベル6最強モンスター
 レベル7最強モンスター
レベル7最強モンスター
 レベル8最強モンスター
レベル8最強モンスター
 レベル9最強モンスター
レベル9最強モンスター
 レベル10最強モンスター
レベル10最強モンスター
 レベル11最強モンスター
レベル11最強モンスター
 レベル12最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧 > 20th ANNIVERSARY DUELIST BOX コンプリートカード評価(みめっとさん)
20th ANNIVERSARY DUELIST BOX コンプリートカード評価
|
|
「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |
| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |
|---|---|---|---|
 Secret ▶︎ デッキ |
8 | JPBS1 | ブラック・マジシャン |
|
原作において遊戯が使用する永遠にして絶対的エースモンスターであり、OCGのみならず遊戯王という作品そのものの顔の1つと言える魔法使い族の最上級通常モンスター。 割と中性的な顔立ちで、EX版など見ようによっては女性のように見えるイラストのものもあったり。 闇魔法使い族の最上級通常モンスターとしては、レベルこそ異なりますが第1期時点でも《コスモクイーン》というより高い攻守を持つモンスターが存在しており、《マジシャン・オブ・ブラックカオス》になってもまだ宇宙を統治する女王には及びません。 これは《青眼の白龍》と遜色ないステータスを持ち、どういうわけか儀式モンスターにならなかった《コスモクイーン》の方を讃えるべきですかね? しかしこちらには数々の良質な専用のサポートカードが大量に存在しているだけでなく、禁止カードとなった《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》も含めて様々な融合モンスターの名称指定の融合素材にもなっており、派生モンスターとなる存在も数しれず。 場や墓地でブラマジ扱いになる同じステータスを持つ効果モンスターがいるから手札・デッキでも名称指定の効果を受けられることと通常モンスターであることだけが差別化点というこのモンスターは別にもうデッキから抜いてもいいよね、となってしまうようなカードは評価時点では出てきておらず、専用サポート効果の指定する領域も含めてその辺りはちゃんと配慮されているのもいいですね。 現在では最上級通常モンスターとしてはお世辞にも高いとは言えない攻守ですが、その独自性でこのモンスターと比肩するバニラ魔法使い族を今後2つと見ることはないでしょう。 原作でもメインで活躍した人気モンスターということでイラスト違いも多数存在するカードですが、個人的にはやはり最初期のちょっと変わったポーズしてるやつが至高ですね。 これまた個人的な話になりますが、私はブラックマジシャン使いの遊戯よりもブラックマジシャンデッキ使いのパンドラを推したいので、パンドラの使用した「悪いブラマジ」をイメージした絵柄のカードももっと出して欲しいなと思っております。 |
|||
 Secret ▶︎ デッキ |
8 | JPBS2 | E・HERO ネオス |
|
同じレベルと攻撃力を持つ通常モンスターである《ブラック・マジシャン》に負けず劣らずの様々な効果に対応する戦士族の「E・HERO」最上級通常モンスター。 個人的には《O-オーバーソウル》とか《ヒーロー・ブラスト》とか《ラス・オブ・ネオス》とかぶっ放してた頃からもう既に強かったです。 同じステージで戦っても到底勝ち目などあるはずもないため、光戦士の最上級モンスターは公式のデュエルで使用可能なものは評価時点でもこのカードしか存在しない。 《ローガーディアン》は今となっては儀式モンスターでまだ良かったと心から思えるのではないでしょうか。 |
|||
 Secret ▶︎ デッキ |
9 | JPBS3 | スターダスト・ドラゴン |
|
アニメ5D’sの主人公である遊星のシグナー竜にして、《スターライト・ロード》の精霊さんでもあるレベル8のドラゴン族Sモンスター。 自身を犠牲に場のカードを破壊する効果をカード種別を問わずに受け止め、蘇生制限が満たされていれば場に帰ってきて何度でも破壊を受け止めてくれる汎用素材のSモンスターで、複数破壊系のバック割りが直撃したら憤死するデッキばかり使っていた私はそれはもうスタロとセットでお世話になったものです。 エイのような独特のフォルムや胸部のコアがそれっぽく見えるのもあってか、当時はエーリアンのレベル8Sにもこんな効果のモンスターがいたらどれだけ良かっただろうかと妄想したものでしたね。 |
|||
 Secret ▶︎ デッキ |
9 | JPBS4 | No.39 希望皇ホープ |
|
別名『希望の敷き物』。 このカード自体も縛りのない汎用ランク4モンスターの1体で、最初期のXながらその打点や効果も悪いものではない。 だが敷き物としての他に代え難い重要性こそが、現在のこのカードの存在意義であり、上に乗っかるやつを実質的な汎用ランク4として扱えるのが非常に大きいです。 |
|||
 Secret ▶︎ デッキ |
8 | JPBS5 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン |
|
攻撃的な能力と守備的な能力とデッキを回す能力が自身のモンスター効果とP効果に詰められた、アニメで主人公が使用した重要なポジションの最上級Pモンスター。 Pスケールは4とP召喚を行うためのPモンスターとしての適性は低く、サーチ効果はPゾーンで自爆して発動するものであることから、さっさと自爆してEXデッキに表側表示で加わり、持ってきたPモンスターで作ったPスケールだこのカードをEXデッキからP召喚して自身の効果による大きな戦闘ダメージを狙うという流れになります。 サーチ効果がきわめて遅効性のものであることからこのカード単体としては割と平凡な存在として扱われるようになり、現在ではPデッキにおける汎用的なPモンスターとして使われることは少なくなりました。 しかし自身の「オッドアイズ」「ペンデュラム・ドラゴン」ネームに関する効果を受けられたり指定をクリアできるのはもちろん、闇ドラゴンやレベル7という形でも様々な派生モンスターにいっちょ噛みしており、《ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン》の名称指定の融合素材だったりもしたりと当然のように独自性を有しているため、そこはさすが主人公のカードといったところですね。 |
|||
 Secret ▶︎ デッキ |
6 | JPBS6 | デコード・トーカー |
|
アニメにおける主人公の表エースのような立ち位置で第一話から登場した2体以上素材で出せる汎用リンク3モンスター。 しかしその能力は今となっては汎用カードとしてもサイバース族や「コード・トーカー」モンスターであることを活かした専用カードとしても優先されづらいものになってしまっている。 自分の場のカードを対象する全ての効果にターン1なしでカウンターできるのは悪くないとはおもうのですが、そのための要求がそれなりに高い上に効果を使うとパワーダウンするので制圧の添え物としてはそれほど向いていない。 評価時点においても未だ空席だらけの汎用リンク3モンスター群ですが、それでいてなおこのカードを試すような動きがまるで見られないことがこのカードの現実といったところです。 リンク先のモンスターが何であれ自身の攻撃力の上昇値に影響がないことと、リンク先のモンスターであればリリースに指定がないのは悪くないと思います。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JPB01 | マジシャン・オブ・カオス |
|
《カオス・フォーム》で儀式召喚できる「カオス」儀式モンスターの1体となるカードで、たくさんいるようで実はそれほど多くない自身のカード名を《ブラック・マジシャン》として扱う能力を持つモンスター。 特に場だけでなく墓地でもブラマジ扱いになるのは評価時点ではこのカードと《竜騎士ブラック・マジシャン》のみであり、その分受けられる専用サポートの恩恵も多くなっている。 自身の持つ能力は発動したその効果を直接妨害できるわけではありませんが、それが相手が発動した永続魔法や永続罠であればそれを破壊することで不発にすることができ、自分の魔法罠カードの効果の発動にも反応するため、フリチェの魔法罠カードの効果に実質的にフリチェとなる除去効果をプラスすることができ、既に場に存在する《黒の魔導陣》や《永遠の魂》などにも反応してサーチや展開や除去などのあらゆる自分の魔法罠カードの効果に破壊効果を加えられるという【ブラック・マジシャン】のデッキコンセプトとも適合した優れた能力です。 後に登場する同じく《カオス・フォーム》で儀式召喚できる《イリュージョン・オブ・カオス》の2の効果で蘇生でき、このカードの3の効果によってあちらを手札から特殊召喚できる点で相互にシナジーしますが、あちらは儀式モンスターの体をしたサーチ札というのが本分であまりモンスターカードとしては場に出てこないので、それと相性が良いことはそれほどの強みとは言い難い。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JPB02 | 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー |
|
《暗黒騎士ガイア》の愛馬を拝借した《ブラック・マジシャン》というデザインの融合モンスターで、そう考えるとこの融合素材指定は何か違うような気がしますが細かいことを気にしてはいけない。 ブラマジを名称指定の融合素材とする融合モンスターの中では《竜騎士ブラック・マジシャン》らと同じく片割れに特定の種族のモンスター1体を指定した特に緩い素材指定であり、《超融合》要員として採用できる他【ブラック・マジシャン】では《ティマイオスの眼》による融合召喚も容易です。 その分効果は打点アップ+貫通+対象を取る効果の無効破壊という一応オールラウンダー感のあるとても素朴なものであり、自身のカード名をブラマジとして能力もなく、独自性や発展性には乏しい。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
5 | JPB03 | 運命のドロー |
|
後攻でも使えるか分からない2つの面倒な発動条件がある代わりにドローの質がある程度保証された《成金ゴブリン》という感じのカード。 発動条件もさることながら、発動後はそのターンは魔法罠カードをセットできず、カード効果の発動もあと1回しか行えないため、引いてきた速攻魔法や罠カードを盤面の1妨害に追加するという使い方ができず、引いてきたカードを元手にした上振れ展開みたいなのも狙いにくく、まず以て意中のカードを引けるかどうかも不確定なのでかなり使いづらい。 『運命のドロー』とか言う割にはすぐに解禁されるフレイバー的にも微妙な発動条件、でもLPが減ってないと発動できないので相手にめちゃくちゃ展開されているのに発動すらもできない場面もあるというのはさすがにちょっとという感じです。 何をドローしたかに関わらずデッキトップから2枚までのカード名が見えていることを活かしたいとか適当なことをとりあえず言っておきたい次第です。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
5 | JPB04 | 拡散する波動 |
|
原作のバトルシティ編で遊戯が使用し、作中ではこの効果による《超魔導剣士-ブラック・パラディン》の全体攻撃によって、海馬の3体の《青眼の白龍》を全滅させてフィニッシュした。 OCGでは最上級魔法使い族が使いこなせるカードとなり、さらに戦闘破壊が確定したモンスターのリバース・戦闘破壊誘発の効果を発動させず、墓地で発動する起動効果なども発動させない《冥界の魔王 ハ・デス》的な追加効果が設定されました。 相手によっては有用な効果にはなりますが、専用サーチがありそうでなかったりする取り回しの悪いカードであり、攻撃モンスターのパワーそのものは変化しないことから、ライフコスト以前にわざわざカード1枚を使ってやる価値があるかは怪しい。 また全体攻撃「しなければならない」効果であるため、手を出したくない相手にも最終的には攻撃しなければならない点にも注意したい。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
9 | JPB05 | 黒の魔導陣 |
|
発動時の効果がサブ効果で場で発揮する効果がメイン効果となるタイプの永続魔法で、《ブラック・マジシャン》のサポート魔法罠カードとしては特に重要なポジションにあるカード。 発動時効果はデッキトップから3枚をめくることによる不確定なサーチ効果となっており、成功すれば1枚のアドバンテージとなり、《魂をのしもべ》などとの併用で確定サーチに持っていくことができる。 場での効果はブラマジの召喚・特殊召喚時に相手の場のカード1枚に対して出せる単体除外というもので、ブラマジを《永遠の魂》のようなフリチェの効果で召喚・特殊召喚することでその効果処理後にお互いのターンに1度使える実質的なフリチェ除去として使うことができ、単体ではそれほど攻撃力が高くない以前に単なる通常モンスターでしかないブラマジにとって大変価値のあるものとなる。 対象を取る効果で名称ターン1はあるものの、継続的に使える上に除去内容が除外でバックのカードにも干渉することができ、【ブラック・マジシャン】における最終盤面でこのカード抜きに話を進めるのは評価時点では困難となるでしょう。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
7 | JPB06 | 永遠の魂 |
|
お互いのターンに1回、フリチェで《ブラック・マジシャン》を蘇生できることに非常に価値のある永続罠カード。 手札からも特殊召喚できるため直引きのケアもできるのが優れていますが、デッキからは特殊召喚できず、できればもう1つ選べる効果として設定されているサーチ効果も活用したいところなのですが、どちらもブラマジが場にいないと発動すらできない魔法カードである上に現在では条件に対してそこまで強力なカードというわけでもないため、大きなアドバンテージを得られる可能性がある《黒・魔・導》を1枚入れるかどうかという程度で選ぶ機会はあまりなさそうです。 さらにこのカードが場にあれば自分のブラマジは相手の効果に対する完全耐性を獲得でき、ブラマジのステータス的にはそれほどの脅威にはならないことも多いですが、永続効果などの発動しない相手の効果も受けず、自分の効果は受けられるためそれによってステータスを上げたり耐性の穴を埋めることができるのでかなり優秀です。 しかし表側表示のこのカードが場から離れた瞬間にブラマジを含む自分の場のモンスターに全体除去が襲いかかってくるデメリットがあり、そうなれば当然このカードが狙われ、状況によっては大きなディスアドバンテージになってしまうのがやはりネックとなります。 発動する効果によるもので効果による破壊なので、厄介なデメリットではありますが回避・軽減のしようがあるのは救いと言えますね。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JPB07 | E・HERO ネビュラ・ネオス |
|
《E・HERO ネオス》のコンタクト融合体となる融合モンスターの1体で、この時期に登場したカードとしては割と奇跡の3体全てが名称指定されているカードです。 何しろ今時出てくるような融合モンスターときたらコンタクト融合体を例に挙げても《E・HERO コスモ・ネオス》のような指定になることが普通なので、初出が海外とはいえ時々こういう指定のやつも作ってくれると嬉しいと感じますね。 ただこのカードの特殊召喚自体は《ミラクル・コンタクト》や《E・HERO グランドマン》などの効果で召喚条件を無視して行った方が良く、後攻から出して捲りにいくよりも相手ターンの展開途中に特殊召喚することが最も有効である性質の効果を持つことから《アームド・ネオス》の効果で相手ターンにEXデッキから特殊召喚する融合モンスターとしても選んでいけるでしょう。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
5 | JPB08 | E・HERO グランドマン |
|
通常モンスターの「HERO」2体を融合素材に指定する「E・HERO」融合モンスター。 評価時点で融合素材として使えるのは最初期に登場した4体の「E・HERO」下級モンスターと《E・HERO ネオス》そして再度召喚されていない場か墓地の《E・HERO アナザー・ネオス》といったラインナップとなっている。 融合素材としたモンスターの元々のレベルの合計値の300倍が自身の攻守になることから下級モンスター同士で融合召喚すると攻撃力は最大でも2400にしかならないので、自身の2の効果の発動条件を考えるとやはり融合素材のうち1体は《E・HERO ネオス》を含んでおきたい。 2の効果は戦闘破壊誘発の効果で自身をリリースすることでダメステでEXデッキから勝つ「E・HERO」融合モンスターを召喚条件を無視して特殊召喚できるというもので、これにより融合召喚でしか特殊召喚できない《C・HERO カオス》(ルール上「E・HERO」扱い)や、特殊な方法でしかEXデッキから特殊召喚できない《E・HERO ネビュラ・ネオス》なども特殊召喚できる。 しかし発動条件があまり良くない上に元々の攻撃が0なのでフリチェの効果無効に悲しいほど弱く、同じ融合素材を使うなら下手したら《始祖竜ワイアーム》を出した方が強いかもしれないというのは結構厳しいところ。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
4 | JPB09 | ダブルヒーローアタック |
|
自分の場に《E・HERO ネオス》を自身の融合素材に名称指定した融合モンスターが存在する時に、墓地の「HERO」融合モンスター1体を召喚条件を無視して蘇生できるフリチェの蘇生札となる速攻魔法。 融合召喚でしか特殊召喚できないモンスターも蘇生できますが、例によって蘇生制限は無視できないので、最低でも2体の融合モンスターを場に出してうち1体は蘇生制限を満たしつつ墓地に送られていないと発動自体ができない。 それでいてやってることがモンスター1体の蘇生という程度では、いくら速攻魔法で汎用蘇生札では特殊召喚できないモンスターにも対応できるとはいえ現在の【HERO】で使うカードとしては到底もの足りない。 一応《E・HERO スピリット・オブ・ネオス》の効果でサーチすることはできますが、やっぱり《E・HERO サンライザー》みたいな展開の中継役となるカードの効果でサーチできないのでは現実的な運用は厳しくなってくる。 やはり特別な事情があるわけでもないのに何年経っても1度も再録されないカードには、それ相応の理由があるというか需要が低いことの表れなんだなと感じるカードの1枚ですね。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
6 | JPB10 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン |
|
初期に登場した「E・HERO」融合モンスターの中では、その分かりやすくフイニッシュ性能の高い能力を持つことから長らく有用なカードとされてきて、融合素材の片割れに融合モンスターである《E・HERO フレイム・ウィングマン》を要求することも《沼地の魔神王》の融合素材代用モンスターを用いることで簡単に賄えたことから「シャイニング沼地マン」とも呼ばれていた融合モンスター。 墓地の「E・HERO」モンスターの数に比例した打点アップ効果に《E・HERO フレイム・ウィングマン》と同じ戦闘破壊誘発の直火焼き効果が付属していることから《フェイバリット・ヒーロー》の装備対象としても高い適性を誇ります。 現在では同じ《E・HERO スパークマン》と《沼地の魔神王》を融合素材とする場合でも他にも色々と有力なモンスターを融合召喚できるようになった他、上記の素材による融合召喚はできませんが、持っている能力の全てがこのカードのほぼ上位互換となる《E・HERO シャイニング・ネオス・ウィングマン》の登場によって今となっては厳しい立場になってしまったと言う感じですね。 とはいえ4期産の「E・HERO」融合モンスターの中ではかなり頑張っている方のカードではあると思いますし、他の効果でちょっとした補助をしてやれば後攻1ターン目から相手のLPを取り切るくらいの火力自体は十分に出せます。 少なくとも無駄に防御性能に能力を振った結果、弱いだけでなく噛み合ってすらいない《E・HERO シャイニング・フェニックスガイ》と一緒くたにされるようなモンスターではないでしょう。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
7 | JPB11 | ラス・オブ・ネオス |
|
DT第1弾の新規カードとして登場した《E・HERO ネオス》の必殺技カードとなる通常魔法。 発動時に効果対象にした《E・HERO ネオス》をその効果処理時にデッキにバウンスすることで、お互いの場を更地するという強力な除去効果を発揮する。 最上級モンスターであるネオスを場からデッキに戻すという厄介な要求がありますが、このカードの登場当時から既に「E・HERO」や通常モンスターのサポート手段はかなり充実していたのでネオスを場に出すこと自体は容易く、《E・HERO アナザー・ネオス》や《E・HERO プリズマー》などの存在からこれを下級モンスターに代行させることも可能でした。 現在では《E・HERO スピリット・オブ・ネオス》が自身のSS誘発効果でこのカードをサーチし、さらに起動効果でネオスをリクルートしてくることまでできるようになったので、発動自体は当時よりもさらに楽ができるようになっています。 ただし効果処理時に対象にしたネオスが場にいない場合は効果が不発になるという弱点があるため、それも踏まえてこのカードに対してとりあえず皆様思うであろうことは「速攻魔法だったらな」ってところだと思いますね。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
9 | JPB12 | ミラクル・フュージョン |
|
遊戯王OCGに《龍の鏡》と共に「墓地のモンスターを融合素材として除外する」という融合召喚の手法を持ち込んだ「E・HERO」専用のフュージョン魔法。 墓地の準備さえできていれば手札・場からの消費はこのカード1枚だけで融合モンスターを融合召喚できることから大きな人気を博しました。 今となってはデッキ融合と違って墓地の準備が必要なのでそれほど強いカードとされることは少なくなりましたが、対応する融合モンスターは現在も増え続けており、ある種族やテーマの融合・フュージョン魔法にこれと同じ仕様のやつがあればどんなにいいだろうかと思っている人も少なくないはず。 これだけの性能でかつ「フュージョン」魔法カードであるにも関わらず、《E・HERO サンライザー》という名称指定の専用のサーチャーまで有しており、これらの要素が同期の《龍の鏡》とは融合召喚されるモンスターの強さに依らないところで決定的な差となっている。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
3 | JPB13 | シグナル・ウォリアー |
|
遊戯王5D’sにおいて「ライディングデュエル」を行う際に場に存在する状態でデュエルがスタートする「スピード・ワールド2」をモチーフとした能力を持つ汎用レベル7Sモンスターでもある「ウォリアー」Sモンスター。 そういうフレイバーの下に生まれたカードなので本当に仕方がないことではあるのですが、自身の効果でカウンターが置かれるタイミングがこれでこの個数で効果を使うために必要なカウンター数がこれなのに、カウンターを取り除いて発動する効果が相手ターンにもフリチェで使えないというのはさすがにないでしょうよという感じです。 後に《ライディング・デュエル!アクセラレーション!》や《シンクロ・ワールド》といったこのカード以外にもシグナルカウンターが置かれるカードが登場し、特に《シンクロ・ワールド》はフィールド魔法なのでこのカードの効果でカウンターを置くこともでき、このカードの強化にも繋がってはいるのすが…。 結局のところシグナルカウンター関連の効果を持つ新たなカードが登場しているにも関わらず、このカードが登場した2018年末から評価時点となる2024年現在まで一度も再録されていないのがこのカードの現実という感じですね。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JPB14 | ジャンク・スピーダー |
|
デッキから可能な限り特殊召喚するというあまりに無茶なことが効果テキストに書かれているSモンスターで、11期にEXデッキからの特殊召喚に関するルールが元に戻ったことで、10期にEXモンスターゾーンが追加されたことによる恩恵を特に大きく受けたカードの1枚。 自身をS召喚するためのチューナーが「シンクロン」縛り、リクルートされるのは「シンクロン」チューナー、発動するターンはEXデッキから展開できるのはSモンスターのみとなりますが、最大で5体のモンスターをリクルートできるのはさすがに並大抵のデッキには真似できる所業ではなく、それらのモンスターをS素材として展開できるSモンスターには制限がないためEXデッキをフル回転させてやりたい放題展開でき、S召喚デッキならではの「宇宙展開」「グロ盤面」を披露することができる。 MDにおいては、通ったら大抵の場合相手は最後までこちらの展開を見届けることなくサレンダーしてしまうため、時々一人回ししないと展開ルートを忘れてしまうという声も。 通れば相手が勝手に割れるし、通らなければこのカードを起点とした展開ができないだけなので、もはや展開ルートは覚える必要はないという暴論まで飛び出すほどである。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
2 | JPB15 | 星屑の願い |
|
自分の場の「スターダスト」Sモンスターが自身の効果を発動するためにリリースされた場合、その効果処理後にそのモンスター1体を対象として効果を発動でき、自分の場に特殊召喚できるという永続罠。 評価時点では《スターダスト・ドラゴン》・《スターダスト・ウォリアー》・《アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン》の3体がこれに該当し、特に前者2体はエンドフェイズにおける自己蘇生を待たずに即座に場に戻っていただくことが可能となり、名称ターン1のない自身の無効効果をそのターン中に再度使用することもできます。 またこの効果で特殊召喚されると攻撃表示である限り戦闘破壊耐性を獲得するため、それぞれの持つ無効効果の圧力の穴が1つ埋まることでより有効な制圧効果になりやすい。 この効果では墓地からの特殊召喚だけでなく除外状態からの特殊召喚も可能なので、「スターダスト」Sモンスターが自身をリリースして効果を発動した際に《墓穴の指名者》や《D.D.クロウ》などで墓地から除外されたとしても、効果処理後に除外状態のそれらのモンスターを対象にすることで問題なく帰還が可能となり、さらにこの効果に対して相手は効果をチェーン発動できないため、上から使われた効果で無効・不発にされることもなく、特殊召喚を防がれる可能性もかなり低い。 ただ《スターダスト・ドラゴン》や《スターダスト・ウォリアー》が自身をリリースして発動する効果はどちらも受動的なものであり、毎ターンフリチェで使えるとはいえ、ごく限られたEXデッキのモンスターしか蘇生・帰還できない上にサーチもできない罠カードということでその汎用性はとてつもなく低いです。 汎用蘇生罠である《リビングデッドの呼び声》や《戦線復帰》にはない専用蘇生・帰還札として、色々と特典をつけて結構頑張っているなと個人的には思うのですが、これでもまだ全然足りてないというのが悲しいところ。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
10 | JPB16 | ジャンク・シンクロン |
|
最初に登場したチューナーモンスターの1体で「シンクロン」チューナー。 【ジャンクドッペル】と呼ばれるデッキのキーカードとされる永久に色褪せないチューナーです。 機械の姿をしていながら戦士族で登場したところ後続の「シンクロン」仲間がこぞって機械族に流れてしまい、代わりに「ジャンク」仲間が戦士族に所属して帳尻を合わせた感がある、そのはじまりとなるカードでもあります。 その効果はいわゆる釣り上げ効果持ちチューナーの開祖となる存在で、自身と自身の効果で特殊召喚したモンスターとでS召喚に繋げようというS召喚のチュートリアル役でもありました。 効果だけを見ると、NS誘発の効果で墓地のモンスターを対象にした墓地からの特殊召喚になるため妨害にめちゃ弱い上に事故要因にもなりうる、モンスターは守備表示で特殊召喚されるので戦闘には参加できず効果も無効になり、蘇生できるのはレベル2以下なので2体で呼び出せるシンクロモンスターもレベル5以下という基本的に戦力としてはそうでもないものに限られるという感じで、いやいや普通に時代に取り残されてるしめちゃめちゃ色褪せてるじゃんと思ってしまうかもしれませんし、確かにそういった一面もあるにはあります。 しかしこのモンスターは戦士族でシンクロンであるが故のサポートの充実から必要な場面で引き寄せやすいという大きな強みがあり、特にコンバーターというジャンク仲間のズッ友の登場によって連続シンクロまでもが容易となり、その有用性はさらに向上しています。 なんだかんだでチューナーとして本来の役割を果たすのが目的のチューナーの中で1番好きなのはこのモンスターというデュエリストも多いのではないでしょうか? |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
8 | JPB17 | ドッペル・ウォリアー |
|
古くからデュエリストたちの間で【ジャンクドッペル】という名前のデッキ、略して「ジャンド」と呼ばれるS召喚デッキの「ドッペル」の方となる戦士族の非チューナー。 自分の墓地からモンスターが特殊召喚された時に自身を手札から特殊召喚できる展開効果と、S素材として墓地に送られた場合に2体のレベル1トークンを特殊召喚してさらなる展開に繋げることができるという能力を持っています。 「ジャンク」の方を担当する《ジャンク・シンクロン》との相性はまさに最高レベルで、レベル2であるこのカードがあちらの召喚誘発の蘇生効果の対象にできてかつそのままS召喚に繋げられるし、モンスターを墓地から特殊召喚する行為がこのカードを手札から自己SSするためのトリガーを引くことにも繋がります。 とはいえ単独では初動どころかまるっきり何もできないタイプのカードなので事故要因にもなり、【ジャンクドッペル】は《ジャンク・スピーダー》さえ通ってしまえばあとはどうにでもなるところが大きいので、かつてほどデッキ内で展開を行うための3積み必須というところからは大きく離れつつあります。 それでもこのカードが展開にからんだ時の伸び方や誘発貫通力には無視できないところがあり、これまで愛用していた一人はおそらくこれからもお世話になることでしょう。 なお稀にこのカード1枚も採用していない【ジャンクドッペル】も見られ、それでもそのデッキが【ジャンク】でも【シンクロン】でもなく概ね「ジャンド」と呼ばれる辺り、本来は【不動遊星】と呼ぶのが正しいデッキになるのかもしれません。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
9 | JPB18 | エフェクト・ヴェーラー |
|
アニメ5D’sで遊星が使用した、相手のメインフェイズにおいてフリチェで相手モンスター1体の効果を無効にする手札誘発モンスター。 アニメではロットンのガトリングオーガに対してこれを使用しクソゲーを阻止したが、今や現実のOCGでもこれが常態化しつつある。 相手ターンの限られたフェイズでしか使えない、マクロ下では使えない、対象耐性持ちには効かない、手札誘発モンスターズでは比較的メジャーなカードなので抹殺されやすいなどの欠点があるが、それを考えても強いカードであることは間違いなく、うらら達のように名称ターン1がないのでダブっても使用可能なのが特に大きく、Gで何枚引いてきても問題ない。 必ずしも場の相手モンスターの効果の発動に反応する必要はないため、永続効果持ちや自身をリリースして効果を発動する起動効果を持つモンスターにも有効な場面があるのはとても有り難いです。 ただし効果を無効にするだけで破壊しないため、アドを稼ぎづらい低速デッキでこのカードを使うのは辛いのですが、先攻で最大展開されるとそれ以上にもうどうしようもないといった事情で、環境次第でメイン・サイドへの投入率は大きく変化するものの、やはり使われることも多くなっている。 そういった性質から基本的には場に出しては使わないのですが、どういうわけかチューナーなので、リンク2のハリのリンク素材とし、リンク2のハリでデッキから呼び出してリンク3のセレーネをリンク召喚し、リンク3のセレーネで墓地から特殊召喚してアクセスに繋ぐ、いわゆる「ハリセレアクセス」ムーブに適した魔法使いチューナーであることも評価されていたが、こちらは2022年7月のリミットレギュレーションでハリファイバーが禁止になったことで大きな強みとは言えなくなっている。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JPB19 | No.39 希望皇ホープ・ダブル |
|
自身の効果による《ダブル・アップ・チャンス》のサーチを介することで、このカード1体であらゆる「希望皇ホープ」Xモンスターをこのカードに重ねてX召喚できる能力を持った「希望皇ホープ」Xモンスターの中でも特に性能の高いカード。 このカードに《No.39 希望皇ホープ》を重ねてX召喚することでその攻撃力は倍の5000になり、さらにサーチしてきた《ダブル・アップ・チャンス》の効果を噛ませることで攻撃力10000になるという【希望皇ホープ】における1キル製造機でもあるカードで、当然《獣装合体 ライオ・ホープレイ》や《No.99 希望皇ホープドラグナー》などをX召喚するカードとしても使える。 これまで専ら他の「希望皇ホープ」Xモンスターの下敷きになるのが仕事だった《No.39 希望皇ホープ》が今度は逆に他のXモンスターに重ねられるテーマのフィニッシャーとなるという作りには感慨深いものがあります。 しかもこの効果は何故かお互いのターンにフリチェで使えるので、自分のターンに使おうとしたところを《灰流うらら》や《無限泡影》に無効にされたとしても完全な死に体にならないのも優秀です。 デッキに《ダブル・アップ・チャンス》が存在しなくなると効果が使えなくなるという弱点があるため、直に引くこと嫌うなら2枚積むか手札や墓地からデッキに押し戻す手段も考えておきたい。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
9 | JPB20 | 希望皇オノマトピア |
|
評価時点における《オノマト選択》でサーチできる唯一の「オノマト」モンスターであり、自身の能力によってさらに4つの関連カード群にも属しているモンスター。 主に「オノマト」要素を取り入れた【希望皇ホープ】において、自身と展開用のモンスターを《オノマト連携》によってまとめてサーチすることが可能なランク4Xモンスターを立てるためのセットとして採用されるカードです。 特に《ズバババンチョー-GC》と《ドドドドワーフ-GG》とは強いシナジーを形成し、それぞれが展開札や誘発貫通札となり、【希望皇ホープ】の初動の成立に大きく貢献してくれる。 3体が揃った時は出来上がる盤面もかなり強固なものとなるため「オノマト」要素を取り入れた【希望皇ホープ】では概ね3枚積まれるカードとなっています。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
4 | JPB21 | シャイニング・ドロー |
|
アニメ及び漫画版ゼアルにおいて、デュエル開始時にデッキに存在していなかったはずのカードを通常のドローで創造とするという掟破りの荒業をモチーフにしたカード。 ドローフェイズの通常のドローでこのカードを引いてきた時にこのカードを公開し続けることで、そのメインフェイズ1にて自分の場の「希望皇ホープ」Xモンスター1体を対象に2つの強力な効果から選んで発動することができる。 《RUM-七皇の剣》と同様に初手や通常のドロー以外のドローでも引いてしまうリスクがあるほか、特定のEXモンスターが自分の場にいることが前提なので使い辛さが否めず、前半の効果で「ZW」を一気付けした場合、追加効果は適用されるもののその攻守をアップする方の効果は適用されない。 後に《ゼアル・フィールド》というこのカードを名称指定でドローフェイズのドロー前にデッキトップに仕込める専用サポートが登場したものの、これの類似カードであり両方の効果が場が無の状態からでもデッキに触れる《バリアンズ・カオス・ドロー》に比べると数段劣る性能と言わざるを得ないでしょう。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
7 | JPB22 | ガガガマジシャン |
|
最初に登場した「ガガガ」モンスターで、実質的に「主人公ストラク」となるスターターデッキには最終の3年目でようやく再録されたカード。 自身のレベルを1から8にまで変動できる能力により、様々なXモンスターのX素材に利用できるほか、レベル変動を活かした効果の数々とコンボが組める。 当然自身のレベルが変わるだけのモンスターに貴重な召喚権は渡したくないので、《ガガガリベンジ》や《ガガガ学園の緊急連絡網》などのテーマサポートも含めた効果によって展開したい。 本当はコントロール奪取魔法とかを大量に入れてEXデッキにはランク1から8までのXモンスターをそれぞれ1体以上揃えるとかすると楽しいと思うんですけど、それじゃあEXデッキの枠を無駄遣いするだけでちっとも強くないのが残念。 デメリットはS素材にできないというこのカードを使うようなデッキではほぼ気にならないものですが、せっかくレベル7になれるのにいざとなった時に《灰流うらら》と一緒に《フルール・ド・バロネス》になれないのはやはりデメリットと言えるのかもしれない。 |
|||
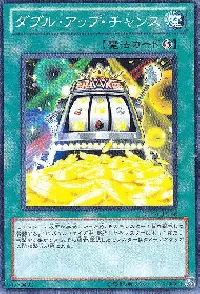 Parallel ▶︎ デッキ |
7 | JPB23 | ダブル・アップ・チャンス |
|
元々は《No.39 希望皇ホープ》の効果とシナジーするテーマ無所属のコンボカードとしてアニメ向けに設計された魔法カードであり、アニメデュエルという名の作り物のデュエルだからこそ成立する実用性の低かったカード。 しかし後に《No.39 希望皇ホープ》と同じ素材指定のランク4Xである《No.39 希望皇ホープ・ダブル》がこれを名称指定でサーチした上で自身に《No.39 希望皇ホープ》を重ねてX召喚できるようになった上に、これまでは倍にしても攻撃力5000止まりだったところをダブルの効果でさらに倍の10000にできるようになったことで【希望皇ホープ】におけるワンキルパーツとして一気に実用性が高まることになりました。 なおダブルに重ねるのを《獣装合体 ライオ・ホープレイ》などにする場合でもこのカードをサチする必要があるため、ダブルを使う以上は必ずセットで採用する必要があるカードとなります。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
2 | JPB24 | かっとビング・チャレンジ |
|
既に攻撃を終えたXモンスターがそのバトルフェイズ中にもう一度攻撃を行えるようになり、その時には《SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング》と同様の効果の発動を封じて攻撃を行えるというカード。 発動条件が弱い、罠カードなのが弱い、追加効果もそんなのがあったら1回目の攻撃の時に使ってるよというかなり微妙なものという感じであまりに強みに乏しい効果であり、遅効性のカード1枚を使ってやるようなことではない。 後攻からキルを取る系のカードはパッと見た性能がそれほど高くなくても評価されることも少なくありませんが、これはさすがに無理なカードです。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JPB25 | オッドアイズ・アドバンス・ドラゴン |
|
カード名通りアドバンス召喚に関する能力を持つ「オッドアイズ」モンスターであり、アニメ版アークファイブに登場しなかったアドバンス召喚に対応するドラゴンを《オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン》が兼任する形となったOCGオリジナルのモンスター。 その効果はアドバンス召喚誘発の効果で相手モンスター1体を破壊するという何と《雷帝ザボルグ》並の代物であり、攻撃力は3000と高いですがリリースが2体必要な最上級モンスターときているのでまともに使うと時代遅れでは済まないレベルで性能が低い。 しかしこちらはレベル5以上のモンスターをリリースに用いる場合は1体のリリースでアドバンス召喚でき、破壊は対象を取らない効果でかつ破壊したモンスターの元々の攻撃力分の効果ダメージが相手に直撃する追加効果も設定されているので、シンプルながらその破壊力はけしてバカにできるものではなく、相手ターンにアドバンス召喚する価値も高いです。 リリースとなるレベル5以上のモンスターは自己SS能力を持つモンスターや《簡易融合》や《簡素融合》でEXデッキから調達したモンスターなどを利用でき、《天空の虹彩》や《ドラゴン・目覚めの旋律》といったサーチ体制もそれなりに良いというのはアドバンス召喚が必要なモンスターにとって何よりです。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
3 | JPB26 | EMスマイル・マジシャン |
|
自身の召喚誘発効果でサーチできる「スマイル」魔法罠カードの中でも《スマイル・ワールド》とのシナジーを強く意識したモンスター効果及びP効果を設定されている「EM」モンスター。 自分の場に存在しているのが仲間内のモンスターのみで自身がスマイル状態という攻撃力が上方向に変動している場合、自分の場のスマイル状態のモンスターの数だけドローができるという能力が目玉であり、サーチしてきた《スマイル・ワールド》を発動することでその条件を満たすことができ、P召喚によってこのカードを含むモンスター3体ほどを同時に展開することができれば大量ドローも狙いやすく、消費は激しいがリンク先に依存しない手札からのP召喚であっても十分なリターンが見込める。 しかし発動後はそのターンの特殊召喚ができなくなるので何枚ドローしてもそこなら盤面を発展させることは難しく、誘発を引き込むかバックを厚くすることを狙うのが精一杯となる。 サーチできる「スマイル」魔法罠カードはそのほとんどが性能が低い上に、それを自己SS能力のない最上級モンスターがやるので使い勝手は非常に悪く、一応Pゾーンに発動してそこからの自身のP効果による自己SSは狙えるものの、そちらも攻撃力の変動と被破壊でトリガーが引かれるものであまり良い条件とは言い難い。 極めつけは《スマイル・ワールド》が何故か永続魔法でもフィールド魔法でもない使い切りのカードと来ており、同期の《シグナル・ウォリアー》と同様にフレイバー重視で実用性の低いカードの部類に入ってしまうカードって感じですね。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
1 | JPB27 | 魂のペンデュラム |
|
P召喚の快適化及びPモンスターのサポートに全振りした「ペンデュラム」永続魔法。 効果としてはスケールの変動によるP召喚可能な範囲の拡張、PモンスターのP召喚の成功報酬となるカウンターによるPモンスターの全体パンプ、P召喚権の追加となっている。 Pスケールが揃ってないと使えない効果+基本1ターンに1度しか行えないP召喚の成功報酬としてはあまり遅くて割に合わない効果という全く嬉しくない組み合わせであり、全体強化とはいえ強化倍率300はさすがにあんまりと言わざるを得ないカードです。 P召喚権は同じ「ペンデュラム」魔法カードである《EXP》で格安で買えるので、併用する価値こそあれどこれを優先しても使う理由は皆無であり、カウンターが乗っていたら効果では破壊されない程度のことすら何故書いていないのかが不思議なカードです。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
5 | JPB28 | オッドアイズ・セイバー・ドラゴン |
|
自分の場の光属性モンスター1体をリリースして手札で効果を発動し、効果で《オッドアイズ・ドラゴン》を指定の3領域から1体墓地に送ることで手札から自己SSできるという、かなり変わった自己SS能力を持つメインデッキの「オッドアイズ」最上級モンスターで「セイバー」にも属しているカード。 場に出た後は2800打点で相手モンスターを戦闘破壊することで誘発する効果により、さらに相手の場のモンスター1体を対象を取らない効果によって破壊する能力を発揮する。 通常召喚や他の方法による特殊召喚も可能で攻撃力もそれなりに高く、効果も素朴で微妙な発動条件ながらもちゃんとアドバンテージにはなっている悪いものではないし、コストはリリースするモンスターを工夫すれば有効活用できる場面もあり、効果による墓地送りで墓地にレベル7の闇ドラゴンである《オッドアイズ・ドラゴン》をデッキから送り込むこともできたりと、前時代的なりに頑張っている性能ではあります。 そして何よりもその存在意義が皆無に等しかった《オッドアイズ・ドラゴン》を名称指定して居場所を与えてやったというのが好印象なカードですね。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
2 | JPB29 | スマイル・ワールド |
|
お互いの場のモンスター全ての攻撃力をそのターン限り変化させる「スマイル」魔法カード。 強化倍率があまりに低いので自軍のモンスターの打点の底上げには到底向かないが、参照するのは場のモンスターの数なのでレベルを持たないXモンスターやLモンスターも含めて、魔法カードの効果を受けるモンスターなら攻撃力が必ず変化するということになる。 カード名はこれですがどういうわけかフィールド魔法ではないため、罠カードである《スマイル・ポーション》の発動条件を満たすのにはあまり役に立たない。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
10 | JPB30 | デュエリスト・アドベント |
|
発動に名称ターン1があってかつ、場への要求がある発動条件が設けられた等価交換のサーチ魔法で、墓地効果などのその他の効果は設定されておらず、何らかのテーマネームを持つというわけでもないので「サーチできるサーチ札」でもない。 そうとだけ言えば現代基準なら「めっちゃ微妙なサーチ魔法」ってことになってしまうわけですが、このカードの場合はサーチ先が多様でかつ性能が高いものも多く、それらのカードを使うようなデッキではこの発動条件を満たすことがあまりに容易いため、デッキに安定性をもたらすことが何よりの仕事であるサーチ札の役目を問題なく果たすことができるでしょう。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
4 | JPB31 | サイバース・エンチャンター |
|
最も緩いL素材でL召喚できるモンスターの1体となるリンク3モンスターであり、《サイバース・ウィザード》というサイバース族の下級モンスターをL素材とした場合のみ適用できる能力があるというとても珍しいLモンスター。 これの《バックアップ・セクレタリー》版である《バックアップ・スーパーバイザー》に比べると、こちらは指定のL素材である《サイバース・ウィザード》が単なる1800打点のアタッカーのようなものでそこに数的アドバンテージになるような効果や展開能力が備わっておらず、ただでさえあちらよりリンク値が1つ高いリンク3ということでそもそも効果を適用できる状態でL召喚すること自体があちらよりも難しい点で劣り、メインデッキに性能の低いモンスターを入れる必要があるためそこのマイナスが大きい。 その分使えるようになる能力はあちらよりも汎用性が高く、表示形式を変更できないLモンスターには効きませんが、お互いのターンに相手の場のモンスター1体に対するフリチェの効果無効ということで制圧の添え物としては十分強いものとなっている。 《サイバース・ウィザード》だって別に我慢できないほど弱いというわけでもないのですが、それでも運用上はあちらを名称指定しているハンデがあまりに大きく、【サイバース族】系列のデッキでも使われることは稀なカードです。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
3 | JPB32 | バックアップ・スーパーバイザー |
|
最も緩いL素材でL召喚できるモンスターの1体となるリンク2モンスターであり、《バックアップ・セクレタリー》というサイバース族の下級モンスターをL素材とした場合のみ適用できる能力があるというとても珍しいLモンスター。 《バックアップ・セクレタリー》自体の効果の汎用性が高くこのカードのL召喚を行う助けにもなるため【サイバース族】におけるL召喚及び効果の適用自体は容易なのですが、肝心の効果の発動条件と発動タイミングと展開の手法がかなり弱いのでわざわざL召喚する価値が感じられない。 自身が戦闘か相手の効果で倒れた時の能力も《バックアップ・セクレタリー》1体が指定の3領域から出てくるだけのリカバリー効果で、前半の効果と繋がっていない何かの保険という感じのおまけ効果にとどまっている。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
3 | JPB33 | デコード・エンド |
|
《デコード・トーカー》の唯一の名称指定の専用サポートカードであり、《デコード・トーカー・エクステンド》が場で自身のカード名を《デコード・トーカー》として扱う意義にもなる魔法カード。 効果の内容的にも《デコード・トーカー・エクステンド》の方がより相性の良いものになっているのですが、3つの効果がいずれも戦闘で相手モンスターを倒してナンボの効果になってしまっているので、そういう隙だらけなカードがサーチも利かないのではさすがに使う価値は低いです。 それぞれの持つモンスター効果と1の打点アップ効果、2と3の戦闘破壊時に発揮する効果、そしてエクステンドの場合は自身の3の効果とは確かに噛み合ってはいますが、噛み合っているからといって必ずしも強いとは限らない。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
4 | JPB34 | サイバース・ウィザード |
|
下級で攻撃力1800+モンスターを横にする効果+自身を含むサイバース族の攻撃が寝かせたモンスターを貫通するようになるという、3期以前のノンテーマGSモンスターズの中にでもいそうな能力を持つカード。 寝かせたモンスターにしか攻撃できない制約がかなり余計でしたが、対象のモンスターが戦闘破壊耐性持ちだったり、自分のサイバース族1体を大きく膨らませることで大きなライフカットに繋がることもある。 《サイバース・エンチャンター》が本領を発揮するために名称指定されているL素材という点に値打ちがあり、そうやって半ば無理矢理「必要なカード」にした割には強い方です。 そうか?と思われるかもしれませんが、少なくとも《マドルチェ・プディンセス》よりは絶対に強い。 残念ながら出てくる方のエンチャンターがショコアラに遠く及ばないので仕方がない。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
7 | JPB35 | リンク・ディサイプル |
|
特定の種族の下級モンスター1体でL召喚できるリンク1モンスターの1体。 よほど大きなデメリットを抱えているとかでもない限り、本来ならそれだけでモンスター効果の質に関係なく価値のある存在なのですが、このカードが指定するサイバース族にはこのカード以外にも下級サイバース1体でL召喚できて有用な効果を持つ《リンク・デコーダー》や《リングリボー》や《転生炎獣ベイルリンクス》といった競合相手が複数存在するため、やはりモンスター効果で勝負する必要が出てくる。 そしてその効果というのが自身のリンク先のモンスター1体をリリースして手札交換を行うという、まともに使うとアド損にしかならないとてつもなく微妙なものになっているため、それらの中では優先度が低くなる。 自分の場のモンスターをリリースできること、墓地に送れること、任意の手札1枚をデッキボトムに戻せることを活かせるなら使用する価値はあり、特に同じく下級サイバース1体でL召喚できる《リンク・ディヴォーティー》の効果を誘発させるために最適な能力となっている。 自身とL素材となるモンスターの種族がこういった素材指定のリンク1モンスターが存在しない種族だったら間違いなく9点以上のカードだったことでしょう。 |
|||
 Parallel ▶︎ デッキ |
9 | JPB36 | セキュリティ・ドラゴン |
|
Lモンスターの中でも最も緩い素材内容となる「モンスター2体」でL召喚できるリンク2モンスター。 相互リンク状態という条件付きですが、展開の中継で出しておくことでノーコストで相手のモンスター1体をバウンスでき、自身のリンクマーカーが真上に向いているので《リンク・スパイダー》や《リンクリボー》などのリンクマーカーが真下に向いているリンク1モンスターのリンク先に出せば容易く相互リンク状態にできることから、メタビ系のデッキで《スケープ・ゴート》を採用する場合に高確率でEXデッキに入ってくるモンスターです。 本来はエンドスケゴをしたいところを仕方なくメインフェイズやバトルフェイズに使わされ、結果ターンが返ってきた時にトークンが3体に減っていても仕事ができるのがいいですね。 あとは《デコード・トーカー・ヒートソウル》辺りでも出して、ドロー効果でドロソや罠カードを引き込むことをお祈りしながらお茶を濁しておきましょうか。 |
|||
※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
- 12/09 02:24 評価 9点 《煉獄の災天》「悪魔族汎用サポートカード。ティンダングルで実際…
- 12/09 02:06 評価 8点 《星辰鋏竜シャウラス》「MDではこいつは未実装。URにされたアルザ…
- 12/09 00:01 コンプリート評価 ねこーらさん ⭐SHINING VICTORIES⭐
- 12/08 22:47 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)
- 12/08 20:48 評価 9点 《アルカナフォースXIX-THE SUN》「《アルカナフォース…
- 12/08 18:51 評価 9点 《星辰竜ムルル》「カルテシア枠。ついでに実質フリチェで無効妨害…
- 12/08 18:14 評価 9点 《電光-雪花-》「罠パカを咎める存在。先攻で使ってもバック妨害…
- 12/08 16:27 評価 10点 《月光黒羊》「ターン1のない融合サーチとリソース回収ができる。…
- 12/08 15:39 評価 7点 《電脳堺甲-甲々》「戦闘破壊耐性がつくので実質アーゼウス。」
- 12/08 15:32 評価 10点 《激流葬》「激↑流→葬! リシドなどの罠ビで舐めてかかった相手…
- 12/08 13:10 評価 10点 《神芸学徒 グラフレア》「メディウスの仲間たちの中では、K9に対…
- 12/08 13:07 評価 9点 《神芸学徒 リテラ》「メディウスの仲間三人の中ではブリフュは勿…
- 12/08 12:09 コンボ モルガナイト押し付け。瞳の魔女モルガナの新コンボ。モルガナイト系の…
- 12/08 12:08 評価 3点 《鬼くじ》「総合評価:罠カードをトップに持ってきて相手の認識を…
- 12/08 11:52 評価 10点 《生還の宝札》「神の領域ゴッドファイブの筆頭。 原作では「モ…
- 12/08 11:27 評価 3点 《スライム増殖炉》「神の領域ゴッドファイブの一角。 毎ターント…
- 12/08 10:05 掲示板 オリカコンテスト準備スレ
- 12/08 08:17 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/08 04:49 評価 10点 《賢瑞官カルダーン》「誰やねんカードだが、墓地に落ちた永続罠…
- 12/08 04:28 評価 9点 《閃刀姫-アザレア・テンペランス》「汎用リンクの中ではリジェネ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻


 TERMINAL WORLD 3
TERMINAL WORLD 3
 BURST PROTOCOL
BURST PROTOCOL
 THE CHRONICLES DECK-白の物語-
THE CHRONICLES DECK-白の物語-
 WORLD PREMIERE PACK 2025
WORLD PREMIERE PACK 2025
 LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
 ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
 LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
 デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
 DOOM OF DIMENSIONS
DOOM OF DIMENSIONS
 TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
 TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
 TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
 DUELIST ADVANCE
DUELIST ADVANCE




 遊戯王カードリスト
遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索
遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ
遊戯王デッキレシピ 闇 属性
闇 属性 光 属性
光 属性 地 属性
地 属性 水 属性
水 属性 炎 属性
炎 属性 風 属性
風 属性 神 属性
神 属性