交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
![CONTINUOUS]() 永続魔法
永続魔法
![EQUIP]() 装備魔法
装備魔法
![QUICK-PLAY]() 速攻魔法
速攻魔法
![FIELD]() フィールド魔法
フィールド魔法
![RITUAL]() 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
![CONTINUOUS]() 永続罠
永続罠
![counter]() カウンター罠
カウンター罠
 永続魔法
永続魔法
 装備魔法
装備魔法
 速攻魔法
速攻魔法
 フィールド魔法
フィールド魔法
 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
 永続罠
永続罠
 カウンター罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
 レベル1最強モンスター
レベル1最強モンスター
 レベル2最強モンスター
レベル2最強モンスター
 レベル3最強モンスター
レベル3最強モンスター
 レベル4最強モンスター
レベル4最強モンスター
 レベル5最強モンスター
レベル5最強モンスター
 レベル6最強モンスター
レベル6最強モンスター
 レベル7最強モンスター
レベル7最強モンスター
 レベル8最強モンスター
レベル8最強モンスター
 レベル9最強モンスター
レベル9最強モンスター
 レベル10最強モンスター
レベル10最強モンスター
 レベル11最強モンスター
レベル11最強モンスター
 レベル12最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧 > RARITY COLLECTION -PREMIUM GOLD EDITION- コンプリートカード評価(みめっとさん)
RARITY COLLECTION -PREMIUM GOLD EDITION- コンプリートカード評価
|
|
「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |
| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |
|---|---|---|---|
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP001 | 紅蓮魔獣 ダ・イーザ |
|
除外されている自分のカードの枚数でステータスが決まる悪魔族の下級モンスター。 それしか効果がないにも関わらず何故か強いという稀有なカードで、それは強化倍率の高さに加え、裏側除外のカードもカウントするこのカードならではの強みがあるからである。 除外されているカードの種類を指定していなかった、そして表で除外とか裏で除外とかそんな概念がほぼなかった頃に設計されたカードであったことが、時を経て活きることになった。 強金や金謙を1枚発動するだけでも2400打点に、強貪ならなんと1枚で4000打点という必殺モンスターに成長する。 強金や強貪は発動こそ必要だが除外はたとえ無効にされても必ず支払われるコストで、さらにこのカードはNSから効果の発動を伴うことなくお化け打点を得られるため、効果破壊耐性・対象耐性はもちろん、SS封じ系とパーフェクトカウンター系の制圧にも強いのが素晴らしい。 特化した構築はもちろん、バーンデッキのもう1つの勝ち筋として投入するのも全然アリだと思いますし、攻撃力5000どころか10000のモンスターとも互角に戦えるそのパワーの高さはとても通常召喚可能な下級モンスターのそれとは思えませんね。 ただし無耐性ということでフリチェの除去は普通に効くし、スキドレ泡影にはめちゃ弱いので、後ろには神罠などをいくつか構えてやるとさらに強さを実感できるだろう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP002 | 終末の騎士 |
|
最初に登場した自身と同じ属性のモンスター1体をデッキから墓地に送る効果を持つ戦士族モンスター群「○○の騎士」で、闇属性を担当するこのモンスターは召喚誘発でデッキから闇属性モンスター1体を墓地に送るという、同シリーズにおける圧倒的に最強のモンスター。 よりによって闇属性に発動条件が最強の墓地肥やし効果が名称ターン1もなくあてがわれてしまった結果、環境デッキの初動として使われてまくって現在の制限カードに落ち着いている。 下級戦士族をサーチする魔法である《増援》が、いつまでも制限カードから緩和される気配のない原因の一因として間違いなく挙げられるであろう存在と言えます。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP003 | 鬼ガエル |
|
ガエルデッキにこのカードあり、と言って差し支えないガエルの圧倒的最重要モンスターにしてガエルの顔となるモンスター。 《粋カエル》と驚異的なシナジーを形成し、最適化を図るとメインデッキ内のガエル&カエルはこのカードと《魔知ガエル》と《粋カエル》で概ね完結してしまう。 自己SS、召喚誘発効果の墓地肥やし、コストセルフバウンスによるガエルの召喚権追加という初動を形成する効果が全て詰まっているが、それら全てが回数制限が行方不明というのもこのモンスターの特徴と言えるでしょう。 現在では3つのうち2つ、または全ての効果に名称ターン1がつくことは間違いなく、このまま生み出す事は凡そ不可能だと思われる奇跡のカードです。 あとは初動で可能な限り安定してこのカードにアクセスする手段さえ整えば完璧ですね、などとずーっと思っていたら、2022年になって登場したスプライトというテーマにこのモンスターの強さと悪さに気づかれてしまい、一気に環境カード&次期規制候補となるカードに躍り出てしまいました。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP004 | 増殖するG 準制限 |
|
元々《黒光りするG》からはじまった「○○するG」昆虫族モンスター群の1体で、現存する数ある手札誘発モンスターズの中でも《灰流うらら》と並んでその最右翼とされるカード。 リミットレギュレーションによる規制以外でデッキからGとうららの枠が完全に消え去る日は果たしてくるのだろうか。 こちらはお互いのターンに完全なフリチェでいつ何時でも手札から投げ捨てることができるので、チェーン発動による1ドロー保障を捨ててでも、発動しないタイプの自己SS能力や《三戦の才》ケアでドローフェイズやスタンバイフェイズにさっさと投げていったり、相手がドロソで指名者やうららを引き込むのを見越して発動するなどのプレイングが必要な場合もある。 墓地のモンスターを参照する効果を使うために、効果は関係なく先攻で手札から投げ捨ててしまうといった使い方もできるでしょう。 ただし動き出しに複数のカードが必要なデッキに採用すると、後攻時に命は繋げても先攻時には自分が動くことの邪魔をしてくることもあるのが汎用手札誘発の常でもあり、手札誘発とは少ない初動で動ける、サーチが豊富、テーマのカードはメインデッキに最小限でも楽々回るガチデッキで使ってこそ真の強さを発揮するのだとも感じますね。 このモンスターの場合は妖怪少女の面々と違って一応の攻撃力はあるので、お互いに誘発事故が起こればたちまちGビートの開幕となる。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP005 | 魔界発現世行きデスガイド |
|
海外生まれのカードとしてOCG界に突如として現れた悪魔族のスーパーアイドル。 その人気たるや「デス〇〇」シリーズとして《魔界の警邏課デスポリス》や《魔界特派員デスキャスター》といった派生モンスターが登場するなど、後のカードデザインにも影響を与えるほどで、ゲームや漫画作品では一介のモンスターカードの枠を超えた「人物」としてほぼ同一のデザインのキャラクターが登場している。 可憐な容姿もさることながらその性能の高さが人気の秘訣で、NS時に手札かデッキの同名カードを含むレベル3の悪魔族をSSするという、直引きケア付きの完全なる1枚初動となるカードデス。 特殊召喚したモンスターは効果が無効になりS素材にもできませんが、X素材やL素材には問題なく使用でき、場を離れても除外されたりしないので《クリッター》や《魔サイの戦士》などの墓地で発動する効果は普通に出てしまう。 X素材にすると、特殊召喚したモンスターが場から墓地に送られた時に誘発する効果が出せないのが悩みでしたが、L召喚の導入によりそれもほとんど気にならなくなりました。 来日してから評価現在に至るまではや十数年、日本語名の設定にはじまり環境での活躍やら規制やら紆余曲折あったカードデスが、2023年現在でも【破械】において《破械神王ヤマ》をリンク召喚するための1枚初動としてバリバリの現役デス。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP006 | スチーム・シンクロン |
|
相手メインフェイズにフリチェで発動できる効果により、このカードをS素材に含むS召喚が可能となる「シンクロン」チューナーの1体。 主にS召喚誘発効果を持つSモンスターを相手ターンにS召喚し、その効果で相手の展開を妨害する目的で使われることになります。 しかしOCG化が若干早すぎたのか他に効果は持っておらず、アニメの時にはあった自己SSが削られてしまったのがかなり痛い。 相手ターンにS召喚ができる能力を持つチューナーとしては、2体素材のSモンスターしか出せない代わりに手札で発動できる効果でこれを行える《ホップ・イヤー飛行隊》が存在しており、総合的に見ればそちらに遥かに劣る性能になる。 このカードを使うなら「シンクロン」ネームを持つことは当然として、機械族や水属性であることを活かしていきたい。 S素材に水属性チューナーを指定するSモンスターとしては《白闘気白鯨》や《氷水啼エジル・ギュミル》が相手ターンにS召喚する価値のある効果を持っています。 機械族チューナーを指定したSモンスターにはこれといったカードがなく、《HSRカイドレイク》の素材指定が機械族でかつ風属性というのが残念。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP007 | 幽鬼うさぎ |
|
何気に対象を取らない除去であるのが優れていると思うカード。 効果を無効にしない代わりにカードを場から退場させるので、場面によってはヴェーラーよりもその力を発揮する。 特に装備魔法・永続魔法・フィールド魔法・永続罠・装備罠の効果の発動であれば、ぶっ壊すことによりそれを不発にすることもできるため、ヌメロン対策としてもメジャーなカードとなっている。 ただしヴェーラーGと同じくマクロの影響下では発動できないグループであることには注意。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP008 | 海亀壊獣ガメシエル |
|
相手モンスターをリリースして相手の場に出せる全ての壊獣たちの攻撃力・守備力を見たとき、最も低い数値(攻撃力2200)であることから重宝されている壊獣モンスター。 種族に関してはジズキエルやドゴランのように他の何かには活かしにくい種族だが、反面《センサー万別》にリリースを妨害される可能性もかなり低い種族ともいえる。 また専用デッキ以外では使用するのは難しいが、実は4の効果自体はかなり強い制圧効果。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
8 | JP009 | 浮幽さくら |
|
手にした大鎌とその効果から、命を刈り取る形をしてるだろ?でお馴染みの手札誘発モンスター群「妖怪少女」の1体で、遊戯王OCGにいくつか存在する根絶やし系の効果を持つモンスターの一種。 こういうカードがメインから入ってくる環境は末期だとかそういう話をする時にも名前が挙がりやすいカードです。 その発動条件から、もちろん狙いは相手の先攻1ターン目における展開に突き刺して相手の最終盤面を弱くすること。 根絶やしにするのは相手のEXデッキだけということから、ドラグーンが無制限の頃は相手のドラグーンだけ根絶やしにして自分はドラグーンを使えるなんてのもよく見たものでした。 ただしこのカードを使うためには自分のEXデッキもそれ相応のものにしなければならず、突き刺したからといって数的なアドバンテージに繋がるわけでもなく、相手が別なプランに移行できるように構築している可能性も考えられます。 大会向け構築以上にカジュアルなデュエルで使うのが非常に困難なカードで、使うとしたらまるっきり「身内メタ」になってしまうその性質から、妖怪少女の面々の中でも特に使用するにあたってのハードルが高く感じる手札誘発ですね。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP010 | 灰流うらら |
|
デッキに触る系のほとんどの効果を無効にできる手札誘発モンスターで、発動コストとしてせめてライフ1000くらいは払って欲しかった感じのカード。 そのくらい守備範囲は圧倒的に広く、その後の手札誘発へのハードルを大きく上げてしまったカードでもある。 相手が先攻の際に命をつなぐためのカードでもあり、逆に自分が先攻の時に相手のGを叩き潰したりして徹底的にマウンティングして反撃を許さないためのカードでもあるという二面性を持つのが最大の罪と言える。 うららが初手にない後攻=手札事故と言わしめるほどのカードになっており、同時に先攻側は是が非でも初手に墓穴や抹殺を引きたくて、抹殺するために自分のデッキにもうららを入れるという泥沼である。 このカードの登場で《同胞の絆》や《左腕の代償》のような高いコストが必要なカード、特に手札を捨てたり、場のモンスターをリリースして発動する系のカードでうららの守備範囲内にあるものは常にこのカードへのケアが必要になった。 基本的には《増殖するG》共々他のカードを押しのけてでも採用する価値はあるというカードである。 特に相手が展開系のデッキを握っている場合、相手に自分が対戦相手として存在すると認識していただくためにも。 ちなみに見た目は妖怪少女の面々の中で一番好きです、うららがうららで良かった。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP011 | 白棘鱏 |
|
手札の水属性モンスター1体を切って手札から自己SSできるレベル4魚族モンスターで、メインデッキの「ホワイト」魚族モンスターの1体。 レベル4の水属性の魚族にはそれぞれが異なる条件で手札から特殊召喚できる《サイレント・アングラー》や《ミナイルカ》や《ゴーティスの兆イグジープ》なども存在しており、それらはこのカードと違い手札や場のカードを消費することなく自己SSすることができる。 このカードを使うなら、自己SSの際に手札の水属性モンスターを墓地に送ることができる点、つまり数的消費があることを逆に活かしていくことになるでしょう。 なおこの自己SS効果は発動する効果ではないため一部の「海皇」モンスターが要求する「このカードが水属性モンスターの効果を発動するために墓地へ送られた場合」という条件は満たさないことに注意したい。 総じて登場当時は今よりも多少は画期的な存在でしたが、現在では少なくとも自己SS能力を持つ水属性モンスターとしてはいたって平凡な存在という印象です。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
9 | JP012 | 屋敷わらし |
|
手札誘発モンスター群「妖怪少女」の1体で地属性担当、デッキに触る3つの効果を捉えるうららに続き、こちらは墓地に関する3つの効果を捉える。 うららの後続ということで、今後妖怪少女の効果はこの路線となり、来年以降は手札に関する3つの効果を無効とかかな?そんなの出したら強すぎじゃない?などと予想されたが、後続のみずきやしぐれはそんなことはなく性能もそれまでの妖怪少女と比べると癖がある感じで、実戦でよく使われる妖怪少女は現時点ではこのカードが最後となります。 このカード自身もレベル3アンデットで例のステータスを持つチューナーであることはうさぎがサイキックであることを除けばそれまでの面々と同じですが、それまでと違って見た目が和風でなく、冬(さくら)と春(うらら)の次は夏かななんて言われていましたが、このカードのカード名には夏どころか季節に関する明確な単語すら使われておらず、結局遊戯王OCGにおける法則の予想なんてまるで意味がないんだなと感じさせられました…。 効果はチェーンブロックを作るサルベージ、リサイクル、蘇生、効果による墓地除外を捉えるもので、発動を無効にするのでうららと違ってダメステでも発動ができるのが特徴です。 特に墓地除外効果を捉えるということで、手札誘発モンスターズの多くが苦手とする墓穴を無効にできるのが最大の強みとなります。 ただしコストで墓地のカードを除外して発動する効果や、サーチやリクルートなどの上記以外の性質を持つ墓地で発動する効果は捉えることができず、墓地関係でも意外と見られない効果も多いことには注意したい。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP013 | ダイナレスラー・パンクラトプス |
|
このサイトで言うところの5点とか6点くらいの微妙なカードばかり量産しまくった「ダイナレスラー」モンスターから独り生まれ出てしまったとんでもないバケモノ。 緩い条件で自己SSできる2600打点、自身を含めた「ダイナレスラー」モンスター1体をリリースすることでフリチェで万能単体除去効果を発揮し、自身をリリースすれば《スキルドレイン》さえも壊せるという、《化石調査》で直にサーチできない以外に文句の付け所のないカードで、そしてそれでも余裕の10点満点。 相手にカードを使わせることにかけては天才的な力を持っており、それなりの打点を持っているので仕方なく効果を使ったりしなくてもよく、このカードの処理に2枚以上消費させられることもざらである。 もはやSS封じなどの何らかの永続系カードで手札から特殊召喚させないくらいしか完全に無害化する方法がない。 今後これほどのクオリティの高さのメインデッキに入る汎用ノーマル最上級モンスターを二度と見ることはないだろうと思うほどに全てが強力なカードです。 後攻時のサイドからの捲り札としての投入はもちろん、後攻からの初動に不安があるデッキの補助役としても適している。 ダイナレスラーデッキで使う場合は自身以外も弾丸にできるので、場でやる仕事のないダイナレスラーを投擲しまくる鬼軍曹と化す。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
9 | JP014 | 混源龍レヴィオニア |
|
第10期に《鉄騎龍ティアマトン》を皮切りにシリーズカードの一種として登場した、ウルトラレアの「○○龍」闇ドラゴンモンスター群の1体。 いわゆる「カオス」特殊召喚モンスターに類似する墓地コストを用いた特殊召喚方法を持つカードで、こちらは3体のモンスターを墓地から除外する必要がある代わりに、どちらか片方の属性だけでも特殊召喚できるのが特徴。 除外したモンスターの内訳によって特殊召喚誘発の効果も変化し、光のみなら対象を取らない自分の墓地からの蘇生効果、闇のみなら墓地利用に繋げさせない相手へのランダム1ハンデス、両方を除外しているなら対象を取らない2面破壊といずれも優れたものとなっている。 自身も闇ドラゴンということもあり、メインデッキやEXデッキに闇と光のドラゴン族が多く採用される【ドラゴンリンク】ではいずれの効果も発動できる可能性があります。 2面を取れる効果がアドバンテージ面では最も強力ですが先攻展開では機能しにくく、そういった中で闇属性モンスターの比重が大きい【ドラゴンリンク】にとって、闇属性のみを除外して出した時の効果が先攻時でも強い効果というのは価値がありますね。 ただし発動ターンは自身は攻撃ができないため、たとえ後攻であっても基本的にはそのターンのうちに特殊召喚のための素材に使われることになり、一度出した後に蘇生しても使える効果がないため、3000という高い攻撃力は《ドラゴン・目覚めの旋律》でサーチできることくらいにしか活かせないことがほとんどでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP015 | サイバー・ドラゴン・ネクステア |
|
VJ付属カードとして登場したカードで、このカードが登場した頃が「また《サイバー・ドラゴン》関連のカードかよ!」と言われていた時期のピークだったと思います。 手札のモンスター1体を捨てて手札から自己SSできるレベル1モンスターで、さらに場や墓地でサイドラ扱いになる効果と召喚誘発の蘇生効果もついているという、類似する自己SS能力を持つ《ビッグ・ワン・ウォリアー》のほぼ上位互換となるカードです。 メタビ系のデッキに《機械仕掛けの夜-クロック・ワーク・ナイト-》を打点補助として採用し、さらに《キメラテック・フォートレス・ドラゴン》によるモンスターの全喰いを狙う場合、採用すべきサイドラは当然打点要員にもなる原種サイドラが優先度が高いものと思われますが、リリースなしでNSできて自己SS条件もより良いこちらも捨て難いものがあると感じます。 ただこのカードの場合は自己SSするために手札を切ることがメタビ系のデッキとは相性が悪く、アドバンテージになる蘇生効果も通常の構築のメタビでは使えそうにないので、結局原種サイドラでいいとなってしまいそうですが…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP016 | 幻創龍ファンタズメイ |
|
かつてサイドデッキの大常連モンスターとしてその名を馳せ、一度廃れた後に評価時点で再びサイドデッキの常連として顔を出しつつある最上級ドラゴン。 相手のLモンスターの特殊召喚に反応して手札から飛び出し、素材要員を場に展開しながら手札交換を行って誘発を引き込みにいくという動きができる。 ドロー枚数とデッキに戻す枚数は相手の場のLモンスターの数によって決定され、1体でも1枚の数的アドバンテージになり、2体以上になっても獲得できる数的アドバンテージは変わらないものの、ドロー枚数が増えるためより質の高い手札交換となります。 手札にきてしまった引きたくないカードをデッキに押し戻す作業をできるだけ手間のかからない方法で行いたいデッキにとっては、単純に手札が増えるよりも価値があることも少なくありません。 またこのカードもただ出てくるだけではなく、自分のや踏み台にされるリスクを大きく軽減できます。 このカード自体の妨害能力は大したものではありませんが、比較的緩い条件で手札から飛び出せるモンスターとしてはステータスも効果も概ね満足できる性能であると言っていいでしょう。 よく「ズメイ」という略称で呼ばれるモンスターですが、これは単なる略称ではなく元ネタとなったドラゴンの正式な名称でもあります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP017 | 爆走軌道フライング・ペガサス |
|
アニメ版ゼアルで登場した【列車】の使い手であるデュエリスト「神月アンナ」ご本人がモデルになっていると思われるモンスター。 召喚誘発効果で墓地の同名カード以外の地機械1体を効果を無効にして守備表示で蘇生でき、それがレベル4モンスターならそのままランク4Xに、それ以外のレベルなら自身の起動効果により自身のレベルを対象にしたモンスターに合わせることで、そのレベル帯のX召喚を行うことができる。 墓地から特殊召喚可能な地機械ならどんなにレベルや攻撃力の高いモンスターでも蘇生できるため、レベル8や10のモンスターを蘇生すれば高ランクのXモンスターも簡単に出すことができ、特殊召喚でも蘇生効果が誘発するため《転回操車》によるリクルートも有効です。 また地機械ならレベルを持たないX・Lモンスターも蘇生可能で、レベルを合わせる効果を使わなければXモンスターでしか攻撃できないデメリットは発生せず、使ったとしても展開関係の制約はないため、自身と蘇生したモンスターでS召喚やL召喚を行うのも普通に有効です。 以上のことから【列車】で使うのが最も力を発揮するカードである一方で、それ以外の地機械テーマのデッキに投入する価値も一定以上あるカードと言えるでしょう。 ただし基本的には召喚権を切る墓地からの特殊召喚なので、妨害にとても弱いのは類似効果を持つモンスターと同じであり、そうなった時にお茶を濁せるリンク1モンスターなども評価時点では存在していないので注意したい。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP018 | 儚無みずき |
|
《増殖するG》のライフ回復版とも言える手札誘発モンスターで、定数のレベルと攻守を持つ妖怪少女と呼ばれるアンデットチューナーの1体。 投げ捨てたにも関わらずライフが回復しなかった場合は自身のライフが半分になってしまいますが、相手がメイン及びバトルフェイズに発動した特殊召喚系の効果にチェーンして投げ捨てればこのデメリットを被ることは稀と言えるでしょう。 しかしドローという相手の特殊召喚した回数がまるまる数的アドバンテージに直結するGに対し、このカードによるライフ回復を盾にしたりライフが半分になるデメリットをチラつかせて相手に展開の中止を迫ることは正直難しい。 何しろ何万ライフがあったところで返せない盤面を作られたら死が先延ばしになるだけなので、返すための手数を増やせるGとは抑止力としての強さが根本的に違うんですよね、ゲームをぶっ壊す力があちらの方が段違いに高い。 お互いのターンのエンドフェイズ以外にいつでもフリチェで手札から投げ捨てられるモンスターとして見るべきところはあり、こちらは墓地に送られなくてもいいので《マクロコスモス》などの影響下でも構わず投げ捨てられるメリットもあります。 ライフ回復なんて何の抑止力にもなってないねと油断して展開してきた相手に対して、お互いのライフ差で威力が上がるタイプのカードで反撃してドーン!なんてのも乙かもしれませんね。 このモンスターが登場する頃は、デッキに触る効果を無効にする《灰流うらら》、墓地に触る効果を無効にする《屋敷わらし》と来てきたので、次は間違いなく、手札に関する3つの効果を無効にする手札誘発が来るなと予想されていましたが、さすがにそんな無茶なカードは出ませんでしたね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP019 | カクリヨノチザクラ |
|
相手の墓地の魔法罠を必要とするその性質から自己SS効果持ちのレベル1モンスターとしては当然として、墓地メタとしても蘇生札としてもどれをとってもあまりに癖が強く、総合的には標準以下の性能という感じのモンスター。 相手ターンに使える効果は1つもなく、少なくとも妖怪少女のそれを予感させるような触れ込みに対してデュエリストたちが期待したものとは遠くかけ離れた何かという印象で、少なくとも強くはないんじゃないかなと…。 4種類のEXモンスターを示す4色のしゃれこうべがとてもオシャレでイラストアドバンテージは高いと思いますが、効果的には敢えてこのモンスターを選ぶ理由がどうにも見当たりません。 自分の墓地のEXモンスターの除外と蘇生を1枚で同時に行えることは何かに使えそうな感じがするだけに、自己SS効果も蘇生効果と同様に相手の墓地に依存せずとも発動できる仕様ならまだ良かったんですがねえ。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP020 | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール |
|
《ブラック・マジシャン・ガール》を初めて名称指定の融合素材とした融合モンスター。 自身の指定する方法以外ではいかなる効果でも特殊召喚することができませんが、融合召喚する手段自体は選べるくらいには色々ありますし、難易度もそう高くはありません。 発揮する効果はお互いのターンにフリチェで使える表側表示のカード限定の《サンダー・ブレイク》となるもので、手札コストを要求されるのは気になりますが毎ターン使える妨害効果としては永続魔法やフィールド魔法の発動時効果にも有効であることも込みでぼちぼちの能力です。 とにかくいかにして少ない消費で融合召喚できるかにかかっているカードという感じですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP021 | キメラテック・メガフリート・ドラゴン |
|
《キメラテック・フォートレス・ドラゴン》の亜種となる特殊な召喚条件を持つ融合モンスター。 あちらと違って一度にたくさんは食べられないが指定の位置にいるEXモンスターで墓地に送ることができるものなら何でも食べられるのが特徴で、強化倍率も高く攻撃力は最低でも2400になる。 しかし11期におけるルールの再変更により、Lモンスター以外のEXモンスターをEXデッキから特殊召喚する場合、必ずしもEXモンスターゾーンに出す必要がなくなったため、それらのEXモンスターに対しては有効な除去手段ではなくなってしまったことが痛い。 現在でも様々な理由でLモンスター以外のEXモンスターをEXモンスターゾーンに出す場面も多少はありますが、あまり期待しない方が良いでしょう。 もちろん強い耐性や妨害能力を持つLモンスターや、エクストラリンクを決めてくるような相手には有効なので、メインデッキに《サイバー・ドラゴン》を採用しているならEXデッキの枠が許す限り1枚は採用しておきたいカードです。 まああまりに展開力が高いデッキにもなると、肝心の除去したいリンク4以上のモンスターがメインモンスターゾーンに出てくることも普通にあるわけですが…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP022 | ミレニアム・アイズ・サクリファイス |
|
《簡易融合》から出して立たせておくことで、そのターンの間うららなどの墓地に捨てるタイプの手札誘発を牽制できる制圧モンスターとして使えるカード。 誘発ケアが不要なところまで展開できたら、自壊する前に特殊召喚のための素材にしてしまえば良く、単独でも《リンクリボー》や《サクリファイス・アニマ》といったリンク1のL素材にしてしまえるのもかなり強い。 《簡易融合》を再度制限に送り込んだ元凶と言われており、それに伴い必要かどうかわからないケアのためにこのカードを出すと、そのデュエル中は簡易サウサクを使えなくなるというジレンマを生むことになった。 自ら動けるサウサクもかなり捨て難いので、この辺りは自分や相手のデッキや踏んだ場数などのプレイヤーの勝負強さや手腕が問われるところでもある。 また融合素材として《サクリファイス》を名称指定しており、もう一方の素材指定が効果モンスターなら何でもOKという激ゆる指定なので、融合素材代用モンスターが入るデッキでは《超融合》とセットで採用しておくのもアリでしょう。 簡易に頼らずに普通に使う場合、他の『サクリファイス』モンスターたちと違って魔法罠ゾーンに空きがある限り自身の効果で何体でも吸えるので、《サクリファイス・フュージョン》の墓地効果や《ミレニアム・アイズ・イリュージョニスト》の手札誘発効果の恩恵を最も受けられる『サクリファイス』モンスターとなっています。 ただし《サクリファイス》やサウサクの持っていたサクリファイスシールド能力を失っていることには注意しましょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP023 | 琰魔竜 レッド・デーモン・アビス |
|
相手の場の表側表示のカード1枚を対象にその効果を無効にする効果を、お互いのターンにフリチェで無条件に出せるという実にわかりやすく強い妨害能力を持つレベル9の「レッド・デーモン」Sモンスター。 モンスターや永続魔法・永続罠のみならず通常魔法や速攻魔法や通常罠さえも捉えるその性質から、相手ターンでの妨害だけでなく自分のターンで相手の妨害を弾き飛ばすことにも使えるし、完全フリチェなので場に降り立った瞬間から相手の効果にチェーンできるようになるためその性能は一級品。 こういう妨害持ちが自分の使ってるテーマにいてくれたらどれだけ有り難いだろうかと確実に感じられる性能です。 ただしS素材縛りは非チューナー側が闇ドラゴンSモンスターというきわめて限定されたものになっているため、使用できるデッキは限定されます。 該当するモンスターにはレベル8に《混沌魔龍 カオス・ルーラー》という大鉄板が存在しており、チューナー側は全くの無指定であるため、こちらとレベル1チューナーまたは自身の能力でレベル1に変化する《レボリューション・シンクロン》のようなチューナーを併用するデッキならまずEXデッキに席が用意されるカードです。 レベル1チューナーの方は《ジェット・シンクロン》のような、ルーラーを出すためのS素材に使った後に自身の自己蘇生能力で続けてこのカードをS召喚するための素材にできるモンスターならなお良いですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP024 | 深淵に潜む者 禁止 |
|
フリー素材で2体素材の汎用ランク4Xモンスターの1体。 X素材に水属性モンスターを用いることで自身を含む自分の場の水属性モンスター全ての打点が上昇し、それにより攻撃力が2000を超える。 しかし水属性モンスターを使わないデッキで使用する場合、攻撃力は下級アタッカー以下であり、素材にレベル4モンスターを用いるため、X素材にしたモンスター以下のステータスになってしまうことも少なくない。 だがその効果はあくまでおまけであり、本命はお互いのターンでフリチェで発動可能な、相手の墓地で発動する効果をそのターン完全に封印するという強力な墓地メタ能力の方となる。 モンスター効果だけでなく墓地効果を持つ魔法罠カードの効果も発動できず、相手メインより前の相手ターンでも使える上に、発動後にこのカードが場を離れても効果が消えないという強いターンスキップ性を持つため、墓地を多用して盤面を作るデッキにとって先攻で相手に出されたこのカードは大きな脅威となります。 このカードやバグースカなど、汎用ランク4Xで1体でここまで特定の領域を厳しくメタれるカードは貴重であり、EXデッキに2〜3枚しかランク4を入れない場合でも優先されることの多いモンスターである。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
9 | JP025 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ |
|
効果破壊耐性だけでなく墓地効果持ちにも強い単体除去効果と、ターン1で使える発動する効果に対するパーフェクトカウンターを抜き放つ『サイバー・ドラゴン』Xモンスター。 まともにX召喚することは困難な素材指定ですか、レベル5機械族モンスター2体でX召喚できる《サイバー・ドラゴン・ノヴァ》に重ねてX召喚することもでき、その方法で出しても効果が劣化することはない。 またそのノヴァも汎用ランク4Xモンスターでもある《星守の騎士 プトレマイオス》に重ねてX召喚できることから、プトレノヴァインフィニティの呪文で制圧の添え物として活躍しました。 ただしこの呪文を唱えるためにはEXデッキを余分に2枠も使うことになり、さらにプトレマイオスにノヴァを重ねる効果を使うためにはプトレマイオスを最低でも素材3体でX召喚する必要もあって、起動効果による場のカードの除去+無効破壊のパーフェクトカウンターだけなら《フルール・ド・バロネス》で1枚からでも可能であるため、現在ではプトレマイオスもこのカードも少なくとも禁止カードに指定されるほどのカードと認識されることはなくなっています。 まあそれはそれとしてターンを跨げば複数回使えるパーフェクトカウンターが弱いわけがないし、モンスター限定とはいえ除去方法はこちらの方が遥かに強いので現在でも使う価値のあるカードというのは間違いありません。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP026 | 真竜皇V.F.D. 禁止 |
|
30打点の圧倒的最強の汎用ランク9。 属性を1つ宣言してどうのこうのと書かれているが、実質的には元々の属性がなにとか一切関係なくターン終了時まで相手フィールド上の全てのモンスターは攻撃できず効果も発動できないという効果である。 しかしよく読むとフィールド以外での効果の発動も捉える仕様になっており、何の属性を宣言しようとフィールドの発動するモンスター効果は封殺できるので、その状況で特に嫌な手札誘発や墓地誘発モンスターの属性を宣言しておくことが望ましい。 当然のように相手ターンでも使えるが、自身がフィールドを離れようとこの効果の発動後に出てきたモンスターであろうと関係ない残存効果という最強裁定から、徒党を組んで相手を圧殺する制圧系モンスターズの一員としても悪名高い。 闇属性を宣言すれば、たとえ発動しない強固な耐性持ちモンスターであろうと、たちまち超融合の餌食となる。 生まれた時期が違うので仕方ありませんが、《極神皇トール》と仕様が逆なんじゃないかと思ってしまいますね。 誘発即時効果なのでどのみち一回は効果を使われてしまいますが、出てきた時にこのカードを始末できるクイックエフェクトがあるなら、こちらのターンでも邪魔してくる前には処理しておきたいところです。 ランク9なので許されていた感が強いモンスターですが、そろそろ限界が近いか…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP027 | 水晶機巧-ハリファイバー 禁止 |
|
幾度となく禁止カード化の脅威に晒されながらも今日まで超展開の起点として生き続けるリンク2モンスター。 後の特殊召喚効果を持つ多くのリンクモンスターの面々にリンク素材に使用する際の様々な制限を設けられるようになった元凶でもあります。 相方は《リンクロス》、セレーネ、アウローラドンなど数多く存在しており、現在では禁止にするほどではないというのが大多数の見解となりますが、ちょっとしたことでいつでも一線を超えられる危うい存在であることは確かという感じです。 同じ機械族でもあるジェットやオライオン、汎用手札誘発でもあるうららやヴェーラーなどの小粒なチューナーと関係が深いイメージが強いこのモンスターですが、リクルートできるのはレベル3以下のチューナーということで、エアベルンなどの案外打点の高いモンスターも呼び出せたりします。 追記:2022年7月のリミットレギュレーションにて、数々のモンスターを身代わりに生き続けたこのモンスターも遂に禁止カードとなりました。 これにより、ただ単にチューナー(特にレベル3以下)であるだけでメリットとなる場面がかなり減ってしまい、ハリファイバーが本当に救済していたのはモンスター効果がへなちょこな、低性能の効果モンスターのチューナーだったのかもしれないとさえ感じますね。 今度ばかりはラドンを隠れ蓑にはできなかったようで、これにはスプライトの影響もあったといったところでしょうか。 さあ今こそ100%の私怨を込めてハッキリと言いましょう、私は誰からも頼られるステキなアナタのことが死ぬほどいけ好かなかった、さらばハリファイバー、願わくば永遠のサヨナラであらんことを。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP028 | 閃刀姫-カガリ |
|
2023年末以降にさらなる新規カードが加わり、実に10種類ものLモンスターが属するようになった「閃刀姫」ですが、それらの中でも原点にして頂点、閃方姫Lモンスターの顔とも言える存在がこのカードになります。 最初見た時は「このアンバランスなイラストは一体何…?」と思ったのも今となっては懐かしい。 その役割はサルベージ効果によって発動に名称ターン1のない《閃刀起動-エンゲージ》や《閃刀機-ホーネットビット》などの連打となり、通した回数がそのままアドバンテージに直結する重要モンスターです。 あまりに簡潔過ぎる効果でこのカードだけを見ても当然強さはわからないわけですが、一度にでも自ら使うか【閃刀姫】の相手をすればその優秀さはすぐに理解できることでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP029 | サクリファイス・アニマ |
|
《サクリファイス》の魂という意のあるカード名で、その見た目は「逆さファイス」という感じのLモンスター。 リンク1で気軽に破壊耐性を貫通する単体除去をかましてくる強力モンスターであり、レベル1を使用するデッキなら《リンクリボー》と共に常に採用の余地がある。 ただしこちらはトークンはL素材にすることができず、除去効果はこのカードの正面にいるモンスターしか対象にできないため、相手がこのカードの存在を意識してモンスターを出す場所を考えれば容易くケアできてしまうという性質がある。 よって有効に効果を使いたい場合、壊獣などの相手のモンスターゾーンの任意の位置にモンスターを出せるカードと併用すると良いでしょう。 他にも単なる中継役として使うことも可能で、たとえば《双穹の騎士アストラム》は自身のリンク素材に「エクストラデッキから特殊召喚されたモンスター」を要求するので、リンクリが既にリンク召喚済みか《強欲で金満な壺》の除外コストで出払ってしまっている場合に出して、その素材とすることができる。 総じてリンクリに次ぐ2番手という感じが強かったこのカードですが、2024年には海外でリンクリが禁止カードに指定されてしまっており、国内そうなればこのカードの存在も無視できないものになるはず。 なお《サクリファイス・フュージョン》の墓地効果や《ミレニアム・アイズ・イリュージョニスト》の効果などが指定する「サクリファイス」の仲間には入れてもらえなかったが、《黄金の邪教神》の登場でこのカードもちゃんと「サクリファイス」モンスターに含めてもらえるようになりました。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP030 | 転生炎獣アルミラージ |
|
通常召喚された攻撃力1000以下のモンスターなら何でも素材にできる超便利なリンク1。 《クリッター》をはじめ多くのモンスターを能動的に墓地に送ることができ、墓地誘発効果を中心に様々な悪巧みができてしまう。 自身がサイバース族であることや炎属性であることが活かせるデッキならさらに有用性が増すが、メインに何も仕込まずともエクストラにセキュアガードナーを1枚挿して変換するだけでも安全装置付きの打点になることができる。 自分の場に対象となる他のモンスターさえ存在していればフリチェで自力で退場できるのも超便利で、このカードの登場でクララ&ルーシカはほぼほぼお役御免になってしまった。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP031 | サンダー・ボルト |
|
不意に放たれた裁きの雷が相手フィールドの全てのモンスターを襲う! 今時モンスターを除去する以外に効果がない通常魔法なんて誰も入れてないでしょと侮っていると、帚やツイツイなどの伏せ除去で探りを入れてから続けて使われると普通に震え上がるカード。 先攻で腐るだの効果破壊耐性持ちに効かないから微妙だの言っても、発動タイミングの指定がなくあらゆるコストも制約もない全体除去としては最高クラスであることは間違いありません。 特にモンスター除去としては、セットモンスターを始末できないライボルや表側攻撃表示のモンスターしか倒せないライストなど比にならない超高性能カードである。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP032 | ハーピィの羽根帚 制限 |
|
サイド込みなら全く入らないなんてことはまず考えられない、全ての罠デッキが何よりも恐れる究極のバック除去カード。 罠デッキを使っていて後攻初手に相手がこれを握っていることが多いと感じるなら、もしかしたら徳を積み足りていないのかもしれません。 いつまた禁止になるかわからないカードではありますが、魔法と同じくらい罠の強さも隆盛しており、よほどの展開デッキでなければ基本サイドに引っ込んでいるということは全く打ちどころがないデッキも少なくないということなので、当分の間は大丈夫でしょう。 何よりも《ハーピィの羽根吹雪》のためにも禁止カードにするわけにはいかないカードといった印象である。 ただし通常魔法は通常魔法、速攻魔法である《コズミック・サイクロン》や《ツインツイスター》の方が勝っている部分もけして少なくはありません。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP033 | 死者蘇生 制限 |
|
怒涛のさ行がプレイヤーの舌を襲う最古にして最高の蘇生魔法で、お互いの墓地から無条件でモンスター1体を蘇生できる至高のカードであり、状況次第では先攻1ターン目からでも余裕で使っていく価値があると思います。 汎用性が非常に高い反面、《ハーピィの羽根帚》や《おろかな埋葬》のようにそのデッキにおける明確な役割が定まっていない、引いてきた時の出たとこ勝負のようなカードであるが故に、現在ではかつてほどこのカードを使うデッキも少なくなりました。 その一方でこれだけ高性能なカードであるにも関わらず、《激流葬》や《聖なるバリア -ミラーフォース-》などと同様にこのカードを名称指定したサポートカードも存在するため、近年はテーマネームを持つ類似魔法に押され気味ではありますが、今後もその存在価値が揺らぐことはないでしょう。 原作において1枚しかデッキに入れられないことが言及されている珍しいカードで、OCGでも2020年現在制限カードとなっていますが、それ故に《アンクリボー》も《千年の啓示》もサーチだけでなくサルベージもできるようにして気を利かせてくれています。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP034 | ミラクル・フュージョン |
|
遊戯王OCGに《龍の鏡》と共に「墓地のモンスターを融合素材として除外する」という融合召喚の手法を持ち込んだ「E・HERO」専用のフュージョン魔法。 墓地の準備さえできていれば手札・場からの消費はこのカード1枚だけで融合モンスターを融合召喚できることから大きな人気を博しました。 今となってはデッキ融合と違って墓地の準備が必要なのでそれほど強いカードとされることは少なくなりましたが、対応する融合モンスターは現在も増え続けており、ある種族やテーマの融合・フュージョン魔法にこれと同じ仕様のやつがあればどんなにいいだろうかと思っている人も少なくないはず。 これだけの性能でかつ「フュージョン」魔法カードであるにも関わらず、《E・HERO サンライザー》という名称指定の専用のサーチャーまで有しており、これらの要素が同期の《龍の鏡》とは融合召喚されるモンスターの強さに依らないところで決定的な差となっている。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP035 | 超融合 準制限 |
|
対象を取らず、発動にあらゆる効果をチェーンさせないその性質から、魔法カードの発動・適用及び特殊召喚自体が事前に封じられていなければ突破できない耐性はほとんどないという素晴らしいカード。 しかもお互いのターンにフリチェで発動できる速攻魔法ときており、これは発動に手札コストを要求されるのもやむを得ないでしょう。 相手モンスターを2体を素材とすることが当然の理想だが、このカードの存在がある以上、例えば「効果モンスター2体」のような、そう簡単になんでも融合素材にできる素材指定の融合モンスターを新カードとして出せないのも実情で、このカードが環境でも活躍するようになって以降は、意図的に自分の場のモンスターしか融合素材にできないような指定になっている融合モンスターも増えています。 ただし魔法の効果またはカードの効果を一切受けないモンスターや、《百万喰らいのグラットン》などの融合素材にできない制約のあるモンスターだけは倒すことができないので注意しましょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP036 | ドラゴン・目覚めの旋律 |
|
このカードと手札1枚をデッキの条件に合った攻守を持つドラゴン族と入れ替える通常魔法。 無効にされた時の損失は大きいですが、一度に2枚サーチができる魔法カードなので当然その有用性は高いです。 条件となる攻守の数値を見て分かる通り青眼の存在を強く意識したサーチ範囲となっており、登場当時はサーチ先が重いモンスターや特殊召喚モンスターばかりであまり高い評価を受けられずにいましたが、青眼関連のカードを中心にサーチ先となるドラゴン族が充実したことで重宝されるサーチ札となりました。 元々は遊戯王Rで海馬が使用したカードで、《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者-》が原作ではその片鱗が見られなかったミュージシャンとして目覚めたことを示すカードでもあります。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
8 | JP037 | RUM-七皇の剣 |
|
ザ・絶対に初手に来てほしくないカードとなる「RUM」カードの中でもかなり特殊な存在。 何しろ通常のドロー以外で手札に引いた時点で発動する手段がなくなり、ドロソとかで引いても腐るというデッキに入れることそのものが常に一定レベルのストレスになるのだから当然初手に来られたらたまらない。 デュエル中に1度しか発動できないため、ピン挿しして引いた時に上振れるカードとして扱うのが基本となりますが、そのために最低2枚、色々選ぼうとすると6枚から8枚のEXデッキの枠を必要とするため、例えこの専用デッキを組む場合でも特殊召喚するモンスターはある程度絞っておきたいところ。 特殊召喚できるモンスターは今となってはどれも古いカードばかりですが、力づくで追加効果を適用できる条件まで満たして出せるだけあってさすがにそれなりに強いXモンスターも存在しています。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP038 | 復活の福音 |
|
自分の墓地のレベル7と8のドラゴン族1体を完全蘇生させる効果に、発動しない効果によって墓地から除外することでドラゴン族の破壊の身代わりになれる墓地効果を持つ魔法カード。 墓地効果の方はよくある1体の破壊の身代わりになるやつと思いきや2体以上の破壊もこのカード1枚で全て守り切れるため、相手がメインフェイズ1開始時に《サンダー・ボルト》を落としてきても盤面を台無しにされないし貴重な妨害を吐かされずに済みます。 サーチ手段のない蘇生札ではありますが、手札に来た際は発動して墓地に送るだけで展開は伸びるわ盤面の硬度は上がるわで良い事づくめです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP039 | おろかな副葬 準制限 |
|
おろ埋同様に、もはやいつ制限カードになってもおかしくないところまできたカード。 そのくらい墓地で発動する効果を持つ魔法や罠はあまりにも増えすぎました。 ご丁寧にも墓地に送られたターンにはその墓地効果を使えないようにされている魔法罠は、単純なフィールド発動との連発に限らず、このカードの存在も意識していると見て差し支えないだろう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP040 | 墓穴の指名者 準制限 |
|
基本的には相手の手札誘発を貫通して自分のやりたいことを無理矢理ねじ込むためのカード。 デッキの回転には直接関係ないため、手札誘発軍団と一緒に複数引いてきてしまうと自分のやりたいことの邪魔になる場合も当然ある。 が、それを差し引いても余裕で強く、場にセットしても使える、ガチでもそうじゃないデッキでも手札誘発入れていても入れてなくても様々な場面で使用可能な汎用性が高すぎる1枚です。 自分のやりたいことだけやってても勝てないという現実を思い知らされるカードで、墓地に同名モンスターがいれば場のモンスター効果も無効にできることからほとんどのテーマデッキ相手に有効な打ちどころがあるのも優秀過ぎます。 展開系のデッキでは抹殺と並んでまず間違いなく採用されるレベルにまで至っているカードです。 使い慣れていない人は、DDクロウのように魔法・罠カードを除外することはできないのは覚えておきましょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP041 | 閃刀起動-エンゲージ |
|
通常魔法1枚の発動で1枚がサーチ、1枚がドローで手札が1枚増えるという、ただの質が保証された2ドローでしかるべきデッキでは実質《強欲な壺》の上位互換などとよく言われるカード。 1ドローが追加される条件はそれほど厳しくない上に、このカード自体にもテーマネームがあってサーチが利くし、発動に名称ターン1すら設定されていない。 評価時点では【閃刀姫】は既に環境上位には位置していないデッキですが、サーチ先にも《閃刀機-ホーネットビット》のような展開を伸ばせる汎用性の高いカードが存在していて出張採用も可能であることから、簡単に無制限とはならず、評価時点でも準制限カードに留まり続けている。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP042 | 強欲で金満な壺 準制限 |
|
第10期に登場した「〇〇で△△な壺」魔法カードシリーズの1枚で、まさしくこれを待っていたという実に素晴らしいドローソースで、評価時点において私が最も好きなドロー魔法です。 EXデッキのモンスターを3体または6体ランダムに裏側除外することにその除外枚数3枚につき1ドロー、つまり最高で2ドローできるというデッキによってはほぼ《強欲な壺》と言えるカードであり、《強欲で謙虚な壺》のように特殊召喚やバトルを封じられないためテンポを乱さないのが素晴らしく、メインデッキから必要なカードが吹き飛ぶ事故が起こらないので概ね《強欲で貪欲な壺》よりも人を選びにくい。 6→6→3と除外していくことで、エクストラデッキを一切使わないデッキなら最後までしっかりドローできるのは素晴らしいが、発動できるのは自分メインフェイズ1開始時に限られており、これを使うと発動後の制約によってそのターン他の効果でドローすることができなくなるので、特に同ターンにおける強貪や《命削りの宝札》との共存ができないことに注意したい。 またメインフェイズ1開始時にしか使えないということは、モンスターの召喚やスペルスピード1のカードの発動を相手の各種クイックエフェクトよりも優先的に発動できる権利を捨てることになる点も無視はできない。 エクストラデッキを大量に使用してまで2ドローをする点から、展開の選択肢が減ってデッキの質が下がる、そもそもこのカードを使うこと前提となると全除外されては困るEXモンスターを無闇に複数採用しなければならなくなることも多くなり、構築段階からエクストラデッキの質を下げることに繋がりかねません。 とまあ色々と気になる点もないことはないのですが、それを差し引いても強いカードです。 |
|||
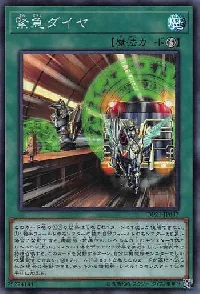 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP043 | 緊急ダイヤ |
|
全種族中でも特に種族と属性の両方を指定した効果が多い機械族ですが、それらの中でも最も大きな集団を作っている地属性の機械族が持つ最強サポート魔法がこのカードとなります。 相手の場に依存する発動条件がありますが、ノーコストで2体のモンスターをリクルートできるのはかなり強力で、守備表示でかつ効果が無効になるものの、自壊系のデメリットはなく、特殊召喚の素材に使うことには全く制限がかからない。 発動ターンの制約はよくある「機械族以外EXデッキから特殊召喚できない」「機械族以外のモンスター効果を発動できない」かなと思いきや、機械族でしか攻撃宣言できないだけなので、リクルートしたモンスターを利用したEX展開も自由に行うことが可能となっています。 速攻魔法なので相手ターンでの発動もでき、そうすればデメリットも関係なくなるし、後攻時にドローフェイズやスタンバイフェイズに手札から発動することもできるため、自分メインフェイズ開始時にまずそれらのモンスターを素材に《フルール・ド・バロネス》のような効果の発動を無効にする系のモンスターを特殊召喚することで、相手が使用するメインフェイズにフリチェで発動できる系の効果にも対応することが可能となります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP044 | 抹殺の指名者 制限 |
|
あらゆるカードによる妨害を先攻から止めてやりたいというデュエリストのあくなき欲求から生まれてしまったカード。 目当てのカードを自分のデッキにも採用しなければならないが、元々自分の身を守る目的・自分のやりたいことを突き通す目的で自分のデッキにも採用されるうららG墓穴泡影などは普通にしていても止めやすい。 罠ビ系のデッキが相手なら強金などのドロソを捕まえるのにも使えたりするだろう。 ニビルが苦手だがニビルをケアすることが自前のカードでは困難な展開デッキは、この抹殺&ニビルセットが一番楽ができると思います。 先攻で握っているだけで問答無用で誘発を貫通でき、お互いのデッキと手札によってはそれだけでほぼ勝ち確レベルまで展開できるこのカード、制限カードとしたのは大英断だったと思いますね。 何年か前までは墓穴抹殺合わせて6枚採用できていたなんて本当に信じられない…。 それはそれとして、撲滅の指名者もちょっと見てみたいななんて思ったりもしてます。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP045 | 魔封じの芳香 制限 |
|
魔法カードの発動タイミングを大幅に遅らせて相手のテンポを乱す永続メタ罠の一種で、セットできないペンデュラムならPゾーンに置くことすらできなくなる。 《墓穴の指名者》や《抹殺の指名者》など、主に自分のターンに手札から使いたい速攻魔法はこのカードの効果の適用下ではそういった使い方が不可能になり、伏せても次の自分のターンがこないと発動できないので、速攻魔法の動きはこのカード1枚でかなり鈍くなる。 先攻で伏せて相手のドローフェイズやスタンバイフェイズで開けば《ハーピィの羽根帚》や《サンダー・ボルト》を一発たりとも撃たれることはなくなるし、場のカードを複数除去する効果が充実したデッキで使用すると、次のターン以降に使おうと相手が伏せてきた魔法カードを使用する前に蹴散らせるのでさらに効果覿面となります。 自分にとっても相手にとっても、発動自体は可能な《王宮の勅命》とどっちの方がやり辛くなるか、デッキによって結構分かれてくる辺りも面白い。 後攻からだと勅命以上に弱いのが気になる感じで、先攻で伏せられても《超融合》・《禁じられた一滴》・《コズミック・サイクロン》といった裏目も多く、正直信用しきれない部分も多いのですが、それでも魔法対策の罠カードとしては間違いなくかなり強い部類になります。 何しろ2022年4月のリミットレギュレーションで勅命は禁止カードになっちゃったので、1枚でそのターンの魔法カードの発動をまるまるストップできるこのカードの価値はさらに大きくなったと言えるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP046 | バージェストマ・ディノミスクス |
|
前衛・後衛両方に効く対応範囲が光る除去罠、しかもフリチェで除外という極めて強力なものとなっている。 破壊耐性や墓地効果を持つ魔法・罠カードにも有効なのは素晴らしいの一言で、状況によっては通常魔法や通常罠に対して打つ価値もある。 モンスターを除去するだけなら、コストがなく操作や大捕で奪われた自分のモンスターを奪い返すといった使い方もできる脱出の方が強いが、召喚誘発系の効果を持つ下級モンスターなどで殴ってくるメタビ気質のデッキなどに対してはこちらの方が有効である。 効果処理時に手札を1枚要求されるが、腐ったカードを有効に捨てる手段として考えることもでき、コストではないので無効にされて払い損にならないのも気が利いている。 耐性持ちモンスターとして復活する効果もあるため、罠を多用するデッキでの除去罠としての汎用性は非常に高い。 メタビで使う場合は手札消費が気になるところだが、脱出やエアフォが効果が薄いデッキや苦手な永続メタ魔法や罠に泥沼にされたら1度は採用を考えてみたくなる1枚ではないでしょうか。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP047 | 幻影騎士団シェード・ブリガンダイン |
|
このカード自体は単なる貧弱なステータスで通常モンスター扱いの通常罠カードの罠モンスターでしかないのですが、その実は様々な価値が詰まっているカード。 「単独でセットしたターンに発動できる通常罠カード」「罠カードのX素材となれるレベル4モンスター」「幻影騎士団ネーム持ち」といった性質から、【蟲惑魔】ではX素材の調達や先攻から《セラの蟲惑魔》の効果を使用する手段として、【クロノダイバー】では《クロノダイバー・リダン》の最も強い効果である罠カードをX素材に持つ時の効果を得る手段として使われてきました。 セットしたターンに発動できる条件として墓地に罠カードが存在してはいけないため、自分が投げつけた《無限泡影》や相手のランダムデッキデスによってこれを邪魔してしまう可能性がありますが、漫画版で登場した「幻影騎士団」カードの中では間違いなく有用性の高い1枚と言っていいでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP048 | センサー万別 制限 |
|
《群雄割拠》の逆バージョンでこちらは同じ種族のモンスターを1体しか出せなくなる。 概ね《群雄割拠》よりも突き刺さるデッキが多い拘束力の高い永続メタ罠で、種族統一系のデッキはこのカードに対処できる除去カードやコントロール奪取を入れているか、融合系などの場への展開を伴わなくても大型モンスターを出せるデッキでなければエクストラからもまともにモンスターを出せずに一方的に負けかねない。 種族がバラバラでかつ低速メタビ系の叢雲ダイーザやサブテラーはもちろん、構築次第では空牙団やTGなどの多種族デッキでも使っていける。 《群雄割拠》と同じく後出ししても強いという他の多くの永続メタ罠と一線を画する性質を持つため、搭載可能なデッキならメインとは言わずともサイドには入れておきたい強力カードです。 ちなみに《群雄割拠》と同時に発動すると、2つの効果がミックスされた結果、お互いに場に表側表示モンスターは1体しか存在できないということになる。 場に出して殴り手とするモンスターを例えばボーダー1種類しか採用せず、残りは全部誘発モンスターズみたいな特殊な構築なら、両方を同時に採用することも可能である。 他にも《ライオウ》&アズルーンの組み合わせで御前センサー両張りなんてのもいけるかと思います。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP049 | 無限泡影 |
|
基本的にアド損になる可能性があるカードの採用は忌避されるメタビ系のデッキにすら採用されることがある素晴らしい罠カード。 後攻からでも勝ちたい、制圧されてもなんとかしたい、そんな希望を繋げてくれる。後出しでも使えるセット時の効果も優れており、メタ系の永続魔法・罠カードや鎮座している神罠を一瞬だけ黙らせてくれる。 また相手は不用意にセットカードがある縦列で魔法カードを発動すると、このカードで無効にされるおそれがあるため、それを意識したプレイングが必要になる。 なんといっても《墓穴の指名者》やその他ほとんどの手札誘発系モンスター効果でケアされないのが強み。罠カードなので《三戦の才》を踏むこともない。 その採用率の高さから抹殺するために1枚だけデッキに入れている高速デッキも少なくない。 ただし対象耐性を持つモンスターやモンスターやフィールド魔法をこちらに押し付けてくるタイプのカード(トーチゴーレムや盆回し)には弱いので注意。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP050 | 大捕り物 |
|
奪ったモンスターがエクシーズ素材になった時と裏側になった時だけはぶっ壊れずに場に残るタイプの永続罠。 ちなみに当たり前ですが、相手がチェーン発動したカードの効果やコストで対象が不在になって不発になった場合、自壊はせずに無意味なカードとして場に残るのでバウンスチャンスです。 効果を無効にしただけ、破壊して墓地に送っただけでは、そのモンスターを蘇生するなりしてすかさず各種素材に利用されて結果妨害の意味がなかったということを防げるのがこのカード特有の強み。 大型モンスターを封じることには長けているが、通常召喚からそのまま殴ってくるだけの下級モンスターが苦手なデッキ、つまりメタビートが苦手とするメタビート相手にも有効なカードである。 ただし相手の手札に魔法・罠を除去する魔法とかがあったらそうもいかないのでそこは好し悪し。 |
|||
※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
- 12/06 12:27 評価 10点 《青眼の精霊龍》「総合評価:《青眼の究極霊竜》を呼び出し妨害を…
- 12/06 11:04 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】
- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)
- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜
- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…
- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…
- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…
- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…
- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…
- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…
- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…
- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ
- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻


 TERMINAL WORLD 3
TERMINAL WORLD 3
 BURST PROTOCOL
BURST PROTOCOL
 THE CHRONICLES DECK-白の物語-
THE CHRONICLES DECK-白の物語-
 WORLD PREMIERE PACK 2025
WORLD PREMIERE PACK 2025
 LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
 ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
 LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
 デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
 DOOM OF DIMENSIONS
DOOM OF DIMENSIONS
 TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
 TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
 TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
 DUELIST ADVANCE
DUELIST ADVANCE




 遊戯王カードリスト
遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索
遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ
遊戯王デッキレシピ 闇 属性
闇 属性 光 属性
光 属性 地 属性
地 属性 水 属性
水 属性 炎 属性
炎 属性 風 属性
風 属性 神 属性
神 属性