交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
![CONTINUOUS]() 永続魔法
永続魔法
![EQUIP]() 装備魔法
装備魔法
![QUICK-PLAY]() 速攻魔法
速攻魔法
![FIELD]() フィールド魔法
フィールド魔法
![RITUAL]() 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
![CONTINUOUS]() 永続罠
永続罠
![counter]() カウンター罠
カウンター罠
 永続魔法
永続魔法
 装備魔法
装備魔法
 速攻魔法
速攻魔法
 フィールド魔法
フィールド魔法
 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
 永続罠
永続罠
 カウンター罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
 レベル1最強モンスター
レベル1最強モンスター
 レベル2最強モンスター
レベル2最強モンスター
 レベル3最強モンスター
レベル3最強モンスター
 レベル4最強モンスター
レベル4最強モンスター
 レベル5最強モンスター
レベル5最強モンスター
 レベル6最強モンスター
レベル6最強モンスター
 レベル7最強モンスター
レベル7最強モンスター
 レベル8最強モンスター
レベル8最強モンスター
 レベル9最強モンスター
レベル9最強モンスター
 レベル10最強モンスター
レベル10最強モンスター
 レベル11最強モンスター
レベル11最強モンスター
 レベル12最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧 > TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ コンプリートカード評価(みめっとさん)
TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ コンプリートカード評価
|
|
「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |
| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |
|---|---|---|---|
 Ultra Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC01 | 黄金卿エルドリッチ |
|
絶大な魔力と無限の富を持つ、永久に輝けし金色のアンデット族モンスター。 両方の効果が《墓穴の指名者》に弱いのはちょっとだけ気になりますが、虚無や勅命でさえも簡単に踏みつぶしていくその効果は素晴らしく、除去が効果破壊耐性持ちに効くというのも最高過ぎますね。 マクロ以外のほとんどの永続メタの影響を受けずに除去効果を出せることから、SS封じを得意とするデッキが非常に苦手とするカードであると言えるでしょう。 手札や場に何らかの魔法罠がありさえすれば効果は全て自身1体で解決しているため単独での出張性も高く、アンデット族という種族にとっての財産にもなっているという大変理想的なカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC02 | 死霊王 ドーハスーラ |
|
アンワRで誕生した究極至高のアンデット族モンスターの王となるカードで、その強さたるや同ストラクの看板モンスターであるはずの《真紅眼の不屍竜》の存在感が無に帰すほど。 《アンデットワールド》と組み合わせることで自身の持つ両方の効果が神がかった強さになりますが、アンワがなくても自身以外の自分の全てのアンデットの効果に対象を取らないモンスターの単体除外を上乗せでき、汎用手札誘発である相手の《灰流うらら》や《屋敷わらし》などを牽制することができるため、その性能の高さは折り紙付きです。 アンワが場に出ているだけでも機能停止に陥るデッキがいくつも存在するくらいなので、対象耐性・効果破壊耐性すらも全く怖くないこのカードまで出されてしまったら、並大抵の種族デッキではとても太刀打ちできないことでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC03 | 屍界のバンシー |
|
数あるフィールド魔法の中でも特に影響力が高く、デッキによっては地獄のフィールド魔法となる《アンデットワールド》をなんとデッキから単独で発動できてしまうカード。 《王家の眠る谷-ネクロバレー》といい元々が強いフィールド魔法に専用の導き手を出されると本当に参りますね…。 願わくば《魔法族の里》や《チキンレース》あたりにもこういったカードをいただけないでしょうかね? その能力は手札から捨てて対応するフィールド魔法をサーチする、というよくあるものではなく、場か墓地から自身を除外することでアンワを手札かデッキから発動するというもので、これをなんとお互いのターンに完全フリチェで使えるという仕様になっている。 《死霊王 ドーハスーラ》とは凄まじいまでのシナジーを生み出し、デッキから発動するのでうららに捕まらない強みもありますが、手札から除外して発動はできないので、フットワークにはやや難があるという印象。 しかし場に出たら出たで、見かけによらず攻撃力1800の下級アタッカーして使用でき、場にいるだけでアンワにマジェスペ耐性を与えてくれる。 強いカードに強いサポートを渡すとこうなるよってカードの典型と言えるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC04 | 灰流うらら |
|
デッキに触る系のほとんどの効果を無効にできる手札誘発モンスターで、発動コストとしてせめてライフ1000くらいは払って欲しかった感じのカード。 そのくらい守備範囲は圧倒的に広く、その後の手札誘発へのハードルを大きく上げてしまったカードでもある。 相手が先攻の際に命をつなぐためのカードでもあり、逆に自分が先攻の時に相手のGを叩き潰したりして徹底的にマウンティングして反撃を許さないためのカードでもあるという二面性を持つのが最大の罪と言える。 うららが初手にない後攻=手札事故と言わしめるほどのカードになっており、同時に先攻側は是が非でも初手に墓穴や抹殺を引きたくて、抹殺するために自分のデッキにもうららを入れるという泥沼である。 このカードの登場で《同胞の絆》や《左腕の代償》のような高いコストが必要なカード、特に手札を捨てたり、場のモンスターをリリースして発動する系のカードでうららの守備範囲内にあるものは常にこのカードへのケアが必要になった。 基本的には《増殖するG》共々他のカードを押しのけてでも採用する価値はあるというカードである。 特に相手が展開系のデッキを握っている場合、相手に自分が対戦相手として存在すると認識していただくためにも。 ちなみに見た目は妖怪少女の面々の中で一番好きです、うららがうららで良かった。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC05 | 呪われしエルドランド |
|
【エルドリッチ】におけるテーマのサーチ札を担当する永続魔法で、評価時点においては関連カードの中でこのカードと《黄金の征服王》のみテーマネームが設定されていない。 その効果は定数のLPを払うことにより「エルドリッチ」モンスター1体か「黄金郷」魔法罠カード1枚をサーチできるという、有効な初動の成立や盤面の強化に繋がる効果を毎自ターン使えるという素晴らしすぎる効果であり、罠デッキの宿命でもある手札事故のリスクを大幅に軽減することができる。 これだけでも10点級の性能なのですが、このカードが魔法&罠ゾーンから墓地に送られることで発動できる「エルドリッチ」モンスター1体か「黄金郷」魔法罠カード1枚のデッキからの墓地送り効果がこれまた強力で、《黄金卿エルドリッチ》の墓地効果のコストにすることで簡単に墓地送りにでき、デッキから墓地送りにできる「黄金郷」永続罠カードにはエンドフェイズにデッキから「エルドリクシル」魔法罠カードをセットできる共通の墓地効果が設定されているし、このカードを場から処分することで一部のEXモンスターの邪魔になる1のデメリット効果ともおさらばすることができてしまう。 このカード本体にはサーチ手段がないのが唯一の欠点で、これが規制を受けて枚数が減ることによってデッキの安定性が低下することは目に見えており、実際に準制限カードに指定されていた経験もあります。 ですがこういった仕様の数々を見ていけば、《パーソナル・スプーフィング》などと同様にそれも至極納得という感じのカードですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JPC06 | 黒き覚醒のエルドリクシル |
|
「エルドリクシル」に属する通常魔法で、「エルドリクシル」魔法罠カードが共通して持つ強い墓地効果+特殊召喚範囲は手札・デッキとなっている。 デッキに触れるので初動札として《白き宿命のエルドリクシル》よりも適しており、魔法カードなのですぐに発動できるという点で《紅き血染めのエルドリクシル》よりも優れている。 その反面通常魔法なので自分メインフェイズにしか発動できず、テーマの性質上《紅き血染めのエルドリクシル》が罠カードであることがあまりハンデにならないので、基本的にはあちらに勝る部分は少ない。 とはいえ墓地効果とその効果でデッキからセットできるカードが強いというだけで十分強いカードであり、その割にはメイン効果もちゃんと強いと言っていいと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JPC07 | 白き宿命のエルドリクシル |
|
「エルドリクシル」に属する速攻魔法で、「エルドリクシル」魔法罠カードが共通して持つ強い墓地効果+特殊召喚範囲は手札・墓地となっている。 カードの種別は3枚の中で最も強い速攻魔法ですが、効果範囲が他の2枚と違ってデッキに触れないので、ほぼほぼ墓地効果となる共通効果が本体という感じのカードになりがちになる。 また共通の墓地効果をフリチェで使えるという点でも罠カードである《紅き血染めのエルドリクシル》の方が優れており、速攻魔法である点で罠カードであるあちらに勝っているとはとても言えない状態になっているのも痛いところです。 それはそれとして墓地効果が強く、それらは全ていずれか名称ターン1なので、墓地効果だけを目的に採用する価値はあります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC08 | アンデットワールド |
|
場や墓地の特定種族のモンスターを参照する効果を多用する種族デッキにとっての地獄のフィールド魔法、これに尽きますね…。 かつて私は植物族グッドスタッフデッキを使っていたことがあるのですが、ロンファはダメ、ローポもギガプラも増草剤もダメ、ギガプラをアドバンス召喚することさえ許されないといった具合でとにかく酷い目を見ました。 相手が相手ならこれ1枚でほぼ完封することさえ可能となるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC09 | 強欲で金満な壺 準制限 |
|
第10期に登場した「〇〇で△△な壺」魔法カードシリーズの1枚で、まさしくこれを待っていたという実に素晴らしいドローソースで、評価時点において私が最も好きなドロー魔法です。 EXデッキのモンスターを3体または6体ランダムに裏側除外することにその除外枚数3枚につき1ドロー、つまり最高で2ドローできるというデッキによってはほぼ《強欲な壺》と言えるカードであり、《強欲で謙虚な壺》のように特殊召喚やバトルを封じられないためテンポを乱さないのが素晴らしく、メインデッキから必要なカードが吹き飛ぶ事故が起こらないので概ね《強欲で貪欲な壺》よりも人を選びにくい。 6→6→3と除外していくことで、エクストラデッキを一切使わないデッキなら最後までしっかりドローできるのは素晴らしいが、発動できるのは自分メインフェイズ1開始時に限られており、これを使うと発動後の制約によってそのターン他の効果でドローすることができなくなるので、特に同ターンにおける強貪や《命削りの宝札》との共存ができないことに注意したい。 またメインフェイズ1開始時にしか使えないということは、モンスターの召喚やスペルスピード1のカードの発動を相手の各種クイックエフェクトよりも優先的に発動できる権利を捨てることになる点も無視はできない。 エクストラデッキを大量に使用してまで2ドローをする点から、展開の選択肢が減ってデッキの質が下がる、そもそもこのカードを使うこと前提となると全除外されては困るEXモンスターを無闇に複数採用しなければならなくなることも多くなり、構築段階からエクストラデッキの質を下げることに繋がりかねません。 とまあ色々と気になる点もないことはないのですが、それを差し引いても強いカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC10 | 金満で謙虚な壺 制限 |
|
壺同士を合体させてみた「○○で△△な壺」シリーズ第5弾。 強謙と違って使用するターンは効果でドローできないが特殊召喚はできる、強金と違って手札は増えないがエクストラから裏側除外するカードを任意で選べるようになった壺。 金満と謙虚というよりは、強金と強謙のあいのこという感じの通称:金謙です。 最大で6枚掘ってサーチできる上に特殊召喚もできるし、誘発食らった後に欲しいカードを取りにいける発動タイミングも選ばないカードが弱いはずもなく、引くか引かないかでデッキが回る強さやスピードがあまりに大きく変わるキーカードが眠るデッキでは、他にサーチ方法があろうと与えるダメージが半分になろうと、EXデッキの面々を1ターンで出し尽くすほどにEXに依存したデッキでなければ採用する価値があると思います。 掘るのが3枚でも十分強いと思いますし、マドルチェのような絶対に引きたいカード(初動・誘発踏み抜き・リブートなど)と可能ならば引きたくないカード(メッセンや姫、2枚目の強金など)が同時に存在するデッキでは、ダメージが半分になるためそのままキルするというのは難しくなりますが、強金以上の働きと安定感が期待できそうです。 メタビ罠ビ視点での評価をしますと、罠を中心としたデッキでは、不確定とはいえ手札=バックを相手に見えないように1枚増やせる強金の方が強いと思いますし、強金→強謙の流れで手札を増やしつつさらに手札の質を上げるという動きができる強謙に勝ってる部分は個人的にはちょっと見当たらない感じです。 逆にそうでないなら、デッキの速度に関係なくかなり多くのデッキで選択肢に入ってきそうな優秀すぎるカードで、超雷龍のケアや手違いの流行り具合なども採用に影響してきそうな予感がするほどには人気と関心が集まりそうなカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC11 | おろかな埋葬 制限 |
|
原作のバトルシティ編で城之内がこのカードと《墓荒らし》を併用したコンボで《人造人間-サイコ・ショッカー》を出すことで、リシドの《アポピスの化神》を攻略するという展開を作り出すために唐突に使用したことが全てのはじまり。 自分のデッキのカードを相手の墓地に置くって一体どゆこと??んな強引な…と当時は思ったものです。 当時はまだ手札1枚を使って制限カードの《死者蘇生》や《リビングデッドの呼び声》による蘇生先を墓地に送っておくだけみたいな数的ディスアド感が半端ないカードでしたが、現在では墓地に送られるだけで誘発効果が出るモンスター、墓地で発動する起動効果を持つモンスターも多く、全く手札を消費してる気がしない至高の墓地肥やし魔法となりました。 《名推理》や《モンスターゲート》や《隣の芝刈り》のようにド派手にとはいきませんが、狙いのモンスターをピンポイントで確実にデッキから墓地に送ることができるこのカードは、しかるべきデッキでは立派な1枚初動となってくれるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC12 | おろかな副葬 準制限 |
|
おろ埋同様に、もはやいつ制限カードになってもおかしくないところまできたカード。 そのくらい墓地で発動する効果を持つ魔法や罠はあまりにも増えすぎました。 ご丁寧にも墓地に送られたターンにはその墓地効果を使えないようにされている魔法罠は、単純なフィールド発動との連発に限らず、このカードの存在も意識していると見て差し支えないだろう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JPC13 | ライトニング・ストーム |
|
このカードを使用するプレイヤーの場に表側表示のカードが存在しない時にだけ使える後攻用の前後衛選べる全体除去魔法。 このカードの登場により、《ハーピィの羽根帚》を実質的に4枚までデッキに積むことが可能になってしまいました。 これが《王宮の勅命》を失った罠デッキにとってどれほどの脅威であるかは言うまでもないかと思います。 一方でモンスター除去の方は守備表示のモンスターに効かないのが意外と気になるカードで、基本的には魔法・罠を除去するカードとして見ておくのが無難でしょう。 また《無限泡影》などと同様に、相手先攻でギルスや盆回しでモンスターや魔法罠カードを押し付けられると使えなくなるので注意。 罠デッキ好きの私が相手に使われる側の体感としては10点のカードですが、使う側になるとなかなかどうして難しいカードという感じですかね。 追記:2022年10月のリミットレギュレーションにて準制限となりました、何気に今回のレギュレーションで一二を争うくらい嬉しい規制です。 制限解除された《サンダー・ボルト》を尻目に準制限なので、やっぱりバックを全体除去するカードの方がモンスターよりも遥かに重く見られているということですね、そりゃ当然だ!そして有り難い! さらに追記:2024年10月のリミットレギュレーションで無制限カードとなりました。 この時は既に《大嵐》が制限カードに復帰済みな上に、様々な永続メタ罠も制限・準制限カードに規制された後での緩和ということで罠デッキにとってはまさに踏んだり蹴ったりという感じですね…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC14 | コズミック・サイクロン |
|
ライフを1000払う代わりに「破壊ではない、除外だ!」をやってのけるサイクロン。 現在ではスタダのような破壊を専門で捉えるカードは減ったものの、破壊耐性を持つものや墓地で発動する効果を持つ魔法・罠カードがかなり増えてきており、状況によっては発動された通常魔法・速攻魔法・通常罠に対してチェーン発動するのも有効という意味でも、ほとんどの場面でサイクロンよりも有効なバック除去札となります。 ただし元々墓穴や抹殺に対しても有効で、さらにこのカードも見ることができる鉄壁やロンギヌスがメインから使われることも多くなっており、ライフコストの有無を抜きにしても一概にサイクロンの上位互換と言い切れないのも事実です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC15 | 紅き血染めのエルドリクシル |
|
デッキから「エルドリッチ」モンスターをリクルートできる罠カードであり、2022年4月施行のリミットレギュレーションにおける唯一の準制限の罠カード。 メインデッキに入る戦闘用モンスターが《黄金卿エルドリッチ》しかいない構築であることも多く、EXモンスターへの依存度も低い【エルドリッチ】にとって、そのエルドリッチが全然来る気配がないというのはさすがに大問題なので、それを解決するこのカードを規制することでその安定性を殺すという意味でも準制限カードに指定されたのは妥当なところではあります。 このカードの場合は「エルドリクシル」魔法罠カードが共通して持つ、デッキから「黄金郷」魔法罠カードをセットできる墓地効果をフリチェで使えるというのも強いですからね。 しかしかつて準制限カードに指定されていた【オルターガイスト】の《パーソナル・スプーフィング》などと同様に、準制限指定の罠カード、特にテーマ専用のものの「そう遠くないうちに制限解除される感」が最初から漂っているところもありますね。 追記:2023年1月のリミットレギュレーションにて予想通り解除されました。 これで評価時点における準制限に指定されている罠カードはなくなり、制限も《レッド・リブート》、《トリックスター・リンカーネイション》、《刻の封印》の3枚となりました。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC16 | 黄金郷のコンキスタドール |
|
発動後モンスターカードとなる「黄金郷」永続罠カードの1枚で「エルドリクシル」魔法罠カードをデッキからセットできる共通の墓地効果に加えて、このカードは発動時に適用できる固有効果が場の表側表示のカード1枚を破壊する効果となっている。 相手の盤面に干渉できる破壊効果でかつ対象も取らないという、評価時点までに存在する3枚の「黄金郷」罠モンスターの中で最も微妙なステータスである代わりに固有効果が最も強いという実にわかりやすい設定になっている。 自身のレベルが5で《黄金郷のワッケーロ》と同じレベルであるというのも優秀ポイントで、2体で《セイクリッド・プレアデス》のX召喚に繋げることもできます。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JPC17 | 黄金郷のワッケーロ |
|
発動後モンスターカードとなる「黄金郷」永続罠カードの1枚で「エルドリクシル」魔法罠カードをデッキからセットできる共通の墓地効果に加えて、このカードは発動時に適用できる固有効果がお互いの墓地のカードの中から1枚を選んで除外するという効果になっている。 《黄金郷のコンキスタドール》や《黄金郷のガーディアン》と違って、自身の持つ固有効果が相手の盤面のカードに干渉できるものではありませんが、フリチェで使える対象を取らない墓地メタということでその妨害性能は非常に高く、これが突き刺さるデッキはそれこそ【エルドリッチ】も含めて数多く存在しています。 ステータス的にも3枚の「黄金郷」罠モンスターの中で最もアタッカー適性が高く、【エンドリッチ】の罠モンスターと言えば概ねコンキスタドールとこのカードの2種類のどちらかを指すことになります。 自身のレベルが5でコンキスタドールと同じレベルであるというのも優秀ポイントで、2体で《セイクリッド・プレアデス》のX召喚に繋げることもできます。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JPC18 | 永久に輝けし黄金郷 |
|
【エルドリッチ】で使用可能な3種のカードの発動全てにカウンターできる「黄金郷」ネームを持つカウンター罠。 評価時点となる現在では、テーマモンスターが自分の場に存在する時に発動できる+テーマネームを持つパーフェクトカウンター罠というのは割とありふれた存在となっており、それらの中には無効後に除外までしてしまう《オルフェゴール・クリマクス》や《サイバネット・コンフリクト》のようなカードまで登場している。 そのような中でこのカードは《ブローニング・パワー》や《ポリノシス》のように、さらに自分の場のアンデット族1体をリリースする必要があり、他の「黄金郷」罠カードが持つデッキから「エルドリクシル」魔法罠カードをセットする墓地効果を持たないので、現在では他のテーマのカウンター罠と比較してた時にそれほどパワーの高いカードとは言えなくなっている。 それでも《神の宣告》では捉えられないモンスター効果にも対応できるカウンター範囲が優秀であることに疑いの余地はなく、《呪われしエルドランド》や「エルドリクシル」魔法罠カードの墓地効果で詰めに持ってこられるカードとしては申し分ない優秀さと言っていいでしょう。 |
|||
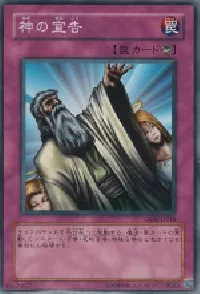 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC19 | 神の宣告 |
|
第1期に登場したはじまりの「神の〇告」カウンター罠、通称「神罠」シリーズにして、ずっと愛用し続けている個人的に最強の、少なくとも最高のカウンター罠だと考えているカードです。 捉える範囲は魔法・罠カードのカードの発動及び発動を伴わない召喚・特殊召喚行為全般となっており「攻めの神宣は強い、守りの神宣は弱い」などとも言われるように、罠デッキが用いる相手が後攻から放ってくる《ハーピィの羽根帚》・《ライトニング・ストーム》・《拮抗勝負》・《レッド・リブート》などへの防御手段としてだけでなく、マストカウンターに突き刺して相手の後攻からの反撃の芽を摘み取るマウンティング的な使い方もできるカードで、相手の初動となるNSや魔法カードをこれで止めたら、相手の動きが止まってそのまま勝ってしまったなんて経験をしたことがあるデュエリストたちも少なくないはず。 「ライフを半分払う」というコストは、発動時の自分のライフポイント次第で重くも軽くもなりますが、現在のライフがいくらであれいつ何時でも支払うことが可能というのが最大の魅力で、相手の魔法・罠カードを防ぐ手段はこれに全て委ねているデッキもけして少なくはないでしょう。 多くの罠デッキにとって、相手が手札から発動したリブートをはじめとするカウンター罠にチェーンできる唯一の命綱になり、とにかく1枚で様々な種類のカードを見られるというのが本当に強くて、ライフの半分程度なんぞ喜んでくれてやるわ思える所以となります。 その一方で手札・墓地誘発の効果や既に場に出てしまっている魔法・罠・モンスター効果に対応できないので、相手によっては自分が後攻の場合に使いどころがほとんどないという弱点もあるため、環境によっては同じカウンター罠である《神の通告》や、《激流葬》や《神風のバリア -エア・フォース-》などのアドバンテージ差を埋められる除去系の通常罠、《群雄割拠》や《御前試合》のような後攻からでも強い永続メタ罠が優先される場合も少なくない。 自分のデッキの急所となるところや苦手なカードは何なのか、どの神罠なら強く使えるのか使えないのかはしっかり考えなければならず、当然対戦するデッキ毎場面毎に適切にマストカウンターを見極める能力も重要となります。 と、まあ長々と講釈を垂れてしまいましたが、これからも何卒私の罠カードたちを帚やライスト、拮抗やリブートなどからはもちろん、《ダイナレスラー・パンクラトプス》や《天霆號アーゼウス》みたいなのが突然出てくることからもお守り下さい神サマ!ってのがホントのトコロです…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC20 | スキルドレイン 制限 |
|
遊戯王OCGにおける永続メタとは古くからSS封じ、墓地封じ、モンスター効果封じの3つと言われており、これらの中から2つ以上に強いビートダウンは相手をメタりながら戦える対応力の高いデッキと言って差し支えないかと思います。 その中でもモンスター効果をメタるカードが最も実用的なものが多いのですが、永続系のモンスター効果封じというとほぼこのカードとイコールになるのではないかと思います。 破壊&対象の両面耐性やメタ系の永続効果なども一瞬で消すことができる「発動しない効果にも強い」のはこのカードの大きな強みですが、このカードの最大の特徴は、効果処理時にフィールドに表側表示で存在するモンスターの効果しか無効にしないということです。 手札・墓地で発動する効果やリリースして発動する系のモンスター効果はもちろん、発動にチェーンしてそのモンスターを裏側にしたり手札に戻したりするような効果を使えば、たとえフィールドで発動したものであってもほとんどのモンスターの起動効果や誘発効果が有効になります。 この性質を上手く利用すれば、モンスター効果を多用するデッキでも余裕で組み込むことができ、それでいて相手のデッキは機能不全レベルに追い込むことができる、まあなんと言いますか負かした相手に「スキドレが強いだけのデッキじゃん」と負け惜しみを言われても仕方ないかなってレベルの非常に拘束力の高いイヤ〜な永続罠です。 魔法罠を除去るだけの先攻1ターン目でなんの役にも立たない魔法罠なんてメインから入れてらんねぇなという具合に、バックの除去をモンスター効果に任せっきりのデッキではこのカードを使われるだけで詰みになりかねないので、やはり帚をサイドからも抜くというのは難しいと感じさせられますね。 追記:2023年4月のリミットレギュレーションで遂にOCGでも制限カードに指定されました。 禁止カード以外で規制を受けている罠カードがまた増えてしまったのは気に入りませんが、このカードならまあいっかどころか当然でしょうと思ってしまう辺り、クソゲー製造機であるにも関わらず多くの人から支持も受けていたこのカードがいかに多くのプレイヤーからいけ好かないと思われていたのかがわかっちゃいますね…。 私なんかはオルターガイストにおけるスキドレ+プロトコルのコンボで大変世話に…ならなかったので、このカードに対する感情として特筆すべきところはないです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JPC21 | 群雄割拠 制限 |
|
近年は環境レベルのテーマでも種族統一されている場合が多く、《センサー万別》ほど有効でないことがほとんどである。 それでも効くデッキにはめちゃめちゃ効くので、種族統一した低速デッキであればサイドに採用していくのはありだろう。 実は自身の効果で一時的に除外されているコズブレもフィールドに戻すことなく葬ることができるその特異性は見逃せない。 ルールが意外に複雑なカードなので、相手に迷惑がかからないように使う人はちゃんと裁定を把握しておきましょう。 例えばこの効果の適用下にある場合、自分の場に存在するモンスターと異なる種族の相手モンスターを対象に《精神操作》や《大捕り物》を発動することは可能であり、そのモンスターはコントロールが移動した直後に墓地送りになる。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JPC22 | 御前試合 制限 |
|
《群雄割拠》の属性版となるルール介入型の永続メタ罠の一種。 遊戯王OCGにおいて、属性は種族の3分の1以下の種類しかなく、そうなるとやっぱり種族の方がバラけやすいから割拠の方が刺さりやすいのかも?という気もしますが、その辺りは環境で強いデッキと自分が使うデッキによって変わるのでそんなに関係ないでしょう。 このカードと《群雄割拠》を両方採用可能なデッキも少なくないため、そういったデッキでは仮想敵と自分のエクストラデッキ事情なども加味しながらより有効だと思う方をメインやサイドに入れていきましょう。 永続メタ罠を複数採用するのにはリスクも伴いますが、割拠御前はある程度後出しも利く永続メタ罠でもあるので、或いは両張りしていくのも良いかもしれません。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC23 | センサー万別 制限 |
|
《群雄割拠》の逆バージョンでこちらは同じ種族のモンスターを1体しか出せなくなる。 概ね《群雄割拠》よりも突き刺さるデッキが多い拘束力の高い永続メタ罠で、種族統一系のデッキはこのカードに対処できる除去カードやコントロール奪取を入れているか、融合系などの場への展開を伴わなくても大型モンスターを出せるデッキでなければエクストラからもまともにモンスターを出せずに一方的に負けかねない。 種族がバラバラでかつ低速メタビ系の叢雲ダイーザやサブテラーはもちろん、構築次第では空牙団やTGなどの多種族デッキでも使っていける。 《群雄割拠》と同じく後出ししても強いという他の多くの永続メタ罠と一線を画する性質を持つため、搭載可能なデッキならメインとは言わずともサイドには入れておきたい強力カードです。 ちなみに《群雄割拠》と同時に発動すると、2つの効果がミックスされた結果、お互いに場に表側表示モンスターは1体しか存在できないということになる。 場に出して殴り手とするモンスターを例えばボーダー1種類しか採用せず、残りは全部誘発モンスターズみたいな特殊な構築なら、両方を同時に採用することも可能である。 他にも《ライオウ》&アズルーンの組み合わせで御前センサー両張りなんてのもいけるかと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC24 | ドラグマ・パニッシュメント |
|
手札もフィールドのカードも減らさずに使えるフリチェ除去罠としては《破壊輪》を遥かに凌ぐカードです。 攻撃力2400以下のモンスターが対象なら《旧神ヌトス》を墓地に送ることで、このカードの効果処理後にヌトスが新たにチェーンを作り、このカードとヌトスの効果でそれぞれ1枚ずつ破壊することで実質1アドになります。 複数除去なのに《スターライト・ロード》や《大革命返し》のようなカードを踏むこともなく、ヌトスは後衛のカードも破壊できるので、メインから魔法罠を割るカードをあまり入れたくないが、特定の永続メタ魔法や罠の存在に悩むデッキにもオススメできる除去罠と言える。 今後墓地誘発の効果を持つEXデッキのモンスターが新たに登場するたびにチェックされること間違いなしのカードだろう。 その一方でEXデッキから特殊召喚できなくなるデメリットは自分のターンに発動すると案外長めになるので注意。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC25 | 激流葬 |
|
第2期に登場し、原作のバトルシティ編で梶木が使用した召喚反応型の通常罠。 NSもSSも両方捉える、場のモンスターを全体除去する罠でかつての制限カードです。 同期の勇である奈落もそうだがSSにも対応してたのが全てという感じで様々なデッキで使用され、アド差を一気に埋めるその捲り性能の高さから、モンスターを展開する際には常に意識しなければいけないカードでした。 その後は汎用除去札としての採用率は低下の一途を辿り、環境から姿を消しましたが、それだけに現在ではほとんどの相手はこのカードをデッキに入れてるなんて考えてもいないはずなので、相手に警戒されにくいという意味では当時よりも使いやすくなっています。 そういう事情もあって、一部のデッキでは採用率が復活傾向にあり、特にフェイカーやアルレキーノなんかは場のモンスターを一掃した上で自己SS効果のトリガーを引けるためその相性は抜群です。 場に出した瞬間に自身の効果でフリチェで一時的にいなくなれる夢魔境や天気、場が空になっても1枚から十分に再展開できるデッキの除去札としても選択する価値はあるでしょう。 自分のNSやSSにも反応するので、自爆させて被破壊誘発の墓地効果を出したり、相手に送り付けられたSS封じやリリース・特殊召喚のための素材に使用することを制限するモンスターを排除するなど、能動的に膠着状態を突破することも可能です。 メタビなんかでは守備力2000以上の下級モンスターが攻撃してくる気配もなく守備表示のまま寝てるだけで結構嫌ですし、せっかくすり潰したアドを横耐えで回復されたらたまりませんからね。 ただし時〜できる系の発動条件なので、チェーン2以降のNSやSSには反応できないので注意しましょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC26 | 無限泡影 |
|
基本的にアド損になる可能性があるカードの採用は忌避されるメタビ系のデッキにすら採用されることがある素晴らしい罠カード。 後攻からでも勝ちたい、制圧されてもなんとかしたい、そんな希望を繋げてくれる。後出しでも使えるセット時の効果も優れており、メタ系の永続魔法・罠カードや鎮座している神罠を一瞬だけ黙らせてくれる。 また相手は不用意にセットカードがある縦列で魔法カードを発動すると、このカードで無効にされるおそれがあるため、それを意識したプレイングが必要になる。 なんといっても《墓穴の指名者》やその他ほとんどの手札誘発系モンスター効果でケアされないのが強み。罠カードなので《三戦の才》を踏むこともない。 その採用率の高さから抹殺するために1枚だけデッキに入れている高速デッキも少なくない。 ただし対象耐性を持つモンスターやモンスターやフィールド魔法をこちらに押し付けてくるタイプのカード(トーチゴーレムや盆回し)には弱いので注意。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC27 | 旧神ヌトス |
|
EXデッキから直接墓地送りにするだけで万能単体除去を出せる融合モンスターであり、それ故にEXデッキのモンスターを墓地に送る効果を持つカードを使用するデッキにおいて非常に高い採用率を誇っている。 《化石融合-フォッシル・フュージョン》関連の融合モンスター群と違い起動効果ではなく誘発効果なので相手ターンに墓地に送れば妨害にも利用でき、特に《ドラグマ・パニッシュメント》で墓地送りにした時のフリチェ除去罠1枚で実質2枚破壊していくやり口はまさにインチキムーブ。 メタビ系のデッキにおいて除去罠を選択する際に、《次元の裂け目》や《マクロコスモス》を使わない・バックを割る手段が欲しい場合、パニッシュとセットで優先して採用していい強さだと思います。 ちなみに《旧神ノーデン》と違って《簡易融合》では場に出せない召喚条件であり、《禁断のトラペゾヘドロン》でも出せないので「旧神」モンスターである意味は現状ないようですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC28 | 共命の翼ガルーラ |
|
《沼地のドロゴン》に類似する2体の融合素材で融合召喚できるわかりやすい《超融合》要員となる融合モンスター。 このカードはカード名の異なる同じ種族・属性のモンスター2体を要求しているため、《超融合》を用いることで相手の使用するテーマによっては相手の場のモンスター2体だけでも融合召喚できる可能性が高いのが何よりの強み。 さらに自身の持つ戦闘ダメージ倍化と墓地に送られた場合に誘発するドロー効果により、強化しなくてもライフ取り要員としても割とバカになりませんし、EXデッキからの特殊召喚のための素材としての適性も高い。 特にドロー効果はどこから墓地に送られても発動できるので、ドラグマ要素入りのメタビで《天底の使徒》や《ドラグマ・パニッシュメント》などでEXデッキから直に墓地送りにしても普通に強いという優れたカードです。 パニッシュを使う場合は《鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusII”》を経由すれば除去範囲も大きく広がるので併用する価値も高い。 これまで《超融合》要員となり得るモンスターはその素材内容や領域指定を割と慎重に調整されてきたイメージでしたが、このカードの登場で1つ上のステージに進んでしまったなという印象ですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC29 | セイクリッド・プレアデス |
|
お互いのターンに完全フリチェで自他問わずに場のカード1枚をバウンスする強力効果を持つランク5Xモンスター。 その効果は攻めに妨害にコンボにと使い途は様々で、制圧の添え物や上手く展開できなかった時や永続メタを引けなかった時の最低限立てられる1妨害として優秀であり、下敷きとしての適性も高い。 サイドラや先史遺産やエルドリッチなどにも採用が見られ、X召喚可能なデッキでは優先的に選択できるモンスターと言えますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC30 | 超弩級砲塔列車グスタフ・マックス |
|
2体並んだレベル10モンスターをそのままフィニッシュブローに変えられる強力なランク10Xモンスター。 書いてあることは1ターンに1度自分メインフェイズに起動効果でX素材を1つ消費して2000ダメージを飛ばすだけなのだが、その間に何のデメリットも書かれていない。 メインフェイズ2では使えないとか発動するターンバトルフェイズは行えないなどはおろか、このモンスターは攻撃できないとすら書かれておらず、こういうモンスターに限って何故か3体素材でもなければ、消費X素材が2個以上ですらないという不思議。 レベル10モンスターが2体以上並ぶ可能性のあるデッキではとりあえずEXデッキに仕込んでおいて良いレベルで、そうすれば何度もデュエルを繰り返すうちに必ず入れておいて良かったと思える時が巡ってくるはず、要らないなら金謙でさっさと弾いてしまってもいいですしね。 素材にするレベル10モンスター2体が神スライムのような攻撃力3000以上のモンスターなら、それら2体でダイレクトアタックした後にバーンで勝利という具合に美しくフィニッシュできますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC31 | No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ |
|
「列車」と呼ばれるモンスター群では、同じ汎用ランク10Xである《超弩級砲塔列車グスタフ・マックス》よりもかなり守備的な能力となっていますが、攻守ともにグスタフよりも高く、こちらは「No.」Xモンスターでもあるカード。 お互いのターンにフリチェで使える効果によって対象のモンスターに自身の効果以外にそのターン中完全耐性を付与するというもので、発動しない効果も防御することができ、《神竜騎士フェルグラント》と違って対象のモンスターの効果を無効にしないので、相手への妨害には向かないが自分のモンスターの補強としてはこちらの方が優れている。 【列車】においては先攻を取った際に《重機貨列車デリックレーン》をX素材にしたこのカードを守備表示でX召喚して、守備力4000+フリチェの完全耐性とそれに連なる除去効果で相手ターンを耐えて、返ってきたターンでこのカードに《超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ》を重ねてX召喚してキルを取るというのが大定番であり、ランク10を出すデッキの先攻時の選択肢として12期の新鋭である《終戒超獸-ヴァルドラス》が必ずしも優先されるとは限らない理由でもあります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC32 | 超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ |
|
レジェンドDPのヒロイン編とも呼べる第4弾にゼアル部門のアンナ枠から登場した【列車】のファイナルウェポンとなるXモンスター。 機械族のランク10Xモンスターに重ねてX召喚できるという「RUM」魔法カードすら不要な特殊な召喚条件を持っており、基本的にはこの方法で出すことになります。 評価時点では該当するモンスターは5種類存在しますが、必要X素材数などを考えると重ねられるのは《超弩級砲塔列車グスタフ・マックス》か《No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ》、たまに《超巨大空中宮殿ガンガリディア》といったところになるでしょう。 攻守ともに4000という高打点から自身の効果によって6000にまでパワーアップし、さらに自身の持つX素材の数に比例してモンスターへの攻撃回数を増やす効果によって、モンスターとの戦闘による戦闘ダメージでキルを取るという実にわかりやすい後攻1ターン目から相手を轢き倒す能力を持っています。 重ねられるグスタフは自身の持つ効果による2000ダメージでこれを後押しすることができ、ドーラの方は先攻時に相手ターンを耐えた後にこのカードを重ねてX召喚することに適した能力を持つため、単なる重ねられ役にとどまらないシナジーがあると言えます。 耐性の類は何もありませんが、出てきたターンに勝利することを目的に出すモンスターなのでそれほど気にすることもないでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JPC33 | 天霆號アーゼウス |
|
レベル12✕2という素材をメインデッキのモンスターでクリアするのは現在のカードプールではどのデッキでも困難だが、戦闘を行ったエクシーズモンスターが場にいれば、そのターンどのエクシーズにも重ねることができるというまさにX’sエクシーズと言った感じのモンスターで、荘厳な見た目に反してその圧倒的な手軽さと、エクシーズを使うなら常に採用圏内になり得るその汎用性の高さは一級品。 同じ機械族で前回のパックで登場した「ランク4に重ねる」ヴェスペネイトから何か色々といきなりぶち上がり過ぎでは!?とも思えます。 まず3000という打点はランク4以下の汎用エクシーズを変換させる前提でも十分強く、さらにフリチェで破壊&対象耐性無視しつつ最終戦士化する効果は脅威の一言。 縛りのない2体素材のランク4で素材消費が1以下で済むモンスターに限っても、直接攻撃できるハートランドラコや、エクシーズ素材を身代わりに自爆特攻できるアークナイト、一発殴って休憩するクラブキング、起き抜けで殴るバグースカ、同じく場を更地にできるビュートなどからの変換が容易である。 素材を2つ持った状態のこのカードを処理できないままエンドフェイズを迎え、そして場にアーゼウスを止められるカードもない場合、実質的な死を覚悟した方がいいかもしれない。 他にも素材さえあれば効果に回数制限はない、戦闘を行ったX以外のXにも重ねられる、アーゼウスにアーゼウスを重ねることもできるなど、強いことしか書いておらず、元々重ねてエクシーズしまくる十二獣との相性も抜群。 1の効果を使うと自分の場も更地にしてしまうので、2の素材補充効果の発動条件とは相性が悪く、こちらはおまけに近いものの、デッキやEXデッキのカードも利用できるため、何かしらのコンボを考えてみたくなる仕様となっている。 その一方で重ねてエクシーズには戦闘を要求するため先攻時の制圧に使うのはほぼ不可能、このカード自身には耐性やチェーン不可などの効果はない、自分のカードもぶっぱするので損失を抑えようとすると必然的に制圧の添え物は前後衛ともに置きづらくなるという弱点もある。 こういった仕様から、相手が使うとバカみたいに強いが自分が使うとなんか微妙だなと感じるカードになりそうな雰囲気もあります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC34 | リンク・スパイダー |
|
特殊召喚に関する使用制限さえ持たなければどんなトークンでも、効果モンスター・EXデッキから特殊召喚されたモンスター・リンクモンスターの性質を併せ持つこのモンスターに変換できる素晴らしいリンク1モンスターで、次なるリンクに繋げるのに非常に適している。 攻撃力0でも文句が言えないはずなのだが、下向きリンクマーカーの1000打点に加え《ジェネクス・コントローラー》などの手札のバニラモンスターを自身のリンク先に打ち出す効果まで備えている。 特に《スケープ・ゴート》を採用する場合は入れない理由が見当たらないカードで、このカードのおかけでメタビでもスケゴから3体以上素材のリンク4も選べるようになりました。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JPC35 | ヴァンパイア・サッカー |
|
第10期のレギュラーパックで登場した「種族のLモンスター」枠のアンデット族版となるリンク2モンスターで、アンデット族ではお初となるLモンスター。 このカードが登場して間もなく「ヴァンパイア」がカード効果に指定されるようになり、その際にはこのカードもそちらに属するモンスターになりました。 効果としては自身の1の効果に連動する形で発動することも可能な2のドロー効果がこのカードの最も有用な能力となり、自分のターンはもちろん、相手ターンに自身や他のアンデット族を墓地から特殊召喚できる効果と併用することでドローを加速させることができる。 【アンデット族】と言えば《ユニゾンビ》や《牛頭鬼》や《不知火の隠者》などによる初動が通らなければ展開がままならないことは周知の事実かと思いますがこのカードも例外ではなく、このカードの場合は持っている能力のほとんどがコンボ向けで単独で使える能力に乏しく、妨害を受けると立てるのも苦労するのに得られるリターンも少ないという微妙なカードになりやすい。 総じて特定の種族のモンスター2体でL召喚できるリンク2モンスターとしてはそれほど強いカードというわけではありません。 Lモンスターでありながら自身の持つ3つの効果がいずれも自身のリンク先を参照しないという点は、自身の持つリンクマーカーが両方下向きで墓地からの特殊召喚が得意なアンデット族であるこのカードとは噛み合っています。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JPC36 | トロイメア・フェニックス |
|
適当にEXデッキに入れるリンク2としては最高のモンスターと言って差し支えないモンスターで、イケてないのはリンクマーカーが下方向に向いてないことくらい。 えっ、これ《トロイメア・ケルベロス》と打点逆なんじゃないの?といつも思います。 ほぼ無いような縛りで1900打点のリンク2は普通に優秀で、さらにリンク召喚成功時には手札コスト1枚と引き換えに相手の魔法罠1枚を叩き割ってくれる効果を発揮し、展開の中継で出すことで露払いになるという汎用の中の汎用リンクモンスターです。 その際相互リンク状態ならドローによって手札コストがすぐに補填されるというおまけつきで、スケゴからの展開でも《リンクリボー》や《リンク・スパイダー》の下に出すことで簡単に条件は満たされます。 コントロール奪取したモンスターを処理したいだけなら、無理して手札を切って効果を使うこともない場面もあるでしょう。 《王宮の勅命》や《センサー万別》を出されると相手の永続メタを始末する手段がメインデッキにないデッキなどには必須かと思います。 ただし《スキルドレイン》相手にはそうもいかず、スキドレに弱いデッキならこのカードにバック割りの全てを託すことはオススメできません。 |
|||
※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
- 12/08 04:49 評価 10点 《賢瑞官カルダーン》「誰やねんカードだが、墓地に落ちた永続罠…
- 12/08 04:28 評価 9点 《閃刀姫-アザレア・テンペランス》「汎用リンクの中ではリジェネ…
- 12/08 04:24 評価 9点 《つり天井》「激流葬と違い任意のタイミングで打てる全体除去の妨…
- 12/08 02:42 評価 5点 《スライム増殖炉》「今の時点では紛れもない産廃だが、 これをそ…
- 12/08 02:34 評価 8点 《ティンダングル・イントルーダー》「ティンダングルモンスターの…
- 12/08 02:07 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「刻印からサーチして妨害用の罠を、うら…
- 12/08 02:00 評価 10点 《ジャッジメント・オブ・アヌビス》「名推理入りの構築では、ハ…
- 12/08 01:34 評価 10点 《星辰竜ムルル》「ジャスティスハンターズ収録のドラゴンテイル…
- 12/08 01:08 評価 8点 《エンジェル・トランペッター》「総合評価:リクルートし、シンク…
- 12/08 00:52 評価 10点 《アルトメギア・ヴァンダリズム-襲撃-》「現状唯一のアルトメ…
- 12/07 22:18 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/07 21:46 デッキ 見神名推理ロールバックアザミナ
- 12/07 19:50 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/07 19:47 SS 第10話 向き合う覚悟
- 12/07 19:31 評価 8点 《朔夜しぐれ》「単純な無効系誘発としての使いにくさは既に他の方…
- 12/07 19:18 評価 8点 《太古の白石》「総合評価:手札コストにしてエンドフェイズに《ブ…
- 12/07 19:08 評価 10点 《青き眼の賢士》「総合評価:《青き眼の精霊》をリンク召喚するこ…
- 12/07 19:05 評価 10点 《Live☆Twin キスキル》「初動に使えば、リィラ展開を止…
- 12/07 18:24 評価 9点 《星辰響手プリクル》「光属性魔法使いという点が一番重要。これに…
- 12/07 16:35 評価 6点 《白き霊龍》「総合評価:展開時の除去を狙いたい。 破壊ではなく…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻


 TERMINAL WORLD 3
TERMINAL WORLD 3
 BURST PROTOCOL
BURST PROTOCOL
 THE CHRONICLES DECK-白の物語-
THE CHRONICLES DECK-白の物語-
 WORLD PREMIERE PACK 2025
WORLD PREMIERE PACK 2025
 LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
 ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
 LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
 デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
 DOOM OF DIMENSIONS
DOOM OF DIMENSIONS
 TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
 TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
 TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
 DUELIST ADVANCE
DUELIST ADVANCE




 遊戯王カードリスト
遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索
遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ
遊戯王デッキレシピ 闇 属性
闇 属性 光 属性
光 属性 地 属性
地 属性 水 属性
水 属性 炎 属性
炎 属性 風 属性
風 属性 神 属性
神 属性