交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
![CONTINUOUS]() 永続魔法
永続魔法
![EQUIP]() 装備魔法
装備魔法
![QUICK-PLAY]() 速攻魔法
速攻魔法
![FIELD]() フィールド魔法
フィールド魔法
![RITUAL]() 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
![CONTINUOUS]() 永続罠
永続罠
![counter]() カウンター罠
カウンター罠
 永続魔法
永続魔法
 装備魔法
装備魔法
 速攻魔法
速攻魔法
 フィールド魔法
フィールド魔法
 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
 永続罠
永続罠
 カウンター罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
 レベル1最強モンスター
レベル1最強モンスター
 レベル2最強モンスター
レベル2最強モンスター
 レベル3最強モンスター
レベル3最強モンスター
 レベル4最強モンスター
レベル4最強モンスター
 レベル5最強モンスター
レベル5最強モンスター
 レベル6最強モンスター
レベル6最強モンスター
 レベル7最強モンスター
レベル7最強モンスター
 レベル8最強モンスター
レベル8最強モンスター
 レベル9最強モンスター
レベル9最強モンスター
 レベル10最強モンスター
レベル10最強モンスター
 レベル11最強モンスター
レベル11最強モンスター
 レベル12最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧 > ストラクチャーデッキ-機光竜襲雷- コンプリートカード評価(みめっとさん)
ストラクチャーデッキ-機光竜襲雷- コンプリートカード評価
|
|
「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |
| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |
|---|---|---|---|
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP001 | サイバー・ドラゴン・コア |
|
最低の紙質を持つ上に激臭漂うストラクとしてデュエリストたちから大顰蹙を買ったストラクの新規カードとして登場した『サイバー・ドラゴン』下級モンスターですが、その性能は評価時点となる現在の【サイバー・ドラゴン】でも一軍を張り続ける超高性能なカードです。 召喚誘発のテーマ魔法罠カードのサーチ効果、墓地発動のテーマモンスターをリクルート効果で1体で2回デッキに触り、攻撃力500以下で《機械複製術》にも対応することに加えて場と墓地で《サイバー・ドラゴン》扱いになる能力まであり、とにかく頭から尻尾まで捨てるところが全くないカードともなれば当然そういうことになるでしょう。 《エマージェンシー・サイバー》で相互にサーチも可能で、召喚したこのカード1体で《転生炎獣アルミラージ》をL召喚して墓地に送ればサーチ対象である《サイバー・リペア・プラント》の発動条件も満たせるなどとにかく隙がありません。 サーチ対象となる「サイバー」「サイバネティック」魔法罠カードは今後も増加が見込めますし、アルミラ以上に適性の高い機械族のリンク1モンスターが登場することでさらに変身できる可能性すら秘めていますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
4 | JP002 | サイバー・ドラゴン・ドライ |
|
サイドラストラクの新規カードとして登場した、カード名に「3」を意味する単語を持つレベル4の『サイバー・ドラゴン』モンスターで、自身を場と墓地で《サイバー・ドラゴン》として扱う効果を持つカードの1枚。 召喚誘発で自分の場の全てのサイドラのレベルを5にする効果によってストラク看板である《サイバー・ドラゴン・ノヴァ》のX召喚を促進する効果を持ちますが、召喚権を使うのにはあまりに微妙過ぎる効果であり、サイドラに両面破壊耐性を付与する効果も効力が全然保たない上に発動条件が自身が除外された場合という謎の設定になっているため使い所に乏しい。 正直『サイバー・ドラゴン』の下級モンスターでは安定の1800打点持ちという点以外に見るべきところがなく、それだけでは《サイバー・ドラゴン・コア》や《サイバー・ドラゴン・ヘルツ》や《サイバー・ドラゴン・ネクステア》などとは到底勝負にならないでしょう。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
10 | JP003 | サイバー・ドラゴン |
|
登場以来、融合や派生モンスターに飽き足らず、当時存在しなかったXやリンクといった新システムをも巻き込み、あらゆる方向にネットワークを拡げ続ける、進化することを止めない機械竜。 まさか光DPもサイバー流がその枠を射止めることになってしまうのか、今から要注目です。 4期の誇るグッドスタッフモンスターズの1体で、アタッカーにもリリース要員にも特殊召喚のための素材としての適性も高く、〇〇版サイドラやサイドララインなる言葉もその中で生まれていくことになる。 既に多くの方によって考察されているので多くは語りませんが、《月の書》などで寝かせても結構高い守備力も特徴の1つと言えるのではないでしょうか? いかにも守備力0っぽい性質のモンスターなんですけどねえ。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP004 | サイバー・ドラゴン・ツヴァイ |
|
第6期の終期に登場した、カード名に「2」を意味する単語を持つレベル4の『サイバー・ドラゴン』モンスターで、自身を墓地で《サイバー・ドラゴン》として扱う効果を持ち、手札の魔法カードを見せれば場でもサイドラとして扱える効果を持っている。 登場当時は《プロト・サイバー・ドラゴン》より使いやすいサイドラの代替品として一定の価値があるカードでしたが、後に登場した《サイバー・ドラゴン・ドライ》と比べるとほぼ下位互換であり、そのドライすらも一切不要になった現在の【サイバー・ドラゴン】ではまず使われないカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP005 | プロト・サイバー・ドラゴン |
|
現在ではもはや何体いるかもよく把握できていない《サイバー・ドラゴン》扱いになるモンスターの中でも最初に登場したカード。 能力は場でサイドラ扱いになるだけで他に効果はないという完全なる代用品であり、後発の類似モンスターと違い墓地ではサイドラ扱いにはならず、本体とは違って下級モンスターという点で何らかの効果で特殊召喚を封じられている状況でも場に出しやすくはあるものの、攻守ともに低くて戦闘要員にはとても使えない。 後発の優秀な類似モンスターたちの存在で完成に存在意義を消されたカードですが、サイドラが制限カードだった頃にサイドラを融合素材に指定する融合体を支えたモンスターであることは疑いようのない事実であるため、その辺りも考慮してここは2点とさせていただきましょう。 公式も一応お情けということなのか、後発のサイドラ扱いとなるモンスターの中にはこのカードと同じレベル3のモンスターは評価時点までに登場していない。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP006 | サイバー・ヴァリー |
|
除外に絡めた選べる3つの効果で壁に手札入れ替えにリサイクルにと色々できるサイバー流のテクニシャン。 単独で攻撃を受け流してドローできる効果と、奪ったモンスターを返すことなく有効に処理しつつ手札を補充できる前半2つの効果が使いやすく、複製で一気に並べたりもできたこともあって一定の人気を誇っていました。 現在の環境でこのモンスターを使用するなら、やはり自身や他のモンスターを除外することをどう活かせるかが鍵となるでしょう。 次元融合も《異次元からの帰還》ももう使えませんし、被除外誘発のカードもなんだかんだで少ないですからねえ、コンボ向きの3つ目の効果の性質からやはり無限ループ系の方向性に活路を見出す運用になりがちな感じです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP007 | サイバー・ラーバァ |
|
「ラーバァ」というあまりに見慣れない字面カード名が特徴のモンスター。 その能力は対応先が同名モンスターのみの被戦闘破壊誘発のリクルーターで相手から攻撃を受ける際には傷を負わずに安全にリクルート効果を使えるというもの。 この種族・属性の組み合わせである必要がなければ《ハイエナ》とかで十分なレベルの性能で、PPに収録されたから高レアリティというだけのカード。 こんなものが10期のコレパのそれもノーレアで再録されるなんて甚だ信じ難い。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP008 | サイバー・フェニックス |
|
炎属性リクルーターであり機械族である《UFOタートル》の効果でリクルートできる《UFOタートル》以外の機械族と言えば?と聞かれた時に、真っ先に思い浮かぶモンスターというイメージで、個人的には逆にこのモンスター以外が思い浮かばないほど。 効果は場に攻撃表示で置いておけば、自身を含む機械族に魔法罠に対して実質的な対象耐性を、倒れても1ドローを入れられるという極めて無難にまとまったものとなっています。 モンスター効果も無効にできるか、戦闘以外で場を離れても1ドローならなお良かったですね。 その場合、後者は名称ターン1が欠かせなくなるでしょうけども…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP009 | サイバー・ダイナソー |
|
漫画版GXの記念すべき第一話に登場した《暗黒恐獣》だったはずのモンスター。 漫画版ではほとんどあちらと同じような効果でしたが、OCGでは相手の手札からの特殊召喚に反応して自身も手札から特殊召喚されて応戦するという能力になっており、当時流行りの《サイバー・ドラゴン》対策を意識したものと思われますが、そうやって出したところで機械族であるこのモンスターは《キメラテック・フォートレス・ドラゴン》に吸収されてしまうため全く対策になっていませんでした。 相手の先攻1ターン目からでも場に出せる貴重なモンスターではあるものの、反応する特殊召喚が限られているため任意のタイミングで出すことが難しく、2500打点程度の他に効果がないモンスター1体を転がしたところでさすがにできることは少ない。 そればかりか自ら《PSYフレームギア・γ》や《無限泡影》の脅威を切ることや、相手の効果の対象となる的を用意したり、相手の場にモンスターが存在することを条件とするカードを使えるようにしてしまうことさえある。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP010 | サイバー・エルタニン |
|
イラストを見ての通り《サイバー・ドラゴン》関連のモンスターですが、カード名や効果の上ではサイドラとは直接関係を持たず、光機械という括りの中で繋がっている特殊召喚モンスター。 自分の場と墓地の全ての光機械を除外することによって特殊召喚でき、その枚数によって自身のステータスが決定するという《邪龍アナンタ》のような能力を持っており、強化倍率はアナンタ以下でぼちぼちといったところ。 しかしこのモンスターの能力で目を引くのは特殊召喚誘発の除去効果の方であり、除外したモンスターの数に関係なく同じクオリティの効果が誘発し、自身以外の場の全てのモンスターが破壊でも対象を取る効果でもない耐性貫通力の高い効果によって墓地送りになる。 その気になればNSした光機械1体からでも場のモンスターを全滅させられることから捲りとして非常に強力で、これを足がかりに後攻ワンキルを狙っていきたいところ。 《終焉の覇王デミス》や《裁きの龍》と同じく自身は残留するため、効果を無効にされたりかなり低い攻撃力で特殊召喚したとしても、召喚権を使っていなければこのモンスターを素材とした展開が見込めるでしょう。 テーマ無所属の最上級特殊召喚モンスターでありながら《エマージェンシー・サイバー》や《サイバー・リペア・プラント》といった魔法カードによる専用のサーチ手段が複数存在しているというのもかなり恵まれていますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP011 | アーマード・サイバーン |
|
サイバードラゴンとその融合体専用のユニオンで、字面やイラスト、長文テキストからいかにも凄いことができそうで全然大したことないモンスター。 融合サイバーの有り余る攻撃力を除去に変換して戦闘破壊耐性を持つモンスターにも強く出られるというと聞こえはいいが、自身には全く戦闘能力がないこのモンスターをデッキに入れて場に出すという労力を計算に入れたらとても使おうという気にはならないはず。 光機械でないが故に一部の関連カードとの連携も取れなくなっているのもイケてない感じで、さすがに失敗強化と言わざるを得ないですかね。 まあこれだけ進化が多岐に分岐しているサイドラシリーズのカードですから、たまにはこういうのもありますってことで。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP012 | サテライト・キャノン |
|
毎ターンパワーチャージを行い、攻撃を行うとこの効果でチャージしたパワーが0に戻るというめちゃくちゃ悠長で効率の悪い破壊兵器。 シクが映える機械のボディやパネル・惑星の紺碧・漆黒の宇宙空間が美しいイラストが特徴だが、アニメ版では効果適用中はえらくテキトーなメーターが描かれただけのイラストになります。 宇宙空間にいるという設定のためパワーが0の間も低級なモンスターには戦闘破壊されないという効果により、自己SS能力がないながらも一定の威厳を保っていたが、現在ではさすがに厳しいカードと言わざるを得ないでしょう。 結局のところ、パワーチャージがこんだけ悠長なのも、この限定的な戦闘破壊耐性に慢心した結果の調整ということに他ならないわけですから…。 アニメGXでオージーン王子が使用したサテライトベースやレーザーバルサムのOCG化が待たれます。 DM3では同名カードでかつこのカードと種族・レベル・パスワードも一致するが、攻撃力2000/守備力1500の雷魔族でイラストも全く別物であり、機械族のくせに《機械改造工場》に非対応という通信融合モンスターも存在していますが、《ライトローミディアム》もOCG化したことですし、こちらもまた何らかの形で出てこられるといいななんて思ってます。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP013 | 太陽風帆船 |
|
アニメゼアルに《惑星探査車》と共に登場した機械族モンスターで、用途こそ違えど現在ではすっかり立場が逆転してしまいましたが、当時はこちらの方が遥かに持て囃されていたカードでした。 それもそのはず、相手に依存しない自己SS能力を持つレベル5モンスターということでランク5のX素材として最適であり、機械族や光属性であることも活かせる素材縛りがあるXモンスターも存在していたとなると、さすがに放っておかれるはずもなかったわけです。 自己SS条件がサイドラよりも緩い分自身の戦闘能力は低く、自己SSするとそれがさらに半分になるので壁として使うのも困難になる。 また放置してると自身のレベルが勝手に上がる効果と同名モンスターが自分の場に1体しか存在できない効果は、自己SS後すぐに特殊召喚のための素材に使用するのであればどちらも大したメリットにもデメリットにもなりませんが、X召喚を行うためのレベルが自分の意志に反して乱れることや、ステータスが半分になることを利用して《機械複製術》で同名モンスターをリクルートすることがこの効果のせいでできないことを考えると、基本的にデメリットとして働くということになります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP014 | ジェイドナイト |
|
「戦闘機」モンスターという括りに属する機械族モンスター群の1体で、攻撃表示の時に自身を含む攻撃力1200以下の機械族に罠カードによる破壊耐性を付与する効果と、被戦闘破壊誘発の効果によって光機械のレベル4モンスターをサーチする効果を持っている。 この攻撃力1200以下の機械族、光機械でレベル4という要素で他の「戦闘機」モンスターとシナジーするような能力になっているわけですが、適用条件の割には発揮する耐性効果は《聖なるバリア -ミラーフォース-》や《激流葬》などを防げる程度の今となっては大した価値が感じられない微妙なものであり、被戦闘破壊誘発限定のサーチ効果はリクルート効果よりも遥かに弱いというのはもはや精査するまでもなく、結果弱い効果しか持っていないので現在では到底使いどころがなさそうなカードになってしまっている。 |
|||
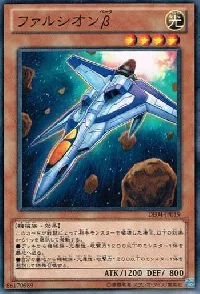 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP015 | ファルシオンβ |
|
「戦闘機」モンスターという括りに属する機械族モンスター群の1体で、戦闘破壊誘発の効果によって指定のステータスを持つモンスター1体をデッキから墓地送りにするか墓地から特殊召喚するかを選べる能力を持つモンスター。 《ジェイドナイト》と同様に他の「戦闘機」モンスターの存在をかなり意識した能力となっていますが、自身の攻撃力もそれらの効果の恩恵を受けるために僅か1200しかないため、トークンなどが相手でなければ効果を使うためには《オネスト》などの他の効果による戦闘補助がまず欠かせない。 戦闘依存のこの発動条件なら特殊召喚されるモンスターの性能を考えても手札・デッキから特殊召喚できても何ら問題なかったと思いますが、6期のカードでかつ名称ターン1とか同名カードを除く指定がなかったので多少仕方なかったところはあり、デッキに触れる効果があるだけ上出来だったといったところでしょうか。 |
|||
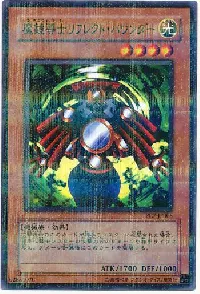 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP016 | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー |
|
原作のバトルシティ編で絽場が使用したモンスターで、戦闘要員兼守備固めを目的に召喚されましたが、結果的に彼がこのデュエルに敗ける一因となってしまったモンスター。 正対したイラストであるにも関わらず、下半身が左右対称ではないというか、歪んだ壺のような何だか歪な形をしているのがとても気になってしまうカードです。 OCGでは攻撃モンスターを除去する効果がなくなった代わりに、攻撃モンスターの攻撃力分の効果ダメージを相手に反射する能力を獲得し、どのようなモンスターに攻撃されても戦闘ダメージと効果ダメージで最低1700ダメージを与えられる。 しかしこの効果を使うと攻撃モンスターの攻撃力に関係なくこのカードは自壊してしまう上に、どんなに攻撃力の低いモンスターに対しても「死に際の魔鏡反射」してしまう強制効果なので、攻撃されたらとりあえず散るという虚弱なモンスターになってしまっている。 現在ではそもそも「攻撃表示のこのカードが相手モンスターに攻撃された場合」という発動条件がだいぶ酷いので、攻撃力1700の下級モンスターであること以上の働きをすることは難しいかなり厳しいカードになってしまっている。 OCGよりも先にDM3に収録されており、この時は魔法使い族のモンスターでしたが、OCG化の際にエースのショッカーに合わせる形で機械族になったという経緯がある。 |
|||
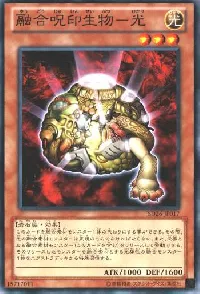 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP017 | 融合呪印生物-光 |
|
評価時点までに3つの属性にそれぞれ登場した「融合呪印生物」岩石族モンスター群の光属性を担当するモンスター。 光属性という闇属性と対になる属性なのでさぞ有用な対応先の融合モンスターがたくさん存在するものかと思いきや、評価時点でも自身の効果で特殊召喚できる融合モンスターはそれほど多くはありません。 かつて《サイバー・ドラゴン》が制限カードに指定されていた時期には、融合素材代用モンスターを融合召喚に使用できない《サイバー・ツイン・ドラゴン》をEXデッキから特殊召喚できる効果を持つカードとして一定の価値がありましたが、個人的には《シャイン・エンジェル》で《慈悲深き修道女》と共にリクルートしてきて、2体で《聖女ジャンヌ》を特殊召喚するモンスターというイメージが強いです。 |
|||
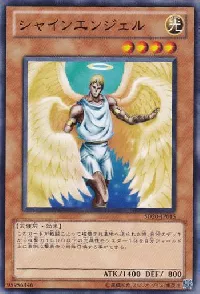 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP018 | シャインエンジェル |
|
第2期に登場した6つの属性のリクルーターの中でも、属性に対する種族設定の適性が圧倒的に高いモンスター。 何しろ天使族は現在でも光属性モンスターの最大シェアを誇る種族であり、その種類数は地属性担当で獣族の《巨大ネズミ》を遥かに凌ぎます。 しかし天使族による天使族のためのリクルーターかと言われると意外とそうでもなく、それ以外の光属性デッキで使われていたイメージの方が強く、それだけリクルート先に優秀なモンスターが多いということの証左とも言えるでしょう。 相互リクルートができるコーリングノヴァや、リクルート先のリクルーターであるユーフォロイドなどの存在から、リクルーターで自爆特攻の数珠繋ぎをする際には是非とも使いたいモンスターですね。 |
|||
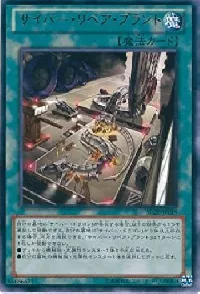 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP019 | サイバー・リペア・プラント |
|
自分の墓地に《サイバー・ドラゴン》が存在する場合に発動が解禁される、光機械のデッキ→手札か墓地→デッキを選べる効果を持つ「サイバー」ネームを持つ魔法カードで、基本的には《エマージェンシー・サイバー》と共に【サイバー・ドラゴン】におけるサーチ札を担当することになるカード。 発動条件の都合で一定確率で事故札となる危険性がありますが、《サイバー・ドラゴン・コア》の召喚誘発効果でサーチしてきて、コアを《転生炎獣アルミラージ》のL素材として墓地に送るだけで、コアが自身を墓地でサイドラとして扱う能力によってその発動条件が満たされる。 墓地にサイドラが3体以上いれば両方の効果を選べるようになりますが、墓地からのデッキ戻しが役立つ場面はそれほど多くないと思われるのでおまけ効果という認識で良いでしょう。 エマージェンシーと比べると《銀河戦士》や《壊星壊獣ジズキエル》もサーチ可能な点が優れており、特にジズキエルが「壊獣」モンスターの中でも種族アドバンテージが高い方のモンスターとして扱われるのはこのカードの存在が大きいです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP020 | エヴォリューション・バースト |
|
DTの新規カードとして登場した《サイバー・ドラゴン》の攻撃名がカード名に使われている必殺技カードとなる通常魔法で、出てくるのがあまりに早すぎた残念カード。 自分の場にサイドラがいる時に相手の場のカード1枚に対して万能単体破壊の除去効果を出すことができ、場でサイドラ扱いになる能力を持つモンスターが爆増していることから発動自体は容易ですが、この発動条件と除去枚数で評価時点では専用サーチやサルベージ手段がない・速攻魔法じゃない・発動するターンの攻撃制限デメリットがあるというのさすがにちょっと厳しすぎるようなという感じで《最古式念導》とかの方がまだ強いと思いますね。 再録もサイドラストラクにおける枠埋めのお情け再録の1回限りという辺りも、その性能の低さを物語っているといったところです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP021 | 超融合 準制限 |
|
対象を取らず、発動にあらゆる効果をチェーンさせないその性質から、魔法カードの発動・適用及び特殊召喚自体が事前に封じられていなければ突破できない耐性はほとんどないという素晴らしいカード。 しかもお互いのターンにフリチェで発動できる速攻魔法ときており、これは発動に手札コストを要求されるのもやむを得ないでしょう。 相手モンスターを2体を素材とすることが当然の理想だが、このカードの存在がある以上、例えば「効果モンスター2体」のような、そう簡単になんでも融合素材にできる素材指定の融合モンスターを新カードとして出せないのも実情で、このカードが環境でも活躍するようになって以降は、意図的に自分の場のモンスターしか融合素材にできないような指定になっている融合モンスターも増えています。 ただし魔法の効果またはカードの効果を一切受けないモンスターや、《百万喰らいのグラットン》などの融合素材にできない制約のあるモンスターだけは倒すことができないので注意しましょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP022 | パワー・ボンド |
|
《リミッター解除》と並ぶ機械族の必殺カードとして昔から多くのデュエリストたちに認識されてきた融合召喚を行う魔法カード。 融合召喚自体は通常の《融合》と全く同じ手法で行われ、それが機械族の融合モンスター限定で「融合」及び「フュージョン」ネームも持たないという《融合》の下位互換ですが、こちらには融合召喚した機械族モンスターの攻撃力が元々の攻撃力分アップ、つまりほとんどのモンスターの攻撃力が倍になる追加効果を持っており、《サイバー・エンド・ドラゴン》のような攻撃力4000以上のモンスターの融合召喚に使用することでその攻撃力は一気に8000を超え、後攻からの1キルに繋げることができる。 そのターンにし損じるとエンドフェイズに融合召喚したモンスターの元々の攻撃力分のダメージがプレイヤーを襲うことになりますが、そのターンのバトルフェイズで勝利すれば関係ないのは当然として、このダメージはあくまで効果によるダメージなので他の効果で0にして流したり、ものによっては逆にこれを相手に受けさせることも難しくありません。 後に専用サーチャーとして登場した《サイバー・ファロス》の発動条件が微妙なのが残念でしたが、さらに後に登場した専用サーチャーである《サイバー・ダーク・キメラ》がより良いサーチ条件でかつこのカードによる融合召喚のサポートまで行える効果を持って出てきたため、このカードの価値もより高いものになったと言えるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP023 | リミッター解除 |
|
第2期に登場した自分の機械族モンスター全体の「現在の」攻撃力を倍化するという凄い魔法。 しかも速攻魔法なのでダメステに手札からでも使えるという、豪快かつ当時ではおよそ考えられない気の利いた仕様になっている。 いくら発動直後に数的アドにならず効果を受けたモンスターはエンドフェイズには自壊するとはいえ名称ターン1もなく、現在ではとてもこの性能のままでは生まれてこないカードの一つと言えるだろう。 当時の下級機械アタッカーだった《メカ・ハンター》・《王室前のガーディアン》・《ガトリングバギー》でも攻撃力は3200〜3700に、罠封じの効果を持つ《人造人間-サイコ・ショッカー》は攻撃力4800となるため、これら2体だけでも8000ライフを全て奪うことができるという事実が程なくして制限カードに指定されたこのカードのパワーの高さを物語っています。 自壊デメリットもとってつけたようなものではなく、リミッターを外して運用したために故障してしまうという極めて機械らしいものである。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP024 | 巨大化 |
|
ゲーム作品ではコンストラクションモンスターのような不気味に組み合わされたキマイラを含め「どんなモンスターでも強化できる手軽で便利な強化魔法」という位置づけのカードで、そのあまりの強化範囲の広さから制限カードだったり、元々モンスターの能力値を倍以上に強化できるカードだったのが、後のゲームに収録される度に1000→500→300と目減りしていった歴史があります。 真DMでは草原神官兵から奪った《メテオ・ブラック・ドラゴン》や《スカルビショップ》に、ペガサスから奪ったこのカードをいかに素早く装着するかがゲームクリアの鍵になるほどの重要カードでした。 そんなこのカードもOCGでは一転、自分がライフ値で優勢なら装備モンスターの攻撃力を半分にし、劣勢なら倍化するというかなり豪快な装備魔法となりました。 モンスター効果や魔法・罠のコストで自らライフを有効に減らし、そうやって出てきた大型モンスターにこのカードを装着して、その倍化した攻撃力で一撃で轢き殺すというのが主な使い方になりますが、相手モンスターにも装備できるため、相手モンスターの弱体化、相手モンスターの攻撃力を倍化させその攻撃力を参照する系の効果で自分のモンスターの打点を上げたりバーンダメージを与えるという使い方も可能です。 優勢・劣勢と言ってもライフ差はわずか100でも問題なく効果が適用され、自分のライフが2000以下とか、お互いのライフ差が3000以上とか、装備モンスターでしか攻撃できない、装備モンスターは相手に与える戦闘ダメージが0などの余計な注文や発動のためのコストなどもないので、現在でも強化系・コンボ系両方の用途で使い甲斐のある良い装備魔法だと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP025 | D・D・R |
|
自社ゲームの音ゲーの1つである「DDR」からカード名を拝借したと思われる除外版の《早すぎた埋葬》と言うべき装備魔法で、さすがにダンス要素はイラストにも効果にも一切ない。 発動するためにはモンスターを除外するという一手順を加える必要があるほか、あちらと違って発動コストが定数のLPから手札1枚になっており、自壊条件も厳しくなって概ね使い難くなっていますが、発動に名称ターン1がなくサーチもサルベージも容易な装備魔法であることに変わりはないので、展開の中で自然とモンスターの除外を行うデッキにおける展開コンボカードとして現在でも一定の人気を誇るカードです。 かつては【植物族】においても《継承の印》とか《薔薇の刻印》などと一緒に使われていたこともありましたね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP026 | トランスターン |
|
Xモンスターのランクを上げる「RUM」ならぬ「LUM」とも呼べる魔法カードで、真に《レベルアップ!》と呼ぶべきリクルート札。 コストで墓地送りにしたモンスターと同じ種族と属性でレベルが1つ高いモンスター1体をデッキから特殊召喚できるという、有効な組み合わせがあるデッキでは意中のモンスターを場に連れてこられるカードとしてなかなか優秀な1枚です。 特にまともに召喚するとリリースが1体必要になるレベル5のモンスターにとっては、レベル4の下級モンスターを用いてそれをデッキから呼び出せる有用なカードであり、もちろん下級モンスターから下級モンスターをリクルートするカードとして使ってもいいし、妥協召喚や自己SS能力を持つモンスターやEXモンスターをコストに用いれば最上級モンスターから最上級モンスターをリクルートすることも難しくありません。 例によってサーチの利かないカードで無効にされた時のリスクも大きいですが、楽しいカードだと思います。 なおイラストに描かれている《メガキャノン・ソルジャー》は地属性であり、闇属性の《キャノン・ソルジャー》を墓地に送ってもこの効果では特殊召喚できず、属性の一致も要求してくるのが先行していた昆虫族専用の《孵化》と最も異なる点なので注意したい。 |
|||
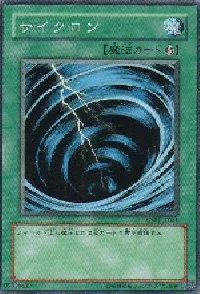 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP027 | サイクロン |
|
良質を通り越して環境を破壊するヤバい魔法カードを大量に世に送り出してしまった第2期のレギュラーパック第1弾「マジックルーラー」出身の割りモノ系速攻魔法。 かつて制限カードだったこともあるこのカード、初期からこのゲームをやっていてお世話にならなかったプレイヤーはまずいないでしょう。 上から叩く!1枚から叩く!発動タイミングを選ばずにノーコストで叩く! とにかくその圧倒的な癖の無さと汎用性の高さとリスクの低さが特徴で、現在は《ツインツイスター》や《コズミック・サイクロン》といった後発の割りモノ系速攻魔法に優先されることは少なくなりましたが、その有用性の高さは未だ健在と言えるかと思います。 サイクロンで伏せてあるサイクロンを壊してしまうのは、その昔よく見た光景でしたねえ…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP028 | 大嵐 制限 |
|
羽根帚が禁止カードになっていた頃のストラク収録札の大常連だったバック剥がし魔法。 自分の魔法罠も破壊してしまう点が帚から調整されていた部分だったのですが、ペンデュラムゾーンに置かれたモンスターも含めた自分の魔法罠の被破壊誘発効果を出すことができる、つまり先攻で展開するためのカードの一種として使うこともできるようになってしまったため、帚と入れ替わる形で禁止カードとなりました。 帚には専用のサポートもありますが、それでもこちらが禁止というのが、単純なアドバンテージ獲得能力だけでなく先攻でも展開に繋がる札として使えるというのがいかに重いかを感じさせられます。 まあ色々と思うところもありますが今はライストなんてカードもあるという状況なので、帚・大嵐・ハリケーンは今後も3種のうちどれか1種を1枚までというレギュレーションを継続していただけると助かります。 2023年12月追記:《ハーピィの羽根帚》とこのカードを同時に使用可能なレギュレーションが実現してしまうなんて…。 《ライトニング・ストーム》が普通に準制限をキープしているので完全に油断してましたね…。 |
|||
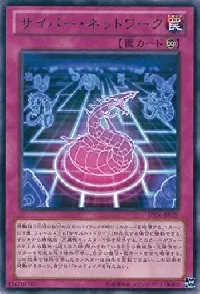 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP029 | サイバー・ネットワーク |
|
《サイバー・ドラゴン》を中心とし、その多様な進化体と派生モンスターに分岐していく様子が描かれたイラストが個人的に好きな「サイバー」永続罠カード。 場にサイドラがいる時に毎ターンデッキの光機械を除外することができ、場から墓地に送られることでこの効果で除外されたかどうかに関係なく除外状態の光機械を一斉に帰還させることができる。 毎ターン無料で除外アドバンテージを稼ぐことができ、除外したモンスターやその同名モンスターに課せられる制約も一切ないのは悪くないのですが、罠カードでかつ場にサイドラやサイドラ扱いになるモンスターが必要なので事故要因になる場合もあり、【サイバー・ドラゴン】自体もそれほど除外することを重要視するテーマではありません。 一斉に帰還できる効果の方も、回りくどい上に発動ターンにバトルフェイズを行えないデメリットがあまりに重くて使いづらく、後攻から1キルを狙うのが主である現在の【サイバー・ドラゴン】ではまず使われないカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | JP030 | サイバネティック・ヒドゥン・テクノロジー |
|
発動条件も発動コストも発揮する効果も全部弱いという謎の隠されたテクノロジー。 「サイバネティック」罠カードなので《サイバー・ドラゴン・コア》でサーチできて、永続罠カードなのでこのカード自体は使い減らないということくらいしか良いところがなく、性能は普通に《炸裂装甲》以下です。 隠されたのはあまりに低性能過ぎて黒歴史だからと思うほどに中々見ないレベルの性能です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP031 | スリーカード |
|
自分の場に物理的にモンスターカードの体をなした同名モンスターが3体以上存在する場合に発動が解禁され、相手の場のカード3枚に対してフリチェの効果破壊を出すことができる罠カード。 炸裂すればノーコストの1枚で3枚を破壊できる強力な効果ですが、発動タイミングが限られるのは当然として必ず3枚を対象にしなければならない融通の利かなさがあり、フルパワーで効果を炸裂させるのは難しい。 そういう罠カードをこのカードの発動条件が満たせる=採用可能なデッキであるからと言ってデッキの除去札として採用するという人はかなり少ないでしょう。 イラストに描かれている【サイバー・ドラゴン】はそれほど無理をしなくてもこの効果を使いこなせるデッキの1つであり、サイドラストラクの再録枠にも選出されています。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP032 | トラップ・スタン |
|
アニメ5D’sにおいて、当時数あるテーマの中でも最強をきわめたBFを使用するクロウが使用した、当時の最強のインチキ罠封じカード。 1度通してしまえばそのターン中はお触れのように除去されることで解除されるということはなく、効果処理時に効果だけを無効化するためカウンター罠ですら無力化することができる。 相手の通常罠にチェーンして発動すれば最低限等価交換になるその使い勝手の良さから、当時人気を誇りました。 現在では手札から発動も可能で、スペルスピード2の効果にチェーンされないリブートという強力な競合相手が存在していますが、こちらはノーコストでノーリスクという圧倒的な手軽さがウリで、自分が使わなくても使われたらめちゃくちゃ嫌なカードであることには変わりありません。 勅命が禁止カードになったことは、このカードにとっては残念なことと言えるかもしれませんね。 |
|||
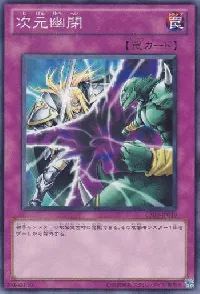 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP033 | 次元幽閉 |
|
対象を取るタイプの攻撃反応型罠の1つで、除去手段が《炸裂装甲》の破壊から除外に変わっているため、より高い耐性貫通力を持つことになり、多くの蘇生やサルベージによる再利用も防ぐことができます。 しかし除去内容が向上していることを除けば、そのやり口は《炸裂装甲》と全く同じで、対象を取る等価交換の単体除去というものは、現在の攻撃反応型の罠カードとしては最低クラスの性能になってしまうと言わざるを得ません。 被破壊誘発や被除外誘発の効果などは置いておくにしても、永続メタとして一定の使用率がある鉄壁の存在から、除外は除去手段としていついかなる場合でも常に100%破壊よりも優れているとも言えないわけですしね。 強くて高いカードというイメージがあり、かつては本当にそうだったので、未だにそれを引きずってる部分は辛いけど否めないと思いますねえ、かくいう私も岩石メタビで愛用していたクチでして…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP034 | 邪神の大災害 |
|
原作のバトルシティ編において、マリクがこのカードを用いてOCGでは不可能なコンボで城之内を葬ろうとしたところ失敗に終わった、作中では発動されなかった罠カード。 その効果は相手の攻撃宣言時というあらぬタイミングでお互いのバックを全て消し飛ばすという変わった割りモノ札です。 発動タイミングはけして良いものとは言えませんが、曲がりなりにもやってることは相手ターンに《大嵐》なので炸裂した時のリターンも大きい。 攻撃宣言時に相手の魔法罠によるモンスターの強化やメタ効果を消し去ったり、自分の魔法罠の被破壊誘発の効果をセルフ破壊によって出すことが可能となります。 現在ではサイドデッキに採用されることさえも稀となりましたが、バトルフェイズを行う気のあるメインフェイズ1で、むやみやたらに魔法罠をセットして的を作ってはいけないよ?という教訓をデュエリストたちに与えたカードと言えるでしょう。 それだけに、相手が適切なプレイングを心がけていればその脅威も半減するというカードでもあります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP035 | 和睦の使者 |
|
完全フリチェで発動でき、効果が通ればそのターン自分の全てのモンスターは戦闘破壊されず、さらに受ける戦闘ダメージも0になる。 この効果は後から別の効果によって消すことができず、そのターン中に戦闘ダメージでライフを失うことがなくなるためほぼ全てのビートダウンデッキに対してターンスキップになるという、防御札としてなかなかすぐれた性能と言えます。 相手の戦闘破壊誘発効果を出させないのはもちろん、自分のモンスターが戦闘を行うことで誘発する効果を安全に使うことにも適しています。 反面数的アドバンテージには繋がりにくく、相手の展開を封じるわけではないため、問題を先延ばしにしただけのその場しのぎ的な性質も強いため優先して採用するようなカードではないかもしれませんが、戦闘を行う必要があってかつその戦闘で生き残らなければならない、或いはまともに使うと大きな戦闘ダメージを受けることになってしまうようなモンスターにとっては貴重なカードとなるでしょう。 例えばリバース時に効果が出るけど自身がその戦闘で破壊されてしまう場合は効果が処理されないというようなモンスターがこれに該当しますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP036 | リビングデッドの呼び声 |
|
汎用蘇生札の一種で、蘇生したモンスターが破壊以外でいなくなった場合は自壊せずに場に残るのが特徴であり、セルフバウンスする蘇生札といえばこの永続罠カード。 このカードに限りませんが、《死者蘇生》や墓穴など相手がこちらの墓地のカードを対象にした時にチェーン発動して、妨害したり妨害されることを防ぐ使い方ができるのが、速攻魔法や罠の蘇生札の最大の利点と言えるでしょう。 ただしその性質上相手ターンに発動することが多く、先に使うと上から墓穴を使われやすいことには注意したい。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP037 | サイバー・ツイン・ドラゴン |
|
《サイバー・ドラゴン》2体を融合素材に融合召喚できる「サイバー」機械族融合モンスターで、自身の召喚条件により融合素材代用モンスターは融合召喚する際の融合素材に使用できない。 2800打点から無条件の2回攻撃を繰り出せる能力によって、相手の場の状況によっては相手に与える戦闘ダメージはサイドラ3体を融合素材とする《サイバー・エンド・ドラゴン》をも凌ぎます。 ただし現在では同じ融合素材で《キメラテック・ランページ・ドラゴン》も融合召喚することができ、あちらは相手のバックを破壊することによる露払い、デッキからの墓地肥やしを行いながら、このカードよりもさらに多い攻撃回数でより多くのモンスターを戦闘破壊したり相手のLPを取ることができ、闇属性なので《オーバーロード・フュージョン》による融合召喚にも対応している。 こちらは元々の攻撃力で勝る点、2回攻撃を行うために効果の発動を伴わない点、光属性なので《オネスト》によって上昇した打点を2回目の攻撃に乗せることができる点などで差別化したいところ。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP038 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ |
|
同じ第8期に発売されたストラクにおいて【ブルーアイズ】が元から存在していたテーマ関連のチューナーである《伝説の白石》を拠り所にしてテーマのSモンスターを獲得したのに対して、【サイバー・ドラゴン】が獲得したXモンスターがこのカード。 素材指定である機械族レベル5モンスター2体という《サイバー・ドラゴン》2体でX召喚することを想定した指定は【サイバー・ドラゴン】においても割と骨の折れる内容であり、現在の【サイバー・ドラゴン】の1軍メンバーだけでこれを行おうとすると《サイバー・ドラゴン・ヘルツ》や《機械複製術》は半ば必須であり、場合によっては《銀河戦士》などの助けを借りる必要も出てくる。 持っている能力はX素材1つと引き換えにサイドラ1体を蘇生する効果、そうやって蘇生したサイドラなどを除外することで自身の攻撃力を一時的に2100も上げて4200打点になるお互いのターンに完全フリチェで使える効果、さらに相手の効果で墓地送りになった時にEXデッキの機械族の融合モンスターを特殊召喚して応戦できるリカバリー効果となっている。 展開効果及び打点アップ効果でフィニッシャー性能が高く、リカバリー効果で出てくるモンスターも中々暴力的な攻撃力やモンスター効果を持っているので悪くない効果ですが、現代基準ではX召喚難度に対して発揮する効果もその発動条件もややパワー不足といったところ。 いくらお互いのターンにフリチェで効果が使えても、それで攻撃力が上がるだけのやつとか何のアドバンテージにも妨害にもならないやつしか立てられない能力では今どき中々評価されません。 後に登場した《サイバー・ドラゴン・インフィニティ》が自身を重ねてX召喚するため下敷きとしてこのカードを名称指定しており、あちらは強力な万能カウンター能力を持っていることからあちらの下敷きとしての役割が専らで、かつてはこのカード自身も《星守の騎士 プトレマイオス》に重ねてX召喚することで厄介な素材指定をクリアしつつランク4Xが立てられるデッキでもインフィニティを使えるカードという役割でした。 |
|||
-
![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 サンダー・ボルト 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 サンダー・ボルト 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 NEOS 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 NEOS 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 青(じょう) 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 青(じょう) 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 SOUL 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 SOUL 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 asd 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 asd 」さんのコンプリートカード評価を見る!
※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
- 12/08 20:48 評価 9点 《アルカナフォースXIX-THE SUN》「《アルカナフォース…
- 12/08 18:51 評価 9点 《星辰竜ムルル》「カルテシア枠。ついでに実質フリチェで無効妨害…
- 12/08 18:14 評価 9点 《電光-雪花-》「罠パカを咎める存在。先攻で使ってもバック妨害…
- 12/08 16:27 評価 10点 《月光黒羊》「ターン1のない融合サーチとリソース回収ができる。…
- 12/08 15:39 評価 7点 《電脳堺甲-甲々》「戦闘破壊耐性がつくので実質アーゼウス。」
- 12/08 15:32 評価 10点 《激流葬》「激↑流→葬! リシドなどの罠ビで舐めてかかった相手…
- 12/08 13:10 評価 10点 《神芸学徒 グラフレア》「メディウスの仲間たちの中では、K9に対…
- 12/08 13:07 評価 9点 《神芸学徒 リテラ》「メディウスの仲間三人の中ではブリフュは勿…
- 12/08 12:09 コンボ モルガナイト押し付け。瞳の魔女モルガナの新コンボ。モルガナイト系の…
- 12/08 12:08 評価 3点 《鬼くじ》「総合評価:罠カードをトップに持ってきて相手の認識を…
- 12/08 11:52 評価 10点 《生還の宝札》「神の領域ゴッドファイブの筆頭。 原作では「モ…
- 12/08 11:27 評価 3点 《スライム増殖炉》「神の領域ゴッドファイブの一角。 毎ターント…
- 12/08 10:05 掲示板 オリカコンテスト準備スレ
- 12/08 08:17 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
- 12/08 04:49 評価 10点 《賢瑞官カルダーン》「誰やねんカードだが、墓地に落ちた永続罠…
- 12/08 04:28 評価 9点 《閃刀姫-アザレア・テンペランス》「汎用リンクの中ではリジェネ…
- 12/08 04:24 評価 9点 《つり天井》「激流葬と違い任意のタイミングで打てる全体除去の妨…
- 12/08 02:42 評価 5点 《スライム増殖炉》「今の時点では紛れもない産廃だが、 これをそ…
- 12/08 02:34 評価 8点 《ティンダングル・イントルーダー》「ティンダングルモンスターの…
- 12/08 02:07 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「刻印からサーチして妨害用の罠を、うら…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻


 TERMINAL WORLD 3
TERMINAL WORLD 3
 BURST PROTOCOL
BURST PROTOCOL
 THE CHRONICLES DECK-白の物語-
THE CHRONICLES DECK-白の物語-
 WORLD PREMIERE PACK 2025
WORLD PREMIERE PACK 2025
 LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
 ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
 LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
 デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
 DOOM OF DIMENSIONS
DOOM OF DIMENSIONS
 TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
 TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
 TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
 DUELIST ADVANCE
DUELIST ADVANCE




 遊戯王カードリスト
遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索
遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ
遊戯王デッキレシピ 闇 属性
闇 属性 光 属性
光 属性 地 属性
地 属性 水 属性
水 属性 炎 属性
炎 属性 風 属性
風 属性 神 属性
神 属性