交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
![CONTINUOUS]() 永続魔法
永続魔法
![EQUIP]() 装備魔法
装備魔法
![QUICK-PLAY]() 速攻魔法
速攻魔法
![FIELD]() フィールド魔法
フィールド魔法
![RITUAL]() 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
![CONTINUOUS]() 永続罠
永続罠
![counter]() カウンター罠
カウンター罠
 永続魔法
永続魔法
 装備魔法
装備魔法
 速攻魔法
速攻魔法
 フィールド魔法
フィールド魔法
 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
 永続罠
永続罠
 カウンター罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
 レベル1最強モンスター
レベル1最強モンスター
 レベル2最強モンスター
レベル2最強モンスター
 レベル3最強モンスター
レベル3最強モンスター
 レベル4最強モンスター
レベル4最強モンスター
 レベル5最強モンスター
レベル5最強モンスター
 レベル6最強モンスター
レベル6最強モンスター
 レベル7最強モンスター
レベル7最強モンスター
 レベル8最強モンスター
レベル8最強モンスター
 レベル9最強モンスター
レベル9最強モンスター
 レベル10最強モンスター
レベル10最強モンスター
 レベル11最強モンスター
レベル11最強モンスター
 レベル12最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧 > 天空の聖域 コンプリートカード評価(みめっとさん)
天空の聖域 コンプリートカード評価
|
|
「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |
| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |
|---|---|---|---|
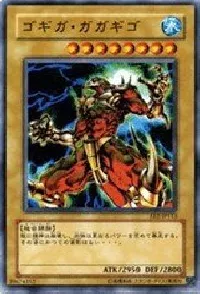 Normal ▶︎ デッキ |
4 | 001 | ゴギガ・ガガギゴ |
|
《ギゴバイト》が《ガガギコ》、そして《ギガ・ガガギゴ》を経て至ることになる、現時点でのダークサイドの最終態となる爬虫類族の最上級通常モンスター。 重い設定であるにも関わらずカード名が回文というおふざけ要素も見られ、長らく爬虫類族で最高の攻守を持つモンスターを通常モンスターであるこのカードが務めました。 《青眼の白龍》は僅かに及ばない攻撃力ですが、《魚群探知機》や《暗岩の海竜神》でリクルートできる通常モンスターとしては最高の攻撃力を持っており、攻撃力を重視するのであればそれらを使用するデッキに採用できる。 当然手札にくるととてもしんどいので、通常モンスターの採用は見送る、または《伝説の都 アトランティス》の適用下ではリリースなしで召喚できる《ギガ・ガガギゴ》に止めるといった構築の場合も少なくない。 他に期待することがあるとすれば、評価時点までに4種類のモンスターが存在する『ガガギゴ』がカード効果に指定されることになるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
4 | 002 | ゼラの戦士 |
|
同一の攻守を持つ地戦士の下級通常モンスター。 単体性能では攻撃力が100低いだけの《戦士ダイ・グレファー》でしかありませんが、《大天使ゼラート》及び《デビルマゼラ》を特殊召喚するために必要なリリースに名称指定されている唯一無二のカード。 そうなると《増援》や《聖騎士の追想 イゾルデ》に対応する戦士族や、《予想GUY》に対応する通常モンスターであることで受けられる恩恵も大きくなってくる。 特殊召喚されるモンスターのうちゼラートは発動条件とコストに対して効果が《サンダー・ボルト》及びそれのやや下位互換となる魔法カードで十分なものでしかなく面白くないため、発動条件となるフィールド魔法の性能と発展性の低さが気になるものの、やはり出ただけで3ハンデスができるマゼラを特殊召喚するために採用するカードになるでしょう。 そういうわけで2つのルートが示されているにも関わらず、結局どう足掻いても堕ちる運命にあるのであった…。 |
|||
 N-Rare ▶︎ デッキ |
2 | 003 | 封印師 メイセイ |
|
《魔法封印の呪符》と《罠封印の呪符》を使いこなせる唯一のカードとして設計された通常モンスター。 通常モンスターなので《予想GUY》によって場に出すこと自体は容易ですが、肝心の「呪符」カードの方にサーチ手段がなく、それらのカードがこのカードがいなくなった瞬間にぶっ壊れるあまりに脆い仕様なので実用性は低い。 それならこのカードは多少場に出しにくかったとしても、1800打点で毎ターン「呪符」魔法罠カードをサーチ・サルベージできるカードであった方が有り難かったでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | 004 | 神聖なる球体 |
|
ヴィーナスが創造する唯一無二のバニラ天使族モンスター。 戦闘能力は低く、ヴィーナスで1ターンで3体全て呼び出して全て各種リリースや特殊召喚のための素材として利用することになります。 初手で2枚以上の直引きは避けたいところですが、逆に初手ヴィーナス&球体0でスタートした場合はそのアドバンテージ獲得力はとてつもないものになります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | 005 | 鉄鋼装甲虫 |
|
通常モンスターの昆虫族として圧倒的最高パワーを誇るモンスターであり、自慢の装甲は弾き返す力よりも弾き飛ばす力の方が遥かに強い。 Gパークによる蘇生にも対応しており、唯一のバニラ最上級昆虫族となるモンスターですが、実は地属性のバニラ最上級としても最高クラスのパワーとなります。 近年通常召喚及び効果による特殊召喚が可能でかつ有用なモンスター効果もある最上級昆虫族は増えつつあるため、採用する場合は通常モンスターであることを活かすことが欠かせない。 3期にもなって効果なしモンスターが実質的な種族のエースを張っていたあたり、昆虫族という種族の苦心がうかがえるが、それだけにこのモンスターに特別な思い入れのあるデュエリストも少なくはないでしょう。 ラッシュデュエルにはこのモンスターに着想を得たセルフパロディモンスターも登場しています。 |
|||
 Parallel Ultra ▶︎ デッキ |
7 | 006 | 裁きの代行者 サターン |
|
最初に登場した「代行者」モンスターの1体で、それらの中では唯一の上級モンスターである土星を担当する天使族モンスター。 当時の天使族モンスターとしては生け贄1体で出せて攻撃力2400というだけでもそれなりのカードでしたが、その効果は自分の場に《天空の聖域》が存在していて自分のLPが相手のLPよりも多い時に自身をリリースすることで発動でき、その差分の効果ダメージが相手に直撃するというものになっている。 つまり自身のLPを16000以上まで回復させることで相手のLPが8000であっても一撃で焼き切ることが可能な能力となっており、先攻1キルが可能なカードである以上はそこにはそれなりの評価をつけるべきカードということになります。 現在では《マスターフレア・ヒュペリオン》にこの効果を代行させることも可能になっており、妨害を受けないことが前提なら実現させることもそう難しくないでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 007 | 英知の代行者 マーキュリー |
|
最初に登場した「代行者」モンスターの1体で、「叡智」ではなく「英知」表記の水星を担当する天使族の下級モンスター。 当時はカード名に共通の文字列を持つだけで効果の上では属する意味がない「代行者」でしたが、現在でもそれらの中でこのカードと《創造の代行者 ヴィーナス》のみ《天空の聖域》に関する効果を持っていない。 ヴィーナスの効果の有用性の高さについては存じている方も多いと思いますが、このカードに関しては全ての「代行者」の中でもぶっちぎりに最低の能力となってしまっている。 能力の内容としては相手のエンドフェイズに自分の手札が0枚の場合に自分のスタンバイフェイズに1枚ドローできるという、後に登場する《サイバーデーモン》のようなものとなっているのですが、発動条件が厳しい上にドローできるタイミングが最悪でドロー枚数も少ないという最低の効果になってしまっており、この程度の守備力では相手のエンドフェイズに特殊召喚しないと相手ターンを生き残ることすら難しいので効果を使える機会自体がほとんどないと言える。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | 008 | 創造の代行者 ヴィーナス |
|
登場当初は特にあてもなく謎の球遊びをするという理解し難い行動と、そのために絶対に直引きはご勘弁な貧弱バニラモンスターを最大3枚も入れなくてはならないその仕様からあまり評価を受けられていませんでしたが、Xやリンクの登場でその評価がとんでもなく爆上がりした代行者モンスターの1体。 何しろ回数制限がないこと、発動コストはライフなので発動するほどカードの枚数が増えること、デッキに触れる効果であること、最悪球体を直引きしてしまっても問題なく展開は行えるという好条件が揃っており、このカード自身にもそこそこの戦闘能力があることも好印象です。 依然として球体を直引きしたくないことに変わりはありませんが、その際のリカバリ方法やヴィーナス本体を場に呼び出す手段も登場当時よりもかなり充実しており、墓地からの特殊召喚はできませんが、最悪バーデクなどの捨て札として使ってしまっても良いでしょう。 貴女のやっていたことは間違ってなどいなかった、やはり回数制限がないカードは末恐ろしい。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
5 | 009 | 力の代行者 マーズ |
|
最初に登場した「代行者」モンスターの1体で、火星を担当する天使族の下級モンスター。 同期の《裁きの代行者 サターン》と同じく《天空の聖域》が自分の場にあることで適用されるお互いのLP差を参照した能力を持っており、このカードは自分のLPが相手よりも多い時にその差分がそのまま自身の攻守になるという能力を持っている。 これによりライフアドバンテージをとにかく重視した戦法をとることで4000を超える攻守を持つようになることもざらにあり、複数体並べることで片方で相手に与えた戦闘ダメージが後続のこのカードの打点にそのまま加わってその脅威はさらに大きなものとなる。 加えて魔法カードの効果に対して完全耐性を持っており、魔法による除去効果なども受けなかった点から在りし日の【天空の聖域】においては間違いなく主軸に据える価値もあったフィニッシャーを担当するモンスターでもありました。 自分の魔法の効果も受けないので装備魔法による自己強化もできませんでしたが、《ダグラの剣》による自分のLPを回復する効果はこの耐性の影響を受けないというのも大きかったですね。 現在では魔法カードに対する完全耐性の価値の低下や、このカードや《天空の聖域》に対するフリチェの除去や効果無効に対してあまりに脆いので厳しいカードとなりましたが、時に6000や8000にすら到達するその打点は「力の代行者」の名に恥じないものがあると思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 010 | 薄幸の乙女 |
|
《薄幸の美少女》のリメイクモンスターとなるカードで、レベルと攻守が変化しており、見た目は悲壮感がそれほどなくなっている以外はあちらとほぼ同じという珍しいリメイク。 能力は攻撃表示の時限定で適用される戦闘破壊耐性となっており、自身が攻撃表示でいる限りこのカードと戦闘を行ったモンスターの攻撃と表示形式を封じる効果を持っている。 3期の戦闘破壊耐性持ちは無条件で無限に効果が適用される《魂を削る死霊》と《マシュマロン》の独壇場であり、大きな戦闘ダメージを覚悟しなければ壁にすらならないこのカードの評価は登場当時から低かったです。 戦闘を行った相手モンスターの攻撃を封じるという独自の能力も、自身が場を離れるどころか守備表示になった瞬間に解除されるというあまりの拘束力の弱さから差別化も困難です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | 011 | 精気を吸う骨の塔 |
|
墓地からの特殊召喚が得意という特徴があったアンデット族にもう1つの種族カラー「デッキデス」の道を拓いた下級アンデット族で、屍界の観光名所。 アンデット族が特殊召喚されるたびに回数制限なく相手のデッキトップから2枚ずつガリガリと削っていきます。 複数並べれば効果は重複する上に、攻撃制限効果が相互に作用して攻撃ロックもかかるという仕様は当時としてはなかなか気の利いたもの。 中途半端なデッキデスは相手に塩を送るだけになる場合が多く、特化するとソリティア的な要素がかなり強くなり勝ちも負けも極端になりやすく、それ故に勝利手段としては敬遠されがちで、後続のアンデット族も徐々にデッキデス戦術からは手を引いていくことになります。 とはいえ特化したデッキを組んでライブラリアウト勝利を狙うだけの価値はあるモンスターだと思いますし、特殊召喚を繰り返す性質上、それらのモンスターを特殊召喚のための素材に使ったサブプランにも移行しやすいというのは良いと思いますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
4 | 012 | ザ・キックマン |
|
特殊召喚誘発の効果で墓地の装備魔法1枚を自身に装備するという、自分が闇属性のアンデット族だということをようやく理解した《凶悪犯-チョップマン》となるモンスター。 代わりに他の効果やP召喚によって特殊召喚する必要があるため、墓地に装備魔法があっても単独で発動条件を満たすことができない。 アンデット族ということで特殊召喚する手段は豊富ですが、【アンデット族】が装備魔法とあまりシナジーする種族ではないのが残念。 装備魔法の持つ発動コストなどを無視できるのは類似カードと同様であり、これのNSでも効果が出るやつが評価時点で実質的に禁止カードである《ガーディアン・エルマ》ということになる。 |
|||
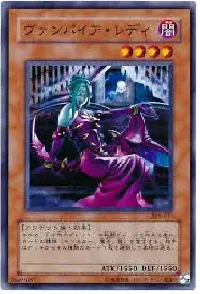 Normal ▶︎ デッキ |
3 | 013 | ヴァンパイア・レディ |
|
《ヴァンパイア・ロード》を下級モンスターにして被効果破壊時の自己蘇生能力を引いたもの。 自己蘇生能力がないのはまだ良いにしても、さすがに攻撃力が少しばかり下がり過ぎているため扱いづらい。 《ヴァンパイア帝国》の適用下なら下級アタッカーとして最低限の役割は持てるし、自身の持つデッキデス効果がこちら側の墓地肥やしと相手の場のカードの除去に繋がる。 単体では1点か2点というところですが、専用フィールド魔法のパンプ値に対する自身の攻撃力がちょうど良い高さで、デッキデス効果によって誘発するあちらの効果が強いのでなんとか使ってやれるレベルと言えるでしょう。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
5 | 014 | アステカの石像 |
|
原作のバトルシティ編でレアハンターが使用したいわゆる壁モンスターとなる下級岩石族で、作中では手札にある時は「壁男」とか「ガーマン」なる異なるカード名であったことで有名なカード。 「さすがの俺でもそれは引くわ」と言わんばかりに全力ノーサンキューのポーズで突き出した両掌が特徴。 その効果は自身が攻撃されることによって相手が受ける戦闘ダメージが倍になるというものであり、高い方の守備表示で攻撃を受け、さらに自身の守備力をダメステで大きく上げる効果と併用することで相手に一撃で致命傷を負わせることができる。 こういった性質から特化したデッキを組むことも可能ですが、その性質上特に友人間のデュエルでの使用に非常に不向きであり、攻撃を強要するカードなどとの併用が半ば必須となる。 下級で守備力2000なので最低減の働きはできますが、効果を活かせなければレベル4地岩石で守備力2000のモンスターは《巌帯の美技-ゼノギタム》などをはじめとして結構色々といるので、やはり専用デッキを組む必要があるでしょう。 自身が攻撃表示の時に相手が受ける戦闘ダメージも倍になること、他の戦闘ダメージ倍化の効果と併用しても倍の倍にはならない点に注意。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 015 | ロケット・ジャンパー |
|
相手の場に守備表示モンスターしか存在しない場合のみ直接攻撃が可能になるという能力を持つ岩石族のダイレクトアタッカー。 相手の魔法&罠ゾーンやフィールドゾーンにカードが出ていると効果が適用されないという《暗黒恐獣》や《ドリラゴ》と同じ欠陥を抱えている。 それでいて攻撃力がそれら以下で何なら《エレキリン》以下では使いようがなく、種族や属性の違いを論じる以前の問題となる。 |
|||
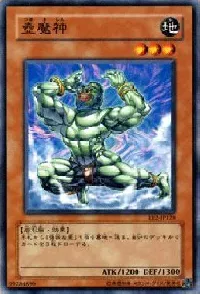 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 016 | 壺魔神 |
|
《ドラゴン族・封印の壺》の関連カードである《壺魔人》に対して、こちらは《強欲な壺の精霊》の関連カードである肉体美が自慢の魔神。 全然リターンが大きくなっていないその性能については語るまでもなく、《強欲な壺の精霊》と違って、《強欲なカケラ》すら収録されている「壺コレクション」の立体化からも弾かれた哀れなモンスターです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | 017 | 伝説の柔術家 |
|
ダメステに発動するデッキトップバウンスという強力効果を持つレベル3岩石、意外と攻撃力もある。 遊戯王OCGにおいては筋骨隆々な人物を岩石とすることもあるらしい。 発動条件は守備表示のこのモンスターと戦闘を行った場合、つまり現在のカードプールでは相手から攻撃された時にしか発動できないため、一度表側になってしまうとただの牽制効果になりがちである。 相手が高打点下級モンスター中心のデッキだとキツい感じで、19打点のモンスターには抜かれてしまうほか、召喚誘発効果を再利用されてしまうことからエアーマンは当時から苦手としていました。 今後このカードが守備表示のまま攻撃が可能になる効果が生まれれば、能動的にも効果を使えるようになるテキストである。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
4 | 018 | 機動砦のギア・ゴーレム |
|
原作のバトルシティ編でレアハンターが使用した守備力2200の下級壁モンスター。 OCGになる前にDM3で登場し、その際にレベル5だったので雲行きが怪しくなりましたが、無事レベル4のままOCG化され、さらに追加のメリット効果も与えられました。 しかしその追加効果というのが、何故か壁としての役割とは真逆となるライフコストを払うことで直接攻撃が可能になるという攻撃的な効果となっている。 機械族なので《リミッター解除》に対応していますが、元々の攻撃力が低く、機械族にはライフコストを払わずとも直接攻撃ができる下級モンスターが何体か存在するので、このカードである必要はあまりない感じです。 下級モンスターで2200という守備力は現在でもかなり高い数値ですが、守備力2200の下級機械族には《BM-4ボムスパイダー》や《ミキサーロイド》も存在するため、これといった特有の強みのないこのカードの総合評価はこのくらいが精一杯かなという感じです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | 019 | KA-2 デス・シザース |
|
一介の下級モンスターながら、デッキの主軸に据える価値のある豪快な効果を持つ闇機械モンスター。 戦闘破壊したモンスターのレベルに比例した効果ダメージを相手に与えることができるのですが、その倍率が500と非常に高く、レベル10のモンスターを葬ることに成功すればそれだけで5000の効果ダメージとなる。 ただし元々の攻撃力は1000しかないため、下級モンスターが相手であっても何らかの効果による戦闘補助は欠かせず、より有効に使うためには自ら高レベルモンスターを相手に送りつけるなどの複数のお膳立てが必要となる。 死デッキがエラッタされてしまったことやレベルを持たないXやリンクの登場も含め、登場当初からこのカードを取り巻く環境は良くも悪くもかなり変化していますが、圧倒的カードプールの増加により総合的に見ると概ね当時よりもかなり運用しやすくなっているかと思います。 隠れファンも結構多そうな良いモンスターと言えるのではないでしょうか。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
3 | 020 | ニードルバンカー |
|
同じパックに収録された《KA-2 デス・シザース》と同じ種族・属性・モンスター効果を持ち、レベルと攻守があちらよりも高くなっているモンスター。 攻撃力が高くなっている分あちらよりも発動条件を満たしやすくなりましたが、それでもその攻撃力は2000未満であり、こちらは上級モンスターになってしまっているので使い勝手がかなり悪くなっている。 登場当時よりもアドバンス召喚・特殊召喚手段共に遥かに容易にはなっているものの、基本的には《KA-2 デス・シザース》を強化した方がてっとり早く、戦闘ダメージではなく自身の効果によるダメージを重視して《月鏡の盾》などを使うならなおさらそうなってくる。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | 021 | ソニックジャマー |
|
元々はDM4のゲームオリジナルカードとして登場したモンスターで、それらのモンスターの中では3期という比較的早い段階でOCG化された機械族モンスター。 OCGではリバース効果モンスターとなり、リバース誘発効果によって相手の魔法カードの発動を一定期間完全に封じるという、発動条件は渋い代わりにかなり強力な効果を発揮する。 類似効果を持つ《真空イタチ》と違って罠カードは封じない代わりに次のエンドフェイズまで発動を封じるため自分のターンにリバースしても強いというのが最大の特徴で、相手ターンでリバースした場合も返しのターンで相手の速攻魔法による妨害を受けなくなるので悪くありません。 自身が場に表側表示で存在する限りといった条件もなく、リバース後に特殊召喚のための素材に使おうと後から消せない効果で魔法カードの発動を相手のみ拘束するので、自分のターンで簡単にリバースできるようになれば先攻時にかなり強いという意味で可能性を感じるカードです。 |
|||
 Parallel Ultra ▶︎ デッキ |
5 | 022 | ブローバック・ドラゴン |
|
《リボルバー・ドラゴン》の上級モンスター版として第3期に登場した機械族モンスターで、お互いに《ガトリング・ドラゴン》の名称指定の融合素材となるモンスター。 生け贄1体で召喚できるようになった代わりに攻守ともに順当にリボルバーよりも低下していますが、自身の持つコイントスを使った除去効果がリボルバーと同じ仕様でこちらはバックのカードも破壊できるようになっており、総合的な性能は上がっていると言える。 攻撃力も2300と当時の上級モンスターとしてはまあまあの数値で概ねリボルバーよりも使いやすいカードであり、登場当時はそのレアリティの高さもあってなかなか人気の高いカードでしたね。 現在では除去範囲はともかくとして、生け贄1体分の差よりは攻撃力が低いことの方が気になる感じなので、どっちもそんなに変わらないのかもしれません。 悪くない性能の割にはあまり再録されていないカードという印象で、闇属性なのもあってか特に機械族テーマのストラクには全く顔を見せていません。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
5 | 023 | 雷帝ザボルグ |
|
全ての「帝」シリーズモンスターで1番最初に登場した、6属性の帝の光属性を担当するカード。 後続の6属性の帝モンスターを見ていくと、このカードだけレベル5だったり、他の帝が属性に対する種族設定が「結界像」シリーズなどと一致する妥当なものになっている中このカードは天使族ではなく雷族だったりと、このカードを作った時点ではシリーズ化を見据えていたわけではなかった可能性も窺える。 効果はアドバンス召喚誘発のモンスターの単体除去という当時としては堅実に強いもので、アドバンス召喚誘発の効果としての有用性は非常に高かったです。 ただし強制効果で自分の場のモンスターも対象内なので自爆する場合があったのはご愛嬌。 同列であるはずの6属性の帝の中ですら、バックにも触れて除去方法もこのカードより強いライザーやガイウスが存在していたので、帝モンスターとして使われることはガイウスが登場した時点でほとんどなくなってしまいました。 同じ6属性の帝同士でも大きな格差が生まれてしまったせいか、上位種となる《轟雷帝ザボルグ》はそれぞれ自身が持つ元々の能力を伸ばした他の最上級帝とは全く異なる特殊な能力を与えられており、これにより他の最上級帝とは一線を画する圧倒的な個性を得ることになります。 また家臣となる《雷帝家臣ミスラ》が女性モンスターであること、「雷様」をイメージしていると思われる特徴的な髪型であることから「エロブロッコリー」呼ばわりされたりもするちょっと不憫でお茶目なモンスターです。 さてこのカードの性能の話に戻りますが、こちらもライザーやガイウスに比べると微妙というだけで別に我慢できないほど弱いわけでもなく、雷族サポートを使うなど愛さえあれば普通に使ってやれるレベルです。 その堅実にわかりやすく強い能力を買われてか、ラッシュデュエルにオリジナルの帝モンスター群が登場した際にはレジェンドカードとしてあららに輸入されています。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 024 | 原子ホタル |
|
テキストのせいで若干分かりづらいですが、セット状態から攻撃を受けても効果はちゃんと発動するので、発動条件としては自身が戦闘で破壊されて墓地に送られた場合と読み替えて差し支えない。 そしてその被戦闘破壊誘発の効果が相手に定数の効果ダメージを与えるだけというものであり、戦闘破壊したプレイヤーに効果ダメージが入るので送りつけとの併用すらかなわない。 何故ホタルのモンスターにこの効果なのかも理解できないし、色々と残念なカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | 025 | マーメイド・ナイト |
|
《海》が場に存在する時に2回攻撃が可能になるモンスターで「水族」のマーメイド。 元々の攻撃力は1500とそこそこ高い数値でありながら《グリズリーマザー》や《サルベージ》にはしっかり対応しており、《海》または《伝説の都 アトランティス》や《忘却の都 レミューリア》であれば攻撃力1700でモンスター・プレイヤー関係なく2回攻撃ができるカードとなる。 しかしそれらのカードがなければ効果なしモンスター同然であり、プレイヤーやトークンを攻撃力するならともかく、攻撃力1700程度ではモンスターとの戦闘に勝つのは難しい。 海デッキが繰り出す技のレパートリーとしての採用になると思うのでそもそも役割が異なるのですが、どうせ自身を含めて2枚以上のカードが必要になるのなら、このカードを使うよりも無条件に2回攻撃ができる下級モンスターを汎用的な装備魔法などで強化したほうがいいようなって感じです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | 026 | 軍隊ピラニア |
|
第3期においてまだまだ到底未発展な種族の1つであった魚族に登場した、割と当時からの隠れファンが多そうな能力を持つモンスター。 その効果は自身の直接攻撃によって相手プレイヤーに与える戦闘ダメージが倍になるというものであり、攻撃力4000以上の状態から直接攻撃をすることで初期LPである8000を削り切ることができる。 自身にダイレクトアタッカーとなる永続効果があるわけないため、直接攻撃能力を他の効果で付与したりこのカードの打点を強化したりと複数のカードによる補助が必要なコンボ向けのモンスターとなります。 補助用のカードは登場当時より遥かに充実していますが、現在では同じ枚数のカードを使うならより容易に似たようなワンショットキルを繰り出すことができてしまうので、思い出の中で活躍していたカードというところが否めないです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 027 | 針二千本 |
|
《針千本》の上位種となる1進化モンスターで、イラストからはあちらよりもさらに凶暴化していることが窺える。 上位種と言うだけあって攻撃力があちらの倍になっていますが、上級モンスターになっている上に守備力と効果の内容が変化していないので、はっきり言って性能はこちらの方がかなり低い。 まずもってアドバンスセットされるようなモンスターを不用意に攻撃することはそうないと思うのですが、このカードの場合は不用意に攻撃されたとしても役目を果たすことは難しいでしょう。 なお《針千本》と《針三千本》がダメステ終了時に効果が発動するのに対し、このカードのみ発動がダメージ計算後となっている。 |
|||
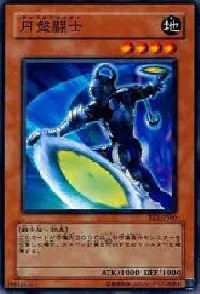 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 028 | 円盤闘士 |
|
守備力が一定以上の数値となる守備表示モンスターに攻撃した際に、ダメージ計算を行わずにそのモンスターを効果破壊できる能力を持つモンスター。 ここでいう「ダメージ計算を行わず」という古いテキストは大抵の場合「ダメージステップ開始時」を指すためセットモンスターに攻撃する場合はその守備力を参照できずに効果を発動できないのですが、このカードの場合はセットモンスターがリバースするタイミングでもある「ダメージ計算前」なので問題なく効果は発動する。 効果としては使いどころはほぼないし、効果内容も後発の《ドリルロイド》のほぼ完全下位互換で、地属性・戦士族の下級モンスターという括りでもテーマに属する《H・C 夜襲のカンテラ》に優先する理由がない。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 029 | 深緑の魔弓使い |
|
第3期においても未だに1つの種族として独り立ちできていなかった植物族に登場した、別種族のサポートモンスター。 サポートモンスターといっても植物族側が恩恵を受けるわけではなく、このモンスターが場の植物族によって攻撃から守られ、その場の植物族をリリースすることでバックのカード1枚に対して単体除去効果を出せるというモンスターになる。 効果の発動にターン1がないことくらいしか見るべきところがなく、破壊すべきカードが必要なので無限機関とするのも難しい。 同じ場のモンスターを射出する系のモンスターでも《キャノン・ソルジャー》や《カタパルト・タートル》のそれとは比較にならない内容です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
4 | 030 | 女忍者ヤエ |
|
コナミのゲーム作品「ゴエモン」シリーズに登場するヤエちゃんをモデルにした忍者モンスター。 風属性モンスター1体をコストに相手の魔法罠カードを全バウンスする効果を発揮する。 露払いとして優秀であり、一介の下級モンスターの所業としてはなかなかですが、戦闘能力はあまり高くなく、魔法罠カードしかバウンスしないのでターンを跨いでしまうとアドバンテージに繋がりにくく、自分の魔法罠カードは戻せないのでコンボ性も低い。 また忍者モンスターとして見ても、コストとなる風属性モンスターが同じゴエモン一行くらいしか存在しておらず、同じ風忍者には類似するバウンス効果を持ち、《忍法 変化の術》適性もこのカードより高いレベル4の《覆面忍者ヱビス》が存在している。 当時の風属性関連の効果を持つカードとしては優秀な方ですが、現在では厳しいカードでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | 031 | キングゴブリン |
|
従えた悪魔の数に比例して自身の能力を飛躍的に上昇させることができるレベル1闇悪魔で、当時まだ種族としてのつながりが弱かった悪魔族で種族統一デッキを組む数少ない動機となるモンスターでした。 自身がまだ弱いうちは他の悪魔に守ってもらうことができ、そうでなくても戦闘を行う相手モンスターの効果を無効にする的な永続効果を持つモンスターへの弱点対策にはなっています。 他に派手な効果などはありませんが、同胞たちをテキトーに場につらつらと並べていくだけで4000ライフを取るモンスターに成長するそのポテンシャルはけして侮れないものかと思います。 |
|||
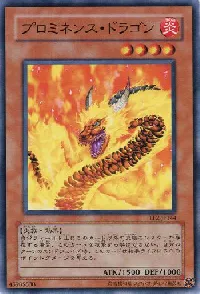 Normal ▶︎ デッキ |
4 | 032 | プロミネンス・ドラゴン |
|
かつて炎族にこのモンスターありというほどにバーン系のデッキで活躍したドラゴンの姿をした下級炎族モンスター。 他の炎族と並べることで攻撃対象にならなくなり、自身も炎族ということで2体目のこのモンスターを並べることで相手に攻撃されることなくバーンを入れ続けることができるというモンスターでした。 出した自分のターンのうちにダメージが入るのは偉いですが、さすがに現在ではバーンダメージ量を含めて何もかもが力不足。 デッキからこのモンスター2体を効果を無効にせず自壊させることもなく出すことができるカードがあったとしても、そのターンのエンドフェイズに計1000ダメージを入れるのが精一杯という感じで、従来のやり方で活躍させるのは到底難しいでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | 033 | 白魔導士ピケル |
|
遊戯王OCGにおけるいわゆる「萌えるモンスターカード」としては、第4期に登場した霊使いよりも先輩で、OCG産萌えカードの超大御所となるモンスター。 ほどなくして《ピケルの魔法陣》なるイラストに本人が出演している罠カードが登場したことからも、当時のこのカードへの反響の大きさがうかがえます。 その見た目に反して、レベル2であるにも関わらず《E・HERO フェザーマン》も殴り倒せる打点を持っていたことはよく語り草になっていたものです。 効果の方ですが、継続的なライフゲイン要員とするには発動タイミングも相まってちょっと無理があるかな?という感じで、このカードが登場した当初においても、例えば《プリンセス人魚》だとかもっと効率が良くて安定感もあるカードはあったよなあという印象です。 上位モンスターである《魔法の国の王女-ピケル》も調整をしくじりまくったとんだ失敗作でしたしねえ…霊使い同様に、今一度強化の場を与えてほしいと願って止みません。 王女ピケルもイラストの良さには定評があるため、できればそちらを活かしつつな感じの《マドルチェ・プディンセス》式強化だと嬉しいのですが、さすがに厳しいですかね? |
|||
 Ultimate Parallel Ultra ▶︎ デッキ |
3 | 034 | 大天使ゼラート |
|
《ゼラの戦士》をリリースに指定した2体の特殊召喚モンスターのうちの1体。 効果は《サンダー・ボルト》と同一のものとなっており、もう片方の《デビルマゼラ》と違って起動効果なので場に残しておく価値も大きく、ターン1がないので連打することもできる。 しかし発動に手札コストが必要でかつ効果処理時に自分の場に《天空の聖域》が必要なので、それで出せる効果がこれではやはり寂しいと言わざるを得ない。 聖域はサーチ体制が厚く、サポートカードもマゼラの効果を使うために必要な《万魔殿-悪魔の巣窟-》よりもかなり充実してはいるものの、フィールド魔法自体の性能はあちらと比べて特別優れているわけではなく、《ゼラの戦士》にとっては役に立たないことは同じなので、マゼラに対する大したアドバンテージにはならない。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | 035 | 光学迷彩アーマー |
|
《金華猫》や《ワン・フォー・ワン》が登場するまではレベル1モンスターにこのカードありという効果を持つ存在として知られていた装備魔法。 その効果はレベル1モンスターに装備できて直接攻撃が可能になるというシンプルなもので、まともに使うなら最初から直接攻撃効果を持つモンスターの攻撃力を強化して使う方が話が早く、装備モンスターが弱化する代わりにどのモンスターでも使いこなせて相手モンスターの弱化にも使える《流星の弓-シール》の方が汎用性は高い。 このカードを使うなら自身の効果などによってそこらへんの強化魔法では到底得られない膨大な攻撃力を得られる《ワイトキング》や《カオス・ネクロマンサー》や《スターダストン》などとの併用が欠かせないでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | 036 | 神秘の中華なべ |
|
それは自分自身をコントローラーであるプレイヤーに食してもらうという究極の利他的行動、を他でもないプレイヤー自身が自分のモンスター1体に強要する悪魔の所業。 生け贄にした自分の場のモンスターの攻守のうち、より美味なる方を選択してライフポイントを回復することができる魔法カードで、速攻魔法であるためお互いのターンでより有効な場面を選んで発動しやすいのが魅力。 自壊が確定しているモンスターや相手から一時的にコントロールを得ているモンスターなどを処理する手段としても使えますが、リンク召喚の導入によってほとんどのモンスターは何らかの特殊召喚のための素材に使えるようになったため、それらのモンスターに特殊召喚に関する縛りがかかっていない場合は、モンスターの処理を目的にこのカードを使うのはさすがにちょっと微妙な感じに。 どのようなモンスターに対してもサクリファイスエスケープが可能な速攻魔法というものは意外に少なくそういう意味でも貴重な存在ですが、それでも相手の盤面に触れたり数的アドバンテージを稼ぐカードではないことも確かなので、このカードを使うなら一度に大きなライフアドバンテージが得られることを活かせるカードも同時に投入しておきたいところ。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
8 | 037 | エネミーコントローラー |
|
原作のバトルシティ編で海馬が使用した魔法カードで、その名の通り相手の場のモンスターをコントロールする2つの効果から選べるカード。 特に後半の効果は、速攻魔法ということでフリチェでバトルフェイズでも手札から発動でき、自分のモンスターをコストでリリースし、相手モンスターのコントロールを奪えるカードとなります。 リリースコストはまともに使うと単なる消費となりますが、対象を取る効果や効果処理時に場から選ばれる効果を避けることにも使えますし、コストとなるモンスターは何でもいいので、相手に送りつけられたどうしようもならない邪魔くさいモンスターを有効に処理する手段としても使えます。 フリチェのコントロール奪取はそのターンしか保ちませんが、相手がそのモンスターを特殊召喚のための素材に使ったり、場のそのモンスターの存在を参照して後続を展開するようなデッキであればそのテンポを乱すこともできますね。 ノーコストで発動できる方の効果が相手モンスターの表示形式を変更するという、現環境では妨害手段としてあまり役に立たないことが多いものであることは残念ですが、それでも最低限の防御札として機能しますし、そのモンスターの守備力が低ければ返しのターンに戦闘で処理できる可能性も高いです。 総じて、現在のデュエルシーンではあまり見かけることはなくなりましたが、その汎用性は十二分に高いと言えるでしょう。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
5 | 038 | 滅びの爆裂疾風弾 |
|
最古の「必殺技」魔法カードの1枚で、自分の場に青眼が場にいる時にだけ使える《サンダー・ボルト》となる通常魔法。 発動ターンは全ての《青眼の白龍》には攻撃宣言をすることができない制約が課せられ、モンスターの全体除去以外の効果はない。 評価時点でサンボルは準制限であり、特定条件下でなければ発動できない上に、発動ターンの制約まであるこのカードを優先する理由はほとんどない。 これに関しては3期のカードなのでやむなしと言ったところで、今登場していれば何らかの墓地効果がついていたり、除去内容が除外だったり、効果破壊に効果ダメージがついたりしていただろうと考えると、やはり登場があまりに早すぎたカードと言わざるを得ないでしょう。 専用のサーチ手段が複数存在するという点で何とか差別化を図りたい。 と、いうものがこのカードに対するテンプレ評価になると思うのですが…。 それはそれとして《青眼の白龍》を使用するデッキである以上は、なんとかしてデッキに入れたくなるカードですよね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | 039 | モンスターゲート |
|
《名推理》と双璧をなす、デッキから大量の魔法罠カードや特殊召喚モンスターを墓地に送る可能性を秘めながら、最終的にはデッキから何らかのモンスターを特殊召喚することができる魔法カード。 無条件でノーコストで使える分、発動に名称ターン1がない強みも存分に活かせるあちらに対して、こちらは発動に場のモンスター1体のリリースを要求されるため、コストの調達に召喚権まで使わされる可能性も考えると強さはあちらより一歩引いたものとなりますが、こちらは一部の例外を除いて最後には必ず何らかのモンスター1体を特殊召喚できるのが強みとなる。 私は不確定要素を考慮しても断然《名推理》派ですが、このカードも悪くない性能だと思います。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
1 | 040 | 電脳増幅器 |
|
原作のバトルシティ編で絽場がショッカーに装備した能力強化系の装備魔法で、OCGではショッカーの持っている罠封じ能力の性質をまるごと変化させ、これを相手にだけ押し付けるというものになった。 古いテキストでは罠カードの効果が無効にならないだけで結局発動は自分もできないテキストだったが、最新版では場の罠カードの発動も封じるのは相手だけであることが明記されている。 しかしこれを装着すると場を離れた時に装備モンスターが自壊してしまうので、ショッカーにいたずらに弱点を増やすだけの結果に終わりやすい。 また原作ではあった装備モンスターの攻撃力を強化する効果がなくなっており、こういった装備魔法はまず装備モンスターのステータスを強化する効果ありきで固有の追加効果であるべきだと私は思いますね。 割とOCG化されたことが奇跡のカードでもあり、不毛な無限ループを作ってしまうような他にない性質が面白いカードではありますが、それにしてもOCG化するのが少しばかり早すぎました。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 041 | ウェポンチェンジ |
|
1ターンに1度、ライフコストを払うことで自分の戦士族か機械族1体の攻守を入れ替えることができる魔法カード。 《右手に盾を左手に剣を》のように1度に複数のモンスターに作用しませんが、あちらと違って永続魔法なので使い減りしないのが特徴。 しかし自分メインフェイズに発動する永続魔法であるにも関わらず、効果の発動が自分スタンバイフェイズという最低のタイミングになってしまっているため実用性に乏しい。 このような仕様ならライフコストなんて必要ないし、複数のモンスターに作用する効果でも良かったし、最低でも永続罠カードで良かったはずなのですがどうしてこうなってしまったのか。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
5 | 042 | 天空の聖域 |
|
第3期に登場し、このカードが収録されたレギュラーパックのパック名にもなった天使族のホームグラウンドとなるフィールド魔法。 しかしその効果は《マシュマロン》が貫通にも強くなるとか《シャインエンジェル》が戦闘ダメージを気にせずに自爆特攻ができるようになるという程度で、種族のサポートとしては何のアドバンテージにもならないかなり質の低い効果でしかありません。 しかしこのカードと同時に登場した、場にこのカードがあることで効果を発揮する数々のカードにとっては欠かせないカードで、現在ではその量も増え質も高くなっており、まさに「カード名が本体」と言えるカードです。 ただそれはそれとして、今登場していたならさすがにもう少しましなカードになっていたことも間違いないでしょう。 |
|||
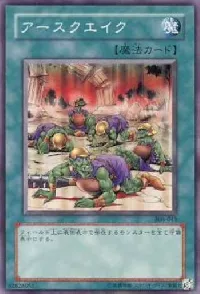 Normal ▶︎ デッキ |
2 | 043 | アースクエイク |
|
第3期に登場したお互いの場の全ての表側表示モンスターを守備表示にする効果を持つ通常魔法。 相手モンスターを守備表示にして戦闘補助としたり、自分の場に召喚したモンスターをそのターンのうちに表側守備表示の状態にできるコンボカードとして使える。 しかし通常はなのですぐに使えることを除けばほとんどの場面でフリチェで使える《重力解除》や《進入禁止!No Entry!!》の方が汎用性が高く、捲り目的なら《闇の護封剣》や《皆既日蝕の書》などの方が使いやすい。 今後《地割れ》や《地砕き》のように名称指定されることもなさそうですし、それこそ「護封剣」カードが効果に指定されたら一巻の終わりという感じですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | 044 | 罠封印の呪符 |
|
すぐに発動できる代わりに場にメイセイが必要でチェーン発動ができない永続魔法の体をしたお触れ。 その性質上、《魔法封印の呪符》と両立はできないので状況に合わせてどちらかを使うことになるのですが、永続的な魔法封じの方がその価値は格段に高く、逆に勅命が禁止カードであることに対してお触れが3枚積める現状で、このカードは使い分けるどころか採用する価値があるかも怪しい。 しかも魔法カードであるためにキャンセラーとスキドレで三竦みを形成するという裁定面でもとても迷惑なカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 045 | 盗人ゴブリン |
|
自分のLPの回復と相手への効果ダメージを一度に両方行うことができる「ゴブリン」魔法カード。 イラストには相手から奪った金品で私利私欲を満たそうとする様が描かれており、それがカード効果に反映された形となる。 カードとしては回復とダメージが同時に行われることで効果が誘発する「ゴブリン」モンスターでも出ない限り名前が挙がることもないでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | 046 | バックファイア |
|
自分の場の炎属性モンスターが被破壊されることで効果が発動し、相手に500の定数効果ダメージを与える永続罠。 1回当りのダメージは小さいですが、戦闘・効果破壊の両方に対応、ターン1なし、場に2枚以上存在していればチェーンを組む形で1度の被破壊で複数回発動するなど割と良い条件は揃っている。 専用サーチがないのは仕方ないにしても、それしかない効果で永続罠というのが辛いところ。 永続魔法かフィールド魔法のサブ効果としてこれがくっついていればなって感じです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 047 | ミクロ光線 |
|
対象のモンスター1体の守備力を0にする通常罠カード。 そういう装置(機械)でかつ《古代の機械巨人》の貫通能力と相性が良いということでストラクチャーデッキ「機械の叛乱」の再録枠にも選出されている。 単独で発動できることを除けば、戦闘補助カードとしては速攻魔法である《死角からの一撃》の方が優れており、対象となるモンスターが効果モンスターでかつ攻撃表示なら対象耐性に強い《アヌビスの呪い》の方が良いため、このカードが使われることはないでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | 048 | 裁きの光 |
|
《天空の聖域》がフィールドゾーンに存在する場合に指定の手札コスト1枚を切ることで発動できる罠カード。 その効果は場のカード1枚を対象を取らない墓地送りによって除去するか、相手の手札1枚をピーピングハンデスするという結構珍しい組み合わせです。 この時期に登場した単体除去カードとしてはやたら耐性貫通力が高く、ハンデス内容も優秀で効果としては結構優秀です。 モンスターがフリチェで使える効果と腐りやすい罠カードの差が如実に表れるところではありますが、《失われた聖域》なら1枚でこのカードをデッキからセットしながらその発動条件を満たすこともできるため、ストラクRで再録機会を得たこと自体には納得です。 旧テキストでは色々と不親切な部分も多かったので、そういう意味でも有り難い再録ですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | 049 | 魔法封印の呪符 |
|
メイセイが場に存在する時のみ発動でき、メイセイがいなくなると場に維持できなくなる勅命という感じの永続罠カード。 効果だけを無効にする勅命と違って魔法を発動すること自体もできなくなるマジキャン仕様なので、発動と効果を無効にされない魔法カードに対しても有効であり、チェーンを積ませたり墓地効果を使うために墓地へ送らせることも許さない。 《魔法族の里》と比較するとチェーン発動できることが強みにも弱みにもなるといったところで、速攻魔法に上から叩かれるのは勅命と変わらない。 メイセイ専用カードとはいえ、勅命が禁止の今、芳香以上の拘束力で継続的に魔法カードを封じられるカードは大変貴重であり、個人的にはかなり魅力的なカードだと感じます。 しかし「開くのは自由だし勝手に壊れたりしないけどメイセイが場にいないと効果が適用されない」という仕様にして欲しかった感じは大いにありますね。 場にメイセイがいないと発動できないのはまあ仕方ないとしても、なにもメイセイがいなくなったからといってその場で砕け散ることはなかった。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | 050 | 光の護封壁 |
|
定倍数のライフを払って発動し、以後その数値に応じた攻撃力以下の相手モンスターの攻撃を無限に抑止し続ける永続罠で、《光の護封剣》から派生して生まれたと思われるカード。 かつて制限カードに指定されていた経験もあり、過剰なまでにライフを払うことができる数少ないカードでもあります。 大方3000から4000ほどのライフを先行投資すれば、その後は場に存在する限り相手モンスターに攻撃されることはほとんどなくなるでしょう。 ただし相手だけの攻撃を抑止する永続罠としては、生きている限り分割払いが必要ですが全てのモンスターの攻撃を止め続けられる《スクリーン・オブ・レッド》の方が概ね低リスクで使いやすく、自分が攻撃できなくても構わないなら無料で発動&維持ができてSモンスター以外の攻撃を止め続ける《シンクロ・ゾーン》などもあります。 5000払って発動してもリンク3モンスターを対象にした《アクセスコード・トーカー》には普通に突破されるため、このカード以外の場のカードを全て壊されてそのままリーサルを取られてしまう可能性もあります。 このカードを使うなら、やはり無条件で一発でライフを8000から1000にまで減らすことすらできることを活かすべきでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | 051 | ソーラーレイ |
|
自分の場の光属性モンスターの数の600倍となる効果ダメージを相手に与える罠カード。 倍率としては相応の高さであるものの、トークンなどの通常モンスターも含むことを除けば、ダメージ倍率が100しか変わらなくてモンスターの属性は不問でかつ相手の場のモンスターも頭数に含む《停戦協定》に優先すべき部分は少ない。 光属性の通常モンスターやトークンを展開できて、この一押しとなる効果ダメージが勝ちに直結するくらいではなけば採用するのは難しく、そういったデッキはかなり限られるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | 052 | 忍法 変化の術 |
|
《忍者マスター HANZO》のNS誘発効果で持ってきて、そのままレベル7以下の該当の3種族のモンスターの特殊召喚に繋げられるという点で有用なカード。 他の効果では指定してデッキから特殊召喚することが容易ではないテーマ外モンスターにとってはとても貴重な存在です。 歴史としては主に《ダーク・シムルグ》や《霞の谷の巨神鳥》などのレベル7モンスターを特殊召喚するためのカードとして使われてきましたが、レベル4以下のモンスターにとっても十分価値がある効果と言えるでしょう。 あとこのカードのイラストに描かれているヤエさんがとってもいいですよね、魅惑の股下デルタゾーンも含めて…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | 053 | 光の召集 |
|
効果によって手札を全捨てして、その効果処理時に墓地に捨てた手札と同じ枚数の光属性モンスターを選んでサルベージすることで、手札か墓地のモンスターと全とっかえされるという罠カード。 お互いのターンにフリチェで使える効果によって墓地のモンスターが手札に加わるので、《エフェクト・ヴェーラー》や《原始生命態ニビル》などの手札誘発モンスターの回収手段としても適しており、相手の《墓穴の指名者》などを避ける効果としても一定の価値があります。 普通の魔法罠カードを捨て札にしてしまうとお得感がなくなるので、手札から捨てられることや墓地に送られることで誘発する効果を持つモンスター、または墓地で発動する起動効果を持つカードなどを捨て札にできるとなお良い。 ただし《マクロコスモス》などをチェーン発動されると手札を全除外するだけで効果処理が終わってしまうので注意したい。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
3 | 054 | ドレインシールド |
|
《魔法の筒》の自分のライフポイントを回復する版となる攻撃反応型の通常罠カード。 攻撃してくる相手によっては1枚で大きなライフポイントを得られる可能性があることを除けば、ライフを回復する手段としてとても優れているとは言えないカード。 さすがに攻撃反応型で数的アドバンテージにならなくて継続性もターンスキップ性もないライフ回復の罠カードは怖くなんともないです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | 055 | アーマーブレイク |
|
装備魔法の発動のみを専用に無効破壊するノーコストのカウンター罠。 効果範囲の狭さがノーコストで使えるというメリットに全然勝っていない系のよくあるカウンター罠の1つです。 イラストで爆破されているのも何故か装備魔法ではなく、通常罠カードでしかも装備カード化すらしない装備カードメタ効果を持つ《ガラスの鎧》とツッコミ所だらけ。 |
|||
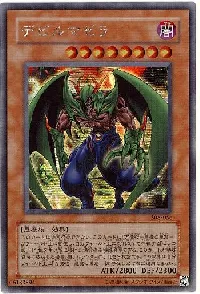 Secret ▶︎ デッキ |
6 | 056 | デビルマゼラ |
|
《ゼラの戦士》をリリースに指定した2体の特殊召喚モンスターのうちの1体。 《大天使ゼラート》と違い特殊召喚された瞬間に仕事が終わり、以降は効果なしモンスター同然になってしまいますが、発揮する効果は相手への3ハンデスというなかなか見ない強力効果となっている。 先攻で発動したい効果なのですが、召喚条件や発動条件がかなり厳しいため使用するなら特化構築にすることが求められ、《予想GUY》や《魔界発現世行きデスガイド》を利用することで、デスガイドから出したEXモンスターや呼び出したモンスターの墓地効果の力も借りれば特定の手札2枚からでもすぐさま特殊召喚することが可能となっています。 発動条件となる《万魔殿-悪魔の巣窟-》の性能があまりに低く、悪魔族であるこのカードすらサポートしないのが残念なところ。 |
|||
 Ultimate ▶︎ デッキ |
8 | 057 | 人造人間-サイコ・ショッカー |
|
原作漫画のバトルシティ編で登場し、絽場から城之内の手に渡った本編でもOCG化された第2期においても大活躍した機械族モンスター。 漫画ではレベル7の最上級モンスターでしたが、DM3でレベル6の上級モンスターだった縁があってかOCGでも生け贄1体で出せるレベル6モンスターとなり、それが大躍進の理由の1つと言っても過言ではないでしょう。 持っている能力は既に場に出ている罠カードの効果を全て無効にし、さらに新たに罠カードの発動自体もさせないという結構貴重なカードです。 発動自体をさせないというのは遊戯王においてはかなり強力な効果で、発動と効果を無効にできない、このカードの発動に対して相手は効果を発動できない、というカードも発動そのものを封鎖してしまえば関係ないということである。 この罠カードを封殺する能力と機械族モンスターの攻撃力を倍にする効果を持つ速攻魔法である《リミッター解除》との相性が抜群で、第2期における【機械族】を支えた存在でもあります。 古豪ながらサポートも充実しており、罠メタとしては未だに優秀なモンスターと言えるかと思います。 ただし墓地で発動する罠カードの効果にだけは干渉できないので注意したい。 |
|||
-
![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!
※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。
更新情報 - NEW -
- 2024/12/21 新商品 PREMIUM PACK 2025 カードリスト追加。
- 01/15 21:38 評価 1点 《ヴェノム・ボア》「メインデッキに入る《ヴェノム》の中では唯一…
- 01/15 20:16 評価 10点 《応戦するG》「古代エジプトにおいて、Gは《死者蘇生》のために…
- 01/15 18:51 デッキ トリシュトリシュエンプラ…
- 01/15 18:43 評価 10点 《封印の黄金櫃》「墓堀りグール「自分からデュエルで使えなくす…
- 01/15 18:35 評価 8点 《金色の魅惑の女王》「ライゼオルのデッドネーターみたいな効果を…
- 01/15 18:20 評価 9点 《闇と消滅の竜》「SINモンスターみたいな条件でポンと出てきて、…
- 01/15 18:13 評価 8点 《サイコウィールダー》「LV3が場に居ると手札から出せるモンスタ…
- 01/15 17:30 評価 3点 《スーパービークロイド-ジャンボドリル》「このあたりの時代にや…
- 01/15 16:00 評価 3点 《竜の影光》「ぶっちゃけ弱いです。 3つ効果が全てのパワーが…
- 01/15 15:53 評価 5点 《鎧騎士竜-ナイト・アームド・ドラゴン-》「漫画版万丈目のリメ…
- 01/15 15:48 評価 8点 《光と昇華の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《闇と消滅の…
- 01/15 15:46 評価 9点 《闇と消滅の竜》「メインデッキのモンスターに戻れた《光と昇華の…
- 01/15 15:42 評価 9点 《光と闇の竜王》「融合版《光と闇の竜》の割と評価が難しいカード…
- 01/15 15:06 評価 3点 《ヴェノム・サーペント》「《ヴェノム》の下級モンスターの一体。…
- 01/15 15:00 評価 2点 《ヴェノム・スネーク》「今見ると《捕食植物》の元になったと思わ…
- 01/15 13:10 デッキ テラナイト
- 01/15 12:39 デッキ ファンカスノーレ
- 01/15 10:59 SS 26話 共同戦線Ⅰ
- 01/15 10:51 評価 1点 《シールドスピア》「何となく強そうな名前とイラストにやる気の無…
- 01/15 10:50 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
 ALLIANCE INSIGHT
ALLIANCE INSIGHT

 PREMIUM PACK 2025
PREMIUM PACK 2025

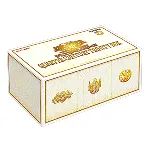 QUARTER CENTURY TRINITY BOX
QUARTER CENTURY TRINITY BOX
 TERMINAL WORLD 2
TERMINAL WORLD 2
 QUARTER CENTURY LIMITED PACK
QUARTER CENTURY LIMITED PACK
 COCO'S コラボ記念カード(2024)
COCO'S コラボ記念カード(2024)
 SUPREME DARKNESS
SUPREME DARKNESS
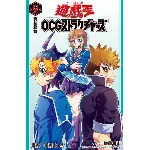 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 9巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 9巻
 遊☆戯☆王OCG STORIES 4巻
遊☆戯☆王OCG STORIES 4巻
 トーナメントパック2024 Vol.4
トーナメントパック2024 Vol.4
 WORLD PREMIERE PACK 2024
WORLD PREMIERE PACK 2024
 COMPLETE FILE -白の物語-
COMPLETE FILE -白の物語-
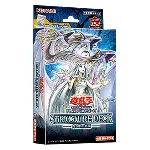 ストラクチャーデッキ-青き眼の光臨-
ストラクチャーデッキ-青き眼の光臨-
 デッキビルドパック クロスオーバー・ブレイカーズ
デッキビルドパック クロスオーバー・ブレイカーズ
 RAGE OF THE ABYSS
RAGE OF THE ABYSS




 遊戯王カードリスト
遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索
遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ
遊戯王デッキレシピ 闇 属性
闇 属性 光 属性
光 属性 地 属性
地 属性 水 属性
水 属性 炎 属性
炎 属性 風 属性
風 属性 神 属性
神 属性