交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
![CONTINUOUS]() 永続魔法
永続魔法
![EQUIP]() 装備魔法
装備魔法
![QUICK-PLAY]() 速攻魔法
速攻魔法
![FIELD]() フィールド魔法
フィールド魔法
![RITUAL]() 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
![CONTINUOUS]() 永続罠
永続罠
![counter]() カウンター罠
カウンター罠
 永続魔法
永続魔法
 装備魔法
装備魔法
 速攻魔法
速攻魔法
 フィールド魔法
フィールド魔法
 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
 永続罠
永続罠
 カウンター罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
 レベル1最強モンスター
レベル1最強モンスター
 レベル2最強モンスター
レベル2最強モンスター
 レベル3最強モンスター
レベル3最強モンスター
 レベル4最強モンスター
レベル4最強モンスター
 レベル5最強モンスター
レベル5最強モンスター
 レベル6最強モンスター
レベル6最強モンスター
 レベル7最強モンスター
レベル7最強モンスター
 レベル8最強モンスター
レベル8最強モンスター
 レベル9最強モンスター
レベル9最強モンスター
 レベル10最強モンスター
レベル10最強モンスター
 レベル11最強モンスター
レベル11最強モンスター
 レベル12最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧 > デュエリストパック-深淵のデュエリスト編- コンプリートカード評価(みめっとさん)
デュエリストパック-深淵のデュエリスト編- コンプリートカード評価
|
|
「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |
| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |
|---|---|---|---|
 Holographic ▶︎ デッキ |
8 | JP000 | No.101 S・H・Ark Knight |
|
かつてフリー素材で2体素材で出せる汎用ランク4Xの中でも大鉄板だった「No.」モンスター。 対象のモンスター1体をエクシーズ素材化するという、完全・対象耐性とコントロール変更耐性を持つモンスター以外に対して有効であり、それらを墓地に送ることも除外することもなく極めて安全に処理できる強力効果を持つ。 2つで出せて2つ使っても自身の効果により1つ残るので耐性もちゃんと使える親切設計なのも素晴らしい。 ただし攻撃表示かつ特殊召喚されたモンスターしか素材化の対象にできないという《鳥銃士カステル》に比べると非常に融通の利かない注文をつけてくるのが玉に瑕で、これが意外と使いにくい上に忘れやすくて困る部分になってしまいます。 なんとなくですが、エラッタ後の《洗脳-ブレインコントロール》とまでは言わずとも、それに近からずとも遠からずみたいな不便さを感じます。 ただしリンクモンスターに対してはもれなく有効なのでそこまで致命的な制約でもありません。 また《天霆號アーゼウス》登場後は、自身の耐性効果により多少の反射ダメージを覚悟の上なら比較的安全に特攻してアーゼウスを重ねられる、そして効果も使用可能な状態という点が評価されている。 |
|||
 Secret Super ▶︎ デッキ |
9 | JP001 | アビス・シャーク |
|
自分の場に何らかの水属性モンスターが先行している必要がありますが、そのモンスターをリリースするなどして減らすことなく手札から自己SSでき、さらにそれに連なる形で特定のレベルの魚族をサーチする効果を発揮する。 サーチ効果付きの自己SSなので《灰流うらら》にチェーンされると自己SSごと止められてしまう一方で、《スキルドレイン》のような場のモンスター効果を無効にするタイプの効果は無視してサーチを行うことができます。 《マーメイド・シャーク》はこのカードをサーチしつつこのカードの自己SS条件を満たすことができるので相性が良く、その場合は召喚権を使うのでこのカードでサーチする魚族は同じく自己SS能力を持ち、このカードと同じレベルを持つ《クリスタル・シャーク》や《ドリーム・シャーク》などが適任となります。 ただしこの効果の発動後にはそのターン水属性モンスターしか特殊召喚できない制約が課せられるため、X召喚以上にL召喚の選択肢は極端に狭くなり、それと同時に自分の「ナンバーズ」モンスターが相手モンスターとの戦闘で与える戦闘ダメージが倍になるという、消えないメリットとデメリットを同時にもたらすという極めて特殊な性質を持っています。 クリスタルを自身の効果で自己SSした場合、このカードの制約も含めて自分は「水属性のXモンスター」しかEXデッキから特殊召喚できなくなるわけですが、このカードとクリスタルはナンバーズXモンスターのX素材にする場合にそれぞれがレベル3と4としても扱うことができるため、水属性ならランク5X以外にも選択肢を広げることができるようになっています。 自身の自己SS後に発揮される戦闘ダメージ倍化を活かすのであれば、水属性のランク3〜5Xモンスターの中でも是非とも「ナンバーズ」に属するモンスターをX召喚したいところで、これだけ限定された指定でも意外と選択肢はあります。 |
|||
 Secret Super ▶︎ デッキ |
9 | JP002 | クリスタル・シャーク |
|
《アビス・シャーク》の最高のパートナーとなるレベル5の魚族モンスター。 あちらの自己SS効果に連なるサーチ効果で手札に持ってきて、アビスを対象に効果を発動し手札からSSするというのが基本の動きとなります。 その際にアビスの攻撃力を半分にしてしまいますが、アビスは元々が戦闘要員ではない上に特殊召喚のための素材に使うことで全くデメリットではなくなるし、自身の効果で特殊召喚した後に場を離れると除外されるデメリットもアビスと共にX素材にすることで帳消しにできる。 さらにこの自己SS効果は墓地からも発動できるため、X素材にして墓地に送ることで繰り返し効果を使うことができ、何気に相手の場の水属性モンスターも対象にできるので、《No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン》を先行させておけば相手の場のモンスターを弱化させつつ手札や墓地から特殊召喚できるカードにもなります。 クラーゲンは「ナンバーズ」に属する水属性のランク4Xモンスターでもあるため、アビスとこのカードの自己SS後に課せられるそれぞれの制約をクリアしつつ、アビスとこのカードでそれぞれの2の効果を適用してX召喚できるモンスターとしても大変都合が良いです。 |
|||
 Secret Ultra ▶︎ デッキ |
8 | JP003 | N・As・H Knight |
|
水DPで登場した《No.101 S・H・Ark Knight》をかなり意識したイラストや能力が特徴の、フリー素材で2体素材の汎用ランク5Xモンスターでもあるカード。 お互いのメインフェイズにフリチェで使える能力により、EXデッキからオーバーハンドレッドナンバーズ1体を自身のX素材として敷き込み、続けて選んだ場のモンスター1体も自身のX素材として敷き込むという能力を持っている。 これにより相手ターンに対象を取らず、破壊でもなく墓地送りでもなく、手札やデッキにすら戻さないモンスター1体の除去が行うことができる。 効果を使う際には自身のX素材を2つ使うことになりますが、この効果を使うとことでX素材は2つに戻るので、次のターン以降に再度効果を使うこともできます。 このカードに無条件で重ねてX召喚できる《CX-N・As・Ch Knight》や、それに重ねらる《CNo.101 S・H・Dark Knight》からの《CX 冀望皇バリアン》という重ねてX召喚の繰り返しでさらなる展開も狙えますが、いずれにせよEXデッキはかなり圧迫することになるので注意したい。 これらの要素を踏まえるとこのカードの下に敷き込むオーバーハンドレッドは性能面を考えても《No.101 S・H・Ark Knight》か《CNo.101 S・H・Dark Knight》のどちらかになり、《カッター・シャーク》や《ランタン・シャーク》などの能力によってレベル3から5までの水属性のX召喚ができる【シャーク】では《No.101 S・H・Ark Knight》を普通にX召喚できる点でも相性が良い。 |
|||
 Secret Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP004 | CX-N・As・Ch Knight |
|
水DPで登場したその見た目に《CNo.101 S・H・Dark Knight》の面影のあるカードで、汎用ランク5Xである《N・As・HKnight》に無条件で重ねてX召喚できる「CX」モンスター。 EXデッキのオーバーハンドレッドを自身のX素材として敷き込むあちらに対して、こちらはEXデッキのオーバーハンドレッドを自身に重ねてX召喚するという、自身が他のモンスターを下敷きにして出てくるのに自身も下敷き要員という実に変わったモンスターで、あくまでもエースは《CNo.101 S・H・Dark Knight》の方ですよといったところでしょうか。 《N・As・HKnight》の効果で《CNo.101 S・H・Dark Knight》AをX素材に持たせ、そちらにこのカードを重ねてX召喚、このカードの効果でX素材となっている《CNo.101 S・H・Dark Knight》Aを取り除いてBを重ねてX召喚、さらにそれに《CX 冀望皇バリアン》Aを重ねてX召喚して墓地の《CNo.101 S・H・Dark Knight》Aの効果をコピーして効果を発動し、仕上げにカード名が変わっている《CX 冀望皇バリアン》AにBを重ねてX召喚するという流れで、相手の場のモンスター3体をX素材化して除去しながら攻撃力7000の《CX 冀望皇バリアン》が誕生する。 それ以外のオーバーハンドレッドとなる「No.」や「CNo.」Xモンスターも自身に重ねられますが、展開に水属性縛りがかかる場合も考えると概ね《CNo.101 S・H・Dark Knight》の一択になりそうです。 ただし一度展開を行うだけでかなりEXデッキを消耗する上に盤面としてはそれほど強いものにはならないことには注意したい。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
7 | JP005 | バリアンズ・カオス・ドロー |
|
水DPのナッシュ枠で登場した水属性とは何も関係ない「セブンス」通常魔法及び「No.」Xモンスターのサポートカードとなる「バリアンズ」魔法カード。 「セブンス」通常魔法には《RUM-七皇の剣》や《七皇昇格》や《時空の七皇》といった優れたものが多く、もう1つの効果もデッキからの2体の特殊召喚からのX召喚という強力極まりないものなっていますが、通常のドローでドローしてこないと使えない《RUM-七皇の剣》と同じ悩みを抱えるカードでもあるので、効果の強さだけをもって評価することはむずかしくなっている。 初手に来ると腐ってしまうカードの効果だけをコピーするカードが同じように手札で腐る性質を持つというのは本末転倒感があり、両方が初手に来た時の悲惨さは計り知れない。 まあリクルートしたモンスターの効果は無効になるとはいえ、魔法カード1枚からノーコスト無制約でほぼ全ての同じレベルのモンスター2体をリクルートできる効果があっていいはずがないのでこれは仕方ないですね。 |
|||
 Secret Super ▶︎ デッキ |
10 | JP006 | 七皇昇格 |
|
炎DPの《七皇覚醒》、光DPの《時空の七皇》と同じく、水DPでバリアンズの一員であるナッシュが選出された際に新規枠を使って世に送り出された「七皇」カードの1枚。 このカードには同名カード以外の「セブンス」魔法罠カード、「バリアンズ」魔法罠カード、「RUM」速攻魔法のいずれか1枚をサーチする効果があり、名称ターン1があること以外は等価交換で癖のないサーチ効果ということで使いやすい。 デッキトップにも設置できることや、墓地効果で手札の「RUM」魔法カードの効果をコピーできる効果があることから引いてしまった《RUM-七皇の剣》を有効活用することを目的に設計された面も強いカードです。 今後は【タキオン】以外のデッキで《時空の七皇》のサーチ効果を使いたい場合に、それをサーチできるカードとして使われる可能性があるかもしれませんね。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
6 | JP007 | 不朽の七皇 |
|
水DPのナッシュ枠で登場したオーバーハンドレッドの「No.」Xモンスターのサポートカードとなる「セブンス」永続罠カード。 自分の場にオーバーハンドレッドの「No.」XモンスターまたはそれらをX素材として持っているXモンスターが存在している場合に2つの効果から1つを選んで発動ができ、主に前半の効果を使用することになるカードです。 毎ターンノーコストフリチェで相手の場のモンスター1体の効果を無効にすることができ、対象にするのは自分の場のXモンスターの方で相手モンスターが持つ対象耐性は貫通するのが強み。 ただし選べるのは対象の自分のXモンスターより攻撃力以下の攻撃力を持つモンスターに限られるため、オーバーハンドレッドを自身のX素材に敷き込みやすい《N・As・H Knight》などはその攻撃力の低さから効果対象としてはあまり適していない。 展開ができていれば繰り返し使える1妨害になる有用なカードですが、これを持ってこられるのが評価時点では《七皇昇格》と《七皇覚醒》しかなのが惜しいところで、発動条件となるオーバーハンドレッドやそれらをX素材として持てるXモンスターが自身の効果で「セブンス」魔法罠カードをサーチできるようになればもっと良さ気な感じがするカードですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP008 | サイレント・アングラー |
|
自分の場に水属性モンスターが存在する時に手札から自己SSできて、それ以外に効果がなく戦闘能力も低いという非常にわかりやすい特殊召喚のための素材要員。 レベル4、水属性、魚族として素材に使っていくことになり、特に水属性縛りのあるランク4Xやリンク2モンスターを出すための補助役に適している。 この方法でSSするとそのターン他のモンスターは手札からSSできなくなるデメリットがありますが、採用するカードやプレイングでカバーできる範囲でしょう。 類似効果を持つモンスターには水族の《サイレンス・シーネットル》が存在しますが、こちらは自己SSする際に効果の発動を伴わない点と、特殊召喚先が縛られない点であちらと比べて多くの場面で優れていると言える。 |
|||
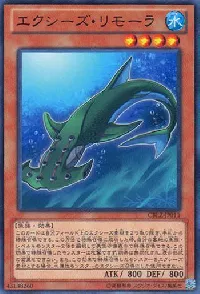 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP009 | エクシーズ・リモーラ |
|
数少ないメインデッキの「エクシーズ」ネームを持つモンスターの1体であり、種族の展開札としての顔も持っている魚族の下級モンスター。 X素材を持っているモンスターが展開されていてかつ自分の墓地にレベル4の特殊召喚可能な魚族が2体以上存在していることが前提の展開効果であり、蘇生したモンスターに課せられる制約も多く、X素材に使う場合も水属性Xモンスターにしか対応していないという結構な使いづらさが目立つ仕様です。 後にランク4の水属性Xモンスターに有用な能力を持つものや魚族に関する効果を持つカードが増えたこと、制約を気にせずに使えるL召喚の導入によってかなり使いやすくはなりましたが、評価時点となる今作られるカードであれば発動条件や効果の適用範囲・制約の数々はもう少し良いものになっていたであろうだけに残念です。 代わりに自己SS能力が発動を伴わないもので、自己SS・蘇生効果ともに名称ターン1が設定されていないという古いカードならではの強みもあるのは救いではありますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP010 | CNo.101 S・H・Dark Knight |
|
101から107までの「オーバーハンドレッドナンバーズ」と呼ばれる「No.」Xモンスターの中でも特に優秀な能力を持つ《No.101 S・H・Ark Knight》の「CNo.」体となるXモンスター。 あちらが持っていた相手の場の特殊召喚されているモンスター1体を自身のX素材とする効果に若干の強化が加えられており、こちらは表示形式を問わなくなったほか、X素材を使うことなく発動できるようになっている。 また自身のX素材を用いて破壊から耐えるあちらに対して、こちらはX素材を持っている状態で破壊され墓地送りになると自己蘇生できる能力があり、あちらをX素材として持つのではなく、あちらが墓地に存在することでこの効果が使えるようになるという非常に珍しい関係性になっています。 自己蘇生の際にはこのカードの元々の攻撃力となる2800LPの回復が行えるだけでなく、類似する蘇生効果を持つ《CNo.103 神葬零嬢ラグナ・インフィニティ》と違ってこちらは自己蘇生後にすぐには攻撃できない代わりにX素材を持たない状態からでも使える前述の能力があり、そちらには名称ターン1が設定されていない上にその効果によって自身にX素材が補充されるため再度自己蘇生を狙うこともできる。 持っている能力が有用でかつ水属性であることから、《N・As・H Knight》及び《CX-N・As・Ch Knight》が指定する101から107までの「No.」Xモンスターとは概ねこのカードを名指ししているものと見て良いでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP011 | バハムート・シャーク |
|
遊戯王OCGにおいて評価時点で2体存在する、両方ともランク4Xモンスターとなる「バハムート」の名前を持つモンスターの、水属性でシャークの方となるカード。 X素材を1つ使うことで自身よりもランクの低い水属性のXモンスターをEXデッキから直に特殊召喚するという、当時としてはかなり画期的だった効果を発揮する。 この効果で特殊召喚したXモンスターは当然X素材を持たず、特殊召喚できるモンスターの種類もかなり限られているため特殊召喚する価値のあるモンスターはそう多くありませんが、X素材を持たなくても使用できる効果があるXモンスターであればこの効果で呼び出す価値も高く、特に万能カウンター能力+自身の効果でEXデッキに戻れるので場に維持したこのカードの2回目の効果でおかわりもできる《餅カエル》とは無類の相性の良さを誇り、水属性のレベル4モンスターを中心としたデッキでなくても【ファーニマル】などの現実的にこのモンスターをX召喚できるデッキなら《餅カエル》を制圧の添え物に加えることも可能としていました。 残念ながらスプライトなどの影響で評価時点における《餅カエル》は禁止カードになってしまいましたが、今後もX素材を持っていなくても場や墓地で効果を使えるランク3以下で水属性のXモンスターが登場するたびにその存在を顧みられるでしょうし、現在でもこのカードやその効果で特殊召喚したXモンスターをX素材とした「重ねてX召喚」という手法で有効利用することができます。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP012 | FA-ブラック・レイ・ランサー |
|
アニメゼアルにおけるシャークこと凌牙と深い関わりを持つ「FA」Xモンスターの1体で、通常の方法でX召喚されることはなく、自身の効果外テキストに書かれた特殊なX召喚方法によってX素材を持たない水属性のランク3Xモンスターに重ねることでX召喚されることになる。 下敷きとしては自身の効果を使うことですぐにX素材が0になる《エクシーズ・アーマー・トルピード》や、《バハムート・シャーク》の効果でEXデッキから特殊召喚したランク3Xモンスターなどが適している。 しかし肝心のこのカードは攻守も持っている能力もカードパワーが低かったりそれぞれの効果があまり噛み合っていなかったりと、お世辞にも場に置いておく価値があるカードとは言い難い。 重ねてX召喚したこのカードにさらに《エクシーズ・アーマー・フォートレス》を重ねてX召喚したり、バハシャが呼び出したランク3Xに重ねてX召喚されているならバハシャとこのカードをX素材にして《FNo.0 未来皇ホープ》をX召喚し、それに《FNo.0 未来龍皇ホープ》を重ねてX召喚するといった具合にあくまで中継ぎで出すカードとして使うことが主となるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP013 | No.71 リバリアン・シャーク |
|
《RUM-バリアンズ・フォース》のイラストにも描かれているバリアンの紋章を模した姿が特徴の「No.」Xモンスターの1体。 アニメにも漫画にも登場していないコレパ出身のOCGオリジナルナンバーズであり、《No.17 リバイス・ドラゴン》とは自身の数字と攻守が反転している点から関連性が窺え、その影響からか評価時点における「シャーク」モンスターで唯一のドラゴン族となるカードです。 その能力は起動効果にて同名モンスター以外の「No.」Xモンスター1体を蘇生し、自身の持っていたX素材を1つ分け与えるという、Xモンスターを特殊召喚する効果を持つXモンスターでかつそのモンスターがX素材を用いた効果も使うことができるというカードになります。 蘇生制限を満たした何らかの「No.」Xモンスターを墓地に先行させる必要があるのは面倒ですが、水属性限定といった指定はないのでこのカードと同じランク3Xモンスターならそれも難しくはなく、X素材を持つ「No.」Xモンスターが2体並ぶので《No.93 希望皇ホープ・カイザー》のX召喚に繫ぐこともできる。 墓地へ送られることで誘発する効果の方は《RUM-七皇の剣》用の効果といったところで、こちらの効果は《バハムート・シャーク》の効果で出した場合でも普通に使えるので、《FA-ブラック・レイ・ランサー》を重ねてX召喚した後に、バハシャとランサーで《FNo.0 未来皇ホープ》をX召喚することで墓地に送ってしまっても良いでしょう。 正直どっちの効果もそんなに強いことは書いていないのですが、蘇生するモンスター及びサーチ対象となる「RUM」魔法カードの種類数ともにとにかく豊富なので、割と個性的な使い方ができるカードだとは思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP014 | RUM-七皇の剣 |
|
ザ・絶対に初手に来てほしくないカードとなる「RUM」カードの中でもかなり特殊な存在。 何しろ通常のドロー以外で手札に引いた時点で発動する手段がなくなり、ドロソとかで引いても腐るというデッキに入れることそのものが常に一定レベルのストレスになるのだから当然初手に来られたらたまらない。 デュエル中に1度しか発動できないため、ピン挿しして引いた時に上振れるカードとして扱うのが基本となりますが、そのために最低2枚、色々選ぼうとすると6枚から8枚のEXデッキの枠を必要とするため、例えこの専用デッキを組む場合でも特殊召喚するモンスターはある程度絞っておきたいところ。 特殊召喚できるモンスターは今となってはどれも古いカードばかりですが、力づくで追加効果を適用できる条件まで満たして出せるだけあってさすがにそれなりに強いXモンスターも存在しています。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP015 | RUM-クイック・カオス |
|
「No.」Xモンスター1体を対象に発動でき、対象のXモンスターよりランクが1つ高い同じ数字を持つ「CNo.」Xモンスターのみを重ねてX召喚できる「RUM」魔法カード。 評価時点では《No.39 希望皇ホープ》を除き各「No.」毎に重ねてX召喚できるモンスターは1体に限られており、もちろん「CNo.」体が存在しないものは効果の対象にできないので対応するモンスターも極めて限られたものになる。 このカードの強みはお互いのターンにフリチェで発動できる速攻魔法であることただ1点のみとなるため、X召喚される「CNo.」Xモンスターの持つ能力も確認しながらそれを活かした運用が肝心となってくる。 EXデッキがかなり圧迫されることになりますが、テーマ内に対応する同じランクのXモンスターが複数存在する【ギミック・パペット】などでは比較的使い甲斐のあるカードです。 |
|||
 Secret Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP016 | 大要塞クジラ |
|
要塞クジラが前回の《城塞クジラ》に続き2度目のリメイクモンスターとして登場。 元々はゲーム用の儀式モンスターの1体として高橋和希氏がデザインしたモンスターの1体だったのですが、原作で使用されたというアドバンテージは絶大だと改めて感じるところでございます。 その性能は大要塞と銘打ってある割には要塞クジラに海の強化値が200ずつ乗っているだけであり、耐性効果などもなく要塞としてより堅牢になったわけでもありませんが、海が場にある時に潜水して海底から攻撃を仕掛けるかのごとく、自分の水属性モンスター全員にダイレクトアタック効果を付与するという非常に攻撃性の高いものとなっています。 メインフェイズに事前に発動しておく必要のある効果ではありますが、相手の超耐性モンスターを全部無視してライフを取りに行くことができ、単独でも2000以上のライフを削り取るのは中々。 また相手バトルフェイズにて相手モンスターをフリチェで迎撃する要塞らしい効果も持っており、これによりバトルフェイズ中に特殊召喚する価値も十分にあるカードとなります。 最後の効果は激流葬などによる自分のカード効果によるものも含め場で破壊された時に、水戦士1体のサーチ・リクルート・サルベージ・蘇生の4つのいずれかを選んで実行できる被破壊誘発効果。 効果範囲となる水戦士には、既に挙げられているこの効果が本来想定しているフィッシャーマン系列やチューナーのパラディオンの他には、バブルマンやアクアドルフィンなどの比較的汎用性の高いモンスターや、氷結界の虎将の面々などが存在しています。 また、《魚群探知機》の追加効果によるリクルートに対応&アトランティスの影響下では《魚群探知機》でサーチしてきたこのカードを追加効果でリクルートした水バニラ1体をリリースしてアドバンス召喚できるという点から、水戦士バニラであるスカルブラッド号なんていう懐かしいモンスターも案外悪くないのではないかと思います。 自己SS効果こそありませんが、《魚群探知機》のおかけでテーマ無所属の最上級モンスターながら持ってくること自体は容易いというのは良いことですね。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
8 | JP017 | 海竜神-リバイアサン |
|
海の強化値200がそのまま元のステータスに乗っかったリバイアサンのリメイクモンスター。 これは同じく今回の梶木枠として登場したデビルクラーケンとジェリーフィッシュのリメイクモンスターも同様です。 海が場にあれば水属性以外の展開を抑止でき、毎自ターンに無条件で発動可能な3種のカードに対応したサーチ効果によってアドバンテージを獲得できます。 特に自身の永続効果を適用するための海を自力で持ってこられるのはかなり偉いと思いますね。 唯一の欠点は上級モンスターながら自己SS効果を持たない点ですが、こちらはアトランティスやステルスⅡといった水属性や海関連のカードのほか、《トランスターン》なども利用して何とか軽めに場に出していきたいところ。 ステータス・効果ともに到底フィニッシャーと呼べる代物ではありませんが、その制圧力とアドバンテージ獲得能力はエースと呼ぶのに申し分ない性能と言えるかと思います。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
7 | JP018 | デス・クラーケン |
|
《海》の強化値200がそのまま乗っかった《デビル・クラーケン》のリメイクモンスターであり強化版となるカード。 なるほど「デビル」の強化版たる名称は「デス」ということですか…。 その効果は場に海と自分の水属性モンスターが必要になりますが、お互いのターンでフリチェで手札の海から出現し、対象の自分のモンスターを救出しつつ、相手モンスターにはゲソサブミッションをぶちかますという奇襲性の高い効果となっています。 場に出た後は相手の攻撃に反応して手札の海に戻っていくことでそれを受け流し、再びシーステルスアタックの構えを作ることができるという、原作の王国編での場面をこれでもかというくらいに再現した効果が非常に好感の持てるモンスターです。 ただし前述の通り手札誘発効果は海が場にないと使えないほか、対象とした自分のモンスターが効果処理時に場にいないとゲソサブミッションできないため、御膳立てが結構大変な上に妨害にも弱いという欠点もあり、場が整えば妨害性能は高い反面、その運用は容易ではないという印象。 一方手札の海に戻る効果の方は単独で発動可能&自身以外を対象とした攻撃宣言にも反応できるということで、フィサリアを戦闘破壊から守ることにも使えるため、総合評価でこの辺りの点数とさせていただきました。 何よりも脇キャラが使用した一介の下級モンスターながら、その活躍ぶりをふんだんに織り込んだカード効果が実に良いセンスだと感じましたので…。 |
|||
 Secret Super ▶︎ デッキ |
9 | JP019 | 電気海月-フィサリア- |
|
《海月-ジェリーフィッシュ-》のリメイクモンスターであり、他の梶木のリメイクモンスター同様に《海》の強化値が元となったモンスターの攻守それぞれに乗っかっている。 1つ目の効果は海を墓地送りにすることによって水属性モンスターを手札から展開する効果で、コストの支払いは手札・デッキ・場で表側になってるやつの3ヶ所から選択可能であり、アドバンテージ面を考えるならやはりデッキからを選択したいところ。 デッキからコストが払える&手札と場からでもいけるので直引きしても大丈夫という点から、海扱いのカードをデッキに入れることを許容できるなら、水属性デッキでは汎用的な展開札として利用することができ、自身のレベルが4ということで《No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン》のX素材を揃えることなどにも適しています。 海を墓地に送るメリットとしてはシーステルスで墓地から海を発動できるというものがあり、そのシーステルスはこの効果でSSするモンスターを《城塞クジラ》にすることでデッキからセットすることが可能です。 2つ目の効果は海に浮かんでいる間、毎ターン相手のモンスター効果か魔法を無力化&吸収して、自身のステータスをアップするというもので、1度でも効果を通せればその攻撃力は下級モンスターとして申し分ない2000に到達します。 原作で《一角獣のホーン》による電撃攻撃を吸収した場面に準拠した効果設定であり、罠には対応しない&効果に直接チェーンしなければならないものの、手札や墓地で発動する効果も捉える上にアップしたステータスはターンをまたいでもそのままなので、妨害にも妨害を踏み抜くことにも使える強力な効果となります。 海デッキの盤面を完成形とするためにマストで添えておきたいモンスターであり、単独でも攻撃を防ぐことはできる《デス・クラーケン》同様に海が無いなら無いで展開要員として為すべき役割がある良いカードだと思います。 |
|||
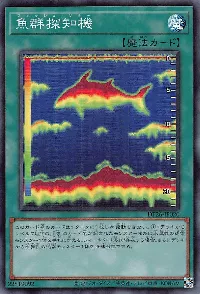 Secret Super ▶︎ デッキ |
10 | JP020 | 魚群探知機 |
|
これまでに登場した全ての海関連の効果を持つモンスター及び原作で梶木の使用したモンスターのほとんどにアクセスできるサーチ魔法。 ただし全ハンかましてくるネオダイダロスだけはレベル7以下という条件でゴメンナサイされている。 また場に海が出ていると追加効果で水属性バニラをレベル制限なくリクルートすることもでき、これにより高い攻撃力を持つ最上級モンスターであるスパイラルやコギガを呼び出してアタッカーとしたり、水バニラチューナーであるウォータースピリットやユスティアなどを呼び出してS召喚やハリファのリンク召喚に繋げることができるほか、リクルートした水属性バニラをサーチしてきたリメイクリバイアサンをアドバンス召喚するためのリリースに充てがうことも可能です。 今の所サーチ先には場を海扱いにできる巫女がいるくらいで、デッキの海を持ってこられる下級モンスターや手札発動の効果を持つモンスターがいないことだけが残念という感じですかねえ、せめて《アトランティスの戦士》でもサーチできれば…。 またパワーを最大限に活かすためには、場に海が存在していてかつデッキにバニラというノイズを入れなければならず、特殊召喚はデッキからのみで手札に対応しないため、リクルートしたい水属性バニラを直引きするリスクも当然あります。 ただサーチ自体は海の存在に関係なく可能なので、有効な初動とするためのワンペアを作るために海デッキでは欠かせない存在です。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
6 | JP021 | 潜海奇襲II |
|
水DPで登場した2種類目の「シー・ステルス」カードとなる永続魔法カードで、《忘却の海底神殿》と同じく場で《海》扱いになるほか、こちらは墓地でも《海》扱いになるので《潜海奇襲》の効果で墓地から発動することもできる。 肝心の効果の方は確かに「シー・ステルス」の名を冠するフレイバーとは非常にマッチしてはいるのですが、何と言いますか評価時点における最新の《海》扱いのカードの割には相変わらずデッキの主軸になるような効果ではないという感じで、いつまで《伝説の都 アトランティス》が最強の《海》をやってるんだかって気持ちは正直あります。 このカードはルール上《海》扱いになるフィールド魔法群と同時に場に出せるカードでかつすぐに発動できる魔法カードということで使い勝手自体は良いと言えるでしょう。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
7 | JP022 | 暗岩の海竜神 |
|
自分の場の海をコストに手札・ デッキから特定範囲のモンスターを1〜5体特殊召喚できる展開系罠カードで、追加効果なしだと2体が上限。 海に関連するモンスターを複数リクルートでき、呼んできたモンスターやタイミングによっては攻めや妨害に使うこともできますが、発動時に海を消費するため無効にされた時のディスアドバンテージは単に数的なものにとどまらない大きさで、通ったとしてもリクルートしたモンスターのパワーの源である海は失われているので、シーステルスとの併用や、リメイクリバイアサンや巫女によって直ちにリカバリーすることが欠かせない。 最大展開を狙うと通常モンスターを複数デッキに入れなければならず、そうなると事故率もかなり上がるため、追加効果は魅力的なリターンではありますが、無理に使えるように構築しなくても良いでしょうかね。 |
|||
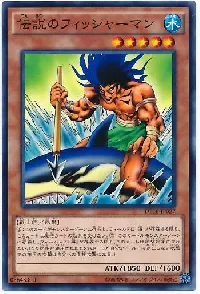 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP023 | 伝説のフィッシャーマン |
|
原作のバトルシティ辺で梶木が使用した、彼にとって海で行方不明となった親父の面影を感じる『魂のカード』となるモンスター。 原作では下級モンスターでしたが、OCGでは当時の下級モンスターとしては《メカ・ハンター》並に高い攻撃力に対して守備力も高めであったのも災いし、レベル5の上級モンスターになってしまった。 種族がDM4と違って戦士族に設定されたので、後に《蛮族の狂宴LV5》を受けられるメリットになったものの、上級モンスターになったことによる取り回しの悪化は痛恨と言わざるを得ません。 しかし同じ2期のレギュラーパックで登場した《伝説の都 アトランティス》の効果を受ければ水属性であるこのモンスターは手札でレベル4になるので下級モンスターのように扱うことができ、《海》扱いであるアトランティスによって自身の魔法に対する完全耐性と攻撃対象に選択されない能力もオンになる仕様で、最初からアトランティスありきの調整がされていたことが窺える。 2期でアトランティスでレベルダウンさせて生け贄なしで出すモンスターと言えば、このモンスターか《カタパルト・タートル》って感じでしたね。 魔法に対する完全耐性は除去魔法を受けない強みであると同時に自身の攻撃力をアトランティスや装備魔法で強化できない弱みでもあり、攻撃対象にならないシーステルス能力も自身しか場にいない時は相手の攻撃が直接攻撃になってしまうため、当時から使用するデュエリストたちを悩ませてきた能力でもあります。 後に召喚条件としてこのモンスターをリリースする必要がある《伝説のフィッシャーマン三世》も登場しており、このモンスターも他の多くの原作出身モンスターに漏れない優遇を受けていますが、場でフィッシャーマン扱いになる《伝説のフィッシャーマン二世》の登場でこのカードの立場は若干怪しいものに。 あとはいくらレアリティが違うからって、このモンスターと同じ種族・属性・レベルでかつこのモンスターよりも低い攻撃力で、このモンスターから攻撃対象にならない能力を引いただけの能力を設定された《深海の戦士》があまりに憐れではないだろうかとは思います。 あれはあれでDM3ではパスワードと通信融合を用いた特殊な方法でのみ入手できる特別なカードなんですけどね…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP024 | 伝説のフィッシャーマン二世 |
|
レジェンドDPの梶木枠で登場した《伝説のフィッシャーマン》のリメイクモンスターの1体であり、先に登場したまるっきり別物となる能力を持つ《伝説のフィッシャーマン三世》とは違い、その効果には《伝説のフィッシャーマン》の面影が残っており、容姿も使用者である梶木によく似たものとなっている。 その能力により自身を場で《伝説のフィッシャーマン》として扱うのでこのカードも《伝説のフィッシャーマン三世》を特殊召喚するためのリリースとすることができ、《伝説のフィッシャーマン》と同じ種族・属性・レベルでこちらの方が攻撃力が高く、《海》が場に存在する時に得られる耐性もモンスター効果への完全耐性というより需要の高いものに変化しているので、基本的にこちらの方が優先度は高いと言えます。 しかしそれを除けばあとは微妙な発動条件のサーチ効果が追加されているくらいで、《伝説のフィッシャーマン三世》を特殊召喚するためのリリースとして《伝説のフィッシャーマン》よりはましなカードという程度でしかないというのも事実ではあります。 なお墓地でも自身のカード名を《伝説のフィッシャーマン》として扱いますが、評価時点ではこれによって受けられる専用の効果は特に存在していないという状況です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP025 | 伝説のフィッシャーマン三世 |
|
アニメ版アークファイブにて、ゲストキャラクターが使用する形で《伝説のフィッシャーマン二世》よりも先に登場してOCG化も果たした特殊召喚モンスター。 《伝説のフィッシャーマン》1体をリリースすることで特殊召喚することができ、SS誘発効果による相手の場のモンスターの全除外、両面破壊耐性+魔法罠カードに対する完全耐性、相手が受けるあらゆるダメージが1度だけ倍になるという、持っている3つの効果が結構ヤバいことばかり書いてあるモンスターです。 特に全除外とダメージ倍化の効果が繋がっているのが強力で、自身はそのターン攻撃ができないものの、他のモンスターを展開することでがら空きになった相手の場に倍化した戦闘ダメージを叩き込めるのは間違いなく強力と言えます。 しかしリリースとなる《伝説のフィッシャーマン》が自己SS手段のない上級モンスターということで場に用意するのが結構面倒で、このカード自身も手札に引き寄せるための専用の有効な手段が特にないというアクセスの悪さから、テキストに書かれている効果の強さほどの活躍をさせることはなかなか難しくなっている。 後に場と墓地で自身のカード名を《伝説のフィッシャーマン》として扱う《伝説のフィッシャーマン二世》が登場したものの、あちらもこのカードが抱える上記のような問題を解決できる効果が全く備わっておらず、少し使いやすいフィッシャーマンという程度の存在にとどまっているのが残念です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP026 | 城塞クジラ |
|
要塞クジラの1度目となるリメイクモンスター。 後に2度目のリメイクモンスターとして登場する攻撃的な《大要塞クジラ》と違い、自身が持ってくるシーステルスアタックの効果と3の効果により、要塞としての堅牢な布陣を敷くことの方に長けた効果となっています。 自己SS効果も持っており、手札からだけでなく墓地にも対応するためデッキから直接墓地送りにするのも有効ですが、その条件はけして軽いとは言えず、何も考えなくてもまず満たせるというほど甘くはありません。 リリースコストをササッと揃える手段を仕込んでおくのは当然として、それを何かに活かせるようにしたギミックは必須と言えるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP027 | 海竜神の怒り |
|
《海竜神-リバイアサン》の効果でサーチすることも可能な「リバイアサン」ネームを持つフリチェのモンスター除去札となる速攻魔法。 さらに破壊したモンスターが存在していたモンスターゾーンをそのターン封鎖するという珍しい追加効果もあるため、相手ターンに相手の場の複数のモンスターを破壊できればその後の相手の再展開も防げる可能性が高く、自分がEXモンスターゾーンにモンスターを出している状態で相手のEXモンスターゾーンのモンスターを破壊すれば、そのターンのLモンスターのEXデッキからの特殊召喚は完全封鎖することができ、妨害札としては中々優秀なカードです。 ただし発動には場に《海》が必要でかつ破壊できる枚数が自分の場の元々のレベルが5以上のモンスターの数に依存する不安定なカードなので事故要因になる可能性も高く、《海竜神-リバイアサン》には他にも色々なサーチ先がある中でこれを優先的にサーチする機会もあまり無さそうなので、最終的にはデッキから抜けていくカードという印象です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP028 | 海竜神の激昂 |
|
《海竜神-リバイアサン》の効果でサーチ可能な「リバイアサン」魔法罠カードの1枚で、原作漫画出身でかつて制限カードの経験もある《激流葬》をサーチする効果を持っている。 墓地効果は自分の場の水属性モンスターが効果破壊される際に墓地からの除外することでその身代わりになれるというもので、これを利用してこのカードでサーチしてきた《激流葬》で自分の水属性モンスターが破壊されるのを防ぐという流れになり、複数の水属性モンスターが効果破壊される場合でもこのカード1枚を除外するだけでそれら全ての身代わりとなることができる。 《激流葬》自体のパワーが結構高いので、《豪雨の結界像》や《神・スライム》を使用するタイプの【結界像ビート】に採用するのもアリなカードだと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP029 | 激流葬 |
|
第2期に登場し、原作のバトルシティ編で梶木が使用した召喚反応型の通常罠。 NSもSSも両方捉える、場のモンスターを全体除去する罠でかつての制限カードです。 同期の勇である奈落もそうだがSSにも対応してたのが全てという感じで様々なデッキで使用され、アド差を一気に埋めるその捲り性能の高さから、モンスターを展開する際には常に意識しなければいけないカードでした。 その後は汎用除去札としての採用率は低下の一途を辿り、環境から姿を消しましたが、それだけに現在ではほとんどの相手はこのカードをデッキに入れてるなんて考えてもいないはずなので、相手に警戒されにくいという意味では当時よりも使いやすくなっています。 そういう事情もあって、一部のデッキでは採用率が復活傾向にあり、特にフェイカーやアルレキーノなんかは場のモンスターを一掃した上で自己SS効果のトリガーを引けるためその相性は抜群です。 場に出した瞬間に自身の効果でフリチェで一時的にいなくなれる夢魔境や天気、場が空になっても1枚から十分に再展開できるデッキの除去札としても選択する価値はあるでしょう。 自分のNSやSSにも反応するので、自爆させて被破壊誘発の墓地効果を出したり、相手に送り付けられたSS封じやリリース・特殊召喚のための素材に使用することを制限するモンスターを排除するなど、能動的に膠着状態を突破することも可能です。 メタビなんかでは守備力2000以上の下級モンスターが攻撃してくる気配もなく守備表示のまま寝てるだけで結構嫌ですし、せっかくすり潰したアドを横耐えで回復されたらたまりませんからね。 ただし時〜できる系の発動条件なので、チェーン2以降のNSやSSには反応できないので注意しましょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP030 | 潜海奇襲 |
|
発動時の効果処理によって手札・墓地の《海》を発動する効果を持った「シー・ステルス」罠カード。 除去されたり《暗岩の海竜神》などで墓地に送られた《海》をお互いのターンにフリチェで再利用することができ、それによりこのカードの持つ選べる2つの効果にもスイッチが入る。 効果の方は元々のレベルが5以上の水属性モンスターが相手モンスターとの戦闘にかなり強くなるもので発動にターン1がないため継戦能力も高く、《潜海奇襲II》の蘇生効果とも相性が良い水属性モンスターの一時的な除外に連なる効果よってこのカードも《海》も相手の効果では破壊されなくなるので場持ちも良い。 効果の内容としてはデッキに触れないし相手の盤面や墓地に干渉できるものでもなく、現代のカードに求められるものとはあまり一致していないという感じで、フリチェで使える強味もそれほど活かせないものの、モンスター同士の戦闘を行うなら放置できるカードではないため、そういうカードが自前で耐性を獲得できるというのは悪くないと思います。 |
|||
 Secret Super ▶︎ デッキ |
10 | JP031 | 海晶乙女スプリンガール |
|
2021年に水DPで登場した新たな「マリンセス」下級モンスターで、【マリンセス】においては《海晶乙女ブルータン》や《海晶乙女シーホース》と共に優秀な初動役として3枚積まれるモンスター。 2024年に光DPで登場した「マリンセス」カードとしても扱う《トリックスター・アクアエンジェル》も含め、自己SS能力を持つメインデッキの「マリンセス」はそのほぼ全てが自分の場に特定のモンスターが存在することを要求する内容のものになっている中で、このカードのみ自分の場から空の状態からでも自己SSすることができる。 自身のレベルが4という【マリンセス】においてのX素材適性が高いという点も《海晶乙女シーホース》にはない利点であり、墓地効果は《海晶乙女ブルータン》と同様に《海晶乙女シーエンジェル》のサーチ効果に直接チェーンさせない《灰流うらら》避けとして機能してくれます。 このカードも1の自己SS条件の内容から一見1枚初動札には到底見えないのですが、これだから単独で1から2やそれ以上を生み出すリンク1モンスターというやつは恐ろしいと感じますね。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
9 | JP032 | 海晶乙女スリーピーメイデン |
|
水DPで登場した優れた自己SS能力を持つ「マリンセス」の上級モンスター。 上級モンスターなので当然単独でNSからの初動札にはならないし、出せたところで「マリンセス」リンク1モンスターのL素材には使えない。 しかし真に重要な要素が一見何のアドバンテージも生み出さない墓地効果にあり、このカードを《海晶乙女ブルータン》の召喚誘発効果で墓地に送っておくことで、《海晶乙女の闘海》を調達する余裕がなかったりそれに失敗した場合やブルータンの墓地効果による不確定サーチが空振りに終わった場合でも、確実に「マリンセス」モンスターを装備した妨害効果を出せる《海晶乙女アクア・アルゴノート》+手札に《海晶乙女波動》という2妨害を用意することができる。 初動にならないカードでピン挿しが安定するため、ブルータンでデッキから墓地に送ったのに、めくったところからも同名カードが出てきてしまって一手分の損になるという心配もなく、ブルータンで墓地送りにするマリンセスとして優先度の高いカードです。 |
|||
 Secret Ultra ▶︎ デッキ |
10 | JP033 | 海晶乙女コーラルトライアングル |
|
水DPで【マリンセス】が手に入れた新たなるリンク3モンスターで、個人的には全てのリンク3のLモンスターを見ても最強レベルの性能を持っていると感じるカード。 まず自身の起動効果によってテーマの最強カードとなる《海晶乙女波動》を持ってこられるという時点でこのカードを経由してリンク4に繋げていくのが確定的なのですが、衝撃的なのが2の自身を墓地から除外して発動する効果であり、《海晶乙女コーラルアネモネ》+「マリンセス」リンク1モンスターを蘇生し、アネモネの効果によって発動前までは自分の場にモンスターがいなかったところが、墓地のこのカードを除外するだけであっという間にリンク数を4の状態に戻すことができてしまう。 発動条件がこれなので使う前に死んでるんじゃないかとか、そんな状況からではもう返せないのではという疑惑もありますが、《海晶乙女アクア・アルゴノート》と《海晶乙女波動》と自由枠である手札誘発などで敷いた盤面をまるっきり無傷で潜り抜けて倒し切られることがそう頻繁に起こるわけでもなく、3ターン目以降を見据えるならののカードが墓地にスタンバイしている状態というのは非常に心強いと言う他ありません。 欠点としてはテーマ内のカードでは効果を発動する前から展開先を水属性に縛ってくる唯一のカードとなるため、このカードを展開に絡めるとそれ以外の属性のモンスターは必然的にEXデッキには採用自体がしにくくなります。 ですがそれを加味した上で採用・使用する価値のあるカードであり、それほどに「マリンセス」罠カードで唯一の実戦レベルの効果を持つ《海晶乙女波動》に確定でアクセスできるメリットは大きい。 |
|||
 Secret Ultra ▶︎ デッキ |
9 | JP034 | 海晶乙女アクア・アルゴノート |
|
水DPで【マリンセス】が《海晶乙女ワンダーハート》と《海晶乙女グレート・バブル・リーフ》に続く形で獲得した3体目のリンク4モンスターであり、現行の【マリンセス】ではテーマのエースを張るLモンスターです。 相手の場のカード1枚に対するバウンスによる除去効果、相手ターンにおける魔法罠カードの効果を無効する妨害能力というこれまでの【マリンセス】には無かった要素をあわせ持っており、手札に《海晶乙女波動》を同時に構えることで相手のほとんどの行動を最低1回は防ぐことができる。 発動ではなく効果を無効にするので、使用ではなく発動にのみ名称ターン1のある魔法罠カードにも強く、この効果を使うための少し厄介な条件も《海晶乙女の闘海》か《海晶乙女スリーピーメイデン》が用意できていれば容易に発動できる状態になります。 現代テーマのエースモンスターが繰り出す圧力としては正直それほど強いものではありませんが、相手ターンに盤面を任せられるというだけでも【マリンセス】にとっては欠かせないカードでしょう。 ただし闘海やスリーピーメイデンを用意できない場合はさすがに《海晶乙女グレート・バブル・リーフ》の方が強いので、その場合はあちらをL召喚した方が良さそうです。 |
|||
 Secret Super ▶︎ デッキ |
10 | JP035 | 海晶乙女の潜逅 |
|
水DPで【マリンセス】が獲得したテーマの魔法カードとしては《海晶乙女の闘海》に続く2枚目の魔法カードで、《海晶乙女シーエンジェル》のサーチ先となるニューカード。 このカードの登場によってこれまでは1枚初動にならなかった《海晶乙女パスカルス》や《海晶乙女マンダリン》までもが1枚初動として最低限の機能を持つようになり、《海晶乙女の闘海》と揃った時に使えるリクルート効果は【マリンセス】が《海晶乙女ブルータン》の召喚誘発効果以外でデッキの任意のテーマモンスターに触れる唯一の手段となるため有用というほかない。 1枚初動にならない点は《海晶乙女の闘海》と同じで、発動にはしっかり名称ターン1も設定されているので複数枚引くとセルフハンデスになるリスクはありますが、【マリンセス】のデッキパワーを引き上げ、ホームグラウンドである闘海に真なる価値を持たせた素晴らしいカードと言って良いでしょう。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
5 | JP036 | 海晶乙女環流 |
|
水DPで登場した新規カードの1枚で、評価時点でも相変わらず《海晶乙女波動》とそれ以外のカードという扱いの「マリンセス」罠カードの中でおそらく最もまともなカード。 自分の場の水属性Lモンスターとそれと同じリンク値を持つ「マリンセス」Lモンスターの入れ替えをフリチェで行う効果を持っており、L召喚扱いになるのでリンク1のL召喚誘発の効果も使えて蘇生制限も満たされるし、手札から発動できる状況ならその使い方にも幅が広がる。 とはいっても波動とそれ以外という扱いである現実に変わりはなく、その波動ですら構築次第ではピン挿しになることも少なくない中で、全く採用されないのではカードプール上に存在しないも同然であり、その点ではより性能の低い他の「マリンセス」罠カードと何ら変わらない。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
1 | JP037 | 海晶乙女渦輪 |
|
水DPで登場した新規カードの1枚で、評価時点でも相変わらず《海晶乙女波動》とそれ以外のカードという扱いの「マリンセス」罠カードの中でも特に酷い効果を持つカード。 《海晶乙女の闘海》と同じく《海晶乙女クリスタルハート》を名称指定した効果を持ちますが、攻撃反応型で手札から発動できるわけでもない罠カードでそれをEXデッキや墓地から特殊召喚すると言われても、3ターンほどで決着をつけることを目指す【マリンセス】にとっては一応相手の後攻となる2ターン目に発動できるカードではあるものの実際には全く需要のない効果でしかない。 墓地効果も《海晶乙女ワンダーハート》の効果とシナジーするという程度で、大して強くないだけでなくあちらが普通に使われないので戦闘ダメージが相手に入らないことも含めて役立つ場面は少ない。 属性DPと言えど7枚も新規カードがあればその中から罠カードの1枚や2枚くらいは3点以下のクオリティになってしまうことも多いのは前身となるレジェンドDPを見ても何ら珍しいことではなく、無かったことにしていいカードだと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP038 | 海晶乙女シーホース |
|
【マリンセス】において《海晶乙女ブルータン》の次に強い初動札となる下級モンスター。 このモンスターの効果テキストだけを読むとこの自己SS条件で一体どの辺りが初動なのか理解し難いと思いますが、このモンスター1体でL召喚できるテーマのリンク1モンスターである《海晶乙女ブルースラッグ》の効果テキストを確認していただければ全て把握できるはず。 自己SS効果が発動を伴わないのも優秀であり、《海晶乙女ブルータン》の2の効果で捲れたらマジで強いのであちらと同じく【マリンセス】では3枚積まない理由はないでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP039 | 海晶乙女パスカルス |
|
「LINK VRAINS DUELIST SET」において「マリンセス」が新規カードとして受け取ったテーマの下級モンスター。 評価時点におけるテーマの下級モンスターとしての立ち位置はちょうど中間くらいのカードという感じで、元々テーマのどの下級モンスター1体からでもリンク4まで行けてしまう【マリンセス】ですが、《海晶乙女ブルータン》や《海晶乙女シーホース》や《海晶乙女スプリンガール》はそれらの中でも特に初動適性が高く、より優先すべきモンスターとなります。 対してこちらは召喚誘発効果で手札から展開ということでワンペアが必要なカードとなるわけですが、特殊召喚できるモンスターがいるならそのまま盤面のモンスターが1体増えることになるので当然悪い効果ではなく、これに《増殖するG》を投げつけられたとしても、この効果で展開した「マリンセス」がレベル4ならランク4Xの大定番である《No.41 泥睡魔獣バグースカ》や展開先が水属性に縛られていても出せる《深淵に潜む者》や《No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン》などをX召喚して誤魔化すこともできます。 墓地効果のサルベージ効果も墓地に送られたターンに使えない制限こそありますが、ミッドレンジでのデュエルを見据えるなら返しのターンで《海晶乙女の潜逅》や《海晶乙女波動》を回収して次の手に備えられるので十分有用な効果です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP040 | 海晶乙女シーエンジェル |
|
評価時点で「マリンセス」に2体存在するリンク1モンスターの片割れとなるカード。 L召喚誘発効果でテーマの魔法カード1枚をサーチするというリンク1モンスターかくあるべしと言うべき素晴らしい効果を発揮しますが、登場時点では該当するカードは何ともなって感じな性能の《海晶乙女の闘海》1枚のみでした。 またもう1体のリンク1マリンセスである《海晶乙女ブルースラッグ》と違ってリンクマーカーが下を向いていないので、EXモンスターゾーンにL召喚すると《海晶乙女シーホース》を展開できないという欠点もあります。 しかし後に《海晶乙女の潜逅》という新たな高性能のテーマ魔法が登場し、そちらが闘海を必要とする効果も備えているためこのカードの重要度も高くなりました。 正直ブルースラッグと相対的に評価したり、サーチ以外にも効果を持っている《スケアクロー・ライトハート》などと比較してしまうと9点でもいいかと思ってしまいますが、いくらなんでもリンク1でL召喚誘発のサーチ持ちとかいう全テーマが憧れるカードが9点ってことはないよねと思ったので10点にします。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP041 | 海晶乙女コーラルアネモネ |
|
マリンセスから【水属性】全体にもたらされた2000打点の超有能リンク2モンスター。 素材となる水属性モンスターに攻撃力1500以下のモンスターを用いれば、自身の効果によってそのモンスターをそのまま蘇生対象とできる。 この手の効果にありがちなリンク召喚誘発ではなくノーコストの起動効果なので、リンク先さえ空いていれば毎ターン効果を使うことができます。 効果を使うとそのターン水属性以外のモンスター出せなくなるため、現存するほとんどの汎用リンク3や4に繋げられないのは残念だが、出したモンスターの効果が無効になるなどのデメリットはないので、《豪雨の結界像》などを蘇生として圧力をかけることもできます。 水属性デッキを組むなら常に存在を頭に入れておきたいカードだが、墓地に送られた時の効果もかなり強くて、これをまるっきり捨ててしまうのはもったいないので、可能ならサルベージできるマリンセスは何かしら入れたい感じではありますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP042 | 海晶乙女クリスタルハート |
|
「マリンセス」のリンク2モンスターの1体であり、変化前の《Gゴーレム・クリスタルハート》が持っていた有用な展開能力が綺麗さっぱり消え去り、防御に特化した全く別な効果に置き換わってしまっているカード。 自身の持つ完全耐性も戦闘破壊耐性と合わせるとそれなりに強固ではありますが、何しろ持っている能力がこれなので【マリンセス】の基本展開には一切関与しないため優先してL召喚されることは少ない。 ただ《海晶乙女の闘海》が場に出ている時に適用されるこのモンスターをL素材としたLモンスターに永続する完全耐性を与える効果はそれなりに有用であり、これにより単にリンク4の「マリンセス」Lモンスターが効果で除去サれなくなるだけでなく《海晶乙女コーラルアネモネ》や《海晶乙女コーラルトライアングル》に対する手札誘発もカードの種別に関係なく弾くことができるのは悪くないと言えます。 このカードの効果テキストだけ読むと無限にイマイチなカードですが、闘海の存在を前提とするならEXデッキに1枚は入れておく価値はあります。 あとこれは個人的な話になりますが、テーマの景観を乱す見た目がかなりイマイチだと感じるカードで、モンスターデザインとしても《Gゴーレム・クリスタルハート》の方が遥かに魅力があったと思っていますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP043 | 海晶乙女ワンダーハート |
|
評価時点で3体のリンク4モンスターが存在する「マリンセス」Lモンスターの中で最初に登場したカード。 「マリンセス」Lモンスターを装備カード化ふる効果を持つ《海晶乙女の闘海》と併用して使い、相手モンスターとの戦闘を介して展開を行うかつてのテーマエースだった存在です。 現在では競合となるテーマのリンク4モンスターである《海晶乙女アクア・アルゴノート》と《海晶乙女グレート・バブル・リーフ》に比べるとあまりに特有の強みになる部分が少なく、状況に応じて出し分けるにしてもさすがにテーマのリンク4は3体も要らないということで主流となる【マリンセス】の構築にはまず採用されないカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP044 | 海晶乙女の闘海 |
|
「マリンセス」のホームグラウンドとなるフィールド魔法で、《海晶乙女の潜逅》が登場するまでは《海晶乙女シーエンジェル》の効果の唯一のサーチ先であったカード。 その効果は何というか、見た目通り初動にならないけどテーマにとって見た目よりずっと重要なカードで、でもやっぱり2枚以上積みたくはないというそんな感じの性能。 打点補助、効果に対する完全耐性、リソースの確保、《海晶乙女アクア・アルゴノート》の妨害能力のスイッチをオンにするといった様々な役割を持ちつつも、このカード自体が1枚初動にならないというのは1枚初動が分厚い【マリンセス】にとってはかなり鈍重なカードにも感じてしまいます。 《海晶乙女の潜逅》のおかげでそれもかなり改善はされてはいますが、依然として2枚以上引いてきたら無限に萎えるカードであることには変わりなく、テーマ内にサーチ・サルベージ手段があることも踏まえると、除外されるリスクを取ってでもピン挿しに抑えて自由枠を作る方が無難でしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP045 | 海晶乙女波動 |
|
【マリンセス】における最強の妨害札となるテーマネームを持つ罠カードであり、テーマ内には他にも割と色々な罠カードが存在していますが、評価時点においては真面目な構築で使われるのはこのカードのみとなります。 自分の場にリンク3以上の「マリンセス」Lモンスターが存在していれば《無限泡影》よりも遥かに自由に手札から《無限泡影》が使えるとくればどう考えても弱いわけがなく、発動に名称ターン1がなくてテーマ内にこのカードをサルベージする手段も複数存在するという、間違いなくテーマの強みと呼べるカードです。 この時リンク2以上の「マリンセス」Lモンスターが場に出ていると副産物となる効果が適用され、自分の場の全てのモンスターがこのターン相手の効果に対する完全耐性を獲得するという、おまけにしてはちょっとおかしな堅さの防御効果となっています。 この耐性の恩恵は「マリンセス」だとか「水属性」だとか関係なく自分の場の全てのモンスターが受けられるので、汎用EXモンスターと併用した盤面でも有用な効果です。 なおリンク3以上でなければ手札からは発動できない、リンク2以上でなければ耐性効果は適用されないというだけであって、普通に場にセットして無効効果を使うだけならリンク1の《海晶乙女ブルースラッグ》と《海晶乙女シーエンジェル》にも使いこなせるカードです。 |
|||
※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】
- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)
- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜
- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…
- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…
- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…
- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…
- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…
- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…
- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…
- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ
- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…
- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…
- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻


 TERMINAL WORLD 3
TERMINAL WORLD 3
 BURST PROTOCOL
BURST PROTOCOL
 THE CHRONICLES DECK-白の物語-
THE CHRONICLES DECK-白の物語-
 WORLD PREMIERE PACK 2025
WORLD PREMIERE PACK 2025
 LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
 ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
 LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
 デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
 DOOM OF DIMENSIONS
DOOM OF DIMENSIONS
 TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
 TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
 TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
 DUELIST ADVANCE
DUELIST ADVANCE




 遊戯王カードリスト
遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索
遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ
遊戯王デッキレシピ 闇 属性
闇 属性 光 属性
光 属性 地 属性
地 属性 水 属性
水 属性 炎 属性
炎 属性 風 属性
風 属性 神 属性
神 属性