交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
![CONTINUOUS]() 永続魔法
永続魔法
![EQUIP]() 装備魔法
装備魔法
![QUICK-PLAY]() 速攻魔法
速攻魔法
![FIELD]() フィールド魔法
フィールド魔法
![RITUAL]() 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
![CONTINUOUS]() 永続罠
永続罠
![counter]() カウンター罠
カウンター罠
 永続魔法
永続魔法
 装備魔法
装備魔法
 速攻魔法
速攻魔法
 フィールド魔法
フィールド魔法
 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
 永続罠
永続罠
 カウンター罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
 レベル1最強モンスター
レベル1最強モンスター
 レベル2最強モンスター
レベル2最強モンスター
 レベル3最強モンスター
レベル3最強モンスター
 レベル4最強モンスター
レベル4最強モンスター
 レベル5最強モンスター
レベル5最強モンスター
 レベル6最強モンスター
レベル6最強モンスター
 レベル7最強モンスター
レベル7最強モンスター
 レベル8最強モンスター
レベル8最強モンスター
 レベル9最強モンスター
レベル9最強モンスター
 レベル10最強モンスター
レベル10最強モンスター
 レベル11最強モンスター
レベル11最強モンスター
 レベル12最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧 > コレクターズパック-運命の決闘者編- コンプリートカード評価(みめっとさん)
コレクターズパック-運命の決闘者編- コンプリートカード評価
|
|
「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |
| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |
|---|---|---|---|
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP001 | 合神竜ティマイオス |
|
《レジェンド・オブ・ハート》で特殊召喚した3種類の「伝説の騎士」モンスターを全て墓地に送ることでEXデッキから特殊召喚できる、種族も見た目も全く竜じゃない合体竜。 他の効果に対する完全耐性を持ち、戦闘を行うダメージ計算時にお互いの場の最も攻撃力が高いモンスター1体と同じ攻守に変化することから、少なくとも戦闘で一方的に倒される場面はそう多くないでしょう。 完全耐性のおかげでダメージ計算時に発動する効果が無効にされることもなく、万が一同じ攻撃力を持つモンスターやダメージ計算時に似たような処理を行うモンスターに戦闘破壊されたとしても、2800打点の「伝説の騎士」モンスター3体が召喚条件を無視して特殊召喚されることでリカバリーされ、EXデッキに2枚目以降のこのカードがあればそれらを墓地に送って再度このカードの特殊召喚も狙える。 逆にこちらから自爆特攻を仕掛けて相手モンスター1体を減らしつつ3体に分裂し、総打点8100で畳み掛けられるカードと捉えることもできるでしょう。 墓地から特殊召喚する場合は蘇生制限を無視できないので、他の方法で特殊召喚できない特殊召喚モンスターでも正規の手順で特殊召喚して蘇生制限をクリアしておくことには意味があるという一例となります。 ただしこのカードを単独で立たせてしまうと相手が場に出したモンスターのいずれかと確実に相打ちを取られてしまうことになり、戦闘破壊された時に発動する効果の方には完全耐性は作用しないので、特に相手がNSした戦闘破壊耐性を持つモンスターに一方的に戦闘破壊された上に、被戦闘破壊効果にダメステでも使える相手の《屋敷わらし》が直撃したら目も当てられないので注意したい。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
5 | JP002 | 伝説の騎士 クリティウス |
|
「伝説の騎士」特殊召喚モンスターの3体のうちの1体となるカードで、特に《クリティウスの牙》に対応しているというわけではないが、作中でその使用者であった海馬をモデルにしたカード。 これら3体は5つの基本ステータスが全て一致するほか、共通の召喚条件・2800打点・《オレイカルコスの結界》を打ち砕くシーンの再現のために設定されたSS誘発の除去効果を持っており、さらに共通の条件で発動できる固有効果もあり、このカードの場合は自分の墓地の罠カード1枚のセットとなっている。 この効果でセットしたカードはセットしたターンでも発動可能となるため、フリチェの罠カードなら攻撃してきたモンスターを除去できる可能性も高く、この効果でセットした罠カードが発動後に除外されることもなく効果に名称ターン1もないので、セットするフリチェの除去罠の発動に名称ターン1がなければ後続のモンスターの攻撃も同じように止めることができる。 とはいえ発動条件が自身が攻撃対象になるということでセットされるであろう墓地の罠カードが相手に見えてしまっていることもあり、実際にはほぼあってない効果で《合神竜ティマイオス》を特殊召喚するためのカードという役割は他の2体と変わりないでしょう。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
6 | JP003 | デス・ウイルス・ドラゴン |
|
《クリティウスの牙》で特殊召喚できるドラゴン族融合モンスター群の1体となるカードで、対応する罠カードは《死のデッキ破壊ウイルス》。 対応する罠カードがエラッタによってかなり弱化してしまっており、発動自体も単独ではできずリリースとなるモンスターも何でもいいというわけにはいかないので、《聖なるバリア -ミラーフォース-》や《破壊輪》を指定する関連カードよりは使い辛いカードになってしまう。 出てくるモンスターもそのレベルが示すとおり下級アタッカー程度のものでしかなく、難解な召喚条件にまるで見合っていませんが、発揮する効果がSS誘発のエラッタ前の3ターン殺し付き《死のデッキ破壊ウイルス》と同等のものと来ており、当然裏目もある効果ではありますが、しかるべき相手に先攻1ターン目に炸裂させればそれだけでゲームを終わりにできる可能性があるというのはやはり魅力があります。 他に能力はありませんが発動時に自身をリリースしたりすることはなく、出すために召喚権を使うことも凡そないと思われるので、効果発動後はためらいなくリリースや特殊召喚のための素材として利用してしまって良いでしょう。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
5 | JP004 | タイラント・バースト・ドラゴン |
|
《クリティウスの牙》で特殊召喚できるドラゴン族融合モンスター群の1体となるカードで、対応する罠カードは《タイラント・ウィング》。 評価時点までに登場している4体の関連モンスターの中では、唯一《クリティウスの牙》より先にOCG化しておらず、原作漫画にも登場していなかった罠カードを要求している。 《タイラント・ウィング》はドラゴン族モンスターの装備カードとなってその攻守を若干上げながらモンスターに対する2回攻撃を可能とする種族限定の戦闘補助系の罠カードで、正直他の罠カードに比べるとあまり使いやすいものではなく、発動後に墓地に送られない性質から1枚で罠カードとしてもこの効果で墓地に送るカードとしても使えることくらいしか良いところがありません。 その分出てくるモンスターの攻撃力は4体の中で最も高く、無条件に使える全体攻撃効果に加えて、自身の能力によって別な自分のモンスターの装備カードという名の翼となることで、そのモンスターの攻守を《タイラント・ウィング》と同じだけ上げつつ無条件の3回攻撃を可能とする能力を付与できます。 どちらの効果を使っても相手の場のモンスターの殲滅や相手のLPを大きく取ることに使えるためフィニッシャー性能はそれなりに高いですが、何しろ対応する罠カードの性能があれなので、状況に応じて出すモンスターをある程度選べる「召喚獣」とか「シャドール」とはさすがに勝手が違うため、専用構築でなければ優先されにくいでしょう。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
6 | JP005 | ミラーフォース・ドラゴン |
|
《クリティウスの牙》で特殊召喚できるドラゴン族融合モンスター群の1体となるカードで、対応する罠カードは《聖なるバリア -ミラーフォース-》。 ミラフォ自体がほぼ全てのビートダウンデッキに対して思いがけない場面で大きなアドバンテージをかっさらう場面もある単独で発動可能な使いやすいカードであることに加えて、出てくるこのモンスターの攻撃力も高いので関連カードの中ではかなり使いやすい部類となる。 効果は見えてるミラフォの発動条件に自分の場のモンスターが相手の効果の対象になることが追加され、さらに全体除去が相手の場の攻撃表示モンスターから相手の場のカード全てに拡張したものとなる。 見ての通りほとんど牽制しかならない効果ですが、他のシステムモンスターなどと並べた時の圧力はそれなりに高く、その場で有効に処理できる手段がなければ存外に手こずりそうなカードという印象を受けます。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
6 | JP006 | クリティウスの牙 |
|
原作漫画にはなかったアニメオリジナルシリーズとなる「ドーマ編」において物語の核となったカードの1枚。 作中では罠カードとこのカード自身が融合することで新たな融合モンスターを生み出すというカードで、OCGでは指定のカード名を持つ罠カードを自分の手札か場から墓地に送ることで、融合召喚扱いではない方法で対応モンスターをEXデッキから特殊召喚するというものになりました。 しかし評価時点では対応する融合モンスター及び罠カードは僅か4種類しか存在しておらず、指定のの罠カードはデッキから墓地に送ったり、墓地から除外することで発動できるわけでもない。 対応している罠カードには《破壊輪》や《聖なるバリア -ミラーフォース-》といった無理なく採用できる除去罠が含まれてはいるものの、通常なら今時あまりデッキに入れるようなカードではないし、何よりも特殊召喚される融合モンスターが揃いも揃って本当にぼちぼちという感じの性能なので、このカード自体のサーチが利かないのもあって使い勝手も使い甲斐もかなり微妙になってしまう。 対応する融合モンスターと罠カードが増えれば増えるほど楽しくなるカードであることだけは間違いないので、いっそのこと10組20枚くらいの新規カードを一斉放出して欲しいと感じますね。 |
|||
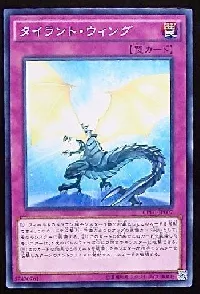 Normal ▶︎ デッキ |
4 | JP007 | タイラント・ウィング |
|
ドラゴン族モンスター1体の装備カードとなり、その攻守を400上げながら《タイラント・ドラゴン》のようにモンスターに対する2回攻撃を可能にするという、《植物連鎖》とかと一緒に6期辺りに登場していそうな平凡な戦闘補助系の罠カード。 しかも装備モンスターが自壊する余計なデメリットまでついており、このカード単体の性能としては使えないことはないけどパワーが低すぎて使わないカードといったところになる。 《クリティウスの牙》によって《タイラント・バースト・ドラゴン》を特殊召喚するために必要なカードであり、通常魔法であるあちらの効果で墓地に送る=基本的に罠カードの方の効果は使えないという仕様の中で、装備カードとして場に残るこのカードは罠カードとしても使用可能という点でシナジーするようになっている。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
5 | JP008 | 伝説の騎士 ヘルモス |
|
「伝説の騎士」特殊召喚モンスターの3体のうちの1体となるカードで、特に《ヘルモスの爪》に対応しているというわけではないが、作中でその使用者であった城之内をモデルにしたカード。 これら3体は5つの基本ステータスが全て一致するほか、共通の召喚条件・2800打点・《オレイカルコスの結界》を打ち砕くシーンの再現のために設定されたSS誘発の除去効果を持っており、さらに共通の条件で発動できる固有効果もあり、このカードの場合は自分の墓地の効果モンスター1体のカード名とモンスター効果のコピーとなっている。 対象とするモンスターによってはかなり強力なカードになることは《ファントム・オブ・カオス》が既に実証していますが、発動条件が自身が攻撃対象になることなので使える機会は少ないものと思われ、他の2体と違ってそのままでは数的アドバンテージにならない効果なので目ぼしいモンスターが墓地にいなければ構わず攻撃される可能性も高い。 いずれにせよ《合神竜ティマイオス》を特殊召喚するために欠かせないカードの1枚であることに間違いはないため、その点での役割は他の2体と変わらない。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP009 | タイムマジック・ハンマー |
|
《ヘルモスの爪》で特殊召喚できる融合モンスター群の1体となるカードで、対応種族は魔法使い族で元となったモンスターは《時の魔術師》。 これらのモンスターはSS誘発効果で強制的に自身以外の場のモンスター1体の装備カードになる能力と装備モンスターに何らかの効果を与える固有効果をそれぞれ持っており、それ以外に能力はない。 このモンスターの固有効果は戦闘を行う相手モンスターをダメステ開始時に除外するという《A・O・J カタストル》や《N・グラン・モール》の類似効果となっており、除外する期間がサイコロの出目によって決まる一時的な除外という変わった仕様になっている。 効果自体は耐性貫通力の高い有用なもので、装備モンスターの攻撃力に関係なくターン1も気にせずに使えるという点で優れていますが、カード2枚を消費してさらに自分の場に他のモンスターを要求する効果としてはあまりに微妙と言わざるを得ない。 仮に自ら攻撃を仕掛けた時に1の目が出たらちゃんとした除去にならないという微妙に不安定なところも手間に見合った効果であるとは言い難いです。 対応する種族が《ティマイオスの眼》で融合素材として墓地に送ることができる『ブラック・マジシャン』モンスターと一致していることくらいは評価したいところ。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
4 | JP010 | ロケット・ヘルモス・キャノン |
|
《ヘルモスの爪》で特殊召喚できる融合モンスター群の1体となるカードで、対応種族は戦士族で元となったモンスターは《ロケット戦士》。 これらのモンスターはSS誘発効果で強制的に自身以外の場のモンスター1体の装備カードになる能力と装備モンスターに何らかの効果を与える固有効果をそれぞれ持っており、それ以外に能力はない。 このモンスターの固有効果は装備モンスターに無条件に2回攻撃できる能力と貫通効果を付与するという非常に攻撃的なものになっている。 装備させるモンスターによってはそのままキルを取ることもできる効果となりますが、守備表示モンスターがいなければ貫通効果は死に効果であり、どちらかというと装備モンスターの攻撃力を上げるか、戦闘を行う相手モンスターの攻撃力を1500下げる効果にでもしておいて欲しかった感じは否めない。 このカードを出すためのカードのサーチが利かず、手間がかかるのに装備モンスターを選ぶタイプの効果ですが、《アクセスコード・トーカー》みたいなモンスターに装備させられれば割と強そうではあります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP011 | 女神の聖弓-アルテミス |
|
《ヘルモスの爪》で特殊召喚できる融合モンスター群の1体となるカードで、対応種族は戦士族で元となったモンスターは《クィーンズ・ナイト》。 これらのモンスターはSS誘発効果で強制的に自身以外の場のモンスター1体の装備カードになる能力と装備モンスターに何らかの効果を与える固有効果をそれぞれ持っており、それ以外に能力はない。 このモンスターの固有効果は自身の効果でモンスターの装備カードとなっている時に相手の効果を1度だけ無効にするというもので、この効果を適用したターンは装備モンスターは無条件の2回攻撃が可能となる。 無効効果はそのターン相手が発動した効果をその効果処理時に無効にするというチェーンブロックを作らない強制効果であるため自分の意志でコントロールすることが難しく、しかもお互いのバトルフェイズにしか使えないので無効にできる効果も限られている。 装備モンスターの攻撃宣言時に相手が発動した効果を無効にしながらさらに攻撃回数を増やして攻撃を行うことができるというわかりやすい効果なのですが、実際の運用ではそのように使える場面は稀であり、使い勝手の悪さばかりが目立つカードという印象です。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP012 | 真紅眼の黒竜剣 |
|
《ヘルモスの爪》で特殊召喚できる融合モンスター群の1体となるカードで、対応種族はドラゴン族で元となったモンスターは《真紅眼の黒竜》。 これらのモンスターはSS誘発効果で強制的に自身以外の場のモンスター1体の装備カードになる能力と装備モンスターに何らかの効果を与える固有効果をそれぞれ持っており、それ以外に能力はない。 このモンスターの固有効果は装備モンスターの攻撃力を1000アップし、さらに装備モンスターの攻守をお互いの場と墓地のドラゴン族の数の500倍強化するという装備モンスターのパンプアップに特化したものとなっている。 関連カードの中では評価時点で唯一の装備モンスターの攻撃力をストレートに強化する系のカードであり、攻撃回数を増やしてキルを狙う《ロケット・ヘルモス・キャノン》や《女神の聖弓-アルテミス》と違い、このカードは攻撃力という数値の暴力でキルを狙うカードとなる。 「レッドアイズ」関連の融合モンスターとしてもはぐれ者となるカードで、色々と手間をかけてやっていることは装備モンスターの攻撃力を上げるだけなのでパワーは高くはありませんが、【ドラゴン族】系統のデッキに《ヘルモスの爪》を入れておくだけで思わぬ高打点を叩き出せることもあるでしょう。 正直ヘルモス関連のカードはその共通部分からしてもう負けている微妙カード群なので、ちゃんと墓地効果とかも設定して種族デッキに《ヘルモスの爪》を1枚入れておくだけで割と強いって方向性でやっていけばいいんだと思います。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
4 | JP013 | ヘルモスの爪 |
|
原作漫画にはなかったアニメオリジナルシリーズとなる「ドーマ編」において物語の核となったカードの1枚。 作中ではモンスターカードとこのカード自身が融合することで新たな装備魔法を生み出すというカードで、OCGでは指定の種族であるモンスターを自分の手札か場から墓地に送ることで、融合召喚扱いではない方法で対応モンスターをEXデッキから特殊召喚するというものになりました。 この効果で特殊召喚される融合モンスターは全てSS誘発効果によって出てきた瞬間に強制的に他のモンスターの装備カードとなる能力があり、作中で新たな装備魔法を作り出す効果であったことがこの能力によって再現されている。 しかしこういった仕様のためか、墓地に送るモンスターとこのカード以外に、出てきた融合モンスターを装備するカードとして適性のある別なモンスターを場に出しておく必要がある上に、肝心の出てくる融合モンスターが装備モンスターに与える効果の性能が《クリティウスの牙》の効果で特殊召喚される融合モンスターのそれ以上に微妙なラインナップになってしまっている。 対応する融合モンスターも評価時点では4体のみで、墓地に送ることができる種族も戦士族・魔法使い族・ドラゴン族の3種族のみとあまりに多様性に欠けているし、やっぱりこのカード自体のサーチも利かないので、クリティウスと同様にせめて新規カードで対応する種族くらいはドンドン増やして欲しいところ。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP014 | ルーレット・スパイダー |
|
原作のバトルシティ編で城之内が使用し、絽場のショッカーとバウンダーを同士討ちさせることに成功したギャンブル系魔法カード。 登場からこのカードの評価時点に至るまでOCGにはルーレットやスロットなどの専用ツールが存在しなかったため、効果の決定にはサイコロを代用した無難な落とし所となりました。 効果の方は、まず発動条件が速攻魔法なのに攻撃反応型という時点で嫌な予感がするわけですが、効果が不確定な割にはギャンブルを成功させた時の見返りが少なく、逆にデメリットは非常に重い上にその数も多いというかなり厳しいものとなってしまっています。 サイコロ界の神ツールであるでたら目ともあまり相性が良くないという、ホント「持ってない」カード。 こんな具合なら、せめて効果の決定はサイコロで代用とかじゃなくてちゃんとルーレットでやらせて欲しいなあって感じです。 まあそんなものを作ったところで他で潰しが利かないし仕方ないとは思いますが、DDDを作っていた頃のコナミさんなら或いはなあなんて思ったりもしちゃいますね。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
6 | JP015 | ダブルマジックアームバインド |
|
原作漫画のバトルシティ編で登場した《マジックアーム・シールド》の関連カードとしてアニメに登場した罠カード。 2体のモンスターをリリースして発動し、2体のモンスターのコントロール奪取するというあちらに比べる分かりやすい効果に変更されており、まともに使うと1枚のディスアドバンテージになりますが、罠カードなのでこれをフリチェで使えるのが強みとなる。 コントロール奪取は自分のエンドフェイズまで保つため相手ターンに発動するのもかなり有効であり、できるリリースにはトークンや墓地に送られることで効果が誘発するモンスターを利用して消費を抑えたいところ。 リスクが高く小回りも利かないカードですが、厄介な制約などはなく、相手エンドフェイズに使っても強いという点は大いに評価したいです。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP016 | ロード・オブ・ザ・レッド |
|
自身に「レッドアイズ」ネームがなく、効果テキストにも「レッドアイズ」カード及び《真紅眼の黒竜》に関する効果が書かれていないが「レッドアイズ」関連のカードという特殊な儀式モンスターで、何気に関連モンスターで炎属性のものはお初となる。 具体的にはこのカードを儀式召喚する儀式魔法である《レッドアイズ・トランスマイグレーション》にテーマネームがあり、あちらの効果でリリースの代わりに墓地の「レッドアイズ」モンスターを除外できるという点で関連している。 持っている効果は自身以外のお互いが発動した効果に直接チェーンする形で反応し、対象とした場のモンスターまたは場の魔法罠カードに対してそれぞれターン1で破壊効果を出せるというものになっている。 発動した効果自体を無効にできるわけではないので妨害能力としては微妙ですが、1体で1ターンのうちに最大2枚のカードを破壊でき、能動的にも除去効果を使える点や【レッドアイズ】では貴重な相手ターンに相手の盤面に干渉できるカードという点では悪くありません。 自身のレベルが8なので《真紅眼の黒竜》などのレベル7モンスター1体でリリースを賄えない点と、自体に「レッドアイズ」ネームがないので他のテーマカードに比べてサーチし辛いのが欠点ですが、レベル10で本体の性能も高い《レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン》なら1体で賄うことができ、《儀式の下準備》を使えば対応する儀式魔法である《レッドアイズ・トランスマイグレーション》ごとサーチ・サルベージすることが可能となっています。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP017 | レッドアイズ・トランスマイグレーション |
|
「レッドアイズ」ネームを持つ《ロード・オブ・ザ・レッド》を名称指定で儀式召喚する儀式魔法。 墓地効果や追加効果などはありませんが、特典として手札か場からのリリースを墓地の「レッドアイズ」モンスターを1体以上除外することで賄うことができる効果がある。 しかし《ロード・オブ・ザ・レッド》はレベル8モンスターであり、墓地の「レッドアイズ」モンスター1体の除外で済ますにはほとんどの場面でレベル10の《レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン》が必要となってしまうため、《真紅眼の黒竜》をはじめとするレベル7の「レッドアイズ」モンスター1体で賄えないのがかなり残念。 《レッドアイズ・インサイト》を使えば、デッキからこの効果で除外するモンスターを用意しながらこのカードをサーチでき、モンスターを名称指定している儀式魔法ということで対応する儀式モンスターごと《儀式の下準備》でデッキから引っこ抜けるというのは悪くありません。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
3 | JP018 | 黒竜の聖騎士 |
|
元々は第3期に登場した《白竜の聖騎士》の《真紅眼の黒竜》版としてアニメに登場したモンスターですが、その時のカード名がこのカードがOCG化されるよりも前に6期で登場した《闇竜の黒騎士》と被ってしまったため、現在のカード名に変更されて9期にOCG化されたという経緯を持つ儀式モンスター。 同じレベルと攻守で効果の仕様が《白竜の聖騎士》よりも強化されており、セットモンスター以外の守備表示モンスターも切り裂けるようになったほか、自身をリリースしてリクルートできるモンスターは《真紅眼の黒竜》を含めた全ての「レッドアイズ」モンスターから選ぶことができる。 さらに自身を儀式召喚するための儀式魔法である《黒竜降臨》にこのカードを儀式召喚すること以外の効果まで設定してあるというサービス付きとなっている。 しかし《レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン》をリクルートできることを除けば、普通にNSもできる《伝説の黒石》に勝っている部分がほとんどなく【レッドアイズ】に儀式召喚要素を取り入れてまで使いたい効果ではないところが否めない。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
4 | JP019 | 黒竜降臨 |
|
本来なら有用であるはずのテーマの魔法罠カードをサーチする効果をあろうことか特定のモンスターをまともな方法で儀式召喚するしか効果のない儀式魔法の墓地効果として設定してしまったカード。 出てくる儀式モンスターである《黒竜の聖騎士》が【レッドアイズ】で必須級の性能というならともかくそんなこともなく、テーマの魔法罠カードサーチは《レッドアイズ・インサイト》でも可能であり、インサイトのサーチも《黒鋼竜》の墓地効果によって行うことができてしまう。 しかも墓地に送られたターンにはサーチ効果を使えないという遅さもあって、サーチ効果だけを目的に採用されるということも少なそうです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP020 | レッドアイズ・スピリッツ |
|
「レッドアイズ」モンスター専用の《黒鋼竜》や《レッドアイズ・インサイト》によるサーチも利くフリチェの完全蘇生札となる罠カード。 墓地効果などの追加効果は何もありませんが、モンスターやプレイヤーに課せられるデメリットなども書かれていないスッキリとしたテキストで、《戦線復帰》と違って特殊召喚時の表示形式も自由です。 しかし評価時点におけるこの効果で蘇生可能な「レッドアイズ」モンスターには相手ターンにフリチェで特殊召喚できることに意味がある能力を持つモンスターがまるで見当たらないので、そうなると《戦線復帰》にはない強みも活かしにくくなるし、せめて自分のターンですぐに使える速攻魔法にしてくれれば良かったのにと言わざるを得ない感じです。 こういうカードがある以上、せめて特殊召喚誘発効果で相手の場のカード1枚を破壊するとかそのくらいの効果を持ったモンスターはいないとウソだろうと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP021 | レッドアイズ・バーン |
|
「レッドアイズ」ネームを持つ罠カードの1枚で、レッドアイズでバーンするというよりはレッドアイズが破壊されたという意味でバーンした場合に発動ができ、その爆風が効果ダメージとなってお互いのプレイヤーを襲うという内容になっている。 破壊されたレベルアイズ次第では1枚で2000を超えるダメージになることもざらであり、【レッドアイズ】が得意とするバーン戦術のダメージ源の一部に組み込むことができますが、このカード自体にはレッドアイズモンスターを起爆させる効果はなく、被破壊は別な行動を起こして行わなければならない。 《トラップトラック》とは神のようなシナジーを誇っており、レッドアイズモンスターを破壊しながらこのカードをデッキからセットして、その効果の処理後にすぐに発動することが可能であり、対象となるモンスターに《真紅眼融合》によって融合召喚を行うことで《真紅眼の黒竜》という名の「レッドアイズ」モンスター扱いになる《流星竜メテオ・ブラック・ドラゴン》を選び、かつ事前に《黒炎弾》を放っていれば、あちらのモンスター効果によるダメージも合わせて8000LPを取り切ることができる。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
4 | JP022 | トゥーン・アンティーク・ギアゴーレム |
|
《古代の機械巨人》に「トゥーン」ネームが加わって、特殊召喚できるようになった代わりに召喚酔いするようになったというカード。 しかし《古代の機械巨人-アルティメット・パウンド》と同じく機械巨人扱いになる能力は持たない中で、《古代の機械融合》や《古代の機械素体》に名称指定されているパウンドのように特別に受けられる効果が存在するわけでもなく、5つの基本ステータスとモンスター効果と見た目が機械巨人と同じというだけで、実際は一般的な「古代の機械」モンスターと何ら変わらないということになってしまう。 同じ攻撃力で特殊召喚も可能なテーマモンスターとして《古代の機械暗黒巨人》や《古代の機械熱核竜》といった優れた効果を持つものが他に存在しており、何よりも召喚酔いすることが後攻からキルを取ることを得意とする【古代の機械】との相性が最悪なので、こちらではまず使われることはないでしょう。 「トゥーン」モンスターとして見ると、通常召喚可能なモンスターの中では評価時点でも最高攻撃力であり、《トゥーンのもくじ》に対応することで他の「古代の機械」最上級モンスター以上に手札に持ってくることが容易であることは確かです。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
9 | JP023 | トゥーン・キングダム |
|
元々はアニメGXに登場したペガサスが使用したカードであり、これが現在の仕様でOCG化されたことでせっかく大幅エラッタを行って作り直された《トゥーン・ワールド》をほぼ無用な存在にしてしまった代替カード。 何しろLPを払って発動するただの置物であるあちらに対し、こちらにはトゥーンモンスターに相手の効果に対する対象耐性とデッキトップのカードを身代わりにしたターン1のない両面破壊耐性を与える効果を持ち、それが場で《トゥーン・ワールド》扱いになるカードというのだから仕方がない。 それはそれとしてデッキや墓地でも《トゥーン・ワールド》であることの原種カードのメリットはもっとあっても良いと思いますが…。 このカードの弱点としてはフィールド魔法なので自分の場に1枚しか出しておけないというものがあり、永続魔法であるあちらと併用することでこのカードが除去されても《トゥーン・テラー》などを発動できるというメリットが一応はあります。 ちなみにイラストはこっちよりも旧イラストも新イラストも《トゥーン・ワールド》の方が個人的に好きですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
4 | JP024 | トゥーン・ロールバック |
|
効果対象にした「トゥーンモンスター」がそのターン無条件の2回攻撃ができるようになる魔法カード。 直接攻撃能力を持つトゥーンの面々とは当然相性が良く、相手に戦闘ダメージを与える度に誘発する効果で数的アドバンテージを稼げる《トゥーン・ヂェミナイ・エルフ》や《トゥーン・仮面魔道士》とはシナジーも強い。 「トゥーン」ネームを持つので当然《トゥーンのもくじ》によるサーチにも対応しているのですが、だからといってそれしか効果がないカードに1枚を消費してデッキスペースを割くというのは現実として厳しいものがある。 デッキに居場所を作った時点からコストは発生していると考えるなら、それに見合うリターンを得にくいこのカードはおそらく採用されることは少ないでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP025 | シャドー・トゥーン |
|
自分の場に《トゥーン・ワールド》が存在する時に相手の場のモンスター1体を対象に発動でき、その現在の攻撃力を参照してその攻撃力分のダメージを相手に与える「トゥーン」魔法カード。 効果はそれだけですが《ミスフォーチュン》と違ってダメージが軽減されたり効果発動後のデメリットや制約なども一切なく、変化後の攻撃力を参照するので引導火力としても使いやすい。 弱くはないと思いますが、名称ターン1があることも含めて「ピン挿し安定の必須カード」ではなく、あってもなくてもどっちでも構わないという意味でピン挿し安定カードという感じで、そういうテーマカードってだいたいのデッキで採用されないよなあってところです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP026 | コミックハンド |
|
元々はアニメGXに登場したペガサスが使用したカードで、コントロールを奪ったモンスターをトゥーン化するという効果が2の効果によって忠実に再現されている【トゥーン】における《強奪》や《堕落》と呼ぶべき装備魔法。 「トゥーン」ネームは持ちませんが効果テキストに《トゥーン・ワールド》のカード名が含まれているため《トゥーンのしおり》によるサーチにも対応している。 ただし《精神操作》だけでなく《心変わり》までもが無制限カードになった今、コントロール奪取が一時的なもので構わないのであれば、発動条件や自壊条件もあるこういったカードが重宝されるということは現在では少なく、登場当時よりも強力なカードであるとは言えなくなっている。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP027 | コピーキャット |
|
原作の王国編でペガサスが使用したコピー系の効果を持つ魔法カード。 相手のカードの効果をコピーするというのは漫画の展開としても映えるし、それが魔法や罠ですらも可能となると心躍らずにはいられないですよね。 しかし実際のデュエルで使うとなると、強さが相手の墓地の状況に依存する上に、特定のカードが2枚も自分の場に出ていないと発動すらできないかなり使いづらいものとなってしまいます。 真DM2でもかなりお世話になった好きなカードではあるのですが、事故要因になり得る上に強さが全く安定しない「弱いカード」の要素が見事にドッキングしてしまってるんですよね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP028 | トゥーン・マスク |
|
自分の場に《トゥーン・ワールド》が存在する時に相手の場のモンスター1体を対象に発動でき、そのレベルまたはランク以下のレベルを持つトゥーンモンスター1体を手札・デッキから特殊召喚できる「トゥーン」罠カード。 出したターンに攻撃を行えない多くのトゥーンモンスターにとって相手ターンにその特殊召喚が行えることは悪い話ではなく、リクルートも可能で召喚条件を無視するので特殊召喚モンスターとなるトゥーンモンスターにも対応済みという気の利いた仕様になっている。 展開できるモンスターは相手の場のモンスターに依存しますが、展開できるモンスターが相手の意志に依存する《トゥーン・フリップ》とは一長一短といったところでしょうか。 評価時点における最新のカードと比較してしまうと身も蓋もないのですが、出てくるモンスターの性能を加味しても《白き森のわざわいなり》とか見せられちゃうとなってところですね…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP029 | トゥーンのかばん |
|
トゥーンデッキで使用できるスーパー《奈落の落とし穴》。 対象を取らないデッキバウンスはメインエクストラどちらのモンスターに対しても有効で耐性貫通力も高く、非常に質の高い除去であることはもはや言うまでもないかと思います。 このカードはワールドの方ではなくトゥーンモンスターが場に存在することを発動条件としているが、トゥーンデッキではトゥーンモンスターやワールドが場にないと発動すらできない専用サポートなんてものはざらにあるので今更そこに言及することもないでしょう。 もくじでサーチできることも同様といった感じだが、ワールドを要求しないが故にしおりではサーチできないので注意。 とりあえず召喚反応型の罠としては十分良質という結論です。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
8 | JP030 | 占術姫コインノーマ |
|
メインデッキの占術姫モンスターとしては、ビブリオムーサが登場するまでは唯一のちゃんとしたカードだったと言える占術姫の下級リバース効果モンスター。 そのリバース効果によりデッキからレベル3以上のリバース効果モンスターをセットできるという、特に上級以上のリバース効果モンスターの資産となるカードでもあり、自身もレベル3で同名カードをリクルート対象から弾いていないのも優秀と言えます。 効果発動後はターン終了時まで占術姫以外のモンスター効果を発動できず、これによりリクルートしてきた《禁忌の壺》などを他の効果で起こしてもすぐに効果を使うことはできませんが、ビブリオムーサというこの効果でリクルート可能な優秀な占術姫リバース効果モンスターが後続の新規として登場してくれたのは幸いです。 また自分にとってデメリットとなる占術姫以外のモンスターの強制効果も発動しないという点にも注目したいですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP031 | 占術姫ペタルエルフ |
|
リバース誘発効果で相手の場の攻撃表示モンスターを全て守備表示にする能力を持つ「占術姫」の下級モンスター。 守備表示になったモンスターはプレイヤーの意志によっては攻撃表示にすることができず、基本的には場に存在する限り攻撃に参加することができなくなる。 相手が相手ターンに展開を終えた後にこの効果を使えれば総打点の大幅な低下を見込むことができ、《占術姫ウィジャモリガン》のリバース効果ともシナジーするようになっている。 アドバンテージを稼ぐタイプの効果ではない時点でそもそもキツいところのあった効果ですが、現在ではL召喚の導入によってこれが有効な妨害になることも少なくなってしまっており、普通の効果モンスターがフリチェで無条件に使える誘発即時効果だとしてもそれほど高く評価されるかは怪しいです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP032 | 占術姫ウィジャモリガン |
|
リバース誘発効果でそのターンのエンドフェイズにおける相手の場の守備表示モンスターの全破壊及びその破壊数に比例する相手への効果ダメージを予約する能力を持つ「占術姫」の下級モンスター。 エンドフェイズ時に改めてチェーンブロックが作られることはなく、同じ「占術姫」モンスターである《占術姫ペタルエルフ》のリバース効果とシナジーするようになっている。 基本的に他の効果による補助が欠かせない効果でかつリバース効果なのでかなり使い辛く、L召喚の導入に伴い相手メインフェイズにリバースしてもほとんどの場面でモンスターの除去は見込めないでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP033 | 占術姫アローシルフ |
|
リバース誘発効果で儀式魔法1枚をサーチまたはサルベージできる能力を持つ「占術姫」の下級モンスター。 サルベージにも対応するとはいえ、《マンジュ・ゴッド》なら召喚誘発効果で儀式モンスターにも対応しているところをわざわざリバース効果で行うというかなり悠長な能力です。 評価時点ではこの能力持ちでリバースモンスターでかつ「占術姫」に属していることによるメリットも大したものではないので、他のほとんどの「占術姫」モンスターと同様に【占術姫】においてもそれほど重要なカードとは言えません。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | JP034 | 占術姫クリスタルウンディーネ |
|
リバース誘発効果で儀式モンスター1枚をサーチまたはサルベージできるという「占術姫」においては《占術姫アローシルフ》の対になる能力を持っているのですが、《聖占術姫タロットレイ》がレベル9の儀式モンスターである都合からかレベル5の上級モンスターになってしまったカード。 どのみちアドバンスセットなんてするわけがないのでレベル5であること自体はそこまで大きな問題ではないのですが、何しろ発揮する効果が下級モンスターだったとしても大して強いわけではないし、後にレギュラーパックで登場したレベル9で効果も優秀な《占術姫ビブリオムーサ》によってその存在意義をほぼ消されてしまっている。 やはり初登場時の儀式モンスター以外のメインデッキの「占術姫」モンスターは、ただでさえリバース効果という厄介なのが1つ乗っかっているだけに、下手な汎用効果にするのではなくテーマネームを指定したもっとちゃんとした効果にすべきだったと強く感じますね。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
8 | JP035 | 聖占術姫タロットレイ |
|
占術姫のエース格となる儀式モンスターで、それなりの攻撃力を持ちますが、自身の効果により手札や墓地から特殊召喚したリバース効果モンスターをお互いのターンにフリチェで寝かせたり起こしたりして妨害などを仕掛ける搦め手を得意技としている。 タロットレイス登場以降は特殊召喚するモンスターをタロットレイスにすることで意中のリバース効果モンスターをデッキから連れてくることもできるようになり、2体を並べればお互いのターンにフリチェで起こすと寝かすを同一ターンに行うことさえもできてしまう。 このモンスターもまさか最高の相方となるリバース効果モンスターが、同じ儀式モンスターで自分自身の死霊になるなどとは思いもしなかったことでしょう。 モンスターをセット状態にする効果は相手モンスターも対象にできるため、単独でも相手ターンでの妨害として機能してくれるのは偉いと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP036 | 聖占術の儀式 |
|
《儀式の下準備》でタロットレイごとデッキから引っこ抜けるのが強みの儀式魔法で、それ以外は概ね《冥占術の儀式》の方が性能は上という感じ。 墓地効果でサーチできる占術姫にビブリオムーサという優秀なモンスターが登場したのは大きいですが、冥占術なら場に直接セットすることができますからねえ。 とはいえ墓地効果に設定されている効果がサーチというのは、消費が嵩みやすい儀式魔法のものとしては優秀と言えるかと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP037 | 黒猫の睨み |
|
1の効果を使用したターン、墓地に送られたターンでも使用可能なお互いのターンにフリチェで発動できる墓地効果が本体となる罠カード。 その効果により「占術姫」モンスターのリバース効果の再利用や表側表示モンスターを参照する相手の効果の回避に利用でき、2体のうち1体は「占術姫」以外のモンスター及び相手の場のモンスターも対象にできるので、テーマ外のリバースモンスターの補助や相手の展開の妨害などにも利用できる。 しかし《威嚇する咆哮》の超劣化版という感じの場で発動する効果が弱すぎで、これを何とかして発動しなければ基本的に墓地に送ることができないし、後半の効果を使うだけのために《おろかな副葬》などを採用してまで使うほどでもない効果という感じは否めない。 1の効果がシンプルに場の対象の効果モンスター1体の効果を無効にするようなものだったらなという感じですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP038 | リバース・リユース |
|
評価時点においても数少ない「リバースモンスター」を効果に指定するカードの1枚であり、罠カードともなるとこのカード以外には《サブテラーの継承》くらいしか存在しない。 その効果は自分の墓地のリバースモンスターを2体まで表側守備表示かセット状態で相手に押し付けることができるというもので、主に《メタモルポット》や《カオスポッド》を用いたコンボデッキで使われるカードとなる。 上記のように墓地のリバースモンスターのリバース誘発効果をどちらの場で発動しても構わないから利用したいという場合は、多くの場面で《バースト・リバース》に優先できるカードとなります。 逆にそうでなければ、リバースモンスター以外にも対応していて、特殊召喚されるのが自分の場であるあちらに汎用性では遥かに劣る。 フリチェで相手の場にモンスターを押し付けられるという性質から、相手のLモンスターのリンク先を埋めたり、セット状態という特殊召喚のための素材に利用しにくいモンスターでモンスターゾーンを圧迫するカードして役立つ場面もあるかもしれません。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP039 | アクアアクトレス・テトラ |
|
アニメでは魚族のモンスター群だったのにOCG化の際にサポートカードを含めて全て水族に書き換えられたテーマとして知られ、既にOCG化されているアークファイブ産のアニメテーマの中で10期以降から評価時点に至るまで一切強化が行われていない数少ないテーマの1つで、EXモンスターどころか単独ではテーマエースと呼べるモンスターすら存在しないモンスター群「アクアアクトレス」に属するモンスターの1体。 これらのモンスターはいずれも自身の攻撃力と守備力が同じ数値であり、持っている効果は場で発動する起動効果が1つのみという共通点があり、このカードの役割はテーマのサポート魔法となる「アクアリウム」カードのサーチとなっている。 毎自ターンが来る度に数的アドバンテージを稼ぐことができ、そこに名称ターン1も設定されておらず、サーチ対象となる「アクアリウム」カードも発動に名称ターン1のない永続魔法なので出したい放題となっており、複数体展開したり蘇生して使い回すことで莫大なアドバンテージを獲得できる。 レベル1なので《ワン・フォー・ワン》や《ワンチャン!?》にも対応しており、《リンクリボー》などのL素材として墓地に送ることで蘇生して使い回す準備をすることも容易です。 しかし基本的に召喚権を使う起動効果ということで各種手札誘発には悲しいほどに弱く、名称ターン1がないので他の効果との併用で貫通も可能とはいえ、肝心の「アクアリウム」カードが「アクアアクトレス」モンスターの戦闘補助を行う永続魔法ばかりで全く数的アドバンテージを稼げないパワーが低いものなので自身の効果の強さを活かしきれていないところが否めない。 唯一《水舞台》が「アクアアクトレス」モンスターに相手のモンスター効果に対する完全耐性を持たせて全ての手札誘発モンスターを弾ける効果を持っていますが、それを持ってこられるのがこのカードになるため、結局直に引かなければ誘発ケアにならない。 もちろん「アクアリウム」カード側にモンスターの展開やデッキに触る効果、アドバンテージになる効果を持ったカードが登場すればすぐさま化けるだけのポテンシャルはあります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP040 | アクアアクトレス・グッピー |
|
評価時点で属するモンスターが3体しかいない「アクアアクトレス」モンスターの中で2体の下級モンスターのうちの1体となるレベル2モンスター。 固有効果となる起動効果は手札の「アクアアクトレス」モンスター1体を特殊召喚する効果となっており、これにより自己SS能力を持たないアクアアクトレスの上級モンスターである《アクアアクトレス・アロワナ》の補助ができ、《アクアアクトレス・テトラ》とアロワナは両方ともサーチ効果を持っているため、展開したモンスターで数的アドバンテージを稼ぐことができる。 また発動に名称ターン1がなく同名モンスターも展開可能であることから、2体目のグッピーを展開することで手札の「アクアアクトレス」モンスターを連鎖的に展開したり、ランク2のX召喚に繋げることもできる。 テトラと同様にEXモンスターも含めて「アクアアクトレス」モンスターの種類が充実してくれば、間違いなく今よりも輝けるカードになるでしょう。 |
|||
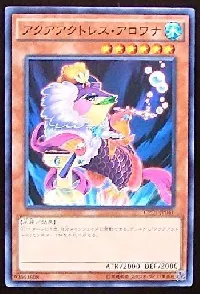 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP041 | アクアアクトレス・アロワナ |
|
評価時点では3種類しか存在しない「アクアアクトレス」の上級モンスター。 固有効果となる起動効果は「アクアアクトレス」モンスター1体のサーチとなっている。 自己SS能力を持たない上級モンスターでありながら攻撃力は2000と低めで、このカードを《アクアアクトレス・グッピー》の効果で手札から展開するためにサーチしたいのに、そのテーマモンスターのサーチ担当をこのカードが担ってしまっているというチグハグさが非常に残念。 ただし《水照明》が場に出ていればモンスターと戦闘を行うダメージ計算の度に無強化の状態からでも4000打点に成長するモンスターとなり、《水舞台》が出ていれば相手モンスター効果に対する完全耐性を獲得し、《水舞台装置》が出ていればさらに打点がプッシュされて《水舞台》との併用だと強化された攻撃力が倍になって5200打点という立派なテーマエースへと成長します。 しかし「アクアアクトレス」に最上級のテーマエースやEXモンスターが登場し、発動時効果で「アクアアクトレス」モンスターをサーチできる「アクアリウム」カードが登場したら、お祓い場になりそうな雰囲気はあります。 |
|||
 Rare ▶︎ デッキ |
7 | JP042 | 水舞台 |
|
《アクアアクトレス・テトラ》の効果でサーチできる「アクアリウム」カードの1つで評価時点ではいずれも永続魔法。 打点を強化する他の「アクアリウム」カードと異なる形で「アクアアクトレス」モンスターを強化する効果を持っており、与える恩恵は「アクアアクトレス」を含む水属性モンスターには水属性以外のモンスターとの戦闘における戦闘破壊耐性、自分の場の「アクアアクトレス」モンスターには相手のモンスター効果に対する完全耐性となっている。 特にこのモンスター効果に対する完全耐性は「アクアアクトレス」モンスターが自身の効果を使う際の相手の手札誘発モンスターのケアとして非常に有効であり、可能ならばテトラでサーチするよりも前に直に引いて場に発動しておきたいカードとなります。 12期に【ギミック・パペット】に登場した《地獄人形の館》はこれに発動時のサーチ効果がついてるようなものなんでそりゃ強いわけですね。 またこれらのカードには共通効果として場から墓地送りになった場合に「アクアアクトレス」も含まれる墓地の水族モンスターを蘇生する名称ターン1のない効果も設定されており、蘇生される「アクアアクトレス」モンスターの持つ起動効果にも名称ターン1がないことから、それらのモンスターを特殊召喚のための素材として墓地に送った後に自らの効果でこれらのカード墓地に送ることで、それらのモンスターを蘇生して効果を連打することも有効ですが、評価時点では「アクアリウム」カードを再利用する手段はテーマ内には存在せず、発動後は特殊召喚できるモンスターが水族に縛られるためEX展開の選択肢は限られることには注意したい。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP043 | 水舞台装置 |
|
《アクアアクトレス・テトラ》の効果でサーチできる「アクアリウム」カードの1つ。 固有効果は水属性モンスターの攻守を300アップ、「アクアアクトレス」モンスターの攻守を300アップするという戦闘補助効果となっており、水属性モンスターでもある「アクアアクトレス」モンスターはトータルで600のアップとなります。 効果が重複する永続魔法ということで評価時点では最も場に複数枚出す価値がある「アクアリウム」カードとなりますが、それでも《一族の結束》などの強化値は下回る数値でしかなく、2枚出してようやく《湿地草原》と同じ打点強化という具合なので、元々の攻撃力が1000に満たない《アクアアクトレス・テトラ》や《アクアアクトレス・グッピー》をこれで強化したところでとても戦闘要員としては役立ちません。 複数枚の発動や《水照明》や《湿地草原》との併用が大前提という感じで、そういう点でもカードとしてのパワーはかなり低めです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP044 | 水照明 |
|
《アクアアクトレス・テトラ》の効果でサーチできる「アクアリウム」カードの1つ。 固有効果は「アクアアクトレス」がモンスターと戦闘を行うダメージ計算時の度に強制的に発動し、そのモンスターの攻守がそのダメージ計算時のみ現在の攻守の倍になるという強力な戦闘補助効果となります。 ターン1もなくモンスターと戦闘を行う度に何度でも発動し、《アクアアクトレス・アロワナ》なら素の状態からでも攻撃力は4000となり、攻撃力が1000以下の《アクアアクトレス・テトラ》や《アクアアクトレス・グッピー》でも、複数の《水舞台装置》や《湿地草原》などと併用すれば攻撃力3000くらいには十分到達することが可能です。 さすがに場に1枚しか存在できない仕様になっているため倍の倍というわけにはいきませんが、効果の仕様の数々を考えれば妥当なところではあるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP045 | 水物語-ウラシマ |
|
「アクアアクトレス」のサポートカードとなる評価時点では唯一の罠カードですが「アクアリウム」カードではないため《アクアアクトレス・テトラ》ではサーチできない。 その効果は墓地に「アクアアクトレス」モンスターが存在する場合に発動が解禁され、対象の場のモンスター1体に「攻守100化」「モンスター効果の無効化」「相手の効果に対する完全耐性」をそのターン限り付与するという攻防一体のものとなっている。 相手モンスターに使えばそのモンスターを無力化することに利用でき、自分のモンスターに使えば相手の効果に対する完全耐性の盾で除去効果などにフリチェで対応することができる。 ただし攻守の100化とモンスター効果の無効化は「アクアアクトレス」モンスターの起動効果と「アクアリウム」カードの効果を用いたパンプアップ戦術とは相性が悪く、《水舞台》の耐性の穴である《無限泡影》の防御に使えないので自分のモンスターを守るためのカードとしての使い勝手は微妙です。 さすがに攻守100からともなると、複数のパンプアップカードに《水照明》の倍プッシュを乗せても戦闘に堪えるパワーを取り戻すのには一苦労となります。 効果自体は結構強いと思いますが、単独で発動できない可能性がある発動条件のついたテーマ無所属の罠カードであることを考えると、このくらいの性能でもせめて墓地からの再セットだとかのもう一声が欲しくなってしまいますね。 |
|||
-
![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 メンタル豆腐デーモン 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 メンタル豆腐デーモン 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 史貴 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 史貴 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 ラギアの使徒 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 ラギアの使徒 」さんのコンプリートカード評価を見る!
-
![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!
「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!
※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。
更新情報 - NEW -
- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。
- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】
- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)
- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜
- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…
- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…
- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…
- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…
- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…
- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…
- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…
- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所
- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ
- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…
- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…
- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻


 TERMINAL WORLD 3
TERMINAL WORLD 3
 BURST PROTOCOL
BURST PROTOCOL
 THE CHRONICLES DECK-白の物語-
THE CHRONICLES DECK-白の物語-
 WORLD PREMIERE PACK 2025
WORLD PREMIERE PACK 2025
 LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
LIMITED PACK GX -オシリスレッド-
 ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-
 LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025
 デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ
 DOOM OF DIMENSIONS
DOOM OF DIMENSIONS
 TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -
 TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター
 TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻
 DUELIST ADVANCE
DUELIST ADVANCE




 遊戯王カードリスト
遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索
遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ
遊戯王デッキレシピ 闇 属性
闇 属性 光 属性
光 属性 地 属性
地 属性 水 属性
水 属性 炎 属性
炎 属性 風 属性
風 属性 神 属性
神 属性