交流(共通)
メインメニュー
クリエイトメニュー
- 遊戯王デッキメーカー
- 遊戯王オリカメーカー
- 遊戯王オリカ掲示板
- 遊戯王オリカカテゴリ一覧
- 遊戯王SS投稿
- 遊戯王SS一覧
- 遊戯王川柳メーカー
- 遊戯王川柳一覧
- 遊戯王ボケメーカー
- 遊戯王ボケ一覧
- 遊戯王イラスト・漫画
その他
遊戯王ランキング
注目カードランクング
カード種類 最強カードランキング
● 通常モンスター
● 効果モンスター
● 融合モンスター
● 儀式モンスター
● シンクロモンスター
● エクシーズモンスター
● スピリットモンスター
● ユニオンモンスター
● デュアルモンスター
● チューナーモンスター
● トゥーンモンスター
● ペンデュラムモンスター
● リンクモンスター
● リバースモンスター
● 通常魔法
![CONTINUOUS]() 永続魔法
永続魔法
![EQUIP]() 装備魔法
装備魔法
![QUICK-PLAY]() 速攻魔法
速攻魔法
![FIELD]() フィールド魔法
フィールド魔法
![RITUAL]() 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
![CONTINUOUS]() 永続罠
永続罠
![counter]() カウンター罠
カウンター罠
 永続魔法
永続魔法
 装備魔法
装備魔法
 速攻魔法
速攻魔法
 フィールド魔法
フィールド魔法
 儀式魔法
● 通常罠
儀式魔法
● 通常罠
 永続罠
永続罠
 カウンター罠
カウンター罠
種族 最強モンスターランキング
● 悪魔族
● アンデット族
● 雷族
● 海竜族
● 岩石族
● 機械族
● 恐竜族
● 獣族
● 幻神獣族
● 昆虫族
● サイキック族
● 魚族
● 植物族
● 獣戦士族
● 戦士族
● 天使族
● 鳥獣族
● ドラゴン族
● 爬虫類族
● 炎族
● 魔法使い族
● 水族
● 創造神族
● 幻竜族
● サイバース族
● 幻想魔族
属性 最強モンスターランキング
レベル別最強モンスターランキング
 レベル1最強モンスター
レベル1最強モンスター
 レベル2最強モンスター
レベル2最強モンスター
 レベル3最強モンスター
レベル3最強モンスター
 レベル4最強モンスター
レベル4最強モンスター
 レベル5最強モンスター
レベル5最強モンスター
 レベル6最強モンスター
レベル6最強モンスター
 レベル7最強モンスター
レベル7最強モンスター
 レベル8最強モンスター
レベル8最強モンスター
 レベル9最強モンスター
レベル9最強モンスター
 レベル10最強モンスター
レベル10最強モンスター
 レベル11最強モンスター
レベル11最強モンスター
 レベル12最強モンスター
レベル12最強モンスター
デッキランキング
HOME > コンプリートカード評価一覧 > ストラクチャーデッキR-機械竜叛乱- コンプリートカード評価(みめっとさん)
ストラクチャーデッキR-機械竜叛乱- コンプリートカード評価
|
|
「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |
| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |
|---|---|---|---|
 Ultra ▶︎ デッキ |
3 | JP000 | 古代の歯車機械 |
|
【古代の機械】にどういうわけか同じ地機械モンスター群だった「ガジェット」の要素を組み合わせコンセプトのストラクチャーデッキ「機械の叛乱」ですが、そのストラクRにおいて登場した両方のテーマネームを持つモンスター。 召喚誘発効果で宣言したカードの種類となる相手の効果の発動を自分モンスターの攻撃時に封じる効果、「ガジェット」に属する宣言したモンスターのカード名と同じカード名になる能力を持っている。 前半の効果は自分のモンスターに「古代の機械」モンスターの持つ共通効果の一部を付与するような能力で、テーマ内においてはその多くが攻撃時に魔法罠カードの発動を封じる能力を持っているため、その穴となるモンスター効果の発動を封じるものとして運用されることになる。 後半の効果は《古代の機械巨竜》や《古代の機械合成獣》の効果を使うためのサポートが主となり、《機械複製術》に対応する攻撃力であることから、そちらとの組み合わせで変化させたカード名のガジェットをリクルートすることもできる。 また《歯車街》の適用下においては、「古代の機械」であり「ガジェット」でもあるこのモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚した《古代の機械熱核竜》は貫通効果と2回攻撃効果を両方とも獲得できる。 しかしこれらの効果はいずれも現在の【古代の機械】においては需要が低く、展開能力がなく単独では何の数的アドバンテージも生み出さないこのカードが使われることはまずありません。 デッキに入れていると熱核竜が稀に2回攻撃ができるようになるカード以上の価値はないと思われますし、その熱核竜が自身の効果が無効になっているとかでもない限りこのカードの1の効果を一切必要としないのも良くないですね。 |
|||
 Ultra ▶︎ デッキ |
7 | JP001 | 古代の機械熱核竜 |
|
ストラクチャーデッキ「機械の叛乱」の看板をつとめた《古代の機械巨竜》が、そのストラクRにてリメイクされ、再度看板を飾ることになった「古代の機械」最上級モンスター。 偶然にも《ダーク・フラット・トップ》が指定する「リアクター」モンスターに属することにもなりましたが、こちらの影響は特に無いと言っていい。 能力としては巨竜と同じ攻撃力で守備力が1000、レベルが1つ上がり、モンスター効果も順当に強化されているといったところで、特殊召喚も同様に可能なので《歯車街》によって特殊召喚するモンスターとして、ランク8Xの素材に使うとかでもない限りは巨竜の仕事をほぼ奪い去る形になった。 しかしモンスター効果を4つも持っているにも関わらず、1の効果は《歯車街》が出ている時に時々使うかもしれない程度の能力、2の効果はそれ自体は強いのですが実際には書かれているだけで使うことのない能力、3以降の効果はそれなりではあるものの、自己SS能力でも相手ターンで使える能力でもないどころか、自分バトルフェイズにおける自身の攻撃時にしか使えない能力というかなり微妙なものとなっており、《究極伝導恐獣》などのストラクRの看板モンスターとしてはかなり控えめな能力だと感じてしまう。 とはいえ、4の効果が3の発動封じ効果とも噛み合っていて、攻撃する度に数的アドバンテージになるものであることは間違いなく、サーチ効果でデッキを回すことや《古代の機械巨人》として融合素材となるのが主な役割である《古代の機械暗黒巨人》よりも単独で戦わせる分には若干強いので、12期の強化を受けた【古代の機械】においてもピン挿しされるなどして一定の需要があるモンスターです。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
2 | JP002 | 古代の機械合成竜 |
|
特定のモンスターをリリースしてアドバンス召喚した場合のみ獲得できる、攻撃後のダメステ中に発動する対象を取らない除外効果と全体攻撃効果、自身を含む全ての「古代の機械」モンスターに攻撃時の相手の効果の発動を封じる効果を与える「古代の機械」最上級モンスター。 ほぼ《古代の歯車機械》と《歯車街》が前提になるような能力で発揮する効果自体はそれなりに強いのですが、戦闘破壊耐性があるわけでもない中で2700という攻撃力がかなりイマイチに感じるカードです。 それならより高い攻撃力を持っていて特殊召喚しても除去効果が使える《古代の機械熱核竜》でいいし、攻撃力が低い分下手したらというか普通に《古代の機械巨竜》よりも弱いモンスターだと思いますね。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
10 | JP003 | 古代の機械飛竜 |
|
属する下級モンスターのほとんどが低性能であり、12期に登場した新規となるモンスターでさえも複数採用することは憚られる「古代の機械」において、登場当時から現在に至るまで唯一どのような構築の【古代の機械】でもまず3積みされるカード。 その能力は両面対応の召喚誘発効果で同名カード以外のテーマネームを持つ全てのカードにアクセスできる能力となっており、そんなカードがアタッカー気質の攻撃力と別なモンスター効果を持っているとなればさすがに使わない手はない。 サーチ後には《古代の採掘機》に由来する変なデメリット制約が課せられてしまいますが、発動前ならセットは自由であり、サーチ先となる「アンティーク・ギア」魔法罠カードに速攻魔法は存在せず、罠カードも評価時点では永続罠の《古代の機械蘇生》と《古代の機械競闘》しか存在しないので、最初から採用しないか《古代の機械司令》の効果で手札から直に場に出すという選択肢もあるので大きな問題にはなりにくい。 《古代の進軍》の登場によって、このカードのNSからスタートしても最終的には《古代の機械射出機》を使用して《古代の機械熱核竜》や《古代の機械暗黒巨人》がリクルートできるようになったりと、さらに役割が大きくなっている。 |
|||
 N-Parallel ▶︎ デッキ |
3 | JP004 | 古代の機械巨竜 |
|
アニメテーマでもある「古代の機械」に何故か作品違いの「ガジェット」をミックスした謎コンセプトのストラク「機械の叛乱」の看板モンスターとして登場したカード。 フィールド魔法を張り替えた時のルールが評価時点となる現在とは異なるものであった頃に、《歯車街》の効果で特殊召喚できる3000打点+αのモンスターとして結構使われていたカードです。 まずルールが変わって《歯車街》の実質的な有用性が下がったところでケチがついたのですが、その後に登場した《古代の機械熱核竜》にその存在意義をほぼ消され、この評価をつけた年に登場した《古代の機械暗黒巨人》に完全に息の根を止められた。 活躍していた当時評価をつけていたなら7点未満はあり得なかったであろうカードですが、全く使う必要がなくなった今評価をつけている以上これは仕方がない。 暗黒巨人は元の《古代の機械巨人》には配慮をしても、別にアニメに登場したわけでもないこのカードにまで配慮する気はさらさらなかったということですね。 ここから復活するというか新たに独自性を得るには、融合素材として名称指定される以外に道はなさそうです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP005 | 古代の機械巨人 |
|
【古代の機械】のエースモンスターとして生み出され、己に課せられた「特殊召喚できない」という天与呪縛と無限に向き合い続けるカード。 通常召喚可能な攻守3000の最上級モンスターで、貫通能力+攻撃時に魔法罠カードの発動を封じるという当時としては破格の性能を誇っていましたが、その代償はあまりに大きかった。 当然アニメテーマのエースがそのまま放置されることはなく、その欠点を補うためのカードがテーマ内からもいくつも出てくることになるのですが、それでも特殊召喚できないという弊害はあまりに大きく、遂には「召喚条件を無視して特殊召喚する」という荒業が使われるようにまでなりました。 それ以外でも融合モンスターの融合素材に名称指定されたり、自身を名称指定した効果を持つカードが登場したりと、機械巨人というカード名であることそのものがメリットになるカードも次々と展開されましたが、《古代の機械巨人-アルティメット・パウンド》でさえも果たせなかった、自身の効果によって機械巨人扱いになる上に特殊召喚も可能で固有効果まで強いというカードが12期にとうとう登場してしまい、その当人である《古代の機械暗黒巨人》によって存在意義がかなり怪しくなってしまいました。 しかし暗黒巨人には手札とデッキで機械巨人扱いになる能力はないため、融合素材の機械巨人としてはこちらの方が優れており、デッキで機械巨人であることに意味がある能力を持つ《古代の機械司令》も暗黒巨人と同時に登場していたりと、テーマ内では召喚条件を無視すること以外にも色々な配慮がなされている。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP006 | 古代の機械合成獣 |
|
同じ「古代の機械」上級モンスターである《古代の機械獣》と違って特殊召喚が可能であり、評価時点において《歯車街》の適用下でリリースなしで出せるようになる上級モンスターの中で最も攻撃力が高い。 これらの性質は自身の特定のモンスターをリリースしてアドバンス召喚した時に効果を得られるという能力と真っ向からかち合うものですが、指定リリースからしてまず何かがおかしいし得られる効果も3つとも書いてないのと同じレベルなので気にする必要はありません。 1つだけ気になることがあるとすれば《古代の機械巨竜》と同じく、攻撃時の魔法罠カードの発動制限くらいはデフォでつけて欲しかったですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP007 | 古代の機械獣 |
|
数少ないメインデッキの「古代の機械」上級モンスターの1体で、《古代の機械巨人》及び《古代の機械巨人-アルティメット・パウンド》以外の「古代の機械」モンスターの中で、同じ「特殊召喚できない」天与呪縛を授かっている唯一のカード。 攻撃する時に魔法罠カードを発動させない定番の能力に加え、戦闘破壊したモンスターの効果を無効にする《冥界の魔王 ハ・デス》と同じレアな能力を持っている。 しかしこの程度の能力と攻撃力で特殊召喚できない上級モンスターというのは厳しいと言わざるを得ず、《歯車街》の適用下ではリリースなしで召喚できることを除けば《古代の機械熱核竜》や《古代の機械暗黒巨人》に優先する理由がない。 下手したらほぼ効果なしモンスターだけど特殊召喚は可能で攻撃力もこのカードよりは高い《古代の機械合成獣》よりも弱いかもしれません。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
2 | JP008 | 古代の機械工兵 |
|
下級モンスター並のステータスであるにも関わらず自己SS能力のない上級モンスターにされており、その割には与えられた能力が大して強くないカード。 《リビングデッドの呼び声》のようなカードにも作用する罠カードの効果に対する無効破壊の対象耐性、「古代の機械」モンスターでは定番の攻撃時の効果の発動制限、攻撃したダメステ終了時に相手のバック1枚を破壊するという3つの能力があり、これにより対象を取るフリチェの除去罠に強く、自身を対象としないものでも攻撃反応型やコンバットトリックを行う魔法罠カードは使わせずに除去することができるという運用ができる。 しかしいくら攻撃した戦闘で自身が破壊される場合でも効果を発動できるとはいえ、この能力で直接攻撃効果も戦闘破壊耐性もないのは厳しいと言わざるを得ず、上級モンスターにしなければならないほど強いカードとはとても思えない。 こんなのでもかつては《カオスエンドマスター》の効果でリクルートできるモンスターの中では上から数えた方が早いレベルのカードとして扱われていた時期もある。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP009 | 古代の機械騎士 |
|
安定の攻撃力1800持ちの「古代の機械」の下級モンスターとなるカードで、それ以上でも以下でもない感じのデュアルモンスター。 古代の機械は主力となるモンスターをEXデッキから出すためにレベル4モンスターがそれほど重要ではなく、特別要求もしてこないテーマです。 となると、デュアルサモンしても古代の機械の共通効果的なものを得るだけの1800打点アタッカーへの評価はこの辺りが精一杯といったところでしょうかねえ。 こんな程度ならデッキに触る系のバニラサポートを受けられる通常モンスターだった方がまだ良かったようなって感じです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | JP010 | 古代の機械兵士 |
|
「古代の機械」モンスターの共通効果的な部分だけを持つ最も基本的なカードでまさしく一般兵という感じの下記モンスター。 それしか能力がないこともさることながら、その攻撃力もとても戦闘要員として使えるものではなく、特に同じレベルで類似する効果を持ち、召喚誘発のサーチ効果まで持っている《古代の機械飛竜》に負けている時点で採用する理由がない。 このカードが《古代の機械戦車》に乗ったのが《古代の機械戦車兵》というモンスターになるのですが、そちらは12期産ということもありちゃんと使えるカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP011 | 古代の機械箱 |
|
8期の終わりに登場したデッキの回転に関わる能力を持つ「古代の機械」の下級モンスター。 サーチまたはサルベージで手札に加わると特定の攻撃力または守備力を持つ地機械1体をサーチする能力を名称ターン1で発揮する。 このカードの登場時には「古代の機械」モンスター内にはろくでもないサーチ先しか存在していませんでしたが、現在では《古代の機械素体》や《古代の機械司令》など対応先にピン挿しなりで採用されるモンスターが存在するため利用する価値はあります。 《古代の機械飛竜》や《古代の機械暗黒巨人》などで両方をサーチできる場合、このカードを経由させることで1枚分の得になり、召喚権がないなどで場に展開できなくても手札融合のための融合素材を稼ぐことには繋がります。 テーマ外にも《無限起動ロックアンカー》のような地機械モンスター群にとっての資産になるような有用なモンスターが存在しており、【古代の機械】においても併用する価値は高いでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
6 | JP012 | ギアギアングラー |
|
地属性の機械族モンスター群の中では影が薄いですが、かつて海外では環境級の強さも誇っていたテーマ「ギアギア」に属するモンスターの1体。 召喚誘発効果で同じ地機械で同名カード以外のレベル4モンスター1体をサーチするという「○○」版の《E・HERO エアーマン》的なシンプルな能力で、自身も同じ地機械である《古代の機械箱》の効果によってサーチが可能であり、【ギアギア】以外での地機械を中心としたデッキでの採用も見込める。 しかし召喚でしか効果が誘発せず、かなり限られたサーチ範囲でサーチ枚数も1枚である割には効果発動後の制約がやけに重く、特に展開先が制限されるのがかなり弱いので、評価時点で登場していたらここまで重い制約ではなかったと思われることを考えると、そんなものを今更採用したくない感じはあります。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP013 | 惑星探査車 |
|
モンスターの体をした《テラ・フォーミング》となるカードであり、あちらと《盆回し》が現在制限カードでかつ、単独でも先攻からすぐに使えるフィールド魔法サーチという点で有用性の高い効果となっている。 しかし場で発動する起動効果であるためヴェーラーや泡影などのフリチェの効果無効や除去効果に簡単に捕まってしまい、多くの場面で召喚権を使用して場に出さなければならず、自身をリリースして発動する効果であるため、うららや墓穴などに無効にされると本当に何も残らず致命的なディスアドバンテージになるという危険性もあります。 その分モンスターの体をしているので場に出す方法はいくらでもあり、NS以外で出しても効果を使えることや名称ターン1がないので発動や効果を無効にされても場に出し直せば再度効果を使えるという利点もあります。 また効果を使うと墓地に機械族モンスターがいる状態になる、自分の場にモンスターがいない状態になりやすい点などから、フィールド魔法を使用してかつ召喚権なしでも展開が可能なセリオンズ、ヌメロン、クシャトリラなどにも採用できるモンスターとなっています。 相応のリスクやデッキとの相性もあると思いますが、個人的には宝玉獣+架け橋(場合によっては副葬)セットよりは直引きや数的なストレスが少なくて好きなカードです。 登場当時と比べると、競合相手となるカードが規制を受けて採用できる枚数が減っている一方で、テーマにおける専用フィールド魔法の重要性が高まったことでその価値が見いだされたというのがイイですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
3 | JP014 | マインフィールド |
|
自分の場に表側表示で存在する状態から場を離れた時にフィールド魔法1枚をサルベージできる能力を発揮するモンスター。 【古代の機械】にはまず間違いなく《歯車街》が採用されることになり、同じ地機械でかつそれを再利用できるカードとして叛乱Rの再録枠にも選出されている。 しかしサーチではなくサルベージという時点で既にそんなに強くないのですが、発動条件が「時の任意効果」で融合素材やL素材にして墓地に送られるとタイミングを逃すため、なおさら弱い効果になってしまっている。 同じ召喚権を使って出して自身を場に維持できない能力なら《惑星探査車》を使った方が良いでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP015 | カードガンナー |
|
アニメGXで十代が何体か使用した「カード〇〇」というカード名を持つモンスターの1体で、アニメで十代が使用したHEROやその関連カードではないモンスターとしては、《ダンディライオン》や《ネクロ・ガードナー》と並ぶ優秀モンスターとして人気を博した下級機械族モンスターです。 元々の攻撃力が500以下の機械族ということで複製に対応しつつも、デッキの上からカードを3枚を墓地に送ることで、自身の効果により攻撃力1900のアタッカーへと変貌します。 デッキからの墓地送りはコストなので、効果が無効になっている場合でも墓地を肥やす仕事は遂行でき、チェーン発動したカードで墓地肥やしを阻止されることもないというのが非常に優れていますね。 さらに場で戦闘・効果・自他問わずに破壊によって倒れると強制的に発動する1ドロー効果には名称ターン1がないため、複製したこのモンスターを激流などで全滅させられても、それら全てがきっちりディスアドをケアしていくという当時のカードとしては考えられない気の利きよう、それでいて当時のカードだからこそ可能な調整になっているという素晴らしい仕様です。 不確定な墓地肥やしということで当然大事な魔法罠を墓地送りにしてしまう場合もありますが、それでも多くのデッキで使われていたことが、そのリスクを補って余りあるほど魅力あるカードであったことを証明していますね。 シンクロ時代に突入すると、レベル3ということで《ジャンク・シンクロン》に肖ることはできませんでしたが、代わりに《デブリ・ドラゴン》で釣り上げられて墓地を肥やしながら《ブラック・ローズ・ドラゴン》になれるモンスターとして重宝されていました。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP016 | ギガンテス |
|
3期に登場したモンスターであり、種族・属性・レベルだけでなく、自身を特殊召喚するための墓地コストの内容まで2期に登場した精霊タイタンと同じという特殊召喚モンスター。 こちらは相手ターンだけ17→20打点になるタイタンと違い元から19打点を備えていることに加え、自爆特攻も含め戦闘で倒されるとダメステにてお互いのバックを全剥がしする強力な除去効果を持っており、これらを召喚権を使わずに行えるその有用性の高さから、登場時はグッドスタッフモンスターズの1体に数えられていた時期もありました。 現在では《ブロックドラゴン》でレベル2アダマシアチューナーと共にサーチしてきて、それらと共に召喚権を使わずに即座に全展開できるモンスターとしてアダマシアデッキで重宝されている。 特殊召喚モンスターなのでアダマシアチューナーの効果では特殊召喚できないため、一見岩石族である意味がほとんどないように見えて、ブロドラが絡むだけでこうも話が変わってくるんだなあという感じです。 |
|||
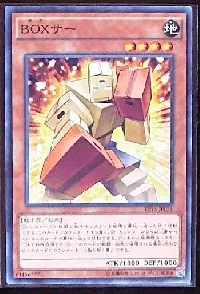 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP017 | BOXサー |
|
ボックスとボクサーをかけた結果生まれたダンボール戦士という、ちょっとした狂気すら感じるデザインが特徴のアタッカー気質の下級地戦士モンスターで、韓国版ワープレ枠だったカードの1枚でもあります。 相手を倒して得たエンブレムが次なる特殊召喚に繋げる力にも自身を守る力にもなる効果が特徴。 発揮する効果自体の汎用性は高く、自身の元々の攻撃力も1800と高めではありますが、この発動条件で自身の攻撃力や攻撃回数を増やす効果を自前で持っていないというのが玉に瑕。 堅実な効果持ちではありますが現環境のテーマ無所属モンスターとしては平凡の域を出ない感じで、少なくとも地属性リクルート効果を真面目に使おうと思ったら他の効果による補助が欠かせない。 見た目があまりにへなちょこなので、それから受ける印象よりは随分と強いなという程度な感じですかね。 破壊耐性がターン1適用ではないことと、自分の効果による破壊にも適用されるのは悪くないと思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
4 | JP018 | ハードアームドラゴン |
|
レベル8以上のモンスターを手札から墓地に送ることで行われる発動を伴わない手札からの自己SS能力と、最上級モンスターのアドバンス召喚のためのリリースに利用することでそのモンスターに消えない効果破壊耐性を付与する能力を持つカード。 戦闘破壊耐性や対象耐性など元々何らかの耐性を持っている、または制圧緑地の高い永続効果を持つ最上級モンスターの弱点を補うことに適しているカードで、かつては《オベリスクの巨神兵》のリリースとして一斉を風靡したことも。 しかし最上級モンスターというのはリリースが2体必要なので、自己SS能力を使って場に出しても依然としてもう1体のリリースかアドバンス召喚するモンスターのどちらかは召喚権を使わずに出す必要があり、コストの内容からしてもそこまで噛み合った能力というわけではない。 また現在では両面耐性がそれほど貴重なものとは言えなくなっているため、効果を通したところで盤石とはとても言えないのも厳しいところ。 逆にリリース1体で召喚できる最上級モンスターに効果破壊耐性を付けるだけでそこそこ強い場面もあったりもするのですが、メインデッキのテーマ無所属カードの役割としてはもう無理かなって感じのするカードです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP019 | マジック・ストライカー |
|
アニメGXで十代が使用したHEROと無関係なモンスターの1体。 使い終えて墓地に送られた魔法カードという、墓地効果でもついていない限り基本的に用済みのカードを除外コストに自己SSできる下級戦士族モンスターです。 緩い条件で自己SSできるということで各種リリースや特殊召喚のための素材として適性が高いのは当然として、このモンスターはダイレクトアタッカーでもあるため、打点を強化してやればフィニッシュも狙えるライフ取り要員となることもでき、モンスターと戦闘を行う場合は戦闘ダメージを受けないので不意の一撃で大幅にライフを削られることもなく、相手の裏側守備表示モンスターに探りを入れるセーフティな一撃を入れたりもできる器用なモンスターという感じでした。 私は自分で戦う気概のある下級モンスターは好きなので、それに自己SSがついていて通常召喚も可能、使い途も様々ともなればこのくらいの点数はといったところです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP020 | 増殖するG |
|
元々《黒光りするG》からはじまった「○○するG」昆虫族モンスター群の1体で、現存する数ある手札誘発モンスターズの中でも《灰流うらら》と並んでその最右翼とされるカード。 リミットレギュレーションによる規制以外でデッキからGとうららの枠が完全に消え去る日は果たしてくるのだろうか。 こちらはお互いのターンに完全なフリチェでいつ何時でも手札から投げ捨てることができるので、チェーン発動による1ドロー保障を捨ててでも、発動しないタイプの自己SS能力や《三戦の才》ケアでドローフェイズやスタンバイフェイズにさっさと投げていったり、相手がドロソで指名者やうららを引き込むのを見越して発動するなどのプレイングが必要な場合もある。 墓地のモンスターを参照する効果を使うために、効果は関係なく先攻で手札から投げ捨ててしまうといった使い方もできるでしょう。 ただし動き出しに複数のカードが必要なデッキに採用すると、後攻時に命は繋げても先攻時には自分が動くことの邪魔をしてくることもあるのが汎用手札誘発の常でもあり、手札誘発とは少ない初動で動ける、サーチが豊富、テーマのカードはメインデッキに最小限でも楽々回るガチデッキで使ってこそ真の強さを発揮するのだとも感じますね。 このモンスターの場合は妖怪少女の面々と違って一応の攻撃力はあるので、お互いに誘発事故が起こればたちまちGビートの開幕となる。 |
|||
 Super ▶︎ デッキ |
9 | JP021 | 古代の機械射出機 |
|
《歯車街》や《古代の機械要塞》をセルフ破壊しながら「古代の機械」モンスターをリクルートできる「アンティーク・ギア」魔法カード。 リクルートは召喚条件を無視するので《古代の機械巨人》なども特殊召喚できますが、現在では《古代の機械暗黒巨人》というより優先度の高いリクルート先が登場しているため、召喚条件を無視できることによる恩恵は以前よりは少なくなっている。 しかし自分の場にモンスターがいると発動できないという厄介な発動条件があるため、かつてはこのカードをサーチできる《古代の機械飛竜》で持ってきてもすぐに使えないことが弱点でしたが、このカードをサーチする効果を持っている上に永続魔法なのでセルフ破壊対象にもなる《古代の進軍》の登場によってさらに有用性が高くなっており、進軍には効果を使うために自分の場のモンスターをコストリリースする別な効果もあるため、飛竜→進軍→このカードの順にサーチすることで飛竜も1枚初動とすることができようになりました。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP022 | 古代の機械要塞 |
|
【古代の機械】においては《歯車街》と双璧をなすセルフ破壊される側のカードで、こちらは魔法&罠ゾーンで破壊されると手札または墓地から「古代の機械」モンスター1体を展開できる「アンティーク・ギア」ネームを持つ永続魔法となっている。 《歯車街》と違って破壊される場所に指定があり、デッキからの展開ができなくなっている中で、召喚条件を無視するわけでもなければ、発動後の制約でテーマ外のモンスターを特殊召喚できなくなったりと、場合の任意効果であるためタイミングを逃さないことと《灰流うらら》に捕まらないことを除くと被破壊時の効果はあちらに劣る形になる。 対してこちらは場に置いておくことで発揮する効果が有用であり、このカードを最初に出しておくことで《古代の機械暗黒巨人》や《古代の機械飛竜》の召喚誘発効果や《古代の進軍》の発動時効果に相手の手札誘発やカウンター罠を当てられなくなるだけでなく、場に出したターン限定の対象耐性と効果破壊耐性によって《古代の機械素体》や《古代の機械猟犬》のような起動効果持ちに当ててくる《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》にも強くなり、後攻から1キルを決める際に相手の妨害のいくつかは踏み潰すことができる。 12期で強化を受けた【古代の機械】においても相変わらず必要なカードとなっており、今後も使われていくことでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
1 | JP023 | 古代の機械城 |
|
特殊召喚できない《古代の機械巨人》や《古代の機械獣》の召喚補助も兼ねる「古代の機械」モンスターのホームグラウンドの1つ。 ただしフィールド魔法ではなく永続魔法なので《歯車街》との共存が可能となっている。 場に置いておくだけでは微弱な戦闘補助にしかならず、一定条件下で置かれるこのカウンターを用いて上級以上の「古代の機械」のリリースの代わりになるのが本分となるのですが、カウンターが置かれる条件があまり良くない割にはこのカードごと処分しないと効果が使えない使い切りのカードであり、テーマ内外に関わらず特殊召喚できないモンスターを補助するカードには他に良いカードがいくらでもあるため使われることはないでしょう。 イラストは結構いいのに出てくるのが早すぎたばかりにこのような効果を設定されてしまって残念な限りです。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
4 | JP024 | 古代の整備場 |
|
前回のストラクである「恐竜の鼓動」に続き、単なるアニメカードのOCG消化の場に使われてしまった「機械の叛乱」に新規収録された「古代の機械」の魔法カードの中で最も有用とされていたカード。 碓かに他のカードが酷すぎるのもあってそれ自体に異論はないのですが、今どきテーマモンスター1体をサルベージするだけの等価交換の魔法カードでは到底性能不足であり、自己SS能力を持つモンスターが《古代の歯車》くらいしか存在せず、手札から捨てて発動する効果を持つモンスターがいるわけでもない【古代の機械】とはそれほど噛み合いは良くない。 《古代の機械箱》と併用するにしても一応トリガーは引けるというだけでサーチ手段がかなり豊富になった現在の【古代の機械】に枠を与えることは厳しいでしょう。 |
|||
 N-Parallel ▶︎ デッキ |
8 | JP025 | 歯車街 |
|
「古代の機械」モンスターにとってのホームグラウンドとなるフィールド魔法ですが、発動時効果でアドバンテージを稼ぐとか場に維持して強いとかではなく、さっさとぶっ壊してナンボという実に特異な存在。 《古代の機械城》のようにテーマモンスターのステータスは上げない代わりに、上級以上の「古代の機械」モンスターを召喚する際のリリースを軽減することができ、これにより特殊召喚できない《古代の機械獣》をリリースなしで、《古代の機械巨人》をリリース1体でアドバンス召喚できるようになるという展開補助をしてくれる。 しかし本体となる効果は被破壊時に指定の3領域から「古代の機械」モンスター1体を特殊召喚できる効果となり、当時はフィールド魔法を張り替えた際のルールの違いもあり、セルフ破壊してデッキから《古代の機械巨竜》を特殊召喚するためのカードとして活躍していました。 現在ではルールの変更によって当時と同様の運用は不可能となりましたが、現在ではテーマ本体にも《古代の機械射出機》や《古代の機械戦車兵》などのこのカードのセルフ破壊を有効に行える効果を持つカードが登場しており、リクルート先にも《古代の機械熱核竜》以上に優先度の高い《古代の機械暗黒巨人》が登場しているため、出張性は弱くなったもののテーマ本体での重要度は当時とは比べ物にならないほど高くなっています。 また「アンティーク・ギア」ネームを持たず、《古代の機械巨人》のカード名が記されたカードでもないこのカードですが、暗黒巨人や《古代の機械弩士》がこのカードを名称指定したサーチ効果を持つのでサーチ体制も十分とかなり恵まれています。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
8 | JP026 | 死皇帝の陵墓 |
|
スピリットなどに代表されるような「特殊召喚できない通常召喚モンスター」にとって、場に出しやすく使い減りしない召喚サポートとして非常に有用性の高いカード。 ライフコストはけして安くはありませんが、下級モンスターを通常召喚するように上級・最上級モンスターを召喚・ セットすることができ、特にそのモンスターが特殊召喚不可でかつアドバンス召喚指定でないNS誘発の効果を持っている、上級以上でありながらリバース時に発動する効果を持っているならこのカードとの相性は最高と言えるでしょう。 注意すべき点は、リリースを0体にするとアドバンス召喚誘発の効果の発動やリリースしたモンスターの能力を参照する効果を適用できなくなること、フィールド魔法でかつ発動を伴う効果なのでチェーンして発動された効果でこのカードが場を離れると召喚行為は不成立となりライフの払い損になること、召喚権が健在でかつリリースを軽減できるモンスターとのペアが揃わないと何もできないカードであり、継続的に効果を使えるような構築にすると事故率が高くなることなどがあげられる。 テラフォ・盆回し・《終焉の地》・ 《メタバース》などに対応するフィールド魔法といえど、1種類のカードにあまりに依存することは危険ということですね。 特化した構築にする場合は、《コストダウン》やスターブラスト、《アンカモフライト》などの類似カードとの比較・併用も考えておきましょう。 |
|||
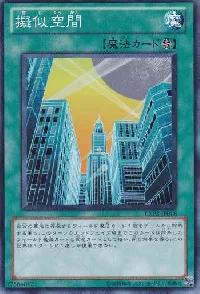 Normal ▶︎ デッキ |
4 | JP027 | 擬似空間 |
|
墓地のフィールド魔法1枚を除外し、そのカード名と効果をエンドフェイズまでコピーできるフィールド魔法。 発動時の効果処理ではないのでチェーン発動した効果によって除去されると効果を出すことはできず、発動時の効果処理となる効果や墓地で発動する効果などはコピーすることができない。 基本的にはターン1で効果を発動できてかつ、リミットレギュレーションによりデッキに1枚しか入れられないフィールド魔法の効果を連発するために使われることになりますが、そうでない場合は2枚目を入れるかそれを持ってこられる《テラ・フォーミング》などを入れた方が良い場合がほとんどで、デッキから除外するわけではないのでこのカードだけ引いてくると事故になってしまう。 《魔法族の里》や《王家の眠る谷-ネクロバレー》をコピーしても相手ターンでは効果を適用できないのであまり意味がなく、このカードを使ってまで、或いはこのカードを使わなければ連打することが難しい効果はそう多くない。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP028 | リミッター解除 |
|
第2期に登場した自分の機械族モンスター全体の「現在の」攻撃力を倍化するという凄い魔法。 しかも速攻魔法なのでダメステに手札からでも使えるという、豪快かつ当時ではおよそ考えられない気の利いた仕様になっている。 いくら発動直後に数的アドにならず効果を受けたモンスターはエンドフェイズには自壊するとはいえ名称ターン1もなく、現在ではとてもこの性能のままでは生まれてこないカードの一つと言えるだろう。 当時の下級機械アタッカーだったメカハン・王室前・バギーでも攻撃力は3200〜3700に、罠封じの効果を持つショッカーは攻撃力4800となるため、これら2体だけでも8000ライフを全て奪うことができるという事実が程なくして制限カードに指定されたこのカードのパワーの高さを物語っています。 自壊デメリットもとってつけたようなものではなく、リミッターを外して運用したために故障してしまうという極めて機械らしいものである。 |
|||
 N-Parallel ▶︎ デッキ |
10 | JP029 | 機械複製術 |
|
原作のバトルシティ編でマリクが使用した低攻撃力の機械族モンスター専用のリクルート魔法。 手札にこのカードがあり、対象となる攻撃力500以下の機械族が場に存在し、さらにその同名カードを引いていてはいけないという条件になりますが、最高のパフォーマンスを発揮できれば特にコストもデメリット制約もなく1体が3体に、しかもデッキから特殊召喚されるという最強カードとなります。 元々の攻撃力ではなく現在の攻撃力を参照するため、攻撃力を変化させれば本来この効果ではリクルートできないモンスターにも対応させることができます。 また《サイバー・ドラゴン・コア》のような場で《サイバー・ドラゴン》扱いになる攻撃力500以下のモンスターを選択した場合でも、攻撃力2100の本物の《サイバー・ドラゴン》を複製することができ、この運用法ならリクルートしたいモンスターを直に引いてこのカードのパワーがダウンするリスクも軽減できる。 今後《赤しゃりの軍貫》のようなデッキでもサイドラ扱いになる効果を持つモンスターが登場すればさらに楽しいことになりそうです。 後進に与えた影響も大きく、このカードの存在のために規制されたと思われる《カードガンナー》、明らかに機械的な見た目なのに何故か機械族にならなかった《エア・サーキュレーター》、逆に明らかに複製させるつもりでデザインしたとしか思えない《SPYRAL-ジーニアス》などが存在している。 なお原作では《万力魔神バイサー・デス》を複製したのですが、OCGではどういうわけか悪魔族に設定するという謎過ぎる判断によりこれが不可能になってしまっている。 正直複製しても仕方ない低性能モンスターではありますがこれはあまりお粗末だと思うので、リメイクの際には是非とも機械族に作り直して欲しいところです。 もっともアニメにおいては悪魔族版と機械族版で2種類もの別なモンスターに差し替えられた《万力魔神バイサー・デス》がリメイク対象になれるかはかなり怪しいですが…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP030 | 地獄の暴走召喚 |
|
アニメGXの初期に「地獄デッキ」を使っていた万丈目が使用し、後にOCGに送り出してしまった4年間に渡る放送を通しても作中屈指の飛び道具となる速攻魔法。 何しろ特殊召喚元が手札やデッキは元より墓地にまで及ぶあまりに広範囲なものであり、基本的に2体のモンスターを、あるモンスターと同名カード扱いになる効果を持つモンスターに対して使用することでそれ以上のモンスターを展開することさえできるこのカードは、サーチできない・トリガーとなるダメステ以外での特殊召喚が必要なので事故る・相手の場にもモンスターが必要なので先攻で使えないから微妙などの一言二言で簡単に片付けてしまいたくはない、強いロマンを感じずにはいられません。 幸いなことに相手の場のモンスターは制限カードや罠モンスターなどの明らかにどこからも特殊召喚することが不可能なモンスターであっても発動が可能となっているため、相手にも特殊召喚される可能性があるとか以前に可能性0のやつしか相手の場にいないので発動条件を満たせずに発動できないなどということがないのはとても有り難い。 結構処理や裁定が厄介なカードなので、せめて使う側はあらゆるケースにおいて起こり得ることを想定しそれを相手に説明できる準備をしておきましょう。 |
|||
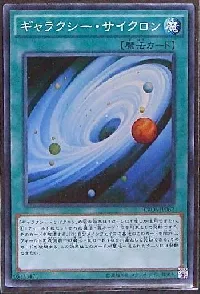 N-Parallel ▶︎ デッキ |
6 | JP031 | ギャラクシー・サイクロン |
|
場で発動する効果でセットされた魔法罠カード1枚を、墓地効果で表側表示の魔法罠カード1枚を破壊する魔法カード。 1枚で2度おいしい系のカードで結果的には数的アドバンテージにもなるので、現存するバック破壊魔法の中では上から数えた方が早い性能ではあると思いますが、速攻魔法ではない上に墓地に送られたターンは墓地効果は使えないため、結局自ターンに1枚除去できるだけのカードなのでそれほど性能は高くない。 両方の効果とも表も裏も破壊できるならともかくそうじゃないというのも使いづらく、除去方法も対象を取る単体破壊で通常魔法にしてはパワーが低いので、今敢えてこれをバック割り札に選ぶ人は少ないでしょう。 それぞれに表裏の指定があるせいで肝心な時に破壊したいカードを破壊できない場面があるというのはやっぱり印象が良くないですね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP032 | 貪欲な壺 |
|
発動条件とその効果の仕様がメリットにもデメリットにもなる2ドローできる「壺」魔法カード。 リソース回復をしながら手札を増やせる名前の通りの貪欲なカードであり、EXモンスターをEXデッキに戻せばデッキを圧迫することすらなく、多くの場面で墓地リソースを失うことに繋がりにくい。 代わりに墓地にモンスターが5体以上存在しなければ発動自体ができないため、手札の質やデッキの回りが悪いと腐る場合もあり、チェーン発動した効果で対象にした墓地のモンスターが1体でも墓地から移動すると効果はまるまる不発にされてしまうため妨害にも弱いです。 《D.D.クロウ》が登場した5期以降は、この辺は特に無視できないデメリットになった感じですね。 ただハマれば《強欲な壺》以上の効力を発揮することもある壺であることは間違いなく、引けばいつでも使えるわけじゃないリスクに見合ったメリットをもたらし得る良い調整のドローソースかと思います。 当時はこれで相手のデッキに戻っていく《ヴォルカニック・バレット》や《ヴォルカニック・バックショット》にそりゃあもう悶絶したもんですよ…。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
10 | JP033 | テラ・フォーミング 制限 |
|
発動条件も発動後の制約も名称ターン1もないが、1:1サーチ以外に効果がない通常魔法で現在も規制を受けている数少ない通常魔法の1枚。 テーマデッキがこぞってフィールド魔法に力を集めすぎた結果遂にこのカードにメスを入れられてしまいました。 さらにテーマ系だけでなく《魔鍾洞》のような汎用系でも極悪なフィールド魔法が登場したため、その後登場した相互互換の罠カードである《メタバース》もあえなく制限に放り込まれてしまうことになります。 10期以降のリミットレギュレーションは、環境テーマに関しては実質構築不能にするような無慈悲なものではなく、キーカードにアクセスできるカードを減らすことでその安定初動を劣化させるという傾向が続いていますが、こちらもその例に漏れない感じで、何度赦しても再犯を犯しそうなこのカードは当分制限カードから動くことはないでしょう。 何かの間違いでワンフォ準のようなことが起こらないとも言えませんが、長くは続かないでしょうね。 当然ですがフィールド魔法を使うテーマは何も環境デッキばかりではないので、こういう時にリンクスのリミット制のようなものが上手いこと効かないもんかなと思ってしまいますね。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
5 | JP034 | 小人のいたずら |
|
お互いのターンに場で発動する効果と墓地で発動する効果により、それぞれがフリチェでお互いの手札のモンスターのレベルを1つ下げることができる通常罠カード。 これによりレベル5のモンスターをリリースなしで、レベル7のモンスターをリリース1体でアドバンス召喚できるようになるわけですが、2つの効果は同一ターンに使用可能なので連打することで自分はレベル6のモンスターをリリースなしで、レベル8のモンスターをリリース1体でアドバンス召喚することもできるようになります。 また効果は相手の手札のモンスターにも及ぶため、S召喚やX召喚を中心とするデッキに対して相手ターンに手札のモンスターのレベルを乱して普段の展開を困難にさせる妨害札として使うこともでき、発動後に手札に加わったモンスターにもこの効果は適用されます。 妨害札として有効な相手は限られていますし、現在ではレベルを乱してもアドリブで展開されたり妥協で《S:Pリトルナイト》を立てられたりもするので登場当時よりは有用なカードではなくなってしまいましたが、一度効果を通したらそのターンはいかなる場合でも効果が覆らないという点は妨害札として優れていると思います。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP035 | 御前試合 |
|
《群雄割拠》の属性版となるルール介入型の永続メタ罠の一種。 遊戯王OCGにおいて、属性は種族の3分の1以下の種類しかなく、そうなるとやっぱり種族の方がバラけやすいから割拠の方が刺さりやすいのかも?という気もしますが、その辺りは環境で強いデッキと自分が使うデッキによって変わるのでそんなに関係ないでしょう。 このカードと《群雄割拠》を両方採用可能なデッキも少なくないため、そういったデッキでは仮想敵と自分のエクストラデッキ事情なども加味しながらより有効だと思う方をメインやサイドに入れていきましょう。 永続メタ罠を複数採用するのにはリスクも伴いますが、割拠御前はある程度後出しも利く永続メタ罠でもあるので、或いは両張りしていくのも良いかもしれません。 |
|||
 N-Parallel ▶︎ デッキ |
8 | JP036 | デモンズ・チェーン |
|
個人的には、対象となったモンスターの効果が無効になるだけでなく、攻撃できなくなるのが非常に優れていると感じます。 いくらそのモンスターが持つ効果が召喚誘発時の一発芸でだとしても、攻撃力が3000以上もあるとなるとさすがに話が別なわけで、すぐに処理できなくても足止め付きなのは間違いなく良い。 ただしそれなら警告や通告で無効にして破壊した方が安全なんじゃないか?という話になるのも事実です。 既に場に出ているモンスターの永続効果に対してでも、相手ターンに手札からも発動できてセット状態から使うとさらなる追加効果もある泡影も存在する今、基本的には何らかの効果で再利用することを前提とした採用、ウリアなどが要求する汎用永続罠としての活用を見出す目的での採用となる。 特にリビデ同様の自壊条件から場に残りやすいという性質があるので、セルフバウンスする永続罠としては代表格と言えるでしょう。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
9 | JP037 | リビングデッドの呼び声 |
|
汎用蘇生札の一種で、蘇生したモンスターが破壊以外でいなくなった場合は自壊せずに場に残るのが特徴であり、セルフバウンスする蘇生札といえばこの永続罠カード。 このカードに限りませんが、《死者蘇生》や墓穴など相手がこちらの墓地のカードを対象にした時にチェーン発動して、妨害したり妨害されることを防ぐ使い方ができるのが、速攻魔法や罠の蘇生札の最大の利点と言えるでしょう。 ただしその性質上相手ターンに発動することが多く、先に使うと上から墓穴を使われやすいことには注意したい。 |
|||
 Normal ▶︎ デッキ |
7 | JP038 | 大革命返し |
|
自分・相手を問わず、魔法罠の効果の発動以外の複数破壊系の効果を全て捉えるカウンター罠。 似た役割を持つスタロは無効破壊した上に場に25打点のスタダを追加して次の破壊にも備えられる非常に優秀な効果を持つが、こちらはカウンター罠なのでさらにカウンターはされ辛く、無効にしたカードを除外するのでモンスターに対して使えた場合のリターンはかなり大きい。 帚やライストなどをノーコストカウンターで受け流せるのは罠デッキにとっては非常に有り難い効果ですが、2連発は防げないという点では魔法による除去に対する対抗手段としては勅命に遠く及びません。 またスタロと同じく単体破壊と破壊以外の除去は捉えられないため、このカードで見たいカードは環境全体で見た時に両手で数えられる程度あれば御の字という感じで、バック剥しを多用する相手でも使いどころはそんなに多くないと思われるので、サイドデッキに入れるにしてもコズサイなどにも強いやぶ蛇の方が優先されているイメージです。 このカードを使うようなデッキは、そもそもエクストラは強金などで投げ捨てる程度でエクストラ依存度自体はあまり高くなく、スタロややぶ蛇と比べた時のこちらの優位性があまり目立たないところも大きいかと思います。 |
|||
※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。
更新情報 - NEW -
- 2024/06/22 新商品 ANIMATION CHRONICLE 2024 カードリスト追加。
- 07/27 11:13 掲示板 評価2以下構築デッキについて
- 07/27 10:21 評価 6点 《影騎士シメーリア》「《竜騎士アトリィ》陣営の《従騎士トゥルー…
- 07/27 10:12 デッキ アーマード・エクシーズ・シャーク
- 07/27 10:11 評価 10点 《マルチャミー・フワロス》「《マルチャミー・プルリア》に続く…
- 07/27 10:04 評価 10点 《紅涙の魔ラクリモーサ》「デモンスミス出張セットで《魔を刻む…
- 07/27 10:02 評価 8点 《六武衆の荒行》「場の《六武衆》と同じ打点の他の六武衆をリクル…
- 07/27 09:04 デッキ ギャラクシーアイズ
- 07/27 08:51 評価 4点 《火器の祝台》「 『夏季の宿題』をネタとした一枚。となれば『冬…
- 07/27 07:43 評価 5点 《XX-セイバー エマーズブレイド》「Xセイバーは厄介なデッキで…
- 07/27 05:56 掲示板 カードリストにおける誤表記・不具合報告スレ
- 07/27 05:54 評価 4点 《火器の祝台》「夏休みの宿題を終わらせる=勝利!! デッキ枚数…
- 07/27 05:41 評価 5点 《火器の祝台》「今回のレギュラーパックの発売前日に判明した6枚…
- 07/27 05:28 評価 5点 《共闘闘君》「今回のレギュラーパックの発売前日に判明した6枚の…
- 07/27 05:11 評価 5点 《至鋼の玉 ルーベサフィルス》「今回のレギュラーパックの発売前…
- 07/27 04:53 評価 1点 《ニュービー!》「今回のレギュラーパックの発売前日に判明した6…
- 07/27 04:43 評価 4点 《回猫》「今回のレギュラーパックの発売前日に判明した6枚のカー…
- 07/27 04:33 評価 5点 《地下牢の徊神》「今回のレギュラーパックの発売前日に判明した6…
- 07/27 02:27 評価 10点 《悪夢の蜃気楼》「最大4枚までドローを可能にする最強クラスの永…
- 07/27 01:08 ボケ 旧神の印の新規ボケ。領 域 展 開
- 07/27 00:30 評価 3点 《手のひら返し》「 《魔砲戦機ダルマ・カルマ》によって絶滅危惧…
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
 RAGE OF THE ABYSS
RAGE OF THE ABYSS


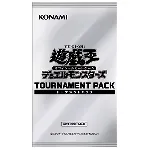 トーナメントパック2024 Vol.3
トーナメントパック2024 Vol.3
 ANIMATION CHRONICLE 2024
ANIMATION CHRONICLE 2024
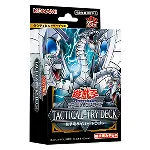 TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン
TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン
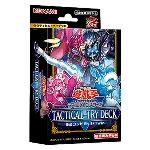 TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin
TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin
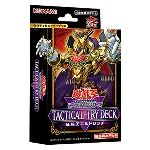 TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ
TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ
 デュエリストパック-輝光のデュエリスト編-
デュエリストパック-輝光のデュエリスト編-
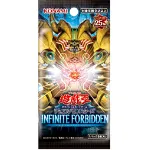 INFINITE FORBIDDEN
INFINITE FORBIDDEN
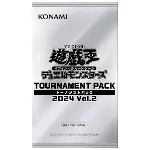 トーナメントパック2024 Vol.2
トーナメントパック2024 Vol.2
 QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE
QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE
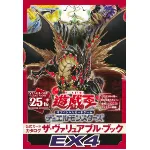 ザ・ヴァリュアブル・ブックEX4
ザ・ヴァリュアブル・ブックEX4
 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 8巻
遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 8巻
 QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY
QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY
 The Legend of Duelist PROMOTION PACK
The Legend of Duelist PROMOTION PACK
 LEGACY OF DESTRUCTION
LEGACY OF DESTRUCTION




 遊戯王カードリスト
遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索
遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧
遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ
遊戯王デッキレシピ 闇 属性
闇 属性 光 属性
光 属性 地 属性
地 属性 水 属性
水 属性 炎 属性
炎 属性 風 属性
風 属性 神 属性
神 属性